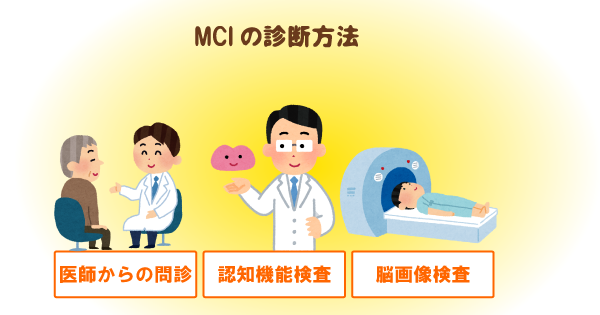特別養護老人ホーム裕和園の髙橋秀明です。
認知症の方々は、これまで「何もできない」「何もわからない」人として扱われてきた過去がありました。
今では認知症に対する偏見は過去に比べて、ずいぶん改善されました。最期まで尊厳を保持し、人生をまっとうするという考え方が一般的になってきていると感じています。
周囲や世間の捉え方は、認知症の方の生き方を大きく変えました。私たちが認知症の正しい知識を得て、適切なかかわりを持つきっかけとして、今回は「認知症の症状別アプローチの方法」についてお話します。
三大認知症を知る
はじめに認知症の定義を確認しておきましょう。『介護保険法』第五条の二には以下の通り定められています。
つまり、「何らかの原因」によって脳機能が低下し、生活に支障をきたした状態こそが認知症の本質です。何らかの原因とは、認知症の定義にあるようにアルツハイマー病、脳梗塞や脳出血など認知症を引き起こす本になる病気を指します。
専門の医師によると、原因となる病気は80種類くらいあるそうです。その中でも代表的なものが「アルツハイマー型認知症」「脳血管性認知症」「レビー小体型認知症」の3つです。これらは「三大認知症」と呼ばれており、それぞれ症状に違いがあります。症状が異なると介護のアプローチ方法も変わってくるので、種類ごとの特徴と一般的な対応方法を確認していきましょう。
認知症のタイプ別介護のポイント
アルツハイマー型認知症
認知症の中で一番多いのがアルツハイマー型認知症で、全体の65%以上を占めると言われています。アルツハイマー型認知症は、初期から記憶障がいなど(中核症状)が現れ、比較的緩やかに症状が進行します。徐々に食事や排泄、着替えなどの日常生活行為ができなくなり、生活全般に介助を要します。
【対処法】
症状が進行すると、「できていること・わかっていること」と「できなくなっていること・わからなくなっていること」の区別がつかなくなっていきます。そこで、介護者は「できなくなっていること・わからなくなっていること」を見極めることが大切になります。また、一部の生活行為がやり遂げられなくなったとしても、介護者がすべて代行し、本人に何もさせないということは避けるべきです。
アルツハイマー型の場合、介護者が一番頭を悩ませるのが、怒りっぽくなったり、暴言や暴力を振るってしまったりする「行動・心理症状」への対応です。行動・心理症状は、記憶障がいなどの中核症状に、不快やストレスなど本人にとって好ましくない環境が影響すると発生するとされています。逆に、記憶障がいなどがあっても、本人が能力を発揮できたり安心できたりする環境が整っていると、行動・心理症状は起きにくいと言われています。対応を検討する方法よりも、環境を整えることが重要なのです。
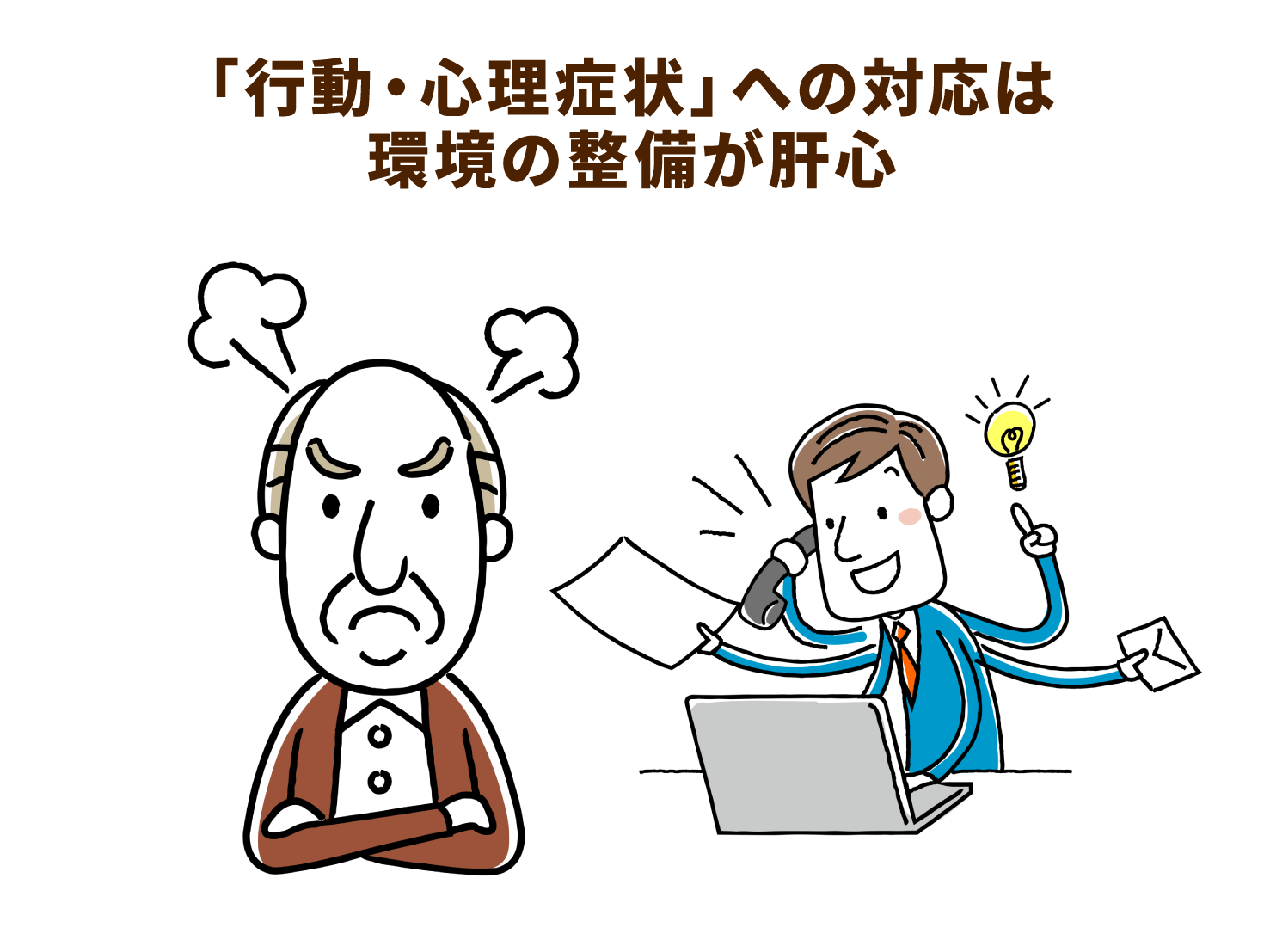
脳血管性認知症
脳出血や脳梗塞などの後遺症として症状が出ることが多いタイプです。緩やかに進行するのではなく、脳梗塞などを再発することにより、段階的に進行していきます。症状は、脳の損傷部位によって大きく変わります。言語障がいや感情失禁(軽い情動的な刺激で笑ったり、泣いたりして感情の調節がうまくいかない状態)などがよく見られる症状です。
【対処法】
脳血管性認知症は脳梗塞などの再発予防と早期発見・早期対応が重要です。「片腕のしびれや麻痺」「言葉が理解できない」「言葉が出にくく活舌が悪い」「ろれつが回らない」「よだれが出ている」「血圧がいつもに比べて著しく高い」などがあったら、脳神経外科を受診し、早期に検査を受けることが重要です。
レビー小体型認知症
レビー小体型認知症の特徴的な症状は、幻視とパーキンソン症状です。アルツハイマー型認知症に比べると、初期には記憶障がいがほとんど見られない方もいます。
【対処法】
私が出会った方で印象的だったのは、実際にはないものが見える「幻視」で、ぼんやりとではなく鮮明に見えているようでした。傾向としては昼間よりも夜間に見えることが多いようです。「あそこにネズミがいる」「隣に男がいる」「子どもがたくさん来ている」というように、まるで本当にいるかのように訴えていました。知識がなかった当時の私は「そんなはずはないですよ」と否定していましたが、訴えは収まらず、逆に興奮してしまうこともありました。そのような経験から今では訴えを否定するのではなく、「私がネズミを退治します」と言って訴えを受け止めて、「ネズミを退治してきましたので安心してくださいね」と伝えることで安心していただけるように接し方を変えています。
レビー小体型認知症は認知機能が比較的保たれているため、上記のようなかかわりで安心してもらえることがあるのです。幻視は壁の模様や影などがきっかけとなっていることもあります。そのため、環境への配慮も必要です。
一方のパーキンソン症状は、動きが緩慢になったり、歩行が小刻みになったりします。また、体内時計のリズムが狂う「日内変動」が起きると、調子が良いときと、悪いときの波が大きくなります。そのため、日内変動の特徴を捉え、調子の良いときは介助量を減らしてなるべく自分で日常のことを行ってもらい、調子が悪いときは介助量を増やして積極的にかかわるなどの対処が望ましいでしょう。
すべての認知症に当てはまるアプローチの心構え
最後に、三大認知症に限らず認知症状態にある方とコミュニケーションをとるときに、私が大切にしている視点をお話します。
認知症の方が見て、感じている真実と介護者が知る現実のズレへの対応
認知症の方が、現実とは異なる言動をされることがあります。介護者は、ついつい認知症の方の言動を否定し、正そうとしてしまいがちです。しかし、介護者の否定的言動は、認知症の方にストレスを与えてしまいます。望ましい対応は、「認知症の方が感じていること(真実)」を受け入れること。そして「介護者が知っていること(現実)」を押しつけないことです。
例えば、私が体験した事例をご紹介します。
施設のショートステイを利用するためにAさん(アルツハイマー型認知症状態)を自宅まで迎えに行きました。同居するAさんの長女さんが「髙橋さん、うちの母(Aさん)が1週間もお風呂に入ってくれないの。どんなに説得しても拒否されて困っちゃう。施設で(入浴)お願いしますね。大変だけど」とおっしゃいました。私は「わかりました」と長女の訴えに応じ、Aさんを乗せて車を走らせました。
施設に向かう道中、タイミングを見てお風呂の話題を切り出すと、Aさんは「私は毎晩お風呂に入っているわよ」と答えました。この場合、認知症状態の本人は「毎晩お風呂に入っている」という真実を抱えています。しかし、私が知っている現実は「1週間お風呂に入っていない」という情報です。ここには大きなズレがあります。
このとき、私はAさんにとっての真実を否定することなく、「そうなんですね」と受け止め、応じました。しかしAさんを否定して「1週間お風呂に入っていませんよ」と介護者が知る現実を押しつけたとしたら、きっとAさんは「そんなことはない!」と怒ったり混乱したりすることでしょう。

知識の記憶は忘れやすいが、感情の記憶は残りやすい
認知症は記憶障がいなどによって「今日〇〇した」という事実を忘れてしまいますが、「楽しかった」「嫌なことをされた」というような感情としての記憶は残りやすいと言われています。
だからこそ、本人の不快なストレスを少しでも軽減し、「うれしい」「楽しい」「心地いい」「安心」だと感じてもらうような言葉がけや、環境の整備が求められています。「認知症だから忘れてしまうだろう」と思って、ついつい強い口調で責め立てたり、否定したりすることは避けましょう。不適切なかかわりによって、本人に負の感情が積み重なると、信頼関係を損なう可能性があります。
認知症の方が「不安を感じるようになる」→「介護者に不満を持つようになる」→「介護者に不信感を持つ」→「不穏(行動・心理症状)になる」のは、典型的な悪循環です。
認知症の人に対しては、「わかる・わからない」「できる・できない」で判断しがちです。しかし、「人は存在そのものが尊いもの」という当たり前の視点を忘れてはいけません。症状別にアプローチ方法を変えることは大事なことですが、私は「こうすればいい」「こうすればうまくいく」というスーパーテクニックは存在しないと考えています。人間関係を構築していくうえで、最も重要なのは関係性づくりです。そのうえでアプローチを考えることが原則だと忘れないようにしましょう。