株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。
私は第162回で、グループホームの入居者の方たちが「自分でやってみよう」という、自発的な行動を促すことにつながる環境を整えることの大切さをお伝えしました。
今回は同じ環境を整えることでも、認知症の状態であるために勘違いや誤りが起きてしまった(または起きやすい)環境を整えることについて、以前筆者が勤めていたグループホームでの実話を基に紹介します。
加湿器をやかんと勘違いして電源を切ってしまう
冬場は室内の乾燥を防ぐために、家庭用の加湿器を全居室に設置していました。といっても、日中はほとんどの入居者の方たちが居室で過ごすことがないので、加湿器を使うのは就寝のときだけです。
夜勤の介護職員は就寝前の支援として、以下のことを行っていました。
- 本人への声かけ(就寝の促し)
- 口腔ケア
- 普段着から寝間着に着替える手伝い
- ベッドまわりの簡単な整頓
- 寝具の快適さの確認(掛け物を気温によって替えるなど)
- 本人への気分や体調などの確認
- 排せつ支援
- ベッドヘの移動支援
- ベッドサイドでの端座位(たんざい:足をおろして座った姿勢)の介助
- ベッド上での仰臥位(ぎょうがい:仰向けの姿勢)の確保などの身体介護
夜勤の介護職員はこのような就寝前の支援の最中に、入居者の方に声をかけながら加湿器を準備し、電源を入れます。加湿器は入居者の方たちにとって馴染みのない製品なので、どんな道具で、何のために使うのかといったことを説明する必要があるからです。
しかし、その説明を覚えておくことが苦手な入居者の方は、10分も経たずに電源を切ります。吹き出し口からモクモクと出てくる白い蒸気を見て、やかんもしくは電気ポットと勘違いして「お湯が沸いた」と思うからです。そんな入居者の方が数名いました。
馴染みのない製品を無理に使う必要はない
しかし「電源を切らないように」と注意をしたり、電源を切られないように細工するなどといったことはしませんでした。湯気が出ていれば電気ポットだと勘違いもするだろうし、お湯が沸いたと思ったから電源を切るという行動自体も間違っていないからです。
また、目的は「居室を加湿すること」であって、「加湿器を使うこと」ではありません。なので、加湿器に代わる加湿方法(代替策)を支援する側が講じればいいわけです。
このときは、濡れたバスタオルを居室内にぶら下げて加湿したのですが、入居者の方にとっても違和感がなく馴染みのある方法だったようでうまくいきました。

ちなみに、当時(10年前)の加湿器は吹き出し口から白い蒸気が出るスチーム式ばかりでした。今であれば、蒸気が出ない帰化式の加湿器を使うという方法もあるかもしれません。
エアコンを適切に扱えない入居者
夏場の就寝時には、居室に設置された家庭用エアコンが活躍します。しかし、入居者の方のほとんどが、リモコンを適切に扱うことを苦手としていました。夏に暖房、冬に冷房を設定してしまったり、気温に合わせた温度調節を間違えてしまったりするのです。
また、リモコンをどこかにしまったことを忘れてしまう方が多く、エアコンを使いたいときに使えない事態が起こることもありました。そこで、リモコンは居室に据え置きせず、施設預かりとして居室の空調は職員が管理していました。
そんなある日のことです。Aさんはタンスの上に乗り、Bさんはベッドの上に置いた椅子に乗り、エアコンのある場所を指で押していました。その場所は、電源を入れると緑色に光るランプの部分です。AさんもBさんも、そのランプを押せばエアコンの電源を切ることができると思ったのです。
タンスの上やベッドに置いた椅子に乗るのは転落する恐れがあるので危険です。そこで何か手立てが必要なのですが、AさんもBさんもリモコンを適切に扱えなかったので、リモコンを居室に据え置きしておくこともできません。さらに、熱中症などを考慮すると、エアコンを使用しないというわけにもいきませんでした。
また、エアコンの場合、加湿器のような代替策もほとんどありません。居室の適温確保という目的に対して、エアコンほど有効な手段がないからです。これらのことから「仕方がない」と現状のままにしておけば、2人はいつか怪我をしてしまったでしょう。
入居者の就寝・起床時間を把握してエアコンの温度を調整
そこで、このときは緑色に光るランプの上にテープを貼り、ランプそのものが2人の目に入らないようにしました。さらにAさんは、エアコンから吹き出す風そのものが気になり、風を止めたかったようなので、Aさんが気づかないように空調の管理を職員が行いました。具体的に行った支援は以下の通りです。
- Aさんが就寝のために居室に戻る前に、職員がエアコンの電源を入れて室内を涼しくしておく
- Aさんが居室に戻る頃を見計らって電源をオフ
- 寝静まったころに再び電源をオンにし、起きる頃に電源をオフ(早朝の気温次第で電源を切ることも)
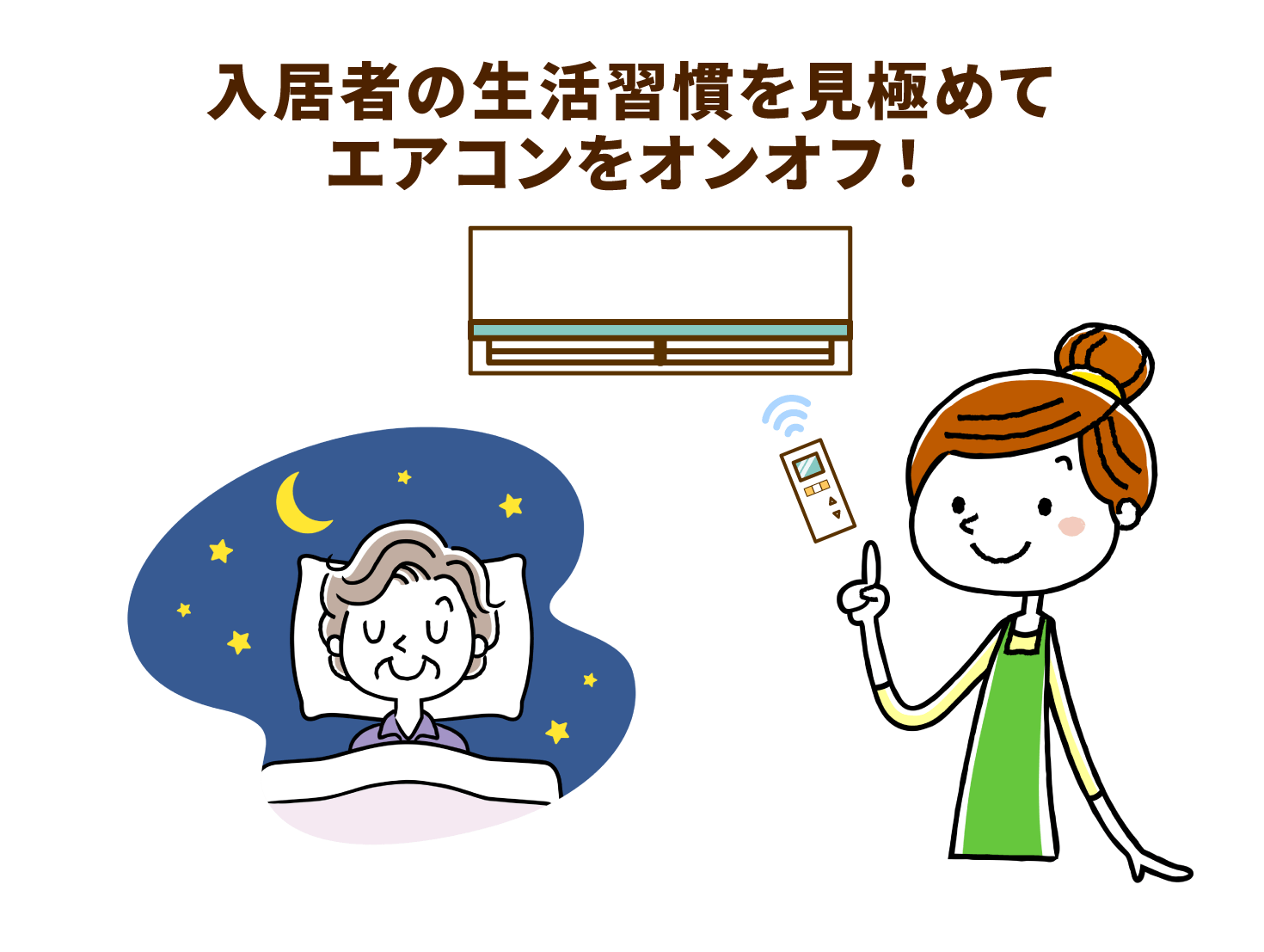
このように、いつ頃寝て、いつ頃起きるのかといった、Aさんのことをよく知る職員だからこそ、Aさんの生活習慣に合わせた対応ができました。
「その人のことをよく知る」ことが、画一的ではない個別対応につながったり、事故等を未然に防ぐことなどにも活かせるのです。
火災報知機を入居者が押してしまう
介護施設には火災報知器が設置されていますが、筆者が勤めていたグループホームでは入居者の方が誤ってボタンを押してしまうことがたびたびありました。火災報知器のボタンには「強く押す」と表示されていますから、押してしまうのも無理からぬことです。
火災報知器は、認知症の状態にある入居者の方たちにとって見知らぬもの。ですので、「これはいったいなんだろう」と見てみたら、そこには、「強く押す」と書いてある。「ああそうなんだ」と、書いてあるとおりに強く押してみた…となるのも当然です。
その経験を基に、次に勤めた新規開設のユニット型特別養護老人ホームで対策を講じました。施設の設計・建設の段階で、火災報知器の「強く押す」と書いてあるボタンにカバーをつけてほしいと要望したのです。表示が目に入らないようにしたいということもありましたが、押してしまう前に「カバーをどける」という動作がひとつ増えることで、ボタンを押すまでに至らないようにしたいという考えもありました。
おかげで、こちらの施設では、入居者の方が誤って火災報知器を押してしまうことはありませんでした。ちなみに今では、火災報知器のいたずら防止用に透明なアクリル板カバーつきの商品もあるそうです。
認知症の状態にある方たちが安心して暮らしていただけるよう、代替製品やアイデアを取り入れた自作品などを活用して、「予測される事故やトラブルを未然に防ぐ」ための「環境を整えること」も大切だと思います。





















