こんにちは。株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。
第13回「認知症ケアはチームプレイ。8つの調べ方を心得て、わが街の“認知症ケア支援策”を存分に活かしましょう!」では、認知症ケア支援策の取り組みについて紹介しました。
今回は、"認知症にまつわる病院受診"について書きます。認知症の方が身近にいる方、どうしたら病院に行ってくれるようになるのかとお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。
診断名がはっきりと書かれているか診断書の確認はかなり重要
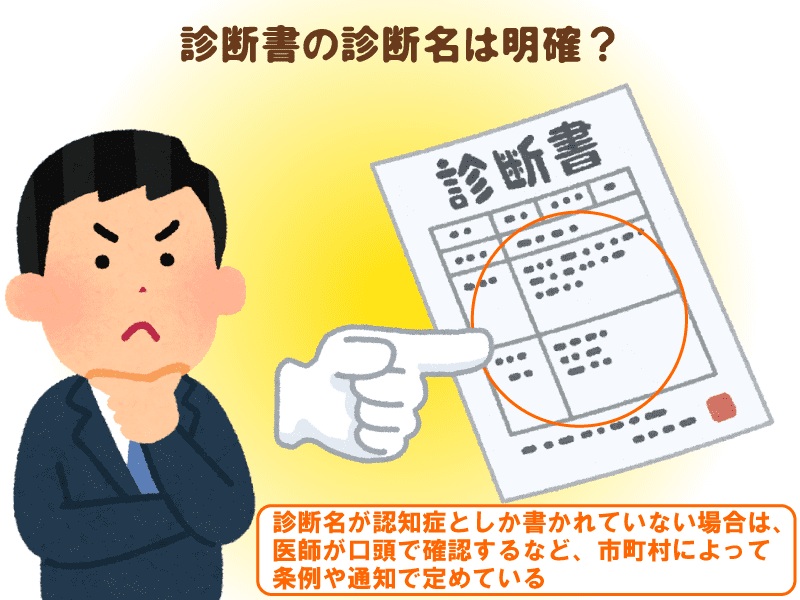
僕は2000年4月から10年半、介護保険法の地域密着型サービスのひとつである認知症対応型共同生活介護事業所(一般的にグループホームと呼ばれる)のホーム長(介護保険の職種としては、管理者兼計画作成担当者)を務めていました。
認知症対応型共同生活介護は介護保険法に基づいて市町村から指定(許可)を受けたもので、市町村から指定(許可)を受けるには「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(2006年厚生労働省令第34号)」という、略して「運営基準」に示された人員配置・建物(設備)・利用料などの基準を備えていなければいけません。
その運営基準は介護保険法に基づく全事業それぞれに定められているのですが、認知症対応型共同生活介護の運営基準には、認知症対応型共同生活介護の入居(利用)対象者についても明記されています。
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
- 第5章 認知症対応型共同生活介護 第4節 運営に関する基準(入退居)
第94条 - 指定認知症対応型共同生活介護は、要介護者であって認知症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供するものとする。
介護保険法に基づく事業なので、要介護者」=「要介護認定において要介護1~5と認定された方」が入居(利用)対象であり、認知症"対応型"ですから、「認知症であるもの」イコール「認知症の状態にある方」が入居(利用)するのが認知症対応型共同生活介護です。そして、「認知症の状態にある」ことは認知症対応型共同生活介護事業者が独自(勝手)に判断するものではありません。
第94条2
認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居(利用)時に、医師が作成した診断書や法文には診断書"等"とあるので、医師の診断が確認できる診療情報提供書・主治医意見書などを入居申込者に提示してもらって、「認知症の状態にある」ことの確認をしなさいということが運営基準に示されています。
また、2012年の介護保険法改正で介護保険法第5条に第2項(認知症に関する調査研究の推進など)が追加され、その条文において認知症の定義が「脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいう(一部抜粋)」と示されました。
診断書などで「アルツハイマー型認知症」「レビー小体型認知症」「ピック病(前頭側頭型認知症)」などの診断名があれば原因疾患が何であるかが確認できますが、そうでない場合(例「認知症」としか書かれていない)は、診断をした医師に口頭などで原因疾患を確認することなどを条例や通知で定めている市町村(認知症対応型共同生活介護事業者の指定(許可)権者)もあります。
早期発見のカギは?メモに残し支援策や今後の予測を立てること

僕は、このような認知症対応型共同生活介護における「認知症の状態」の確認を見聞きするたび、グループホームのホーム長時代に聞いた、認知症にとても知見の深い医師の言葉を思い出します。
「梅本さん、診断書に“認知症”としか書かない医者のことは信用しちゃいけないよ」。医師いわく認知症の診断は、「問診(ご本人と、ご本人の状態を身近で見ている方の両方から症状について話しを聞く)」「認知機能テスト(ほとんどが質問に口頭や筆記で答える)」「画像検査(MRIやCTによって、脳の萎縮状態などからアルツハイマー型や脳血管性などの原因疾患、どの程度病状が進行しているのか、ある程度判断ができるか)」によって総合的に行うそうで、設備が整っているのであればSPECT検査(脳血流シンチグラフィ)も行うとのこと。それによって脳内の血流量が少なくなっている場所を特定できるので、より原因疾患などの診断が確実になるのだそうです。
医師の言葉が続きます。「診断書に“認知症”としか書いていない医者は検査をせず(原因疾患の推察をせず)に、診断書に認知症と書いているといっても良い。もしかしたら認知症じゃないかもしれないのにね。でもね、検査だけで認知症の診断はしちゃいけない。もちろん問診だけでもダメ。問診・認知機能テスト・画像検査の結果、すべてを踏まえて総合的に診断しないと」。
認知症の状態は、原因疾患によって特徴的な症状も経過も違います。なので、問診や認知機能テスト、画像検査によって、認知症の状態であること、原因疾患や進行具合を総合的に診断してくれていることは、僕ら支援専門職には大切なことなのです。というのも、原因疾患や進行具合を知ることは、支援専門職である自分たちが考え抜く・考え出す支援策や今後の予測(ご本人の状態変化など)を立て、支援の準備をしておく上で重要な情報のひとつだからです。
また、自宅生活を続けている方の中で「認知症かな?」と認知症が疑われる場合も、適切な方法によって診断を受けることが大切です。そうでないと、認知症の状態ではないのに不要な薬を処方・服用すること(そもそも飲む必要がない薬)によって別の症状などが現れてしまうかもしれませんし、もし認知症の状態であれば、診断結果(原因疾患や進行具合等)に併せて、ご本人やご家族と治療方針を決めていくこともできるようになります。。
さらに、認知症の状態は「早期発見・診断」が重要です。早期発見・診断によって、原因疾患が正常圧水頭症、脳腫瘍、慢性硬膜下血腫などの場合は、脳外科的処置で認知症の状態そのものを治すことができたり、アルツハイマー型認知症などの場合は進行を遅らせるたり、また支援(介護)者側が対処することができるようになったりと、認知症の状態が起因となるさまざまな影響(行動・心理症状など)を小さくすることができる可能性があります。
この早期発見・診断につなげるには、ご本人の状態を身近で見ている方が「おかしなことは、まず記録をとっておく」ことがカギにんります。それまでその方になかったような言動、身近で見ている方が「あれ?」と思うことが2~3つと起こってきたらメモを取っておく(記録する)。そして受診する際に、医師に手渡し読んでもらう(もしくは、近くの地域包括支援センターなど支援専門職に手渡し相談する)。何せ、医師を前にすると緊張して伝えたいことが伝えられなかったり、ど忘れしてしまって伝えなきゃいけなかったことが伝えられなかったなんてこともありますから、メモを取っておくことでより正確な情報を医師に伝えることができます。
ちなみに、僕が勤めていたグループホームで入居者さんが病院受診する際は、受付で前回受診からのご本人の様子・毎日の睡眠の様子(何時に眠り、何時に起きたか。途中起きてきたことも含む)などをまとめた記録を手渡し、診察前に医師に読んでおいてもらえるように頼んでいました。認知症の状態にある方の中には集中力を持続させることが苦手な方もいるので、できるだけ診察時間を短くしたかったからです。それに、ご本人の目の前で記録を手渡すと、ご本人にしてみたら「それ何?」と不安や不信を感じても仕方がない。そんなことも避けるためです。
受診をしてもらうにはその人の"必然性"を作ってあげる

僕が勤めていたグループホームに入居していた岩田さん(女性:仮名)。彼女は入居してから約1年、ほぼ毎日睡眠時間は3時間弱。日によっては一睡もしない日もあった。当然、昼間は眠くなるはずだが、談話室でウトウトとはしても、他入居者さんの声、人が行き交う物音、テレビの音など、何かしらに反応し目を覚ます。じゃあ部屋に戻って少しは昼寝でもと職員が誘っても、「いいよお。オラ眠くなんかねえよお」と言って断り、他の入居者さんのほとんどが談話室で過ごしている中、一人で部屋に戻るのが寂しいのもあって部屋で休むことはない。談話室で横になることをすすめても「何でオラひとりこんなところで寝なきゃいけねえんだ」となり、職員の休憩室に誘っても「悪いからいいよお」と誘い水には乗らない。
僕も含め職員は徹底して約1年間、彼女の眠りが浅いこと・短いことの原因を探ったが答えが見つからない。夜しっかり眠れるようにあの手この手と手立てをうってみたものの当たりが見つからない。関わりだけではどうにもならない・もう打つ手がないと判断し、認知症の診断(問診・認知機能テスト・画像検査)や診療に実績があり、認知症に知見の深い医師がいる大学附属病院のメンタルクリニックを受診することにした(当時は認知症疾患医療センターは存在していなかった)。
岩田さんは入居から今日に至るまで認知症の検査等も受けたことがなかったので、支援者側の僕らは余計に受診をしてもらいたかったのだ。
「オラ、どこも悪くねえ。今まで風邪ひとつひいたことねえ」と日頃からよくそう口にしていた岩田さん。「病院に行きましょう」と誘っても、「嫌だよ」「行かねえ」「なんでオラが病院に行かなきゃいけねえんだ」と返されるのが目に見えている。案の定、一度の誘いは断られてしまった。そして、この日に行こうと決め、主治医に診療情報提供書を書いてもらい、病院に予約も入れたある日。
梅本:「岩田さん、何年生まれだったかな?」
岩田さん:「あっ?え~と、大正○年だったかな」
梅本:「おっ、大正○年。じゃあ今年○○歳ですね」
岩田さん:「そうなのか。○○歳かあ。オラそんな年取ったんかあ」
梅本さん:「そうそう岩田さん、○○市から手紙が来てましてね。今度○○歳以上の人は健康診断を受けなきゃいけないって…」
岩田さん:「うん?そうなのか…」
梅本さん:「ほらっ」(○○市とプリントされた封筒(グループホーム宛に○○市から届いた封筒を使いまわし)、その封筒の中には職員が作った健康診断のお誘い文章。それを岩田さんに見てもらう。)
岩田さん:「ありゃあ…ほんとだなあ。でも、金かかんだろ?」
梅本:「ちょっと見せて(岩田さんから職員お手製の文章を受け取り…)。いや、無料みたいだねえ」
岩田さん:「そっかあ。じゃあ受けてみるかな…。で、いつだって?」
梅本:「うん?あ~、今日だって。僕も一緒に行くから、行きましょうよ」
岩田さん:「う~ん、そうだなあ。じゃあ行くべっか」
一度岩田さんに「病院に行きましょう」と誘って断られたのは当たり前。岩田さんは「どこも悪くない」と思っているわけですから、岩田さんにしてみたら断る(行かないと判断した)のは至極当然、ごもっともなわけです。
また、「認知症かもしれないんだから」とか、「最近物忘れがひどいでしょ」「全然寝ないでしょ」などと言って、本人を説得して病院に連れていくなんていうのはほぼ無理。いくら支援者側にとっての「現実(認知症かも・全然寝ない)」を岩田さんにぶつけても、岩田さんには自分にとっての「事実(認知症じゃない・寝ないなんて言いがかりだ)」があり、そこ(現実と事実)にはズレが生じているからです。
しかも、認知症が岩田さんにとっての事実につながっているので、ズレをなくすために、支援者側にとっての現実に彼女を適応させよう(合わせさせよう)としても岩田さんにとっては、ただ辛いだけのことなんです。ましてや無理矢理病院に連れて行くっていうのは一番NGです。なので、○○市からの(使い回しの)封筒・職員が作った健康診断の文章という道具を使い、言葉を交わしていく中で、「それじゃあ、しょうがねぇなぁ」といった、ご本人(岩田さん)にとって病院に行くことが納得できる理由、言わば、ご本人にとっての"必然性"を作っていったわけです。
そして最後にもうひとつ。このご本人にとっての"必然性作り"を誰がやるのか?それは必ずしもご家族でなければいけないわけじゃありません。大切なのは、誰の言葉に一番耳を傾けるのか?それは、主治のお医者さん、地域包括支援センターの職員さん、民生委員さん、いやいや近所の仲良しさん、それとも一番の親友さんなのかもしれません。




















