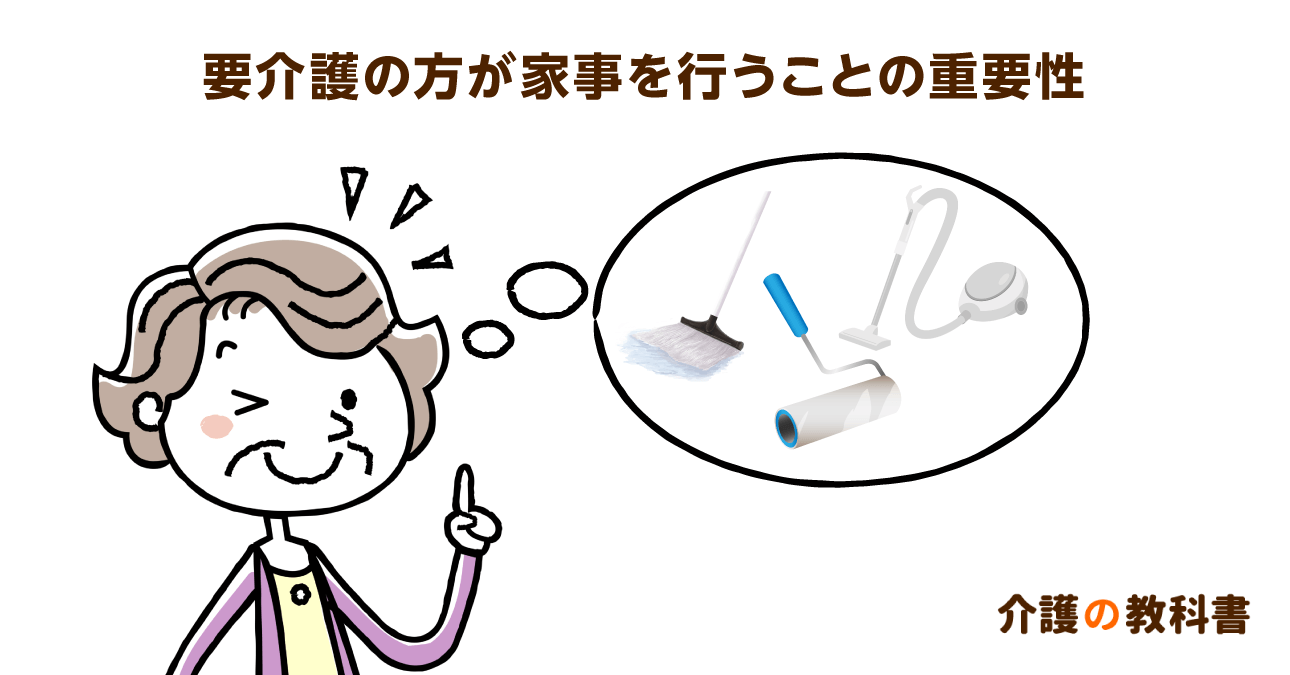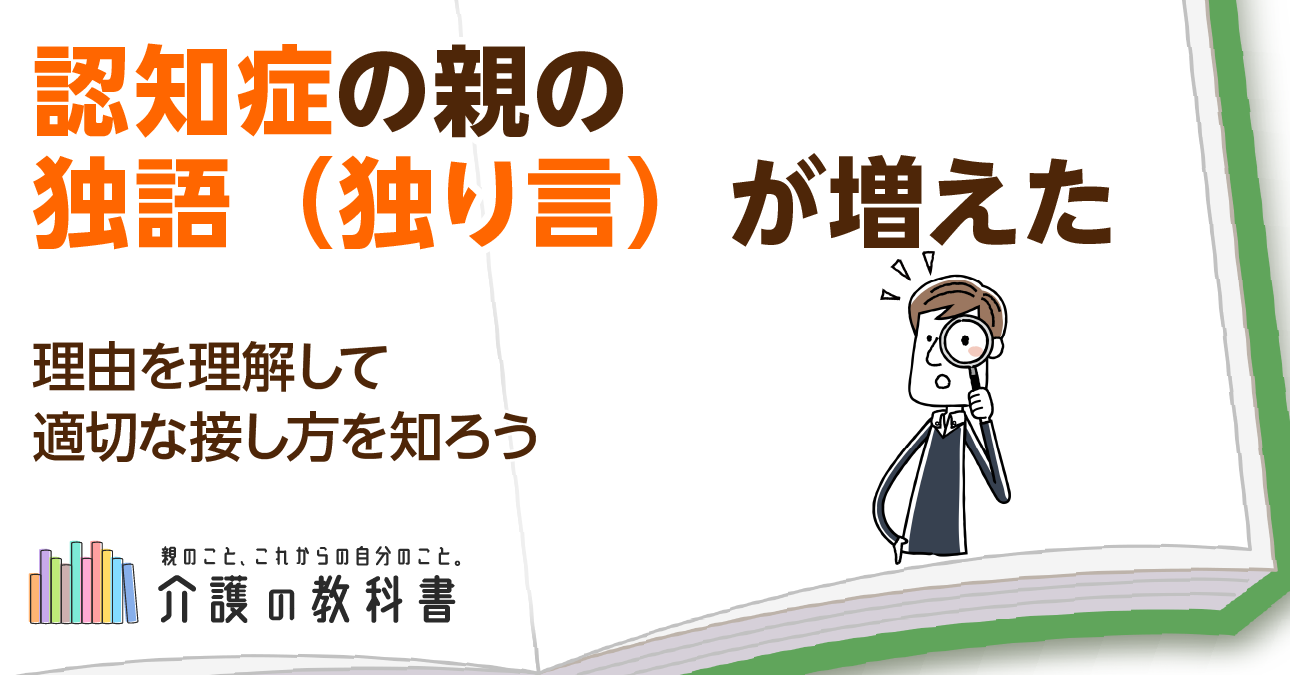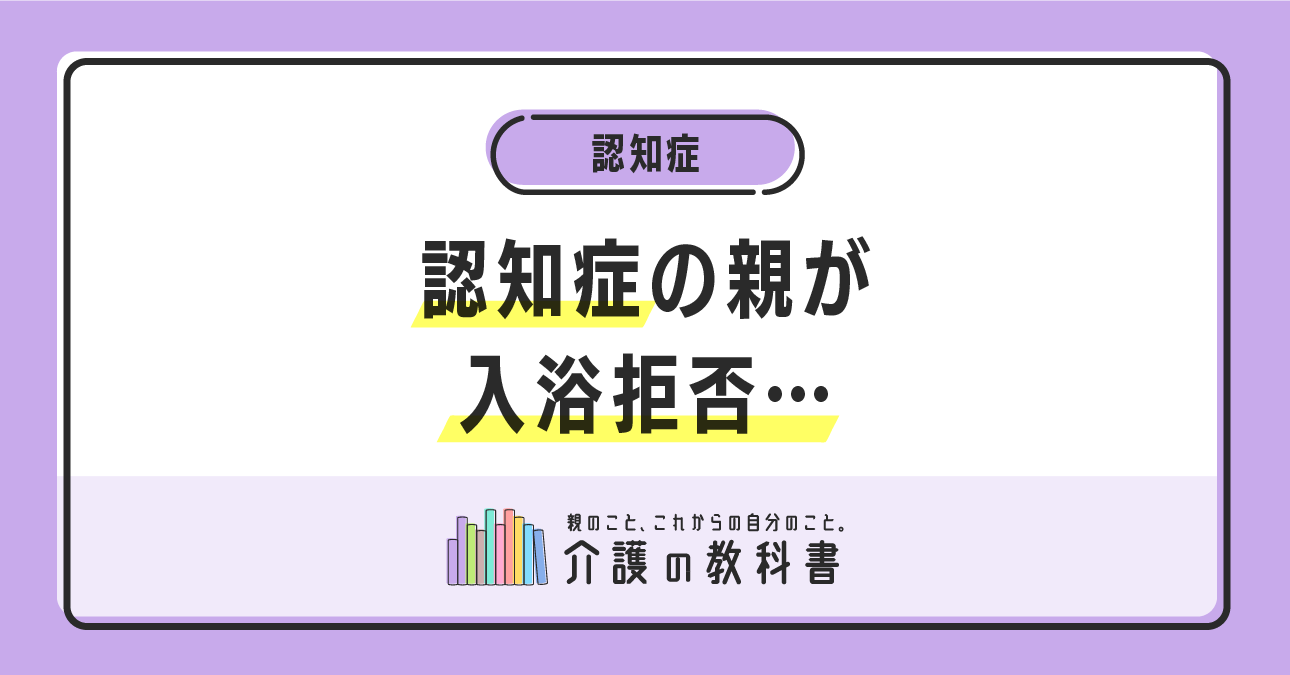株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。
今回は、要介護の方が行う「家事」についてお伝えします。
家事と余暇活動のどちらを優先すべきか
筆者が以前ホーム長を務めていたグループホームでは、認知症の状態にある入居者の方たちが、職員の支援を受けながら食事の献立を考えて買いものに行ったり、料理をしたり、掃除や洗濯などの家事も分担して行ってもらってました。そのグループホームに月1で約2時間程度、介護相談員の方2人に訪問してもらっていたのですが、あるときの訪問の際、こんな提案をいただきました。
介護相談員「梅本さん、入居者の方とお花を育ててみたらどうですか?」
筆者は、介護相談員の方がそう奨めてきたのか、思い当たるところがありましたが、確認のために問い返しました。
筆者「どうしてそう思われたんですか?」
介護相談員「こちらのグループホームに伺うと、入居者の方はいつも職員と買いものに行ったりご飯をつくっているか、お掃除をしているところしか見かけないものですから」
予想通りの回答でした。つまり、「家事ばかりに取り組んでいないで、花を育てるといった余暇活動にも取り組んではどうか」という意味で聞いたのです。さらに介護相談員の方は「もっと生活の中に楽しみがあってもいいんじゃないかと思いました」と言葉を続けました。
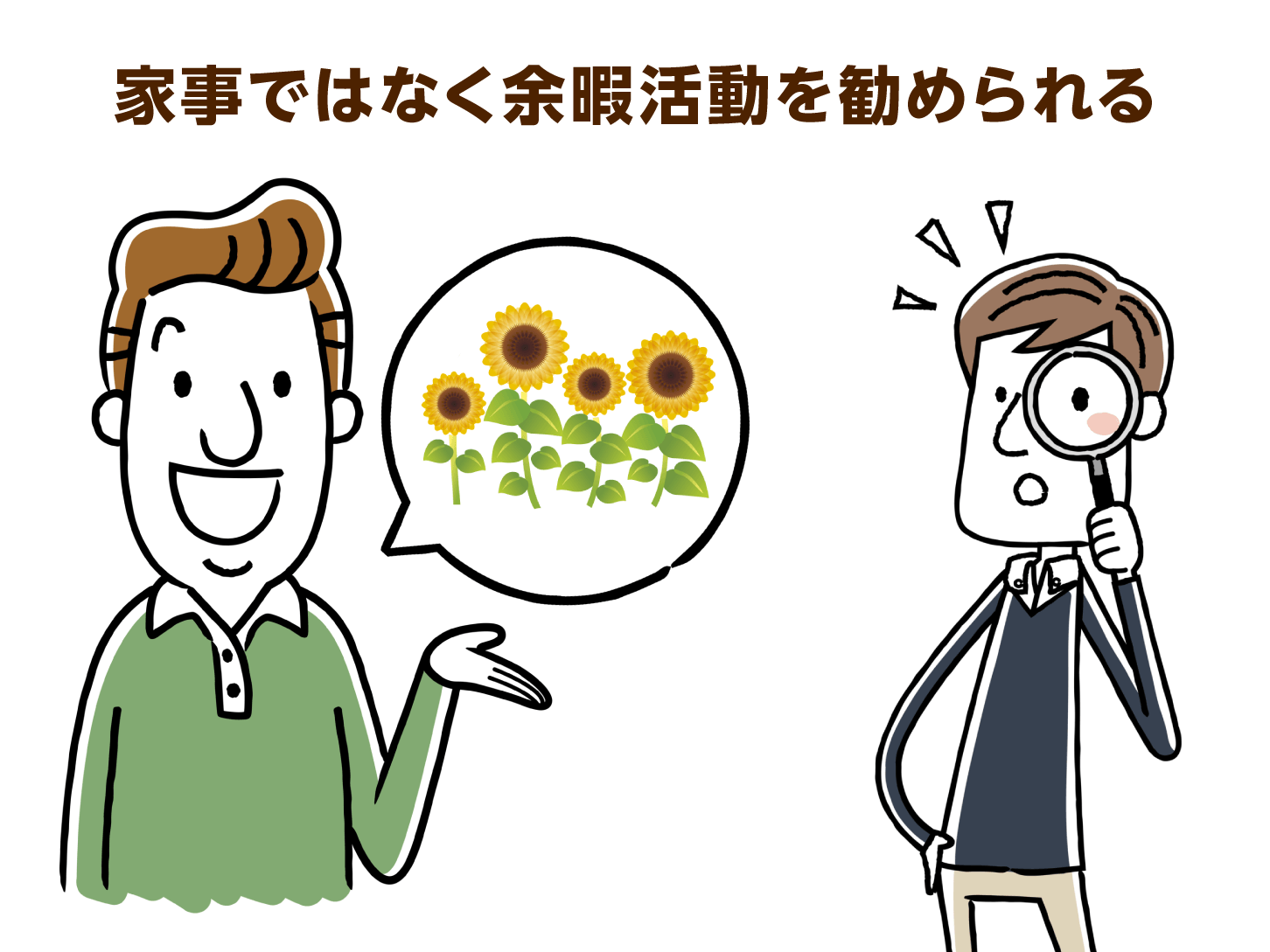
私は、花は育ててはいないが、余暇活動(非日常的活動)にまったく取り組んでいないわけではないことを介護相談員の方に伝えつつ、次のように語りました。
筆者「花よりも腹の方が先ですね(笑)」
介護相談員「えっ?」
筆者「おっしゃることは理解できます。でも、花を育てることよりも、自分たちの昼ごはんを自分たちで用意することの方が先じゃないですかね。人間、食べなきゃ死んじゃいますから」
筆者は、非日常的活動を否定しているわけではありません。一方的に「介護者に何でもやってもらう、お世話される」のではなく、認知症の状態・要介護状態にあっても「自分でできることは自分で行う」という、かつては当たり前に送っていた暮らしをベースにした場合、「花を育てることと「食」にまつわる事柄のうち、どちらの優先度が高いのか」ということを介護相談員の方に伝えたかったのです。
用事やその日の気分にあわせて1日のスケジュールを組む
また、非日常的活動に割く時間がなかなか取れないというのも正直なところでした。朝食づくりからはじまり、その後片づけをして洗濯や掃除をしていたら、あっという間に昼食の準備や買いものに行く時間。ほかにも家事はたくさんあります。しかし入居者の方たちは高齢ですから、私たちと比較すれば、これらの家事に要する動きはゆっくり、ゆったりです。
また、認知症の状態であるため、家事がスムーズに行えることはほとんどなく、見当違いの行動や物事のつじつまがあわないなんてことが常にあります。つまり、自立している私たち以上に、家事のすべてに労力と時間がかかるわけです。まさに「自分の暮らしに必要なことを頑張っていたら日が暮れていた」状態です。
ちなみに筆者が務めていたグループホームでは、かつては当たり前に送っていた暮らしに重きを置いていましたが、来る日も来る日も家事ばかりの画一的な毎日ではありませんでした。通院が複数重なっていたり、日時の変更ができない用事など、家事よりも優先すべきことがあったり、そもそも家事に対して入居者の方たちの気分が乗らなかったりするときもあります。
そんなときは、職員側で献立や買いものを済ませたり、弁当を買ったり出前を頼むこともありました。また、「天気の良い日に家事なんてしたくない」となれば、家事をせずにピクニックに出かけたりもしていました。このように、私が勤めていたグループホームでは、優先度やそのときの気分、天気などからその日その日を組み立てていたので、決して同じような日はなかったのです。
居住系施設の設備や食事は以前の暮らしからかけ離れている
ここで改めて、「家事」とは何か確認してみます。辞書によると家事とは「家庭生活を営むための大小いろいろの用事。掃除・洗濯・炊事など」とありました。そんな家事を楽しみながら行う人もいれば、家事のプロや研究家もいます。ですが、面倒に感じる人の方が多いのではないでしょうか。
とはいえ、家事は日常生活を送るうえで欠かせないですし、それをやめることはできません。それは要介護の状態になっても同様なのですが、要介護の方が居住系施設に入居すると、その方の暮らしから家事は存在そのものが消えてしまいます。
そうなるのは当然で、そもそも居住系施設の運営基準などに定められる設備(建物の造り)では、家事を行うために必要なものが定められていません。また、食事については入居者の方たちが調理などに関わることがない「給食型」です。運営基準や食事の形態からもわかるように、介護保険制度は要介護状態にある方たちが居住系施設で家事を行うことを想定していないのだと思います。これは、支援専門職のサポートを受ければ、かつての暮らしに欠けることのなかった家事において、まだまだできることがあるのにその機能や能力を発揮する環境がないということなのです。

グループホームは認知症の方にとって重要な社会資源
居住系施設の中でも、グループホームには次の規定が定められています。
共同生活住居は、その入居定員(当該共同生活住居において同時に指定認知症対応型共同生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第百四条において同じ。)を五人以上九人以下とし、居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。
利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。
このように、設備基準の中に「台所」が定められており、「食事その他の家事等」は利用者と介護職員の共同で行うことを努力義務として定めている居住系施設は、グループホームだけです(そのほかでは小規模多機能型居宅介護のみ)。つまり、グループホームは「自炊型の食事」「入居者の方たちが家事を行うこと」が可能な機能と役割を持っています。さらに認知症の状態にある方にとっては、かつての暮らし方を取り戻したり維持したりできる社会資源なのです。
ということで、筆者は職員とともに、グループホームだからこそ持っている機能を活かし入居者の方たちが家事を行うことを支援していきました。次回は、その実践の中で学んだ「家事には脳や体を使うことがたくさんある」ことについてお話しします。