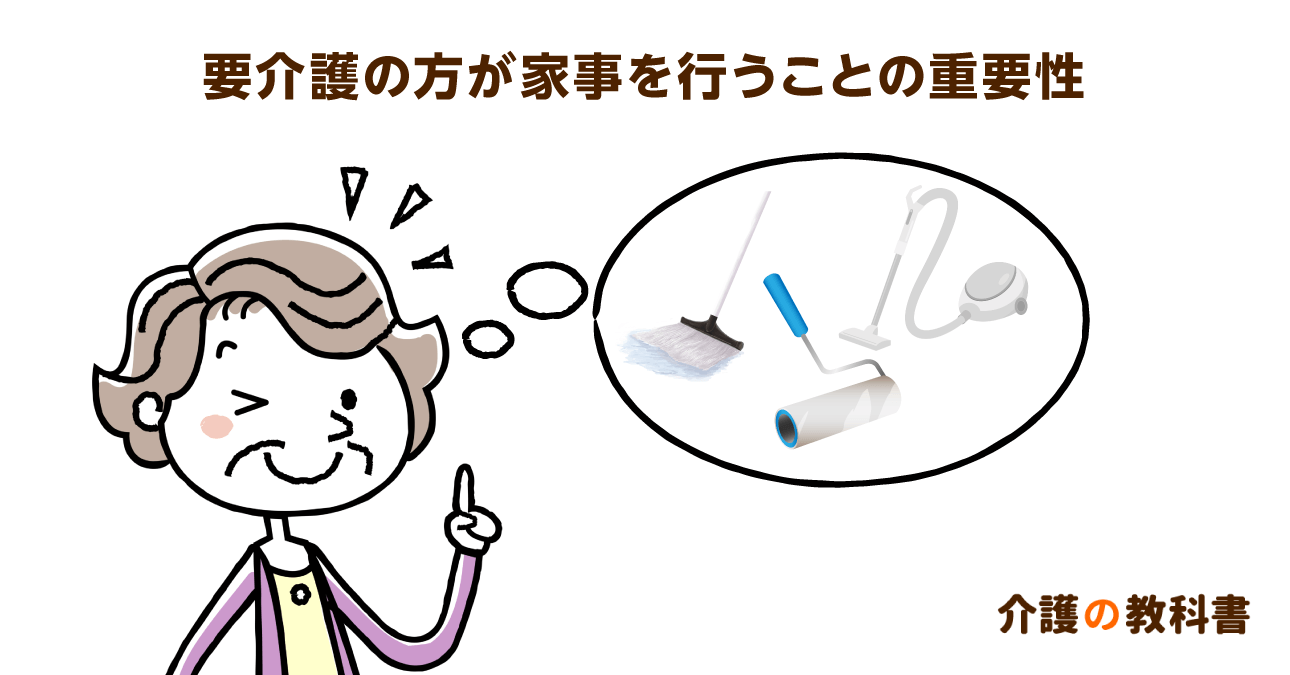株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。
今回は、かつて筆者がホーム長を務めていたグループホームで実際にあったエピソードを基に、「介護とは何か」について考えてみたいと思います。
食料を買いに行くTさんと職員
下記の会話は、介護職員と入居者であるTさんのものです。
職員「Tさん、買いものに付きあってもらえませんか」
Tさん「買いもの?何を買いに行くんだ?」
職員「夕飯をつくるので、その材料を買いに行きます」
Tさん「おお、そうか。よっこらしょ」
そう言いながら立ち上がり、買い物の誘いに応じてくれたTさんは当時、御年96歳。足腰が弱ってはいましたが、シルバーカーを使えばまだまだ自分の足で歩くことが可能です。Tさんは職員と一緒に、グループホームの近所にあるスーパーに歩いて向かいました。そして店先に着くとシルバーカーを置き、ショッピングカートを押して移動。店内では、職員と協力しながらお目当ての食材を探しに行きます。
ショッピングカートに乗せられたカゴの中が、入居者の方と職員の分をあわせた11人分の食材で山積みになったところで、職員がTさんに「Tさん、そろそろお酒がなくなるので買っていきませんか」と声をかけます。夕飯時に晩酌をするTさんとの買いもの終わりは、日本酒を買うのが恒例だったのです。
Tさん「おお、そうか、(ワンカップのお酒を持って)それじゃあ、これにするかな」
職員「(2リットルのお酒を持って)Tさん、こっちの方が多いですよ。どうせなら、こっちにしたらどうですか」
2リットルパックの日本酒を職員が奨めても、Tさんが選ぶのはいつもワンカップ。その理由は、このあとの彼の発言からわかります。
Tさん「俺は明日家に帰るからさ。今晩の分があればいいよ」
しかし、Tさんは明日もその次の日も自宅に帰ることはできません。とはいえ、Tさんの認識では明日自宅に帰ることになっているため、ワンカップを選ぶ彼の判断は正しいというわけです。だからこそ、2リットルを奨めた職員はTさんを否定したり、自身の意見をゴリ押しすることはありません。笑顔で「そうですか」と返答することで、彼の判断を受け止めて支持します。この場はそれで良いのです。

介護者がご本人にカート押しをさせていると誤解される!?
さて、そんなこんなでワンカップの日本酒をショッピングカートのカゴに入れ、レジに向かったTさんと職員。レジで順番を待つ間、職員はTさんの疲労具合を確認します。
職員「Tさん、疲れましたか」
Tさん「そうだな、ちょっとだけな」
職員「少し座って休みましょうか」
Tさん「いや、大丈夫だよ」
職員「それじゃあ、カートを押すのを代わりましょうか?」
Tさん「大丈夫。自分が押すよ」
職員は上記のやりとりにおけるTさんの発言だけでなく、Tさんの表情や顔色、呼吸、歩行・立位の状態を会話しながら確認し、「この後もTさんにショッピングカートを押してもらうかどうか」「休憩を入れるかどうか」などを判断します。今回もそれらを行ったうえで、このままTさんにショッピングカートを押してもらうことを選択しました。もちろん、職員は転倒したときに備えて、いつでもTさんを支えられる距離にいます。
そうこうしているうちに、いよいよレジの順番が回ってきました。すると、店員の方が職員に話しかけてきました。
店員「あなた、ちょっとひどいんじゃないの」
職員「えっ!?」
店員「高齢者の方にこんな重いカートを押させるなんて可哀想でしょ」
職員「あっ…いや…」
店員「あなた介護やってる人でしょ。だったら、高齢者の方には優しくして労わってあげなきゃだめじゃない」
食材を自分で買いに行くのは普通のこと
介護保険制度における施設・事業所の食事のあり方は、利用者の方が考えたり何かをすることを想定してはおらず、施設や事業者側がすべて用意するという「提供型」であり、「給食型」でもあります。
しかし、そんな介護保険制度の中にあってグループホームの食事だけは「自炊型」を想定しています。そのため、支援専門職のサポートを受けながら、入居者の方たちが何を食べるかを考えて買いものに出かけ、その中で街の人びとと触れ合いかかわりあうことができます。さらに調理にも取り組むため、それらを通じて入居者の方同士や職員と協同したり、成果をわかちあったりすることも可能です。
このような自炊型の取り組みは、認知症の状態でなかった頃の入居者の方たちの暮らしでは当たり前にあったことで、特別なことではありませんでした。もっと言えば、要介護状態にない高齢者の方たちの多くは、自分の足で動けるうちは自分の足で街に出かけ、買いものもしています。
なのでTさんは職員の支援を受けながら、「かつての自分の暮らしの中に当たり前にあった」食材調達のための買いものをしていただけなのです。しかし、それを知らない店員の方にとって、御年96歳のTさんは、"優しく労わってあげるべき存在"。だから、「代わりにやってあげなさい」と職員に注意したのです。

高齢者の方に家事を無理にやらせているわけではない
こういった感覚を持つのは一般の方だけに限らず、同業者の中でもいらっしゃいます。筆者がグループホームのホーム長を務めていたときの上司には、「高齢者であり認知症なのだから、買いものや食事づくりは職員がやってあげるべきだ」と猛烈にそこでの実践を否定されました。ほかにも「食事をつくらされたり、掃除をやらされたりして、入居者の方が可哀想だ」と言われたこともあります。
今回の場合、Tさんと買いものをともにした職員はTさんの疲労具合を確認(アセスメント)し、支援方法を描き(ケアプラン)、実行していました。職員はただやらせているわけではないということです。複数人での買いものであれば、一人ひとりの歩行状態や認知症の状態、そのときの気分(感情)などを加味して、職員はその場で支援内容を見立てます。そのうえで、入居者の方同士や入居者の方と職員との間で助け合いを促したり、歩行状態が不安定な人には、荷物を持つことを代わる場合もあるのです。
食事づくりでも、調理に必要な身体・知的能力や技術力は入居者の方それぞれです。なので職員は一人ひとりが能力を発揮しやすいような環境づくりや調理の段取りを行います。やりたくない方には、その都度声かけや環境設定を通じて本人が「やってみよう」と思うような誘い水を投げることはあっても、無理にやらせることはありません。
「一方的にやってあげる」は介護ではない
高齢者だから、認知症の状態だから優しく労わって何でもやってあげる
もっともらしく聞こえますが、筆者の心には響かないどころか、このような介護観が偽善のようにも思えてしまいます。というのも、「一方的に何でもやってあげる」はやさしいようでありながら、要介護状態にある方たちから自分の力でできることを奪うことになるからです。
私たち介護支援専門職の仕事は、介護保険(公金)を使って要介護状態にある方たちを不活性化することでも、廃用に導くことでもありません。かつてその方の暮らしの中にあった"当たり前"を取り戻せるようにすることです。そのためには、「かつての暮らしの中にあった当たり前」が遠ざかってしまいがちな「優しく・労わって・何でもやってあげる」こそ、支援者と要介護状態にある方たちから遠ざけなければいけないと思うのです。