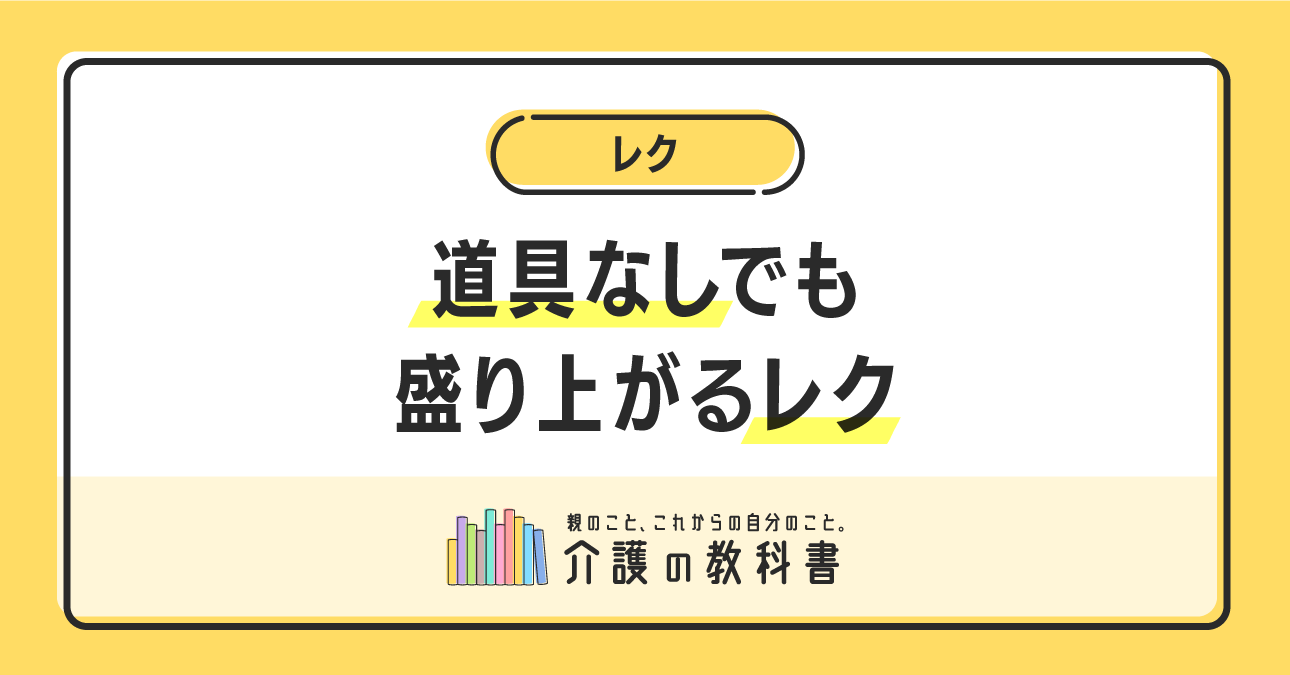こんにちは。特別養護老人ホーム裕和園の髙橋秀明です。
今回は「特別養護老人ホーム(以下、特養)や介護老人保健施設(以下、老健)等施設でのレクリエーション(以下、レク)」についてお話します。利用者の方に対してレクに取り組む施設は多く、日ごと、毎月ごとにプログラムを決めて取り組んでいる施設もたくさんあることでしょう。実際、筆者の働く特養でも、日ごと月ごとにレクや行事を企画し実施しております。
「大納涼会」で家族・地域との繋がりを強固に
筆者が働く特養での最大規模のイベントは「大納涼会」です。これは特養単体のイベントではなく、法人全体のイベントとなります。利用者の方やその家族のみならず、地域住民の方々も多く参加し、総勢1,500人を超える方々が来場される地域でも有数のイベントです。
大納涼会は利用者の方にとって「お祭り」(非日常)を楽しむ機会です。浴衣に着替えて屋台で焼き鳥や焼きそばなどを食べ、お酒やジュースを飲んだり、盆踊りを踊ったりして楽しいひとときを過ごします。これは利用者の方に楽しんでもらうという一面もありますが、「特養の基本方針に応える」という目的もあるのです。特養の基本方針には、以下のように明記されています。
特養基本方針(第二条の4)
特別養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ)、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
この大納涼会以外にも大きなイベントとして「敬老会」を実施しています。このようなイベントが特養の基本方針にある「地域や家庭との結びつき」につながると同時に、地域の方々に「特養という施設の存在や支援」を知ってもらう機会だと思っています。この大納涼会や敬老会がきっかけとなり、地域の方々が「私たちにできることがあれば…」と言ってボランティア活動につながったケースもあるのです。

コロナ禍でも実施した「100歳お祝いの会」
新型コロナの影響を受け、一般的に施設で面会制限やイベント自粛をしているという声を耳にします。そんな中、筆者の働く特養では利用者Aさんの「100歳お祝いの会」を実施しました。Aさんは医師から看取り期(回復が見込まれない状態と医師が判断し、近い将来死が避けられないと思われる状態)であると言われています。
そんなAさんのお祝いの会に、ご家族4人と役所の職員さんが来園。施設からは介護職員や介護支援専門員、筆者、そして法人理事長や施設長も参加しました。来園したご家族は言いました。
「新型コロナが流行しているからお祝いの会は諦めていました。でも、こうやって母だけの、母のための会を開催してくれたことは一生忘れません。制限がある中でこのように特別な日をつくってもらえて、常日頃から母が大事にされていることが身に染みてわかりました」
「新型コロナ対策だから」という理由で今回の機会を中止したとしても、家族はきっと理解を示したでしょう。しかし私たち専門職に求められることは、「新型コロナ対策を行いつつ、できることを考えて実行に移すこと」だと思います。人生のラストステージを託された私たちだからこそ、「残された人生を有意義だと感じてもらえるように、あきらめずに支援をすることが大事」 だと感じた1日でした。
僕が介護の仕事をし始めた17年前は、1人のためにお祝いの会をするということはありませんでした。施設のイベントとして誕生日会を開催していましたが、それは月の終わりにその月の誕生者をまとめて祝う形式的なもの。でも時代は変わり、今では多くの施設において「本人のため」にお祝いをすることが通常となっています。
レクの目的は自立した日常生活を獲得してもらうこと
施設職員が行事やイベントを企画し、実行する意味や目的は何でしょうか。僕がまだ介護職員だった15年以上前のお話です。当時、僕は深く考えもせず、とにかく「利用者・入居者に楽しんでもらえるように」という非常に曖昧で情緒的な考えから、施設のレクに力を入れていました。
そのうちレクをすることが目的となり、職員だけが盛り上がって、入所者・利用者はただその場所にいるだけ(強制的管理的に参加を強いられる)という状況が生まれてしまったのです。「生活の主体者は入所者・利用者」とは名ばかりに、職員が一方的に「してあげる人」、入所者・利用者は「してもらう人」という構図に陥っていました。

そういったレクに対して「これで良いのか」と疑問を感じ、職員たちと介護保険法や僕が当時働いていた老健の基本方針を徹底的に読み込み・考え・実行をしました。
基本方針にはこのように書かれていました。まず、「起きる→着替える→食事をする→歯磨きをする→お風呂に入る→着替える→寝る」という一般的な日常生活を、まずは入所者・利用者自身が可能な限り自分の力(身体・知的能力)を使ってやり遂げられるように支援を変更。そのうえでレクのあり方も見直していったのです。
利用者の方が主体的に参加できる体制へ
特養の基本方針に以下の一文があります。
「入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って」
この方針に従って、まずは「レク内容に選択肢があり、入所者・利用者が選択する」ことに尽力しました。つまり、利用者の方が「やってみようかなぁ」と可能な限り興味・関心を持ち、主体的に参加できるように仕掛けていくということです。
囲碁や将棋、カラオケ、映画などが代表的なものですが、これらは利用者の方から職員が聞き取りをして選択肢を用意しました。当然ながら利用者の方はそれぞれ個性があります。1人で映画を観る人もいれば、小グループになってお互いにコミュニケーションを図りながら楽しんでいる、レクの選択肢を増やすことでそんな風景がたくさん見られるようになったのです。
特養や老健におけるレクは「主体的に能動的に」がキーワードと考えます。介護施設でのレクは、一般的に「全員で歌を歌う」「体操をする」などがイメージとしては強いですが、利用者の方が選択肢の中から選択をするという風に変わってきています。今回の記事が施設を選ぶ際の参考になるとうれしいです。