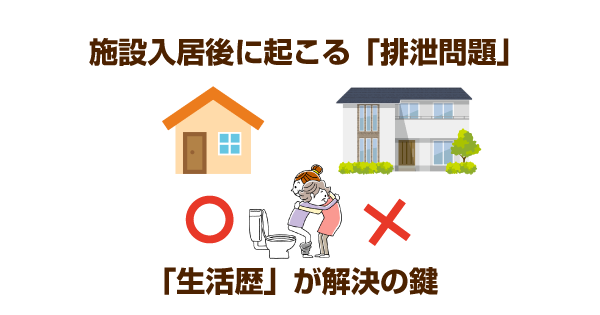皆さん、こんにちは。認知症支援事業所 笑幸 代表の魚谷幸司です。
認知症とかかわりの深い状態の1つが「閉じこもり」がです。認知症と閉じこもりの関係のパターンには以下の2種類があります。
- 認知症になった後で閉じこもる
- 閉じこもるようになった結果として認知症になる
今回は、割合としては多く見られる後者の「閉じこもりが原因で認知症になる」理由や、介護する家族の向き合い方について考えていきたいと思います。
コミュニケーションが減ることで語彙力・会話力が低下
まず、どうして「認知症になってしまうか」ですが、理由としては「家という閉じられた空間」にずっといることが大きく関係しています。家という閉じられた空間では、人とのかかわりは家族など限られた人だけになってしまうからです。なぜこれが認知症になるトリガーになってしまうのか、説明していきます。
かかわる人が家族だけになることで、会話の内容が「わかる範囲のありきたりなもの」になってしまいます。その会話のなかでは決まった言葉だけでことが足りてしまい、話が広がっていかなくなるのです。この状態で普段とは違う場面に遭遇したとき、そのときに応じた適切な言葉を発することが難しくなるという支障が出て認知症となっていきます。
言葉に限りませんが、「人は使わないと忘れていく」ので注意が必要です。

認知症の症状「被害妄想」により家族を疑ってしまう
認知症の方々に多く見られる症状として「被害妄想」があります。この被害妄想ですが、一番被害を受けるのは家族である場合が多いです。普通に考えれば、本人にとって最も身近で頼れる存在である家族がなぜ疑われるのでしょうか。疑われた家族からも「なぜ私が?」という声をよく聞きます。
そこで想像して欲しいのですが、大切にしているものをなくしたとき、皆さんならどうしますか。まずは「自分で探し」、そのうえで「知らないと思いながらも家の人に聞き」、そして「その日のことを思い出して考える…」。このような行動をするのではないでしょうか。それは、家ではない別の場所や、家族以外の人とかかわることができているからなのです。
しかし閉じこもりになると、疑うつもりはなくても良くも悪くも唯一かかわりのある家族に目が向いてしまいます。
それがしっかりされているときならまだ良くても、もの忘れが始まると自分でなくしたとは思えず、どうしても家族を疑ってしまうようになるのです。それは認知症の症状であり、決して悪気があるわけではありません。閉鎖的な空間の世界だけで暮らしているとどうしてもそうなってしまうのです。
家族以外の人とかかわってもらう
認知症の原因となりうる「閉じこもりを防ぐための向き合い方」をする必要があり、具体的には外出してもらう必要があるでしょう。しかし、これまで閉じこもりだった人に外出してもらうには、それなりの目的が必要です。そこで大切なのは、家族以外の人にできる限り多くかかわってもらうことです。
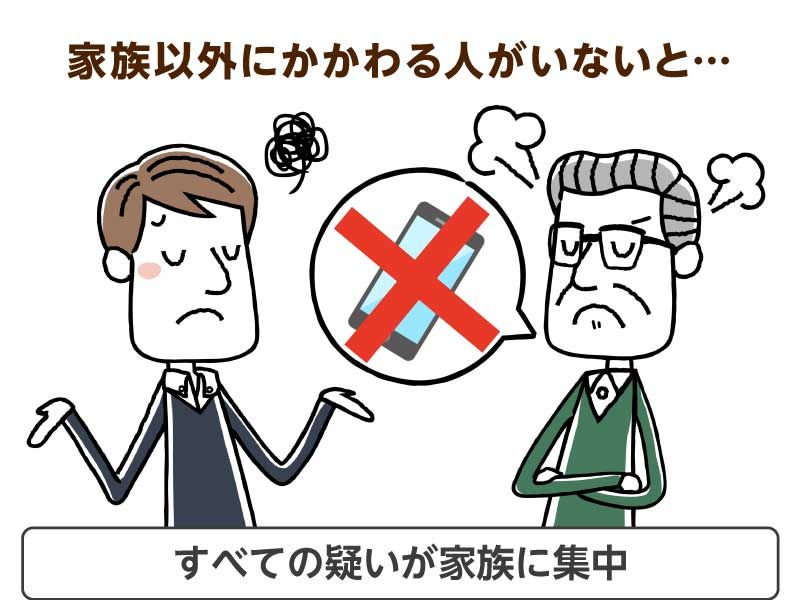
デイサービスやデイケアなどの「通いの場」を活用
1つの例としては、ただ散歩に行くのではなく家族以外の第三者と散歩に行って外食をするなど、楽しみとなる目的を設けることが重要です。その意味で効果的なのが、デイサービスやデイケアといった通いの場に赴くこと。そこでは職員をはじめ、いろいろな人とかかわることができます。
馬の合わない人と出会って行くことを嫌がる場合もあるでしょう。そのとき、家族はその気持ちを受け止める向き合い方をして欲しいのです。閉じこもりの状態でずっと顔を合わせていたときは余裕がなかったと思います。しかし、短時間でも離れることで客観的に相手をみることができるようになり、少しずつ余裕も生まれてくると思います。
通いの場へ赴くことは、本人だけでなく家族にとっても良い結果につながります。この結果から家族の認知症の人に対する対応が良くなり、相手も穏やかに過ごしていくことができるというわけですね。