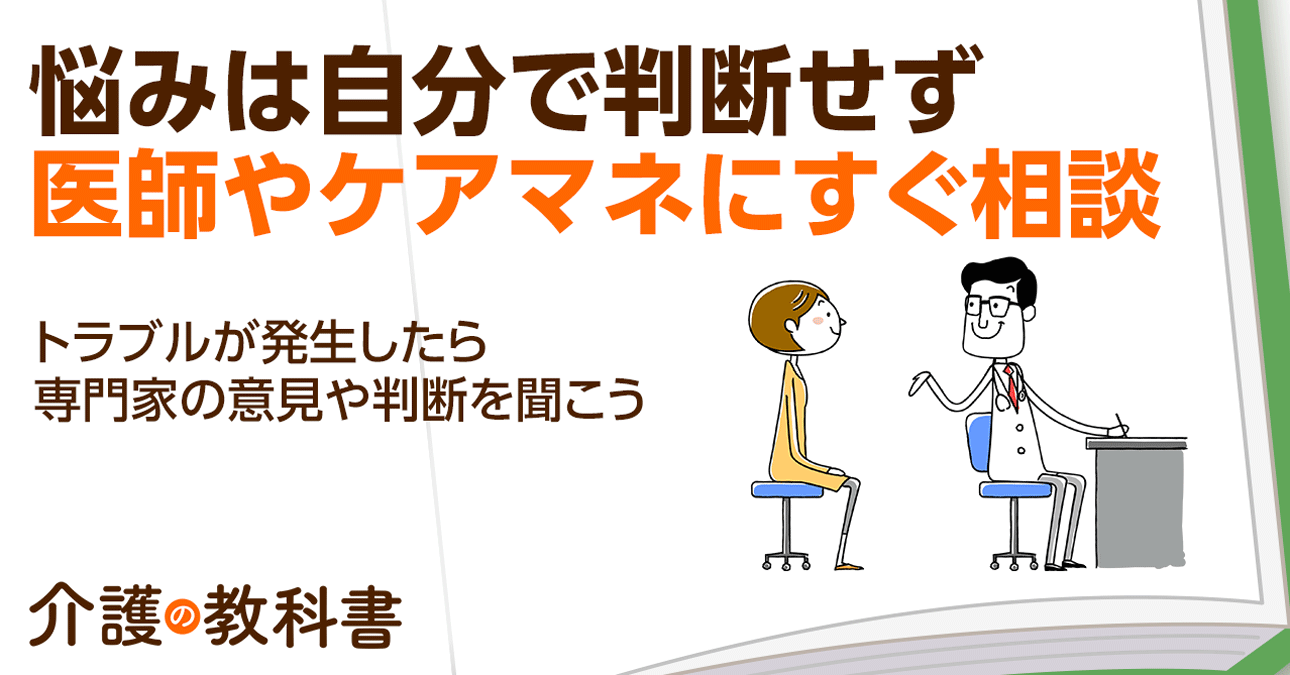株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。今回は前回の続編で、「支援を断る利用者への声がけ」についてです。例を交えて紹介していきますので、よろしくお願いいたします。
いら立ちの裏には「利用者に問題がある」という意識がある
第145回でお伝えした、利用者の方へのリスクやトラブルを助長させる職員の特徴は以下の通りです。
利用者の方に「大声で叫ぶ」
利用者の方と「言い争いをする」
大声の制止も言い争いも利用者の方を悪い方向へ刺激しますし、これらを続ければ続けるほど職員は冷静さを失っていきます。それと同時に、いら立ちや腹立たしさも増していきます。
なぜそうなるのかというと、いら立ちや腹立たしさの根底に「利用者の方が自分(支援者側)の思い通りにならない」という思いがあるからです。支援場面では支援者が利用者の方に対して食事や入浴、排せつ、リハビリなどに「支援者が誘う」ことが多く、その誘いを「利用者の方が断る」ことがよくあります。
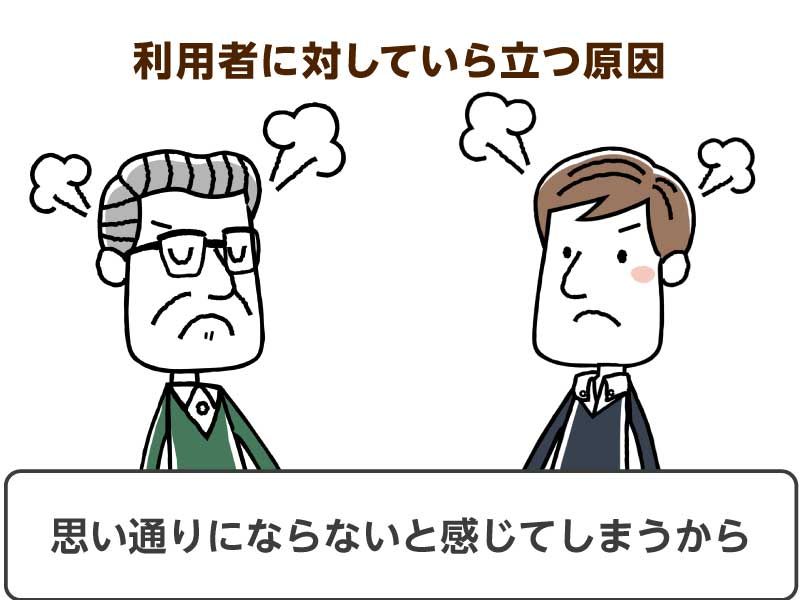
「誘ったけど、断られた」というとき、介護の業界でよく使われるのが「拒否」という言葉です。「声がけしましたが、入浴を拒否されました」、「入浴拒否する○○さん」といった言葉の使い方をするときがあります。
僕はこの「拒否」という言葉の使い方に、「せっかくお風呂に入れてあげようと思ったのに、断るなんて…」といった支援側の意識、もっと言うと、断った利用者の方は「悪者」=断った利用者の方に「問題がある」と感じてしまいます。そしてそういった意識には、前述した「利用者の方が自分(支援者側)の思い通りにならないことからのいら立ち」などと相通じるものがあるように思うのです。
本人の納得する「必然性」を盛りこむ
僕がホーム長を務めていたグループホームに入居していたAさん(女性)は、認知症の状態にあるため、前に入浴した記憶はなく入浴への意思表示もしない方でした。なのでAさんには、職員が入浴に誘う(入浴を促す)支援が必要です。
職員とAさんの会話
職員「Aさん、お風呂に入りませんか?」
Aさん「お風呂?入りたくないわ」
ここまではいつも通り。Aさんを入浴に誘っても、必ず断ってくるのです。
職員とAさんの会話
職員「そうですか。でも、どうして入りたくないんですか?」
Aさん「腰が痛くてしょうがないんや」
職員「あら、そうなんですね。でも、それだったらお風呂に入った方がいいですよ」
Aさん「なんでや?」
職員「お医者さんが、腰が痛いときはお風呂に入ってあたためた方が良いって言ってましたから」
Aさん「医者がそう言ってたんか?」
職員「ええ。だからお風呂に入って、腰を楽にしましょうよ」
Aさん「そうやなぁ。医者がそう言うてたんなら入るかなぁ」
そして、この日はこのままお風呂に入ったAさんでした。
別の日、いつも通りに入浴の誘いをAさんは断りました。理由は、「明日帰るから」ということでした。
職員とAさんの会話
職員「そうですか。明日、帰られるんですか?」
Aさん「そうやぁ。明日、息子が迎えに来てくれて、帰るんや」
職員「息子さんが迎えに来られるですか。だったら、お風呂に入っていただきたいんですけど…」
Aさん「なんでや?」
職員「実は息子さんから『迎えに行くときはお風呂に入っておいてほしい』と頼まれているんですよ」
Aさん「うちの息子にそう頼まれてるんか?」
職員「ええ、そうなんです。なので、お風呂に入っておいてもらえませんか?」
Aさん「息子がそう言うてるならしゃあないなぁ。それやったらお風呂入ろか」
Aさんが職員からの入浴の誘いを断る理由のほとんどは、「腰が痛いから」か「明日帰るから」でした。そんなAさんにとっての「お風呂に入る必然性」は、お医者さん、もしくは息子さんが、「お風呂に入るように言っている」だったわけです。そのことを知る職員は、いくつかの選択肢を考えたうえでAさんを入浴に誘っていたわけです。
臨機応変な対応には「断る理由」の把握が必須
そのときによって異なる「理由」を提示するAさんに対して応じられるように、職員は「引き出し」を複数持っているのです。この「引き出し」を複数持つためには、断る理由が何なのかを知る必要があります。
入浴を断りたい理由としては、以下の通りです。
- 今は入りたくない
- 気になることがある
- 気に入らないことが起こった
- 他人に裸を見られたくない
- そもそも風呂を好まない
- 誘われ方(態度や言葉づかい)が気に入らなかった
- 誘った人が気に入らなかった
- 誘った人の言っていることがわからなかった など
また、本人にとっての事実としては、下記の3つがそれにあたります。
- 昨日入った
- 具合が悪い、調子が悪い
- この後すぐ家に帰る など
上記のように、断る背景には、何かしらの理由があるはずです。そういった背景へのアプローチもないまま、「誘いを断った=入浴することを拒否された」と判断するのは、おかしなことではないでしょうか。ましてや、誘った(支援者)側に原因があるのであれば、なおさらだと思います。
「引き出し」を複数持つというのは、ここまで記した「誘いを断られた際の声がけの数」だけを指しているものではありません。利用者の方への対応がうまい職員は、同じ利用者の方でも、そのときの体調や環境などが影響して生ずる「心身の状態」や様子の違いに対し、声がけの内容を変えたりするのです。
逆に、利用者の方への対応が下手な職員はどんな心身状態でも、またはどの利用者の方でも同じパターンで対応し、自分の唯一の型にはめ込もうとします。そして、自分の型にはまらない利用者の方に苛立ったりすることも多いのです。相手やそのときの状況によって、自分の対応を変えられる=「引き出しを複数持つ」ことが、介護現場では欠かせないのです。

断られたら一度時間を置くことも大事
さて、改めてAさんの入浴時に話は戻ります。
職員とAさんの会話
職員「Aさん、お風呂に入りませんか?」
Aさん「お風呂?入りたくないわ」
ここまではいつも通りです。入浴の誘いを断る理由は「腰が痛いから」か、それとも「明日帰るから」なのか、どれだと思いますか?
職員とAさんの会話
職員「そうですか。でも、どうして入りたくないんですか?」
Aさん「今日は、風呂に入るような気分やないんや」
Aさんが入浴を断る理由が、「ただ入りたくないから」である日も当然あるのです。そんなときは、「そうですか」とAさんの気持ちを受け入れ、いったん時間を置くことにしていました。これはAさんへの入浴の誘いに限らず、グループホーム全体の支援の考え方の1つとして、「今、このままであっても差し支えないことこのままに(またはそのまま)にしておく」こととしていたからです。
今回のAさんのケースでは、「そのときにお風呂に入らなくても病気になるわけではない」から、無理に勧めずに、少し時間をおいてからまた誘ってみることにしたわけです。このように、「押してダメなら引いてよう」という対応も、ときには必要なのです。