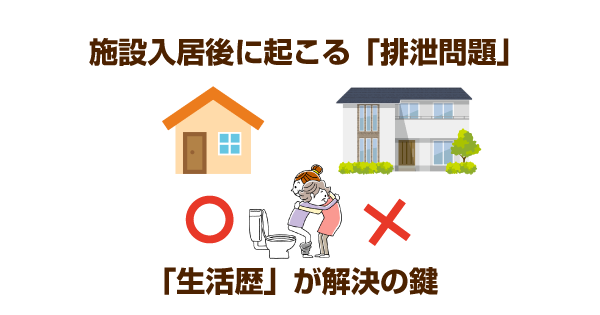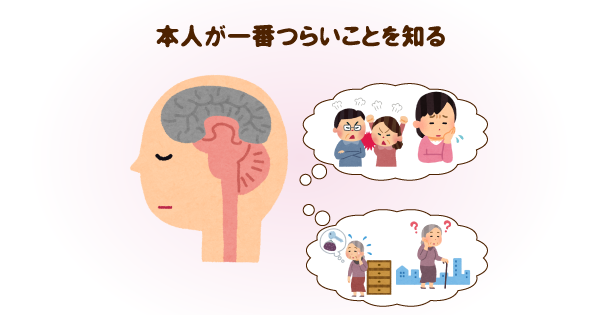こんにちは。
デイサービスで看護師として勤務している、認知症LOVEレンジャーの友井川愛です。
今回は、認知症の方が「家に帰りたい」と帰宅願望を示したときに、どう考えて接するべきかについてお話します。
「帰宅願望」は単なる「問題行動」と捉えるべきではない
認知症の方のなかには、帰宅願望を頻繁に示す方がいらっしゃいます。
そのような方は、施設やデイサービス、ご自宅にいても「家に帰る」「仕事に行く」「学校に行く」とおっしゃることがあるのです。
こうした行動は、介護するご家族や施設職員からすると、「問題行動」として認識されやすいと思います。
介護する側からすると、「家に帰る」と認知症の方から言われたとき、「こんなに一生懸命ケアを頑張っているのに」と思うかもしれませんね。
なんだか自分の努力を否定されたような気持ちになり、認知症の方に対してきつい口調になったり、最悪の場合は暴力を加えてしまったりする可能性もあります。
しかし、本当に帰宅願望を示すのは「問題行動」でしょうか。
私はそう捉えるべきだとは思いません。
「帰宅願望」を訴えるのは、「介護される自分を拒否」したいから
帰宅願望は、単に「認知症の周辺症状」で済まされることではありません。
なぜなら「帰宅願望」を示しているということは、「介護拒否」を示しているとも考えられるからです。
認知症の方が「介護拒否」するのは、「単にケアを拒否している」とだけ考えて良い問題ではありません。
介護拒否の本質とは、若い頃の自分とは違う、老いた自分(かつてできたことができない・物忘れが多くなる)を受容できないという「自分自身」への拒否であると同時に、「介護される」自分への拒否なのです。
要は、「介護関係」への拒否だと考えられます。

これを踏まえると、例えば「デイサービスで介護されている自分」や「何もしないでこの場にいる自分」に対しての拒否から、「帰宅願望」という行動症状につながっていると考えられます。
認知症のタイプに「回帰型」があります。
このタイプの方は「家に帰る」「職場に帰る」などと言い、目的を持って出ていきます。
こうした方は、介護されている自分への拒否から過去の自分の役割を持ちだしたり、「この場所にいたらいけない」という焦燥感から帰宅願望をみせたりすると私は考えます。
「家に帰る」「会社に帰る」と言うことが多いようですが、本当にご自分の家や会社に帰りたいのではなく、「自分のいるべき場所」に帰りたいという意味があるのです。
認知症ケアの際に重要な3つの原則
では、もし実際に認知症の方が帰宅願望を示したとき、どのように対応すれば良いのでしょうか。
これからご紹介する認知症ケアの原則を、理解して実行することが重要なのではないかと考えています。
3つの原則とは、「物的環境を整える」「役割を感じてもらう」「信頼関係をつくる」というものです。
- 物的環境を整える
- 在宅の場合…過去にしていたこと、それに近いことができる環境をつくるなど
施設の場合…その方の個性が発揮できる場所をワンコーナーつくるなど - 役割を感じてもらう
- 認知症の方の現在の身体、精神状態に応じてできる範囲内で役割を果たしてもらう(周囲から認められることで居場所があると感じられる)
- 信頼関係をつくる
- 介護関係ではない信頼関係をつくる(認知症の方は介護関係から逃げたいと考えている。これを理解せずにケアを受け入れるよう説明すると、ますます介護者の立場を強調してしまう結果になる)
これらの原則を実行して認知症の方が安心できる環境をつくることが非常に重要です。
「一人の人間として」認知症の方とかかわって、信頼関係をつくろう
上記の環境づくりのなかで最も大切なのは、「信頼関係をつくること」です。
これは、「ケアをする介護者自身が介護関係から脱却して、一人の人間として認知症の方とかかわることで信頼関係を構築すること」だと私は考えます。
では、実際にどのようにかかわるのが良いでしょうか。
頻繁に家に帰りたいと訴えるAさんのケース
以前、私が勤めていた施設を利用していたAさんのケースで考えてみましょう。
Aさんは70代の女性です。
軽度の認知症の症状がみられるようになり、日中デイサービスを利用するようになりました。
息子夫婦と一緒に暮らされているのですが、日中は夫婦ともに働いていることからAさんが心配になり、ご家族がデイサービス利用をAさんに勧めました。
このとき、ご家族はAさんを心配して良かれと思い、デイサービスの利用を決めました。
しかし、Aさん本人の気持ちを聞かずに話が進んでしまったことで、Aさんは自尊心を傷つけられ、「自分が家族から見捨てられた」「自分はもう役にたたないから施設に行かされている」と感じていたのです。
このため、Aさんはデイサービスに来たとしても、自らの意思ではないので、すぐに「息子がお腹を空かせて待っている」と言って出て行こうとされる訳です。
そして、この「腹を空かせている」とは、息子さんが子どものころのことです。
このことから、Aさんが子育て真っ最中だった時期(家族から頼られて役割が明確に感じられていた時期)に帰ろうとしていることがわかりますね。
しかし、残念ながらデイサービスの職員は、このことを洞察したうえでAさんにかかわれていませんでした。
そのため、出て行こうとするAさんに対して、職員は、なんとか説得して施設に時間内は引き留めようと声かけしていたのです。
こうなったのは、職員の自分は介護者であり、Aさんは認知症高齢者、利用者であるという思考があるからと私は考えます。
こうした対応は職員という立場で説得という方法でかかわっているだけで、本質的な問題から逃げているのです。
私はAさんが施設の玄関から出ていった際、「私も買い物に行くので」とAさんに声をかけ、一緒にしばらく歩きました。
そのときも、天気や食べ物の話などのたわいもない普通の会話をしただけです。
するとAさんは、出て行くときには険しい表情でしたが、歩いているなかで穏やかな表情になりました。
最後には、私が「料理が苦手だ」と話すと、「施設に帰ってつくり方を教えてあげる」と言い、自らデイサービスに戻られたのです。
このときAさんに変化が起きた要因は、まず私が職員として引き止めなかったこと。
加えて、介護関係から降りて職員ではなく一人の人間として向き合ったことで、Aさんと信頼関係が構築されはじめたことでした。

それからというもの、Aさんは職員やほかの利用者に料理の作り方を教えるという役割を楽しむようになりました。
ご自分の居場所で安心して過ごすようになり、デイサービスに来ても落ち着かれるようになったのです。
認知症の方は常に不安や焦燥感を感じやすい傾向にあります。
そのため、私たち介護者が、認知症の方が安心して過ごせる環境を整えることが、非常に重要なのです。