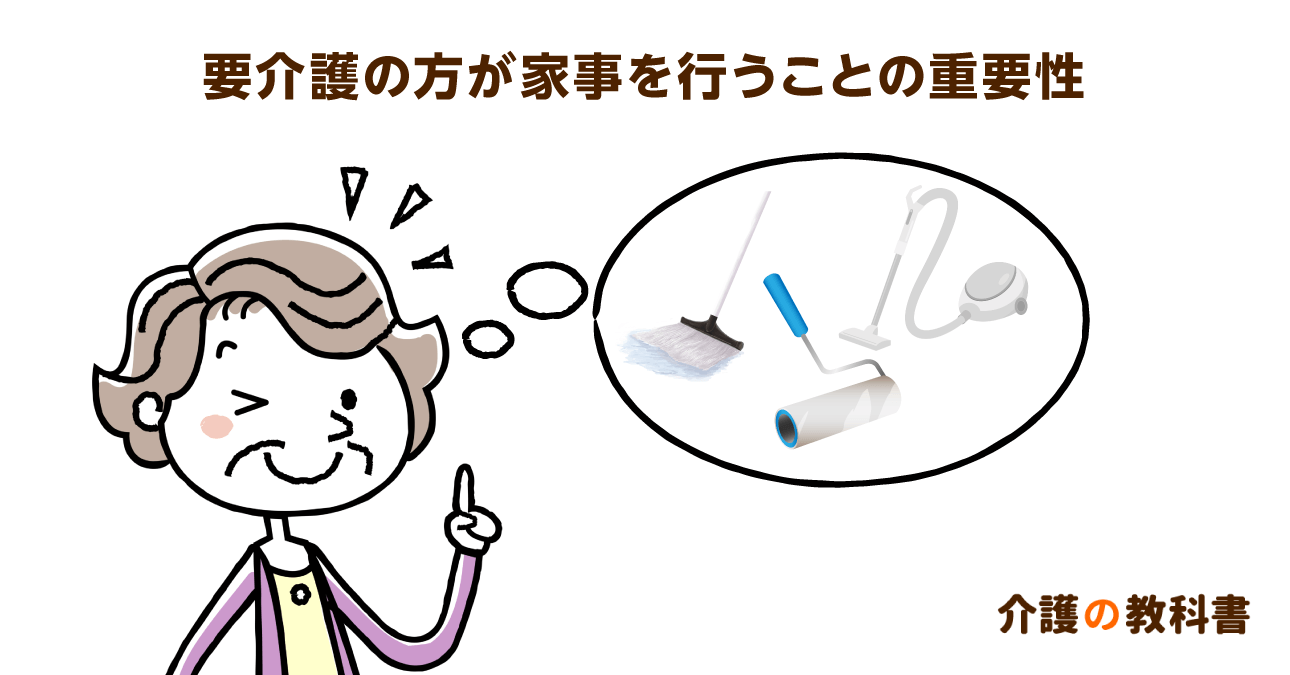みなさん、こんにちは。認知症支援事業所 笑幸 代表の魚谷幸司です。
介護が必要な高齢者が生活する施設には、いくつかの種類があります。
なかでもグループホームは、認知症の方だけが入居する施設で、ほかの施設とは支援の特徴に違いがあります。
そして今、介護が必要な高齢者が増えていくなかで、グループホームの在り方も従来のものとは変わりつつあるのです。
今回は、グループホームの成り立ちから、これまでの軌跡、そして現状について、約10年にわたって働いていた私の経験を交えて話をしたいと思います。
グループホームの成り立ち

みなさんは、グループホームの正式名称と、グループホームが生まれた経緯をご存じでしょうか。
グループホームの正式名称は、「認知症対応型共同生活介護」と言います。
多くの介護施設では、例えば特別養護老人ホームの正式名称である「介護老人福祉施設」などのように、名称の最後に“施設”とつきます。
しかし、グループホームはその正式名称からもわかるとおり、介護が行われる“共同生活の場所”なのです。
現在のグループホームのモデルとなったのは、1940年代から高齢者福祉に力を入れているスウェーデンのグループホームです。
私が学生だった25年ほど前には、まだ日本にグループホームは数ヵ所しかありませんでしたが、介護保険が始まった2000年4月より急増し、現在に至ります。
少人数制で行き届いた認知症ケアができるグループホーム
グループホームとは、認知症の人が少人数で生活をする施設で、自分でできることは利用者本人にやってもらいながら、できないことは職員の手を借りるという形態の施設です。
大きな施設でたくさんの高齢者に、画一的な介護をするのではなく、少人数という強みを活かして個々人の状態に合わせた介護をしていく支援のスタイルが特徴的です。
私自身、そういったグループホームの支援方法を学生時代に知識として学んでいましたが、グループホームでいざ働き始めると、しばらくは戸惑うことばかりでした。
グループホームは、生活をしているすべての人が認知症で、基本的には1つのフロアに9人しか生活していません。
私はグループホームに勤める前に、寝たきりの人も介護が必要な人も50人以上いた特別養護老人ホームで働いていましたが、時間の流れが明らかに違っていました。
私が勤めて間もない頃に言われたエピソードを1つ紹介します。
その日の私は、グループホームにまだ慣れておらず、何をして良いかわからないものの、何かをしなくてはという思いからフロアを行き来していました。
そしてそれを見ていた先輩職員が、「何もないのに何をウロウロしているんだ、そこで一緒にテレビを見ているだけで良いんだよ」と声をかけてきました。
それからしばらく、私の仕事は一緒にテレビを見ること、一緒に話をすること、一緒に洗濯物を畳むことでした。
それまで、絶えず時間に追われながら介護をしてきた私は、「ここに何をするために来ているんだ」という思いでしたが、この支援の方法こそがグループホームなのだと知ったのは、それからしばらく経ってからになります。
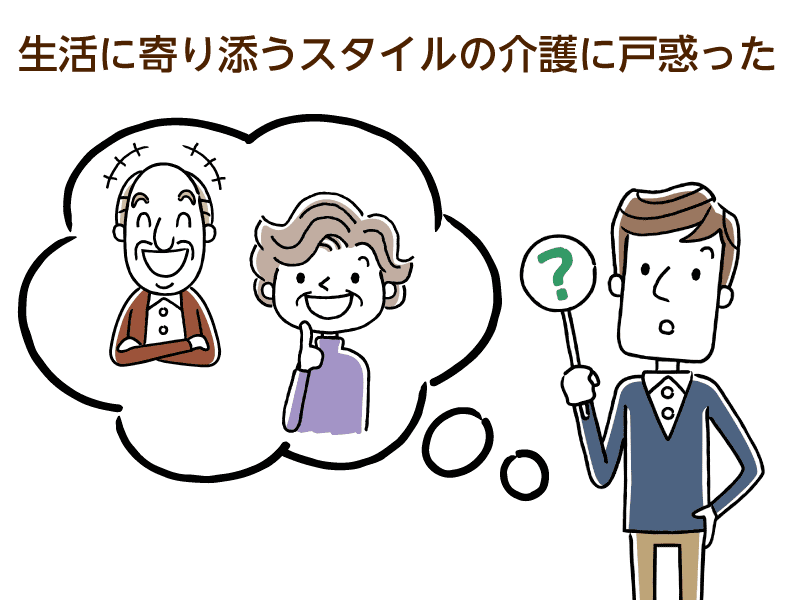
慣れてきた頃には、これこそ自分が求めていたゆっくりと一人ひとりにかかわることができる理想的な支援だと思えるようになりました。
認知症の進行度が悪化すると、ケアが行き届かなくなる
さながら大家族のように、できないことは助け、一緒にご飯を食べ、風呂に入り、遠足に行き、時にはケンカもし、そんな日々が今となっては良い思い出です。
しかし時間の経過とともに、当たり前ですが、できることが少なくなる、認知症が進む人が出てきます。
初めはそれが数人であっても、気がつけば多くの人が、認知症が進行している状態になっていました。
それは「できることはやってもらう」という、グループホームの本来の趣旨とはかけ離れていく状態でしたが、だからといって退居してもらうわけにはいきません。
結果として手のかかる多くの人に時間をとられ、申し訳ないと思いながらも、ある程度できることがある方には、コミュニケーションをとる時間が短くなっていったのです。
その結果、そうした利用者の機嫌を損ねてしまい、対応が必要となる悪循環に陥ったのです。
この時期には、不適切な表現かもしれませんが、ミニ特別養護老人ホームといった感じでした。
看取りの対応を求められるようになっている現状
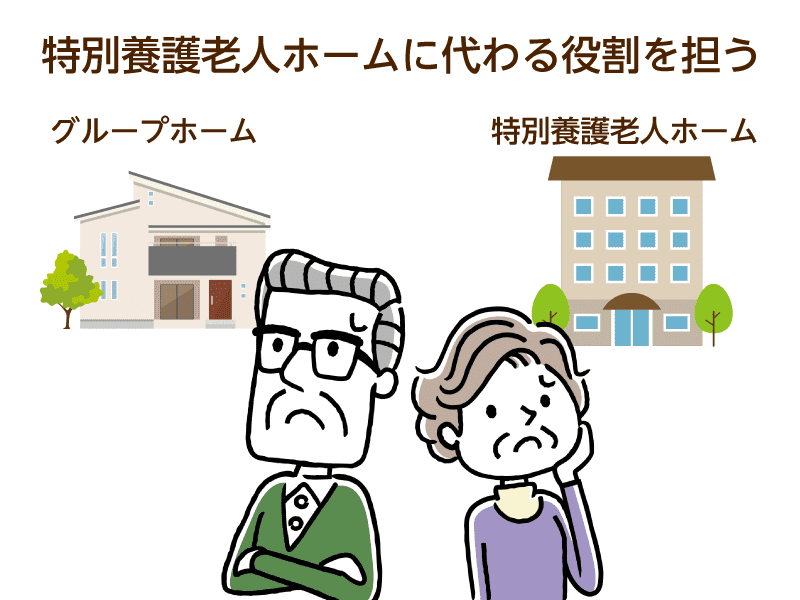
しばらくして、国は強制はしないものの、グループホームで看取り(亡くなるまでの介護)の対応をするように方針を転換しました。
なかなか入居することが難しい特別養護老人ホームに代わる役割を想定していると考えられます。
さほど多くない限られた職員の数で、重度の認知症の方々を看取るまで対応するのは正直とても大変でしたが、思わぬ副産物もありました。
看取りをする度に、働いている者が成長するということです。
人が老いていき、やがて亡くなるという過程を見ていくのは、介護職にとって何にも勝る勉強になります。
全国の多くのグループホームでは、ここまでで説明してきたような毎日が繰り返されているのです。