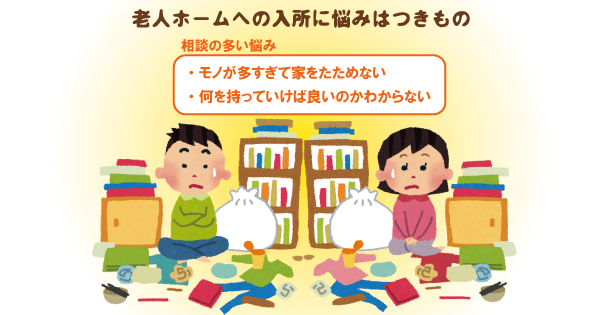株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。僕は24年間の介護業界での仕事を通して多くの高齢者と接し、介護施設のいろいろな現場・実態を目の当たりにしてきました。
今回は、そんな“僕が見てきた介護施設”と“認知症介護”をみなさんに知ってもらいたいと思います。
けっこう過激な内容ではありますが、目を背けずに認知症介護と向き合っていただきたいです。ぜひ最後まで読み進めてください。
僕が見てきた過去の認知症介護

1993年。今から24年も前のこと。19歳だった僕は福祉専門学校の学生として、実家のある市内の特別養護老人ホーム(以下「特養」)に2週間の現場実習に赴いた。
生まれてはじめて足を踏み入れた特養。そこに入所する人たちを見て、僕は不思議に思った。男性は坊主かスポーツ刈り、女性はサイドも後ろも短く刈り上げられている。100名の入所者の人たちが、みな同じ髪型なのだ。
そんな実習初日から抱いた疑問を施設内を案内してくれていた生活指導員(現在は「生活相談員」という)に問いかけると、「入所者の人たちの髪の毛は職員が手入れするのが大変だし、髪が洗いやすいからみんな短髪にしてもらう」、のだと言う。そして、その後すぐに知った。この、一同に短くカットされた髪型が「特養カット」と言われていることを。
そして一律は髪型だけではない。多くの男性は青のジャージ、女性はエンジ色のジャージ。服装までもが同じなのだ。
そんな中、認知症(当時は「痴呆」という呼称)の状態にある人たちのほとんどはつなぎ服を着ていた。ファスナーが背中にあって手が届かないようになっているつなぎ服や、両足と胸元のファスナーがお腹の部分で合流しそこに鍵をかけるタイプのつなぎ服など、一度着用したら(させられたら)自分で脱げないさまざまなタイプのつなぎ服があり、「おむつを外すから」「便を弄るから」と否応なしに認知症の状態にある人たちはそのつなぎ服を着せられていた。
次に驚いたのは食事の風景だった。そこで見たのは、「こうしないと食べない」「食事介助に時間がかかる」からと、職員がご飯の上にすべてのおかずを乗せて、みそ汁をかけてぐちゃぐちゃにかき混ぜ、それを食べさせられている認知症の状態にある人たちの姿だった。中には、「薬を飲まないから」と、粉薬をもご飯にかき混ぜられている人もいた。
認知症介護の過去 認知症が精神疾患と判断されたことも…

僕が実習に赴いた特養は、「65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者」のための施設として、1963年の老人福祉法制定とともに誕生しました。
当時、認知症は精神上の障害とされていたそうで、認知症の状態にある人たちも特養に入所する対象に含まれていましたが、精神疾患とされた認知症の状態にある人たちは治療・医療の対象とされ、多くの人が精神病院に入院して(させられて)いたそうです。
また、介護保険制度(サービス利用は利用者と事業者との契約)となった現代とは違い、当時の特養は、行政が入所を決定する市町村の措置です。
そこに1964年9月12日「精神障害等、手のかかる老人は措置せずともよし」とする厚生省からの通達(老人福祉法第11条第1項第3号の特別養護老人ホームへの収容の措置について:昭和39年9月12日社老第28号)が出されたため、精神障害などとされていた認知症の状態にある人は特養の入所対象外とされてしまいます。
当時のことが記録された雑誌のコラムを読むと、「なんでこんな状態になったのか?原因もわからず、相談できる場所もない」、「特養には入れない…座敷牢に閉じ込めるか、精神病院か老人病院に入れるか」。そんな家族の声が書いてあったのが忘れられない。
この苦しみは、1987年に厚生省が「老人ホームへの入所措置等の指針について(1987年1月31日社老第8号)」を通知し、特養への入所措置が見直されたことで、認知症の状態にある人が特養に入所するのが当たり前になるまで続きます。制度化され、国民(市民)の誰もが必要となれば利用(入所)できるはずの特養だったにもかかわらず、当時の認知症の状態にある本人とその家族は、20年以上「特養には入れない」ということに苦しんだわけです。
入所前面接で出会った2人の高齢者
今から20年前の1997年。新規開設する特養の生活指導員だった僕は、施設が開設するまで毎日のように入所を予定している人たちの入所前面接を行っていた。
- チヨジさん(男性)
- 親類の家に身を寄せて暮らしているという彼に会いに行くと、出迎えてくれた親族の方が「チヨジはここ(母屋)にはいません」、「こっちです」と彼のもとへ案内してくれた。「納屋」。母屋から少し離れた場所にあるそこにチヨジさんはいた。
- 真冬だったが暖房器具はひとつもなく、外風が吹き込む中、使い古した一組の布団にくるまって彼は寝ていた。
- 便をまき散らしたり、大声をあげたりする。止めに入れば暴れ、殴りかかってくる。親類の方たちは「自分達には手に負えない」からと、チヨジさんを納屋に移したそうだ。ちなみに親類の方が彼の顔を見るのは、1日2回食事を運んだときだけだという・・・。
- リンさん(女性)
- 彼女が入院している精神病院を訪ねてみると、案内された病室はカギがかけられた鉄製のドア。その先に、20畳ほどの大部屋が拡がっていた。尿臭、便臭が漂うこの病室(大部屋)は、2つある窓には鉄格子、畳みは擦り切れ、あちらこちらに何度も尿や便を拭き取った後が残っていた。
- そこには、男女問わず8人ほどの痴呆(当時の呼称)の状態にある人たちがいた。「あ~っ、あ~っ…」と叫び続けている男性。四つん這いになって部屋中を動き回っている女性。呼吸をしているのかと疑いたくなるほどに薬を大量に飲まされ、眠っている人もいた。
- そしてリンさん。小柄な彼女は正座する足を崩すことなく、口からヨダレを垂らし、鉄格子の窓をボーっと見つめている。僕がどんなに声をかけても、彼女は返事どころかちょっとの反応もしてくれない。それどころか、声をかける僕に、目線すら向けることがなかった。
昔は施設入所の選択肢があまりなかった でも今は少しずつ認知症の理解が進んできた
時はまだ介護保険施行前の措置入所の時代。前述したとおり、僕が生活指導員だった1997年当時は認知症の状態にある人が特養に入所することは当たり前になっていましたが、自分で入りたい施設を選ぶことは本人も家族もできません。利用(入所を希望)する側に選択肢がなく、自己選択ができなかったのです。
また、僕が勤務していた特養の地域範囲である市町村で作成した入所待機者(措置)名簿に記載された人たちの多くが、精神病院や老人病院に入院しているか、1986年の老人保健制度改正によってできた老人保健施設に入所していました。
当時は、認知症の状態であっても可能な限り自宅で生活することを支援するための訪問、通所、一時宿泊型(短期入所)施設の数も少なく、自宅で生活することが難しくなると特養しか入居型施設がないと言えるほど、入居型施設の選択肢(種類)も乏しかったからです。
みなさん、いかがだったでしょうか。目を背けたくなる内容もあったかもしれませんが、20年前に僕が実際に目の当たりにしたものです。
今では、認知症の状態にある方が暮らす場である“認知症対応型共同生活介護(グループホーム)”が全国に1万3,000ヵ所もあり、その他の入居型施設の種類も一般の方からすれば「どれがどんな施設だかわからん」と言えるほど多くあります。
また、介護保険制度がスタートしてから入居型施設の数も種類も急激に増えましたし、自宅生活を支える小規模多機能型居宅介護といった自宅生活の新しい支え方(サービス)も登場しました。
僕がチヨジさん、リンさんに出会った20年前と「こんなに変わったのか」「こんなに増えたのか」と強く感じるほど、支え方や暮らす場の選択肢が一変したように思います。
介護保険制度が始まって約20年、認知症に対する理解や行政の政策も進んできました。次回は、そんな「行政が行っている認知症関連の施策」をみなさんにお伝えし、今回に引き続き、認知症に対する理解や支援策等は、確実に進歩・発展してきていることを感じていただければ思っています。