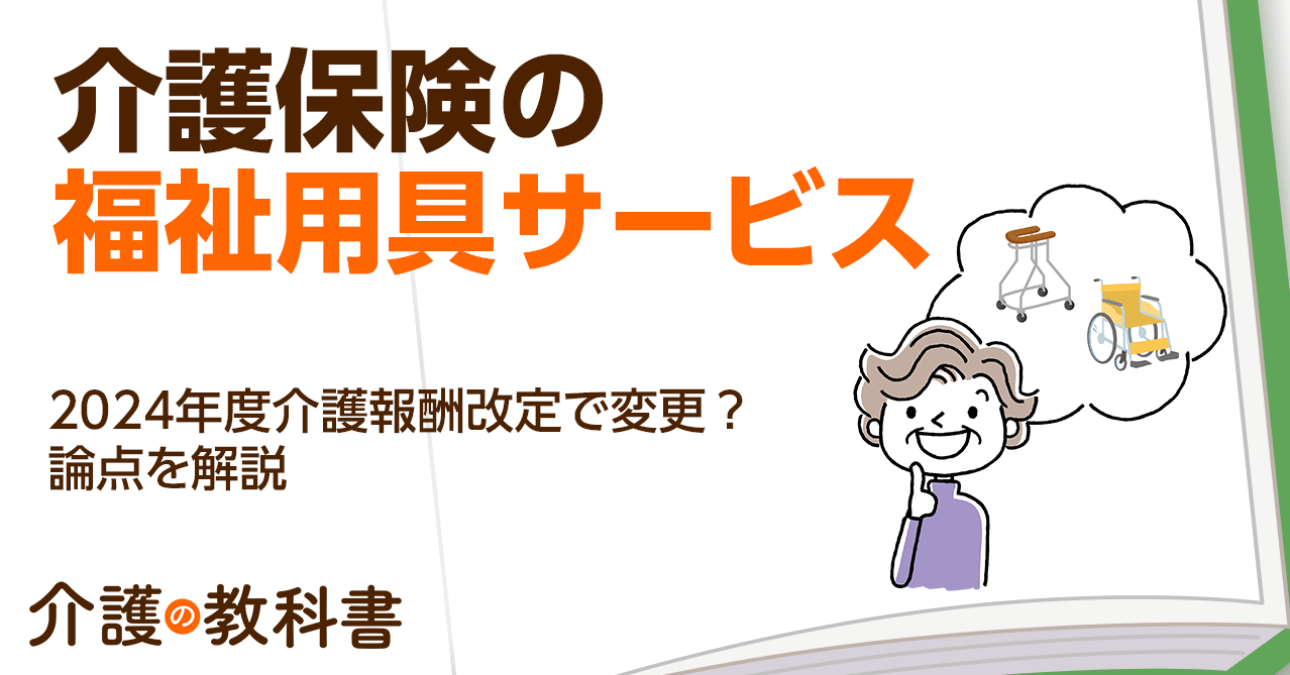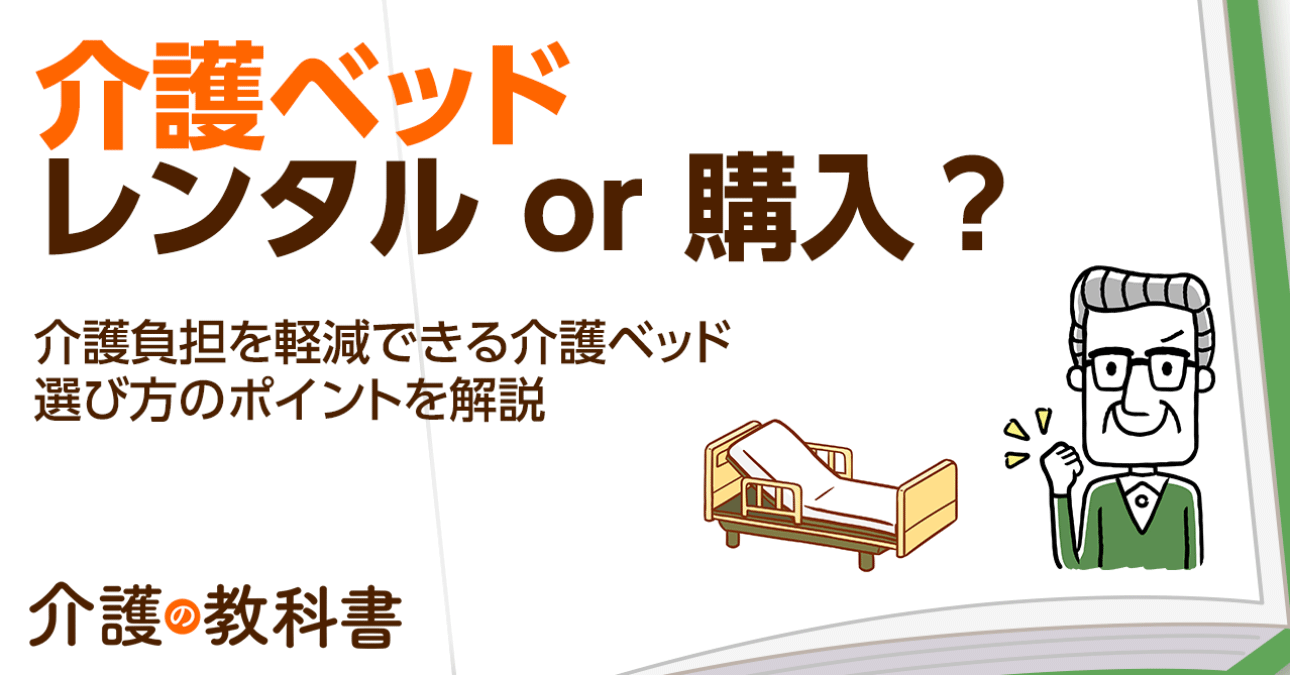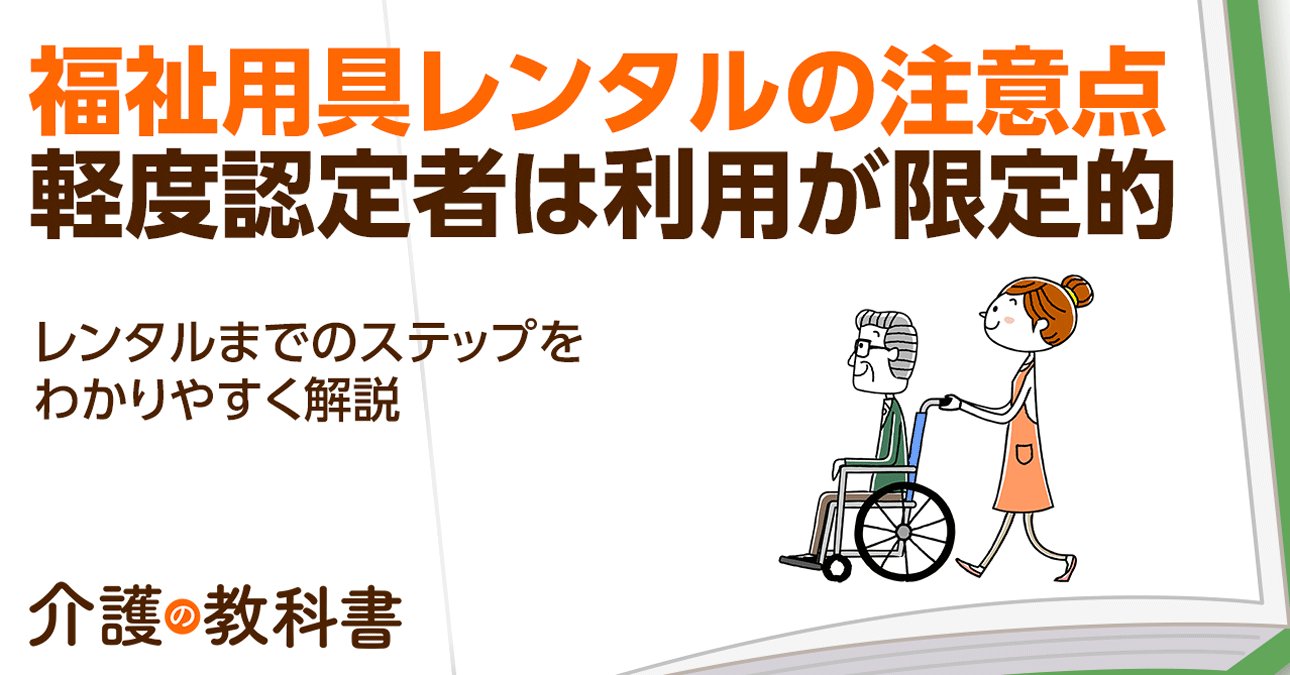ケアプランセンターはぴるす代表の大内田省治です。
今回は、介護現場などで使用される福祉用具について解説します。
介護保険制度で定められた福祉用具
介護保険制度における福祉用具とは、介護が必要な高齢者の日常生活を助ける、または身体の機能訓練のための用具のことです。
例えば、日常生活で歩行が困難な方は車椅子も代表的な福祉用具の一つです。また、住宅に取り付けるスロープや、認知症の人の徘徊を感知する機器なども含まれます。
このように、要介護者である利用者が、自分の家で自立した日常生活を営めるようにする福祉用具は、保険給付の対象となっています。
保険給付の対象品には貸与品と販売品の2種類があります。主に貸与品は複数の人が繰り返し使用できるものであり、販売品は直接肌に触れるなど、特定の人しか使用できないものです。
貸与品
- 車椅子(電動カート含む)
- 介護用ベッド
- 歩行器(押し車含む)
- 歩行補助杖
- 床ずれ防止用マットレス
- 移動用リフト(吊り具部分)
- スロープ
販売品
- シャワーチェア
- ポータブルトイレ
- 移動用リフトで使うシート
福祉用具の選定は、ケアマネジャーが判断するのではなく、主治医からの意見や指示を基に、リハビリの専門職(理学療法士や作業療法士など)、福祉用具専門相談員など、多職種が連携して利用者の身体的動作を確認して決めます。
貸与品で対応した方がメリットが大きい
貸与される福祉用具のメリットは、利用者の身体状況に合わせて、その都度変更できるといった点があります。
福祉用具を変更するときも、多職種が集まって担当者会議を開き、そこで再度利用者の身体動作確認などを行ったうえで、変更します。
使用されなくなった貸与品は回収されて、また新たな福祉用具に交換されます。
一方、福祉用具を購入した場合は、使用しなくなった後も利用者の手元に残ってしまうので、処分に困るといったケースが出てきます。
そういったことをなくすためにも、ケアマネジャーは「貸与品」をできるだけ利用するように勧めています。
また、福祉用具の活用方法には「住宅改修」といった方法もあります。
これは、自宅内の壁に手すりを設置したり、床材を変更したりすることで、転倒しにくいように改修することなどが当てはまります。
手すりの設置については、現在は玄関の上がり框(かまち)に設置する据え置き式の手すりや、トイレの便座にカニはさみのようにはさんで固定する「トイレフレーム」といったものが貸与品に該当します。

福祉用具貸与・販売の議論で抜け落ちているポイント
福祉用具については、貸与か販売かで議論が分かれることがあります。
厚生労働省では、介護保険の福祉用具の貸与・販売の見直しについて話し合う有識者会議を立ち上げました。
そのなかで、一番の争点となっているのが介護給付費の抑制です。
例えば、「歩行補助杖や歩行器、手すりなどの安価な福祉用具を貸与から販売に切り替え、ケアマネジメントの費用がかからないようにすべき」とか、「ケアプランの内容が福祉用具貸与のみの場合は、ケアマネジャーの介護報酬を引き下げる」といった議論がされる見込みです。つまり、福祉用具の貸与においてケアマネジャーのかかわりを制限しようとしているのです。
しかし、仮にこれらの議論が実現したら、利用者にさまざまなデメリットが生じる可能性があります。
例えば、福祉用具を導入することで、ケアマネジャーはケアプランを立案するため、毎月モニタリング訪問を行う必要があります。こうした訪問は、特に独居高齢者の方などの見守りなどに効果的です。
また、利用者の中には、ホームヘルパーやデイサービスといったサービスの必要性があるにもかかわらず「自分でまだ何でもできる」といった思いから、サービス利用に消極的な方もいらっしゃいます。
そんなとき、福祉用具貸与を行うことで、ケアマネジャーとのかかわりができ、そこから利用者へのアプローチのきっかけをつくることができます。
ケアマネジャーが日常生活に関与することで、介護の不安などの解消にも役立ちます。
ケアマネジャーは、介護保険制度のプロとしてだけでなく、高齢者の日常生活における相談役といった側面もあります。
よくケアマネジャーの研修では、介護保険のサービス(フォーマルサービス)と、それ以外のサービス(インフォーマルサービス)を結び付けることが仕事だと教えられます。
そのため、ケアプランの作成業務以外でも、さまざまな相談に応じています。
例えば、自宅のトイレが水漏れしたとか、水道管が凍結して破裂したので、業者さんを紹介してほしいなどといった、介護保険以外の相談です。
近年「振り込め詐欺」などが横行するなかで、ケアマネジャーに求められている役割は重要性を増しています。
利用者にとって、ケアマネジャーというのは「最後の砦」というべき存在なのです。
福祉用具貸与によって生まれる副次的なメリットも考慮に入れて、議論を進めていただきたいと思います。