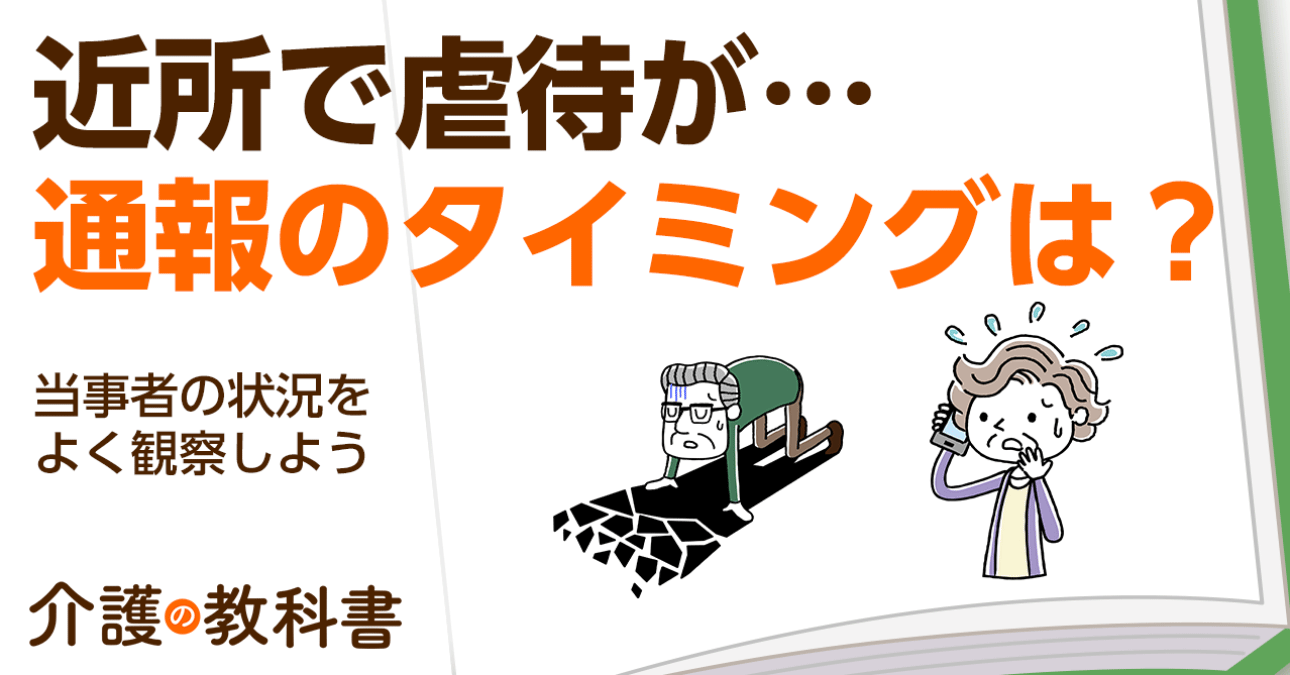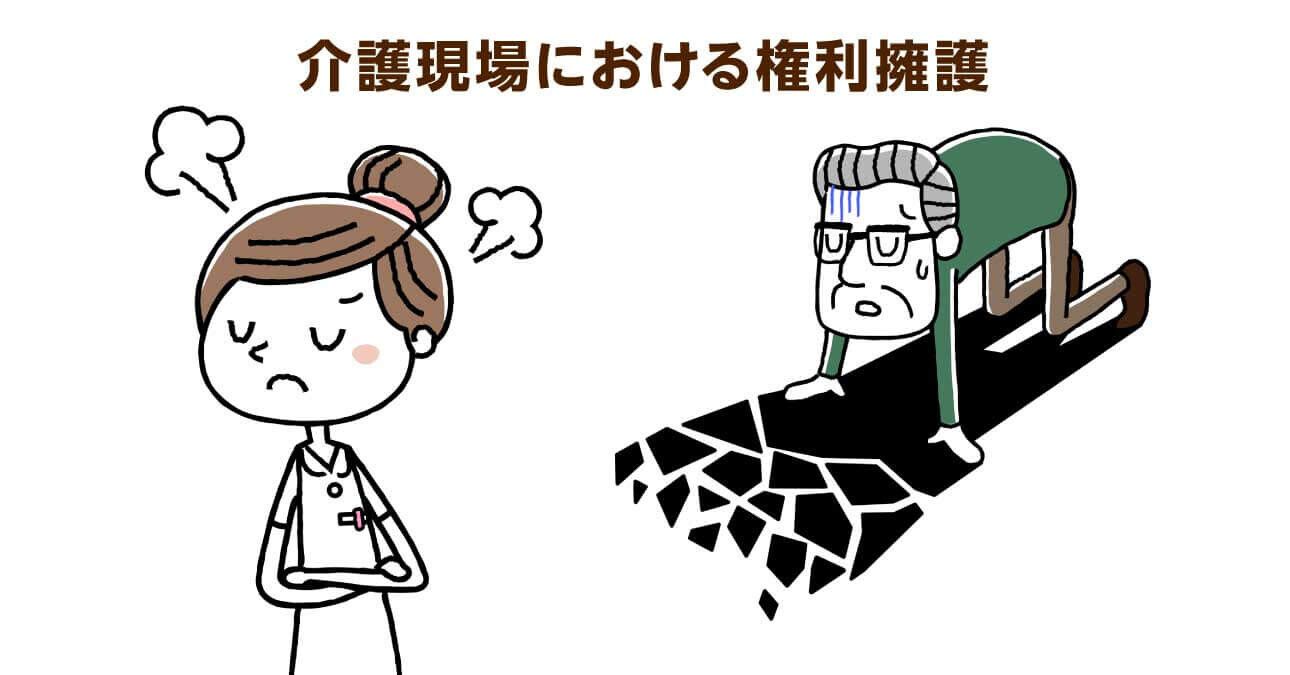医療と介護の連携支援センター長谷川です。
今回は、高齢者虐待と介護者による虐待について、私の所属する高齢者支援センターでの対応を中心にお話させていただきます。
高齢者虐待の定義と判断基準
まず「高齢者への虐待」と聞いて皆さんはどんなイメージを抱くでしょうか?
高齢者虐待については、高齢者虐待防止法で定義されています。この法律を広い意味で捉えると、「高齢者虐待とは、高齢者と何らかの保護などが期待できる他者からの不適切なかかわりによって、高齢者の権利利益が侵害され、生命や心身または生活に何らかの支障をきたしている状況、またはその行為」となります。
高齢者虐待は、以下の種類に分類されています。なお、セルフネグレクト(自己放任)は高齢者虐待防止法では定義されていませんが、町田市では、高齢者の尊厳を図るという観点から、セルフネグレクト(自己放任)も虐待の一種と捉え下記の6つを定めています。
- 身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること
- 放置放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、養護者以外の同居人による1・3・4に揚げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること
- 心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
- 性的虐待:高齢者にわいせつな行為をすること、または高齢者にわいせつな行為をさせること
- 経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分することや、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること
- セルフネグレクト(自己放任):一人暮らしなどの高齢者のなかには、認知症やうつ症状のために生活に関する能力や意欲が低下し、自分で身の回りのことができないなどの状態のために、客観的に見ると本人の人権が侵害されている状態
この定義に基づいて虐待が行われているか否かを判断しています。
虐待は在宅で起こるケースが多い
では、実際に虐待のケースはどれぐらいあるのでしょうか。東京都福祉保健局の『平成30年度高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果』を参考にしてみましょう。
まず施設での件数です。2018年度に東京都で受付された「養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する相談・通報件数」は209件でした。2017年度は167件だったので42件増加したことになります。
そのうち「事実確認を行った事例」は171件にのぼり、「虐待の事実が認められた事例」が59件、「事実が認められなかった事例」が60件、「判断に至らなかった事例」が52件でした。
一方、事実確認を行わなかった38件について、「虐待ではなく調査不要と判断した」が1件、「調査を予定している、または検討中の事例」が24件、「その他」が13件でした。
次に在宅でのデータを見てみましょう。
2018年度、都内で受け付けた養護者(高齢者の世話をしている家族、親族、同居人など)による高齢者虐待に関する相談・通報件数は3,759件で、前年度比で172件増加しています。事実確認の結果、「区市町村が虐待を受けた、または受けたと思われたと判断した事例」の件数は、2,786件で、前年度から58件増加しています。
要介護施設従事者などからの虐待件数209件と在宅での擁護者からの虐待3,759件で、合計3.968件となります。
施設従事者による虐待件数は総数の約5%となります。とはいえ、5%だから許されるというわけではありません。虐待は1件たりともあってはいけないものだと思いますが、要介護施設従事者からの虐待は大きく報道をされる傾向にあると思われます。
社会的な影響があるかと思いますが、実際は総数の5%ということもしっかり伝えてほしいと思います。一部では介護職員の処遇や賃金の低さなども理由として挙げられますが、実際には特定の原因ではなく、さまざまな要素が絡み合いながら起きたものだと感じます。もちろん、虐待はあってはならないことではあることは忘れてはいけません。

地域一体で発見することが大切
一方、虐待の95%は在宅で起きており、私たちは早期に虐待を発見する必要性があります。ただ在宅での虐待はひっそりと進んでいる場合が多く、発見が遅くなる傾向があります。皆さんと一緒に高齢者虐待の早期発見を行うためにも、ポイントをいくつか知っておいていただきたいと思います。
- 家族が介護や介助に対して疲れており、対象者の悪口などを言っている
- 暑い日や寒い日、雨など天候の悪い中に長時間一人でいる
- 郵便物や新聞などが溜まったまま放置されている
- 家の周囲にゴミなどが放置されていたり室内が散乱している
- 身なりが整ってないない状況がみられる
- 家から怒鳴り声や鳴き声、大きな声が聞こえる
ほかにもありますが、地域の方で思い当たることがあればぜひ最寄りの地域包括支援センターなどにご相談ください。
また、ケアマネジャーが介入しているケースでどのように虐待が発見されるか少しご説明いたします。
ケアマネジャー自体が虐待と思われる状況を確認するケースは非常にまれです。ケアマネジャーには1ヵ月に1回以上の訪問とモニタリングが義務づけられています。しかし、その中で身体状況の詳細な確認はなかなか難しいのです。現在は新型コロナウイルス感染症における臨時的取り扱いにおいて、モニタリングも本人や家族状況に併せて電話や文書でのやり取りなど非接触の方法が取られていることもあります。ケアマネジャー自身が虐待を発見できるケースは少ないと感じています。
そこで最初の気づきになるのが介護保険事業所のかかわりです。例えば、デイサービスやデイケアであれば週1~2回利用していて、通所での入浴サービスを行うこともあり、その中で身体状況を確認できます。
また、利用料の支払いが行われているか、通所へ来る際に衣類が整っているか、送迎の際の家族の様子など「いつもと違う」状況があれば、デイサービスやデイケアの管理者や相談員からケアマネジャーに連絡をすることもできます。
通所だけではなく訪問系サービス(訪問介護や訪問看護・訪問リハビリ)においても週1~3回程度、自宅に訪問して、サービスを提供するにあたって事前にその方の心身状況を確認できます。
また、毎週ではありませんが、中には訪問診療の先生や訪問歯科医師、民生委員の介入など、ケアマネジャー以外にもサービスを利用していれば複数回ご利用者を守る体制があります。
そのいずれかで、「いつもと違う」状況があれば、ケアマネジャーは他サービスに連絡を取りながらその方の状況をしっかり確認を行い、地域の支援センターや行政と協力しながら対応していきます。

対応の結果、実際に虐待とは判断できないケースも多々ありますが、それで良いのではないでしょうか。虐待かどうかで悩んでしまい、発見が遅れてしまうことの方が私は危険だと感じています。早い段階で周囲が気づくことにより、気づかずに虐待になっているケース(※1)や虐待と自覚がないケース(※2)にも対応できると考えます。
(※1:認知症により徘徊するので部屋や家から出さないようにしている・経済的に苦しいので病院や介護施設を利用することに制限をしている・良いこと悪いことの理解を促すために本人を立たせたりなど行動を制限してしまうなどのケース)
(※2:本人が夜間におもらしなどをしないように水分制限をおこない脱水状態に陥らせてしまう・本人がいやがるのでおむつが汚れている状況でも交換をしないなどのケース)
サービスの介入などがない方については、地域住民の皆さんの見守りが早期発見の第1歩となります。ぜひ皆さんの協力をいただきながら、誰もが安心して暮らせるよう虐待を防いでいきましょう。今回も最後までお読みいただきありがとうございました。