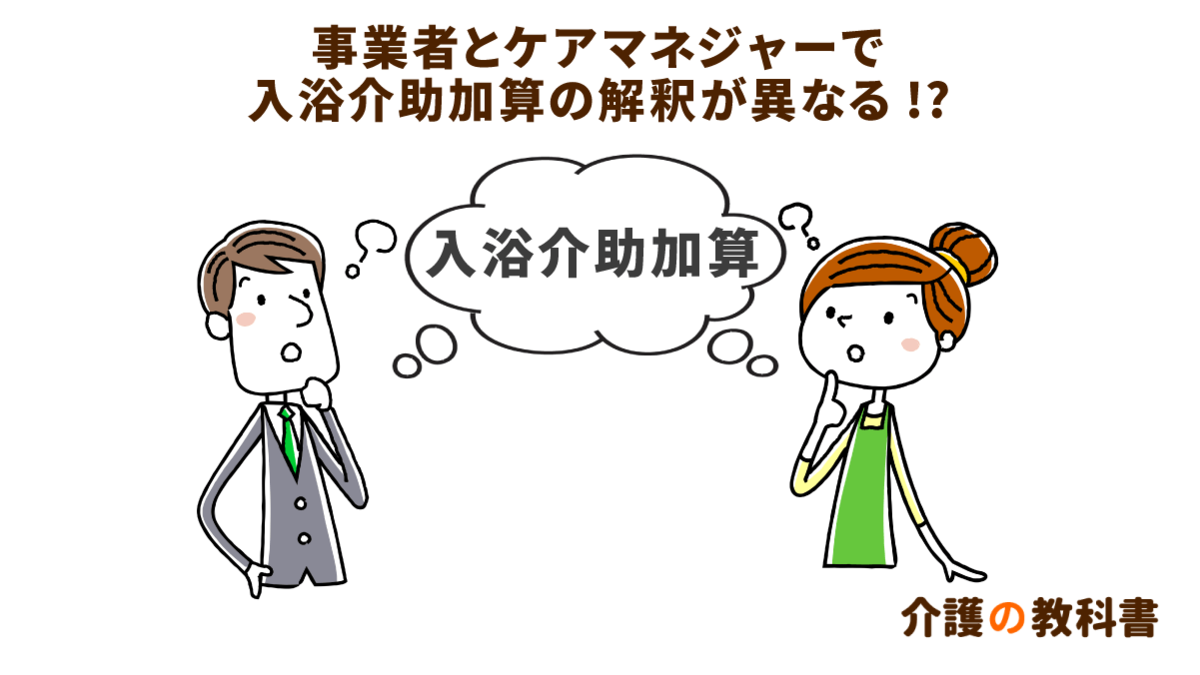町田市医療と介護の連携支援センター長谷川です。
今回は、2021年4月の「介護報酬改定」についてご説明させていただききます。介護報酬改定は3年ごとに行われるもので、今年度から第8期介護保険事業計画として、さまざまな報酬改定が行われています。
その中で、デイサービス(通所介護)において改定された、「入浴介助加算」についてお話いたします。この加算算定に関するケアマネジャーと通所事業所との間での考え方や、私自身の考えを述べさせていただきます。
入浴介助加算の算定要件
デイサービス(通所介護)における「入浴介助加算」は、2021年4月の介護報酬改定で新たに設けられた加算です。入浴サービスの質を高めるための施策として単位数が見直され、個浴中心に新たに2種類の評価区分が設けられました。
改正前の入浴介助加算…50単位
↓
改正後の入浴介助加算(Ⅰ)…40単位
改正後の入浴介助加算(Ⅱ)…55単位
この点数だけ見て理解することは難しいため、厚生労働省が出している算定要件を見てみましょう。
算定要件
1.入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合に算定(改正以前の入浴介助加算と同様)。
2.医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等が利用者の居宅を訪問(※個別機能訓練加算で行う居宅訪問と併せて実施可能)し、利用者の状態を踏まえて浴室における利用者の動作・浴室の環境を評価すること。
3.機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問した者との連携の下で、利用者の身体の状況や訪問により把握した利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。
4.入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。
ケアマネジャーとデイサービスで解釈が異なる理由
今回この加算を取り上げたのは、ケアマネジャーとデイサービス事業者で認識が異なる事例が生じているためです。「入浴Ⅰ」の算定要件で、改定以前の入浴介助加算と同様との表記に従えば、「50単位/日→40単位/日」と単位数は減少します。そのため、1週間に2回入浴をしていたとすると、「8回分×10単位と80単位/月(約800円)」の減少となります。
この場合、ケアマネジャーは単位数が減るので大きなプラン変更は発生しないと考えますが、デイサービス側は逆になります。大規模な事業所であれば、1日に入浴を10人行うところも存在します。10単位/日×1日10人×30日=3,000単位(約3万円)となります。入浴で行う業務量は変わらないにもかかわらず、単位は下がるので、デイサービスの多くは「入浴Ⅱ」への移行を試みようとしました。
その結果、2021年3月下旬から4月にかけて、入浴を行っている事業所から、ケアマネジャーに対して「入浴Ⅱを算定します」という連絡が入るようになりました。そうなるとケアマネジャー側では単位が上がる形になるので、加算算定のための根拠を確認することになります。しかし、ここでケアマネ側には一つの疑問が生じました。
それは上記の算定要件にある2~4についての解釈です。
当初、私の所属する町田市ケアマネジャー連絡会会員の多くは、「自宅で入浴ができる方でないと算定できないのではないだろうか」と解釈していました。そもそもデイサービスで入浴サービスの対象となるのは、多くが何らかの理由で自宅で入浴ができない人なのです。
例えば、「要介護度が重く、入浴時の負担が大きい方」「自宅での入浴設備が整っていない方」「医学的管理が必要な方」など、自宅での入浴サービスを想定していない方も多く存在しています。そんな中、「そもそも自宅では入浴を行わない・行えない方が、この加算の算定対象になるのだろうか?」という点でした。事業所から連絡を受けたケアマネジャーの多くから、私自身も含めご相談を多く受けました。私自身も、当初は「既存のままであれば入浴Ⅰ」「在宅での入浴ができる方が入浴Ⅱ」であると認識していました。

「入浴実施を目指す」が意味すること
そこで、所属する職能団体として保険者である町田市に問い合わせさせていただき、2021年4月2日の段階でホームページにて回答をいただきました。
その内容は「自身で又は介助によって居宅での入浴実施を目指さない場合、入浴介助加算Ⅱの算定は行わないものと考えます」でした。
ここで、この文章についてケアマネジャーとデイサービス側で様々な解釈と見解が生まれていくことになりました。
- 入浴実施を目指しても果たせなかった場合は?
- 実施を目指すための期間設定は?
- 住宅改修や福祉用具が必要な場合は?
私が知り得る限り、4月中はこの加算自体を算定するデイサービスは市内になく、各デイサービス事業所も一旦様子を見るという形になりました。
算定するにあたり、事前に居宅を訪問して浴室の状況確認や計画書の作成も要件に入っているからではないかと思われます。この入浴介助加算においての解釈や見解については町田市だけではなく、全国的なものだったようです。最終的には厚労省から『令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)』が2021年4月26日に公表されました。
その中で具体的な事例での解説もされており、理解が進んだ部分もあると思います。
「結果」ではなく「プロセス」への評価
「入浴Ⅱ」での評価基準に関して、私は「結果での評価」ではなく自立支援に向かう「プロセスへの評価」が重視されていると感じています。
今までの介護報酬は「デイサービスを○○時間利用したので、○○時間の報酬算定を請求する」といった流れでした。「入浴や個別機能訓練など、実際に行われたことに対して算定する」といった報酬でした。
その部分が、利用者さんの自立支援に向かっていると考えられます。つまり、入浴の場面において、本当に必要な介助をアセスメントしたスタッフも含め、「多職種のチームで計画を立てて実行に移して適宜見直しを図る」というプロセスに対しての評価だと考えます。
この流れは、利用者さんの進捗状況は多種多様なため、現状は時間的な縛りがないのだと感じています。入浴介助を行うにあたり、対応したスタッフだけではなく、さまざまなスタッフ、介護される方、そしてご本人自身がかかわりながら対話を繰り返し、ご本人が入浴動作にかかわる一連の動作の一つひとつを再検討。最終的に自立した入浴へのイメージを共有していくことや、ご本人が考える自立した生活についてケアマネジャー側とデイサービス側が共有を行うことなど、その実現に向けたプロセスが大切なのだと思います。

2021年4月の介護報酬改定では、デイサービスとケアマネジャーだけではなく訪問介護とケアマネジャーなど各分野で相互理解や解釈をしっかり共有することが求められている部分が多くあります。
その中で、ケアマネジャーは多岐にわたるサービスを幅広く理解する必要があります。なおかつケアマネジャーの制度変更や遵守すべき項目の追加があり、それらへの対応も必要とされています。今まで以上に業務が多くなり、重要な役割を任されているのです。
私自身、支援センターや町田市ケアマネジャー連絡会の一員として、実際の現場でさまざまな苦労をされているケアマネジャーの一助になりたいと考えております。今日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。