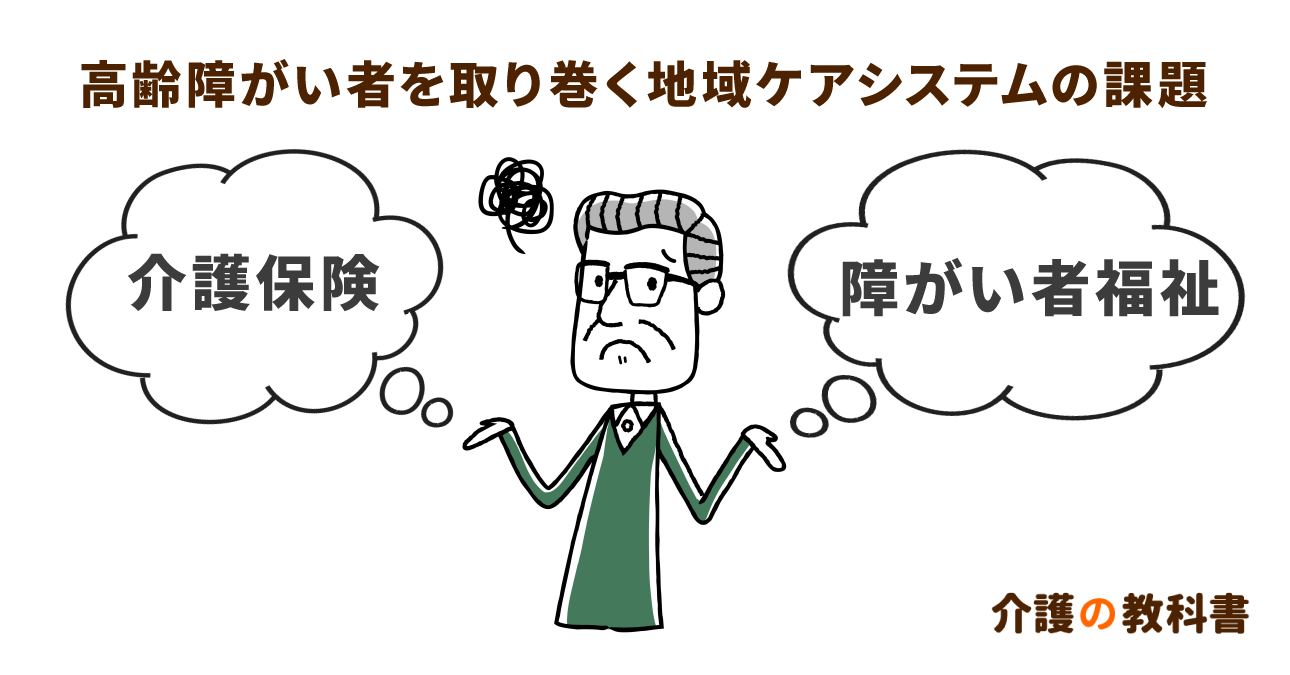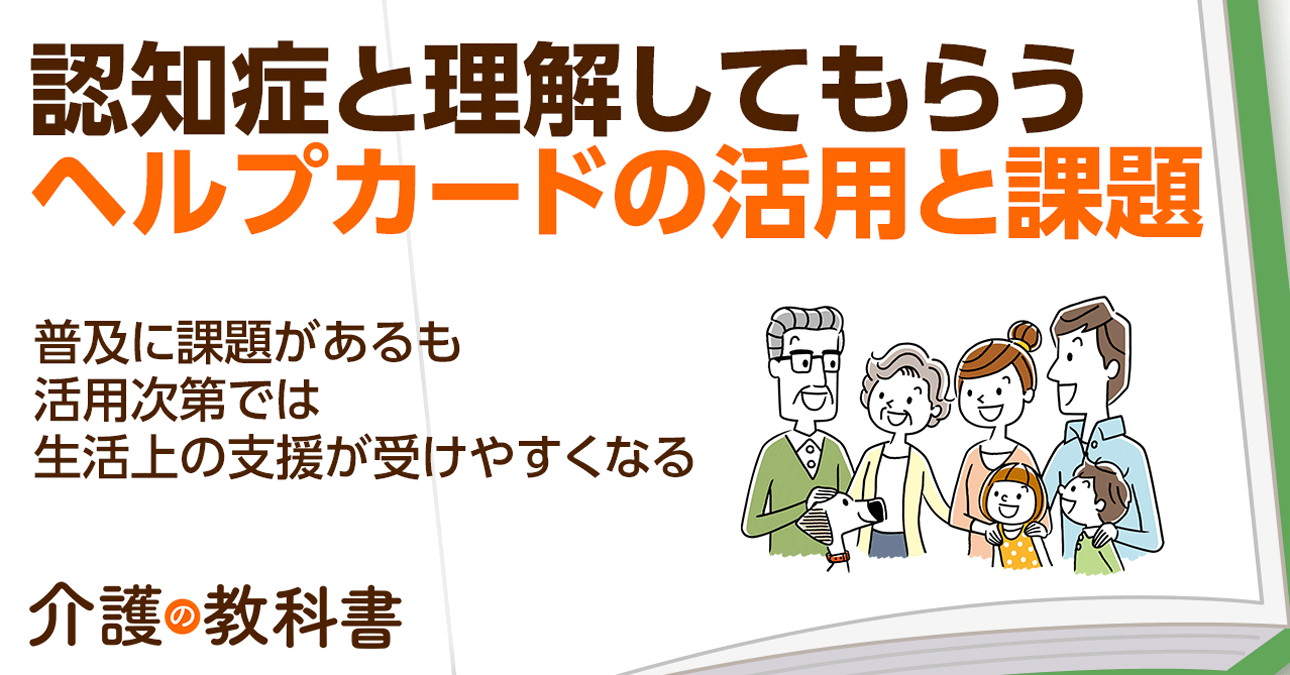こんにちは。ケアマネジャーの小川風子です。
今回は「介護保険と障がい者福祉サービスの併用」について、お話します。
65歳以下で要介護になった場合も保険は使える
介護を必要とする状態になったとき、高齢者(基本的には65歳以上)であれば介護保険を申請します。そして何らかの要支援、要介護度の認定が出ればケアマネジャーがついてケアプランを作成。介護保険サービスを利用した生活が可能です。
では、高齢者でない(65歳以下)のに要介護状態になった場合はどうなるのでしょうか。その場合、「障がい者」というカテゴリーで介護を受けることになります。その場合の介護保険に代わるのが、「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」、略して「障害者総合支援法」です。
障害者総合支援法には、介護保険と同じようなサービスがたくさんあります。例えば、介護保険での訪問介護について、障害者総合支援では「居宅介護」がありますし、通所介護(デイサービス)は「生活介護」があります。
もちろん、障害者総合支援法にもケアマネジャーと呼ばれる役職があり、こちらの正式名称は「相談支援専門員」です。細かい仕事の内容や資格の取得方法などは違いがありますが、サービスの調整を行い、計画書を作成するという役割は同じ。
ただし、障害者総合支援法ニおけるケアマネジャーの資格を取得するには障がい者の方に対しての仕事の経験が必要です。よって、その手の知識を豊富に持っている職種となります。つまり、「高齢者・障がい者の方とともに専門知識を持ったケアマネジャーがサービスの調整をしてくれたり、相談に乗ってくれる」ということです。
しかし、介護保険と障がい者のサービスを併用した場合、そうではなくなることがあります。
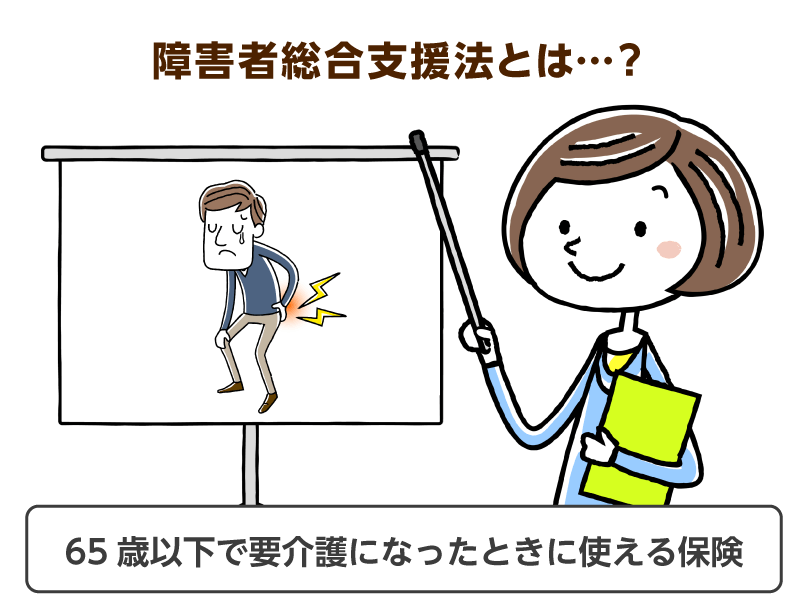
高齢者になると介護保険に切り替わる
介護保険は、「他法より優先される」という大原則があります。簡単に説明すると、「介護保険でできることがあるなら、まずはそちらを利用してください」ということです。この前提に基づき、64歳まで障害者総合支援法を利用して生活していた方は、65歳になると介護保険の申請を行い、その結果に応じたサービスを利用しなければなりません。
障害者総合支援法と介護保険は同じようなサービスの多い制度ではありますが、ルールや締めつけは介護保険の方が厳しいです。なにより、計算方法が違います。
介護保険は区分支給限度額内で好きなサービスを組み合わせて生活できますが、それは「単位」という考え方で限度額内に収めたときの話。早朝や夜間などの時間帯に訪問介護などを利用すると、加算がついて25~50%増の単位が必要となります。
対する居宅介護などは給付された時間内でのやりくりなので、昼間に1時間ヘルパーを利用しようが夜中に1時間利用しようが、同じ1時間です。なので、障がい者サービスの頃に就寝介助や起床介助でヘルパーを利用していた場合、介護保険に変わると途端に単位のやりくりが厳しくなる可能性があります。
また障がいの程度が重く1日中介護を必要な方の場合、障がい者の方のサービスには「重度訪問」という制度があります。これは支給される時間も長く(人によっては毎日24時間支給の場合も)、サービス内容もかなり自由。ヘルパーは見守りや、そばで過ごすだけでも大丈夫です。
ところが、この重度訪問を使って1日に何時間もヘルパーにいてもらっていた方が介護保険に移行した場合、限られた時間しかサービスを使うことができないので、生活は一変します。
障害者総合支援法の保険を使っていた頃より時間も短くなるし、ヘルパーのできないことも増える。
このパターンで非常に困る方が少なくありません。また、そういった場合に介護保険の制約をすんなり受け入れてもらえないことも多く、ケアマネジャーとして悩ましい問題です。
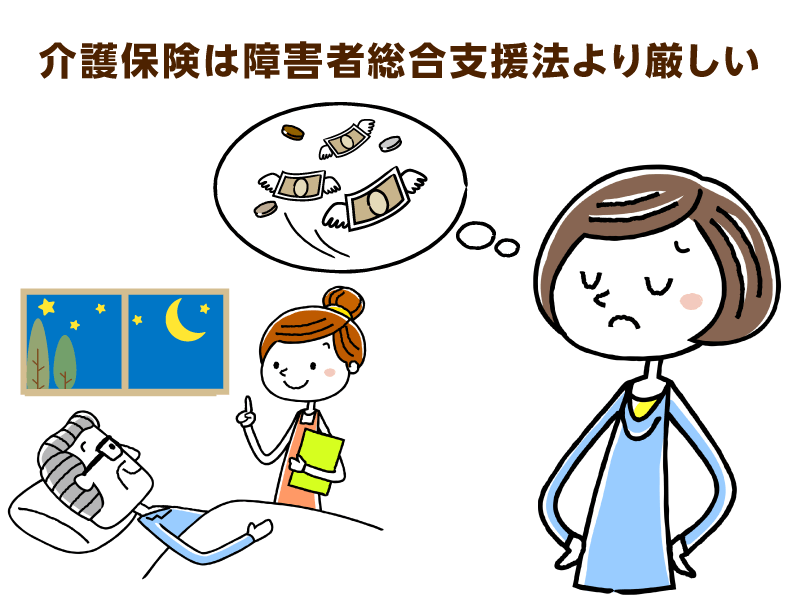
重度の方は障がいの保険を申請できる
では、障がい者の方が介護保険サービスに移行した場合、「時間が短くなる」「制約が厳しくなる」ということがあっても、我慢しなくてはいけないのでしょうか。
多くの自治体では、要介護5(自治体によっては要介護4でも)で介護保険をマックスに利用している障がい者の方が、介護保険のサービスでも時間が足りないとなった場合、障がい福祉課に申請し、障がいの保険での必要な時間をもらうことができます。ただ、これは簡単に支給されることはありません。原則は介護保険が優先なので、その中で生活する必要があります。
「介護保険の単位では足りないので障がいの時間をください」と頼みに行くのは介護保険のケアマネの仕事です。ケアプランや利用票、足りない理由などを添えて、障がい福祉課とやり取りします。介護保険を利用し、そちらにケアマネがつけば、その後のサービスの調整は介護保険と障がいのどちらもすべてケアマネジャーが行うのです。
もし支給時間が障がいの方で出ても、そのサービスを行ってくれる事業所を探すのは介護保険のケアマネの仕事。障がい福祉課も何かあればケアマネに連絡してきます。
ヘルパー事業所のケアマネジャーを頼ろう
筆者はケアマネジャー、介護支援専門員として日々仕事をしています。介護支援専門員の資格を取るために、しっかりと介護保険の勉強をし、試験や研修を経て知識をつけてから仕事をしているわけです。介護保険におけるほかのケアマネジャーの方も、介護保険の勉強をしっかりした介護支援専門員です。しかし、障がいの保険の勉強している方はほとんどいません。
介護支援専門員の資格を取るためには、もともとの職種(現在は国家資格のみ)での5年の実務経験が必要なのですが、その実務経験は「介護保険関係の仕事で積み上げた」というケアマネジャーが大半を占めています。
ヘルパー事業所であれば、介護保険も障がいの保険も両方行っているところが多いので、そこで働いた経験のあるケアマネジャーなら、どちらも精通しているかもしれませんが、そうでないケアマネもたくさんいます。ですから、はじめから障がいのサービスを利用すると決まっているのであれば、そういった実務経験を積んだケアマネジャーを探すといろいろな話が早いかもしれません。
介護保険と障がいの保険は似ているように思えますが制度が全然違いますので、利用者さんが理解するのは難しい部分も多いのです。もう少し両方の制度がわかりやすくなり利用しやすくなればいいなと思っています。