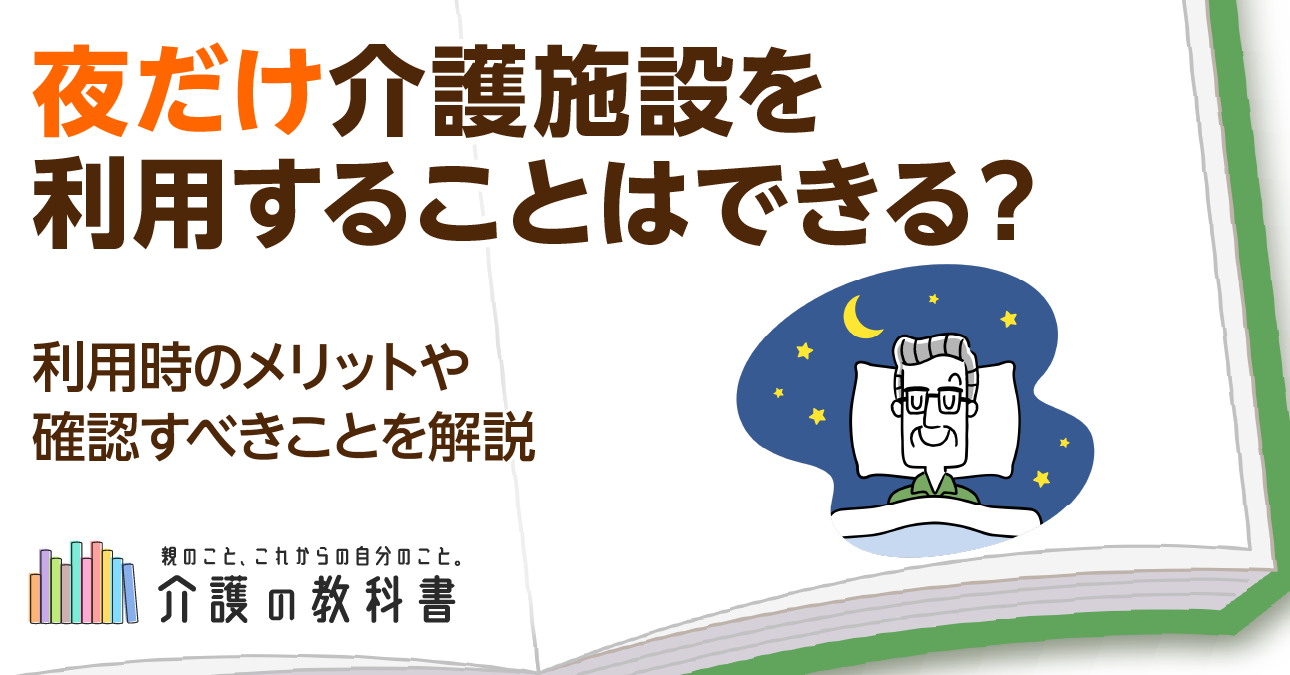皆さんこんにちは。(医)創生会町田病院地域連携課の長谷川昌之です。
今回は、入院費用が高額なときにやるべきことをお話いたします。
入院費用が払えない場合は、早めに病院に相談しよう
皆さんは、入院時の費用を準備していますか?
入院するような事態はほとんどの方にとって急に訪れるものなので、まとまった額の準備をしていることはあまりないと思います。
また、がんや脳梗塞などの病気の治療費は高額なため、請求書を見て驚くことになるケースも少なくありません。
多くの病院では、入院時に保証金を納めてもらったり、保証人を立ててもらい入院費用をしっかり支払っていただける体制をとっています。
もし保証金や、保証人、入院費用などを準備できない場合、早めに病院側にその旨を伝えましょう。
後から支払えないと話すより、事前に話すことで、病院側の受け入れ方も変わります。
(例えば分割払いを認めるケースもあります)。
最悪、入院費用が支払えない場合は、退院、転院、施設への入所を求められたり、入院先との関係が悪化したりすることもあります。
繰り返しますが、病院側に対して、入院前に早めに状況を説明することが大切です。
入院や治療が必要な際、公的な制度や、自分で加入している保険などの利用で、負担軽減につながるケースもあります。
このケースでもやはり早めの相談が重要です。
また、場合によっては、本人や家族だけでは判断できないこともあるので、できる限り早めに家族・親族と相談することも検討してみてくださいね。

公的な支援や民間の保険を申請しよう
私たちが病気になったときにかかる医療費の負担軽減のため、さまざまな公的制度が設けられています。
もし利用対象であれば、その制度を積極的に活用しましょう。
行政機関などで手続きを行えば、病院での一時的な支払いもなくなるケースもありますが、手続きが間に合わずに一旦全額を負担する場合もあります。
そのため、入院日数やおおよその支払い金額などを、病院の窓口に確認しましょう。
「限度額適用認定証」を申請して「高額療養費制度」を活用しよう
入院や手術で診療費用が高額になる場合、「高額療養費制度」を活用できないか、調べてみることをおすすめします。
この制度を利用するには、以下の2ステップを踏む必要があります。
- ①「自己負担限度額に係る認定証(限度額適用認定証)」というものを、保険者(自分の所属する健康保険組合)から交付してもらう
- ②「自己負担限度額に係る認定証(限度額適用認定証)」を病院の窓口に提出する
上記の2ステップを踏んで「高額療養費制度」を利用することで、診療費用の本人の負担額が年収に応じて軽減されます。
この制度では年収に応じて自己負担の限度額が決まっているため、この限度額を超えた金額を返金してもらえるのです。

ちなみに、診療費用の全額を支払った後でも、保険者に申請すれば、この制度で払い戻しを受けられます。
ただし、事前の申請・提出で、請求額に制度が適用されて、一時的な多額の現金の支払いを軽減できるので、事前の申請をおすすめします。
補足ですが、限度額適用認定証を交付してくれる「保険者」とは、お手持ちの保険証の発行元の健康保険組合のことです。
限度額適用認定証の申請が必要な場合は、以下に問い合わせてください。
- 国民健康保険に加入している場合…市区町村の行政の担当窓口
- 職場の健康保険に加入している場合…勤務先から発行された保険証に記載された窓口(不明な場合は会社の担当者へ確認してください)
そのほかにも、「高額療養費受領委任払い制度」や「傷病手当金」「一部負担金減免制度」なども活用できる可能性があります。
ぜひ行政の窓口などへご相談してみてください。
自立支援制度
「自立支援制度」とは、精神や体の病気の方の医療費に対して、自己負担限度額が設定される制度です。
この支援の対象者は、以下の方に限られます。
- 精神疾患を抱えた方
- 関節拘縮などがある、肢体が不自由な方
- 白内障などの視覚障がいがある方
- 心臓機能障がいなどの内部障がいがある方
自立支援制度は、指定の病院のみで使用できる、対象者の条件に制限がある、申請に時間がかかる傾向があるなどの点に注意が必要です。
手続きや申請については、入院後早期に地域の保健所や行政の窓口へ相談しましょう。
「医療費控除」を申請しよう
ここまで解説してきたような制度を利用した方も、利用しなかった方も、1年間の医療費が10万円を超えた場合は、確定申告を行い「医療費控除」申請を行いましょう。
対象となる医療費には、基本的に病気の治療などに必要となる費用や薬代などになります。
お勤めの方などは税金の支払いが減額されるのでこちらも忘れずに活用しましょう。
障害者年金や介護保険の申請
もし退院にあたり、障がいの程度が重い場合は「障害者年金」や「介護保険」の申請も検討しましょう。
あまり考えたくない部分でもありますが、入院後の生活をどこでどのようにするかを考えるときには、必ず検討しましょう。
入院したら早めに、行政の窓口や地域の包括支援センターへ相談することをおすすめします。
公的制度ではすべての医療費を賄えない
ここまで説明してきた公的制度では、すべての医療費や入院時の自己負担額を賄うことができません。
例えば、個室を希望した際の差額ベッド代や、食費、先進医療にかかる費用などは含むことができないのです。
その際には、ご自身で加入している民間の医療保険で、自己負担分を賄えないか確認しておくことが大切です。
また、入院で支払う金額ばかりに注目してしまいがちですが、働いている方が入院したとき(特に長期になった場合)、生活費をどうするかも、忘れずに検討しなくていけません。
このように入院費の支払いが困難になるような状況があれば、すぐに行政の窓口などへ相談することが必要です。
併せて、自分が加入している民間の保険について、以下のことを確認しましょう。
- 保険会社の連絡先
- どのような場合対象になるのか(通院時も保険金は給付されるのか)
- 入院何日目から保険金が給付されるのか
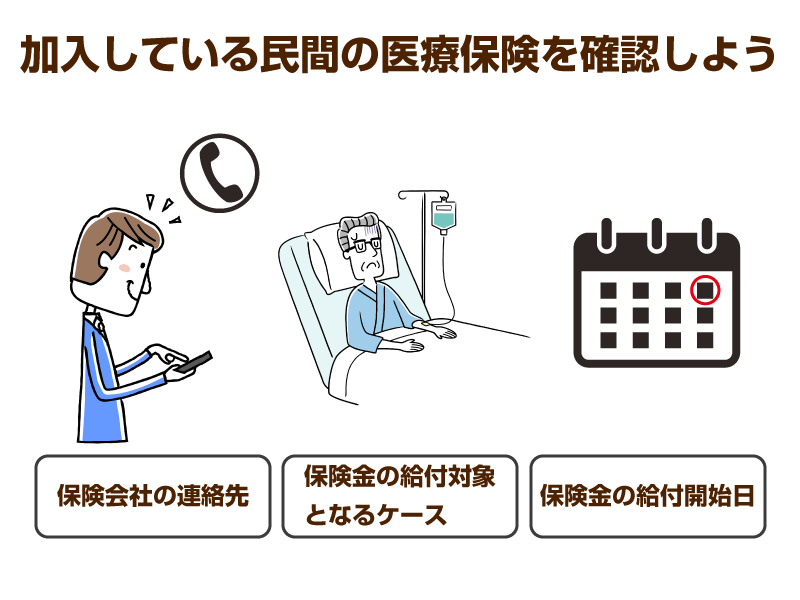
最後に一言
急に入院する事態は、いつ・誰に・どこで発生するかわかりません。
もしもの場合や万が一に備え普段から、お金のことも話しておきましょう。
ちなみに、今注目を集めている「人生会議」や「アドバンスプランニング」とは、体調が急変したときの備えを話し合うことを意味します。
本人や家族が安心して治療に専念するためにも、入院時に必要な手続きをするための連絡先などを、一覧にまとめておくことをおすすめします。