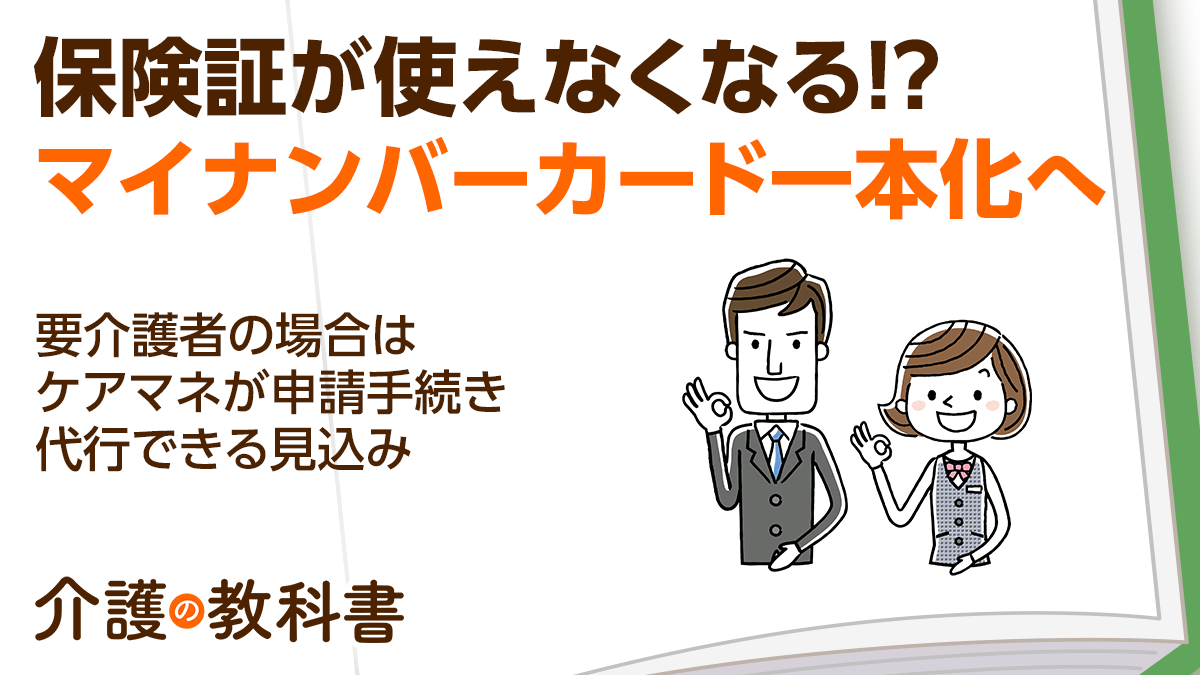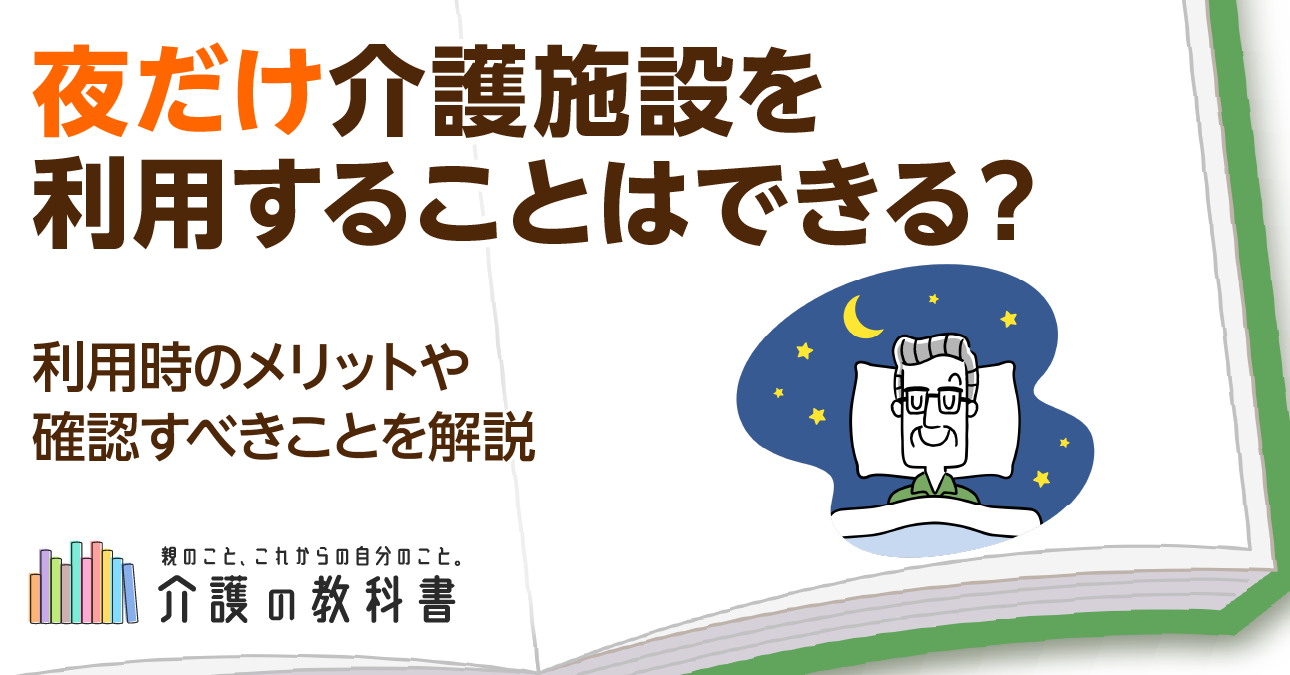現在、健康保険証等がマイナンバーカードに一本化されるように制度改正が進んでいます。
その中で、役所などに行くのが困難な高齢者も多くいらっしゃるかと思います。
今回は、役所などに手続きに行くのが困難な場合、どのようにしたらよいのかをケアマネジャーの視点から解説していきます。
ケアマネジャーの代行が許される手続き業務
まず、ケアマネジャーが要介護者のために行っている各種申請手続きは、以下のようなものがあります。
- 要介護認定の新規申請や更新申請
要介護認定区分の変更申請 - 要介護(要支援)認定の新規申請等については、本人や家族、地域の民生委員でも手続きは可能です。
- 介護保険被保険者証
介護保険負担割合証などを紛失した際の再発行 - 介護保険被保険者証や負担割合証の紛失時の再発行・居宅申請・介護認定審査会資料請求や住所変更手続きなどについてはケアマネジャーが代行しています。
- 居宅申請
ケアプラン作成時の介護認定審査会資料請求 -
介護保険のサービスを利用するには、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。手続きに行くのが困難な場合は、ケアマネジャーや民生委員等に依頼します。
ただ、要介護(要支援)認定の申請をしただけでは、サービスを利用することはできません。
サービスを利用するためには「ケアプラン」という書類を作成し、それに位置付けたサービス事業所(ホームヘルパーやデイサービスなど)を招集して、実際にサービスに入る頻度や時間等の打ち合わせを行う担当者会議を行わなければなりません。
そのため、介護保険のサービスを利用したいときは、ケアマネジャーに依頼する必要があります。
- 住所変更に伴う住民票・健康保険証・介護保険証などの変更手続き
- 利用者本人や家族からの委任状があれば可能です。
- 各市町村で独自に実施しているサービスを利用する際の手続き
- 例えば、配食サービスや緊急通報システムの設置手続き、おむつ給付などの申請も行います。
ケアマネジャーが代行できない手続き
一方で、ケアマネジャーが代行できない手続きも存在します。
例えば、以下のような手続きです。
- 介護保険負担限度額認定証の申請手続き
- 高額介護サービス費の申請手続き
- 高額医療合算介護サービス費の申請手続き
- 社会福祉法人利用者負担軽減対象確認証の申請手続き
- 市民税課税世帯に対する特別減額措置の手続き
これらの手続きは、市民税課税世帯か非課税世帯かで変わってくるため、ケアマネジャーが手続きを代行することができません。
また、施設入所や介護老人保健施設や介護老人福祉施設(特養)などのショートステイを利用するために必要な「介護保険負担限度額認定証」の申請手続きも代行できません。
本人の預貯金などの資産要件を満たす必要があり、申請時に通帳を持っていかなければならないため、利用者本人で申請しなければなりません。
このようにケアマネジャーや民生委員などが代行できる手続きもあれば、できない手続きもあるのです。

ケアマネジャーが申請を手助けできる可能性
政府は、2024年秋から健康保険証とマイナンバーカードの一本化を円滑に進める方針を示しました。
その説明では、要介護の高齢者など、市区町村役場まで自分で申請に行くのが難しい人への支援策として、代理人(ケアマネジャーや施設長など)を通じたマイナンバーカードの交付を幅広く活用できるように要件を緩和するとされています。
加えて、本来業務に配慮したマニュアルを作成・普及するとともに、申請の取りまとめや、代理での受け取りなどに対する助成も行うといったことも言われています。
ただ、前述のように、ケアマネジャーは資産など、おもにプライバシーに関することは申請代行できないため、家族の支援が不可欠な部分もあるのではないかと考えています。
現時点では手続きの詳細については不明点が多いものの、ケアマネジャーがかかわって、申請を簡略化できる可能性は大いにあります。
健康保険証は、病気などを抱える高齢者にとっては日常的に使用するものです。一本化ということなので、これまで使っていた紙の健康保険証は、将来的に利用できなくなることでしょう。
事前に慌てることがないよう、不明点があれば市役所の窓口などで相談しておくことをおすすめします。そのうえで、いつどうやって健康保険証になるのか、今後の動向を注視しておきましょう。