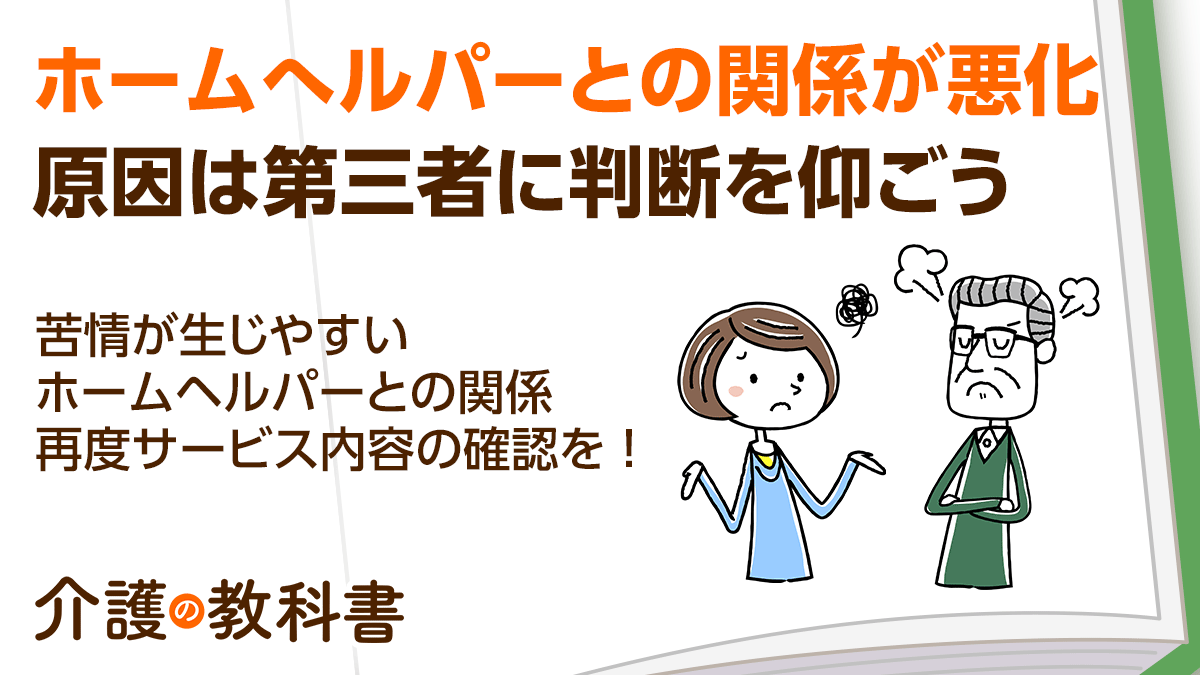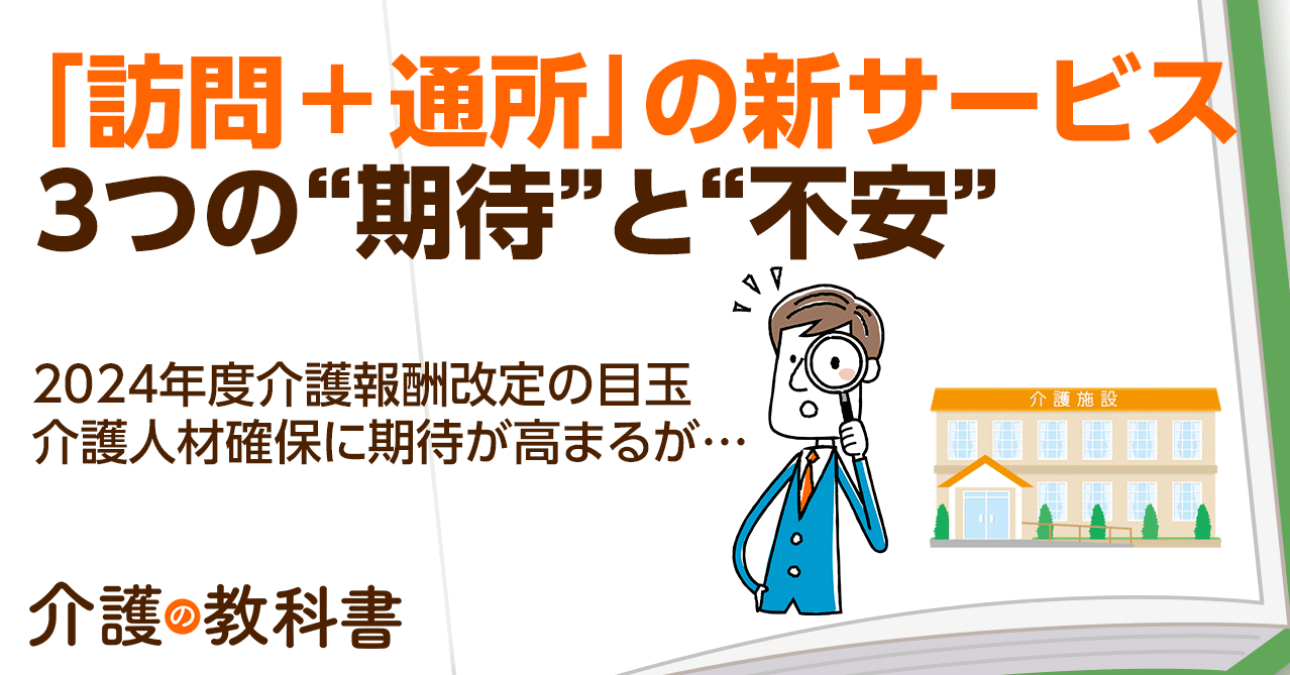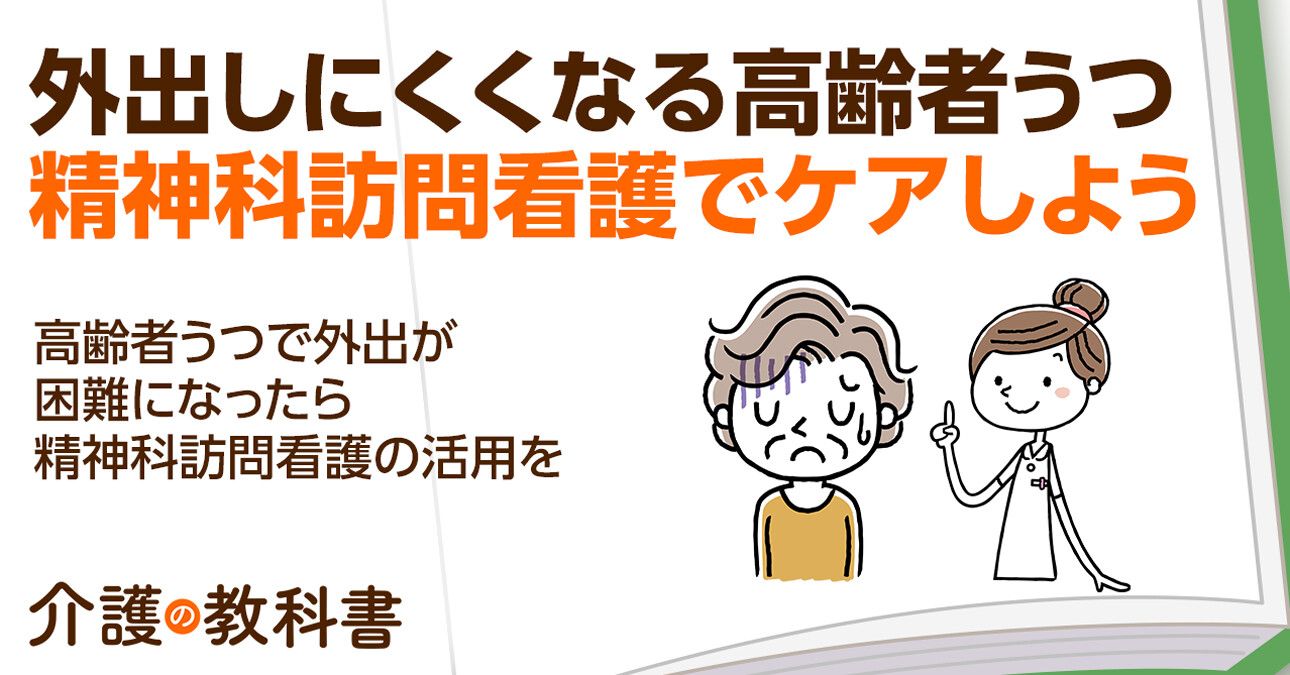介護保険サービスなどに対し、どうしても生じてしまうのが利用者やご家族からの苦情です。
その中でも皆さんの生活に一番近いホームヘルパーさんへの苦情から、折り合いが悪いなと感じてしまった時の対応について考えてみましょう。
苦情白書について
毎年東京都では介護サービスの苦情白書を発行しています。
苦情白書は、その年の苦情の件数や内容・今後の対応策のポイントなどが掲載されます。
それによれば、2021年度における苦情の受付件数は3,262件。苦情相談者は、利用当事者41.5%、家族48.5%で、全体の約90%を占めています。
苦情のうち約12%にあたる200件がホームヘルパー(訪問介護)です。
苦情に至る理由は、利用者やご家族が家事手伝いのようにホームヘルパーさんを扱ってしまったり、介護保険では定められていないサービスを依頼するなど、利用者や家族が原因となることがあります。
対して、ホームヘルパーの態度や定められたサービス内容の不履行・ヘルパー事業所としての対応に問題があったりと事業所側に起因するものなどケースによってさまざま考えられます。
私の経験上、いきなり公的な機関に苦情に至ることは多くありません。その前に利用者や家族から要望がホームヘルパーや事業所にあるはずです。
それでも納得されない場合、公的な機関への苦情に至ると思います。そうなったときは、利用者や家族、ホームヘルパーや事業所との折り合いが非常に悪くなっていると考えられます。
訪問介護ってどんなサービス
折り合いがつかないのは、ホームヘルパーの業務内容についての説明不足や理解不足から始まることが多いと感じています。
そこで改めて介護保険制度におけるホームヘルプ(訪問介護)について知ることが大切です。
訪問介護とは、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ホームヘルパー(訪問介護員)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)を行うものとされています。
そのサービス内容により、次の3類型に区分されています。
| 類型 | サービス | 例 |
|---|---|---|
| 身体介護 | 利用者の身体に直接接触して行われるサービス | 入浴介助 排せつ介助 食事介助など |
| 生活援助 | 日常生活の援助であり本人の代行的に行われるサービス | 調理 洗濯 掃除など |
| 通院等乗降介助 | 通院等のための乗車または降車の介助※ | 乗降者 |
この中でも、私は②の生活援助の部分でのサービス内容で食い違いや過度な要求が発生する場合が多いと感じています。
生活援助の中には調理・洗濯・掃除などがありますが、利用者への直接的な援助であるかどうか、日常生活の範囲内かどうかが重要なポイントになります。
例えば、利用者の家族のための家事や調理、家族の衣類の洗濯、来客の対応などは利用者への直接的な援助ではありません。
また、庭の掃除や草むしり、飼っているペットの世話、日常生活の範囲以上の大掃除、窓のガラス磨き、お正月の準備などは想定されていません。この部分を最初にしっかり説明を行い、利用者や家族に理解していただくことが大切です。
最初に確認をしていても、お付き合いが長くなると、ホームヘルパーとの距離感が近くなり、このラインが曖昧になってきます。利用者や家族は「これぐらいならサービス内容を超えるけどお願いできそう」「これぐらいなら負担にならないから大丈夫だろう」と考えてしまう傾向があります。

【事例】タバコの購入はヘルパーに頼めるか
私も同様の事例に直面したことがあります。
Aさんは、週2回家事援助でホームヘルパーを利用していました。Aさんは下肢の病気で屈むことが難しく、お風呂やトイレの掃除、床掃除などが困難になっていました。
そこで、ホームヘルプサービスを活用して家事援助を行っていました。サービス開始当初、入っていただいていたホームヘルパーが退職するにあたり、別のホームヘルパーがサービスに入る形になりましたが、ある日Aさんから私宛てに「ヘルパーさんを交代してもらいたい」との連絡がありました。
Aさんに「どうしてですか?」と理由をお聞きすると、「ヘルパーさんがタバコを買ってきてくれない」とのことでした。前のヘルパーさんは購入してきてくれたのに、新しく来るヘルパーさんは、「タバコは購入できないんです」と拒否されたといいます。
そこで初めてAさんがホームヘルパーにタバコの購入を依頼していたんだなと知ることになりました。介護保険法によって定められている買い物代行の内容は、あくまで「日常生活に最低限必要な品物」が対象です。
タバコは嗜好品として取り扱われるので、通常ホームヘルパーは購入できません。そのため、私は「そのヘルパーさんは変なことを言ってるわけではないですよ」とお伝えしましたが、Aさんは納得がいかないようでした。
電話では説明が難しいと判断し、後日訪問をして再度買い物についてのルールのご説明とケアプランで定めているサービス内容について説明させていただきました。
その中でもAさんは「前のヘルパーさんはしてくれたのに」と話していました。事業所とも話しましたが、そのヘルパーが退職されているので詳細は不明だが、おそらく頼まれたついでに近隣のコンビニで購入していたのではないかとのことでした。
この場合、ケアプランにないサービスにもかかわらず、ヘルパーに依頼したら購入してくれたのでいつしか当たり前になってしまったのかもしれません。また、ヘルパーも一度OKしてしまったために断れなくなってしまったのでしょう。
ケアマネージャーとしては、常々サービス内容の確認と最初の説明の理解がしっかりされているかの確認も併せてする必要があったと反省しています。
タバコの購入については、ご自身か家族で対応していただき、ヘルパーには通常のサービスを行ってもらうよう調整しました。
このように一度行ってしまうと、利用者や家族もやってもらえると思ってしまうことがあります。その後できないと言われると、今までやってくれたのにとサービスが減らされたと感じてしまうかもしれません。良かれと思って一度でも引き受けてしまうと関係悪化のリスクが伴うのです。
ヘルパーに対する悩みは誰に相談すれば良いのか
介護保険でのホームヘルパーを利用する際はケアマネージャーが介在しています。
そのため、悩むことがあればまずは最初にケアマネージャーに相談するのが良いでしょう。ケアマネージャーは介護保険法に定められている中立公正・介護保険制度の順守を義務として定められています。その中でしっかり判断してくれると思います。
ただ、ヘルパーとケアマネージャーが同じ事業所の場合、連絡を躊躇される方もいるかもしれません。
直接ケアマネージャーに相談しづらい場合は、お住まいの地域の地域包括支援センターにご相談されるのも一つの手段かもしれません。地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを地域でサポートする施設で、高齢者のための総合相談窓口でもあります。
また、地域内のケアマネジャー向けにケアマネジメント支援の業務を担う公的な立場でもあります。
もし相談しても納得がいかない場合は、お住まいの市区町村の高齢部門を所管する部署に窓口が設置されていますので、そちらにお話する方法も考えられます。

お互いに折り合いが悪くなってサービス中止や事業所の変更に至る場合、決して気持ちの良いものではありません。そうならないためにも疑問に思ったことは事業所やケアマネージャーに相談しましょう。
ヘルパーに対する苦情は、コミュニケーションが少ないことが要因の一つだとも感じています。利用者の生活に一番近い役割を担うホームヘルプサービスは介護保険の中でも欠かすことのできないサービスです。
ぜひお互い積極的にコミュニケーションを取って、気持ちよくサービスを活用できるようにしましょう。