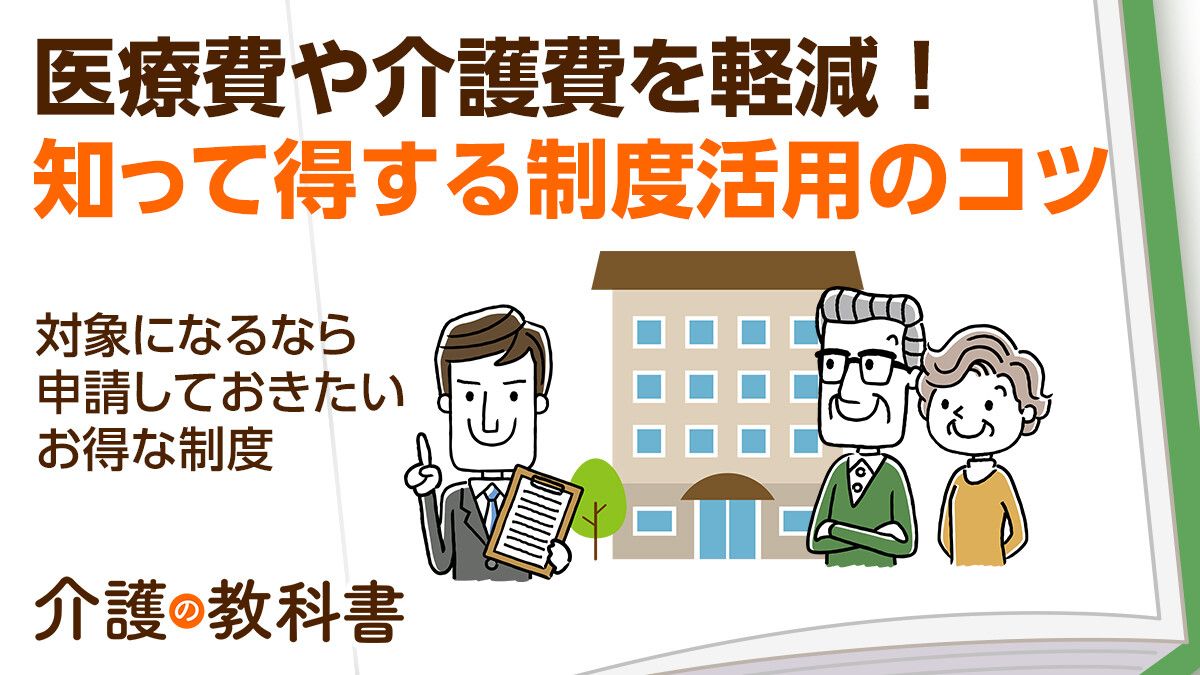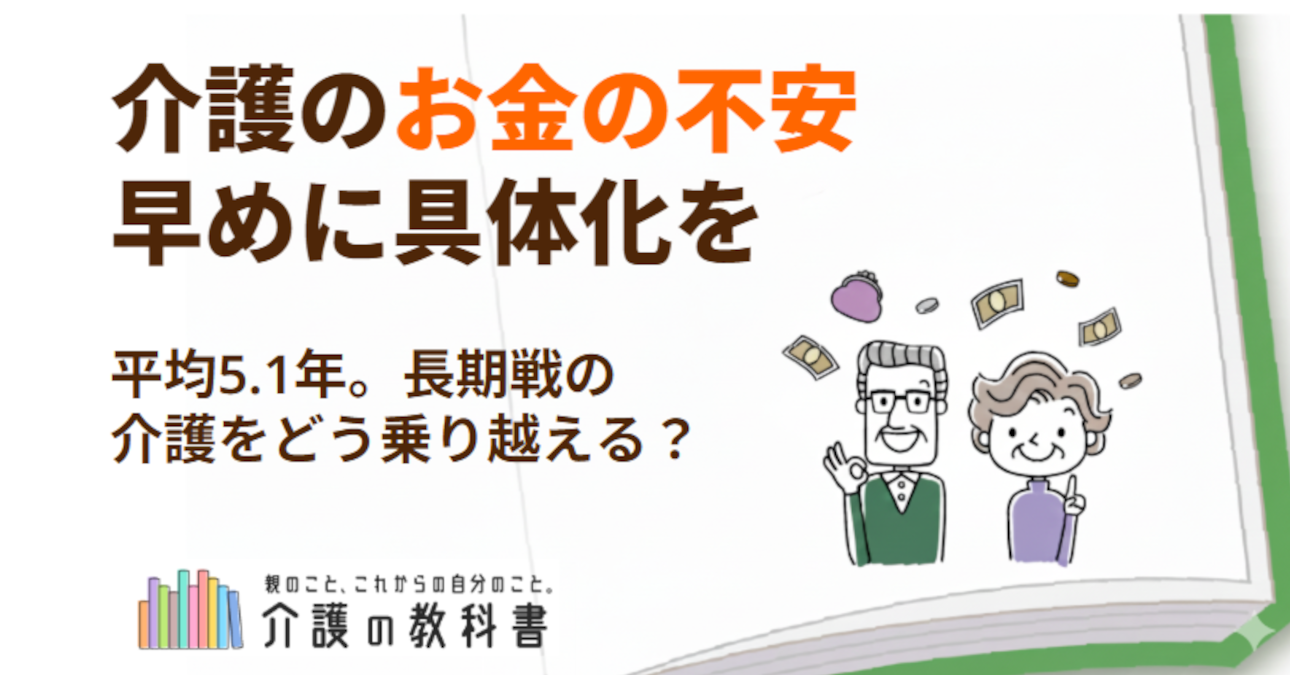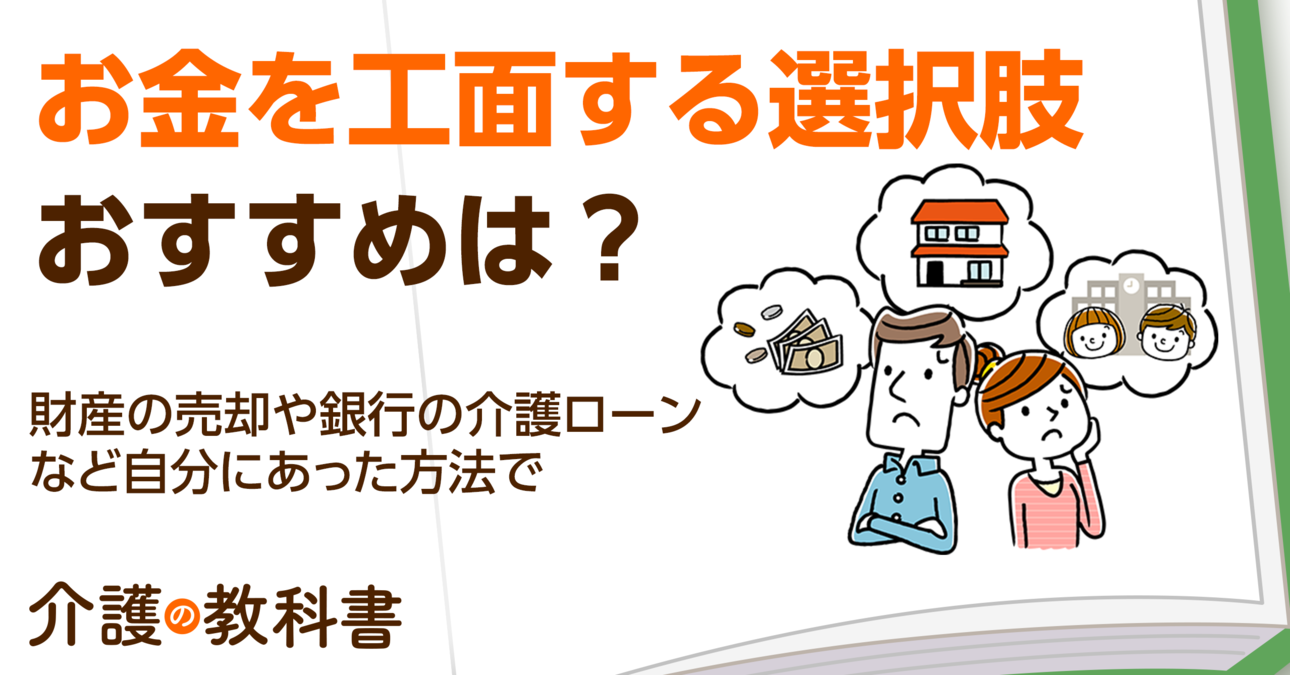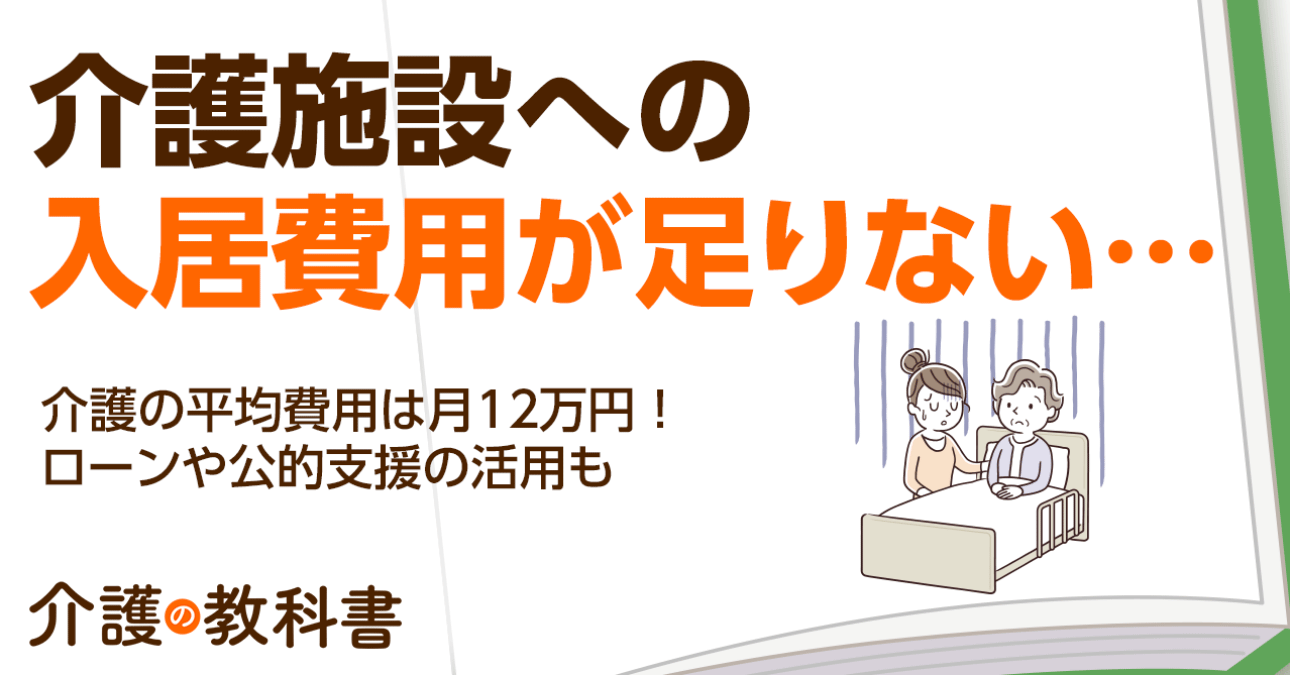もうじき年末を迎えますが、皆さん毎年恒例の年末調整や確定申告等の準備はされているでしょうか?
今回は、介護を必要とされている方や障がいがある方などが使える控除や制度を説明いたします。
控除や制度は基本的に申請を行わないと活用できませんが、周知されていないものもあります。また、申請書類の準備など理解してそろえていないと、いざ申請してみて書類の不足や不備があったりしてしまうことも。
今回は控除や制度などを解説するので、ご自身が対象かどうかを検討してみてください。
医療費控除に含まれる介護サービス
まず初めに医療費控除についてです。
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間にご自身や同居する家族などが10万円(または年間所得の5%の少ないほう)の医療費を支払った場合、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算されます。
所得控除を受けることができる制度で広く知られている控除だと思われます。
医療費控除と聞くと、あくまで病院などでかかった医療費と思いがちですが、実は介護保険でのサービスにも一部活用できる場合があります。
医療費控除の対象となる介護保険の居宅サービス
医療費控除の対象となるのは、介護保険の中でも医療系サービスとされているものです。基本的には医師等の指示や意見が必要になります。
医療費控除に含まれる介護サービス
①訪問看護※
②訪問リハビリテーション※
③居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】※
④通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】※
⑤短期入所療養介護【ショートステイ】※
⑥定期巡回・随時対応型訪問介護看護
⑦看護・小規模多機能型居宅介護
上記①~⑦の介護保険居宅サービスを利用していることが前提ですが、下記の介護保険サービスも医療費控除に含むことが可能です。
⑧訪問介護【一部制限あり】
⑨夜間対応型訪問介護
⑩訪問入浴介護※
⑪通所介護
⑫地域密着型通所介護
⑬認知症対応型通所介護※
⑭小規模多機能型居宅介護※
⑮短期入所生活介護【ショートステイ】※
※介護予防サービスを含む
ご自身やご家族の中で、もし対象になる介護保険サービスを利用していれば、毎月送付される支払いの領収書などをしっかり保管しておきましょう。
介護保険サービスを利用されている方は医療機関を利用されていることが多いので合算して活用できる制度です。
また併せて知っておきたい知識が、おむつ代も居宅サービス等において、医療控除に含まれる場合があることです。これは医療機関などが発行する「おむつ使用証明書」がある場合に限ります。
なお、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の場合には、「おむつ使用証明書」に代えて、市町村が要介護認定にかかわる主治医意見書の内容を確認した書類、またはその写しが必要となるのでご注意ください。
不明な場合は、担当してくれているケアマネージャーや包括支援センターなどに確認してみましょう。
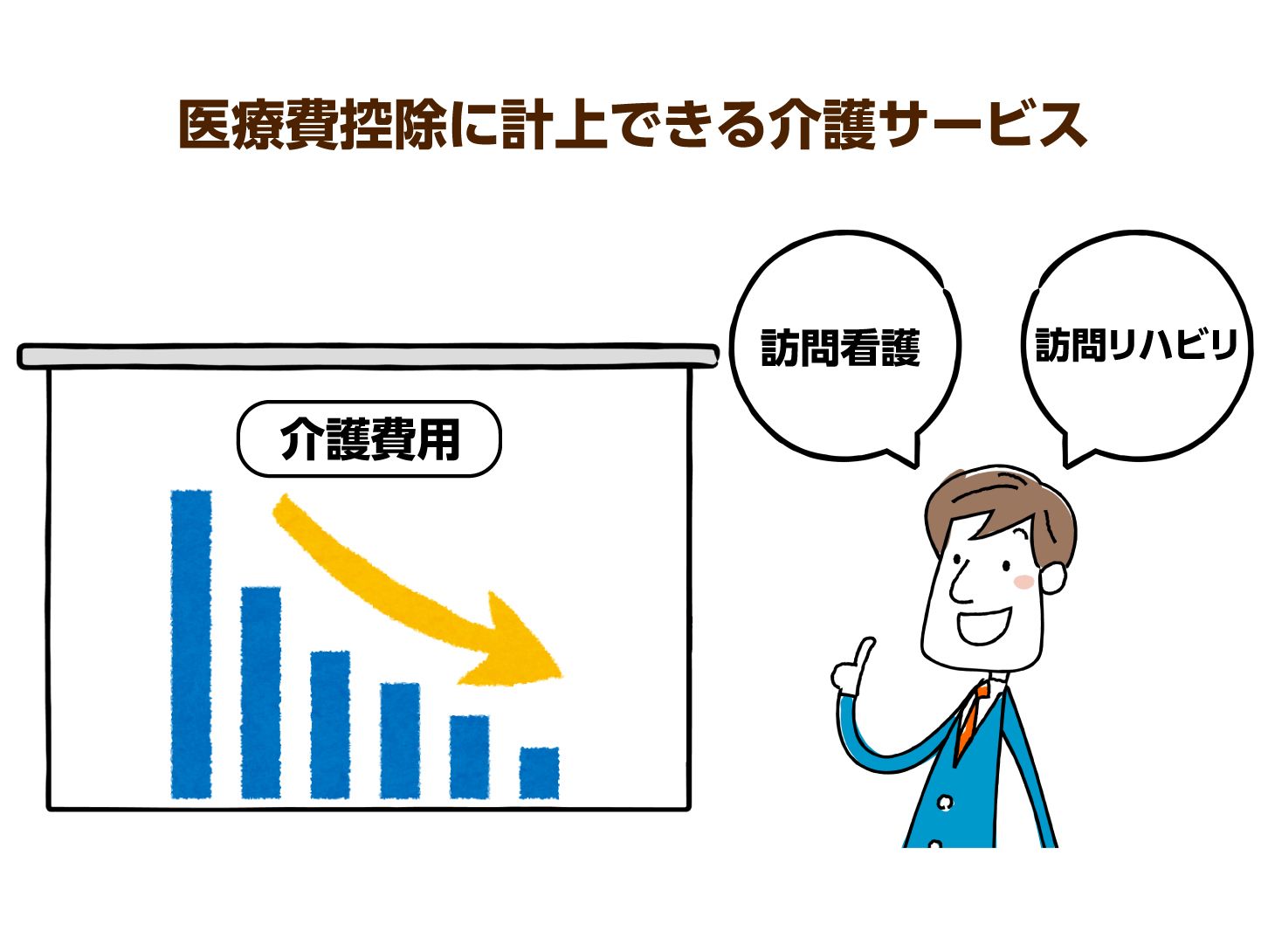
極端に医療費と介護費が高くなったときに使える制度
医療費控除や確定申告とは別に、「高額介護合算療養費制度」があります。この制度は2008年4月から利用できるようになった制度です。
この制度は、医療保険と介護保険における1年間(8月1日~翌年7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が著しく高額だった場合に、自己負担額を軽減する制度で申請をすることによって負担額の一部が払い戻されます。
この制度を活用するにはいくつかの条件があり、条件に該当する世帯は対象となります。
- 国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度の各医療保険における世帯内であること
- 1年間の医療保険と介護保険の自己負担合算額が、各所得区分に設定された限度額を超えた世帯であること
所得区分に応じた限度額は以下になります。
| 基準額(年額) | ||
|---|---|---|
| 一般 | 市町村税非課税者 | |
| 現役世代(70歳未満) | 67万円 | 34万円 |
| 後期高齢者医療制度 | 56万円 | 31万円 |
例えば、市町村税非課税の低所得に当たる方は1年間で医療費30万円、介護費用30万円で合計60万円を支払ったとしましょう。その際、基準額となる31万円を超えた金額(29万円)が支給されます。
ご自身が対象となるかなど、詳細については各区市町村の窓口で相談してみてください。
障がい者控除を受けられる特例
次に利用できる制度として障がい者控除が挙げられます。
障がい者控除とは、障がいのある人やその家族が受けることのできる税法上の制度のことです。障がい者控除は大きく3つの区分に分けられます。
- 障がい者
- 特別障がい者
- 同居特別障がい者
障がい者控除は障がい者手帳がないとできないと思われていますが、実はそうではありません。例えば、特別障がい者は以下のような方が認定されます。
- 身体障がい者手帳の等級が1級もしくは2級
- 精神障がい者保健福祉手帳の等級が1級
- 原子爆弾被害者の認定を受けている
- 重度の知的障がいがある
次に、障がい者は、下記にあてはまる場合と定められています。
- 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている
- 身体障がい者手帳に身体上の障害があると記載されている
- 療育手帳などの交付を受けている
- 戦傷病者手帳の交付を受けている
- 65歳以上かつ市町村によって障がい者控除の対象と認められている
国税庁のサイトを確認すると、より詳しく書かれていますので確認してください。
なお、基本的には障がい者手帳が必要ですが、障がい者手帳を申請中の場合は特例として障がい者控除を受けられる場合があります。
この場合は医師の診断書で代用することもできるので、控除の書類を提出する時期に間に合わないときは、お住まいの市区町村の窓口へ相談・確認をされてください。
また、障がい者手帳を取得していなくても、市町村が発行している「障がい者控除対象者認定書」を持っている場合も障がい者控除の対象となります。
この「障がい者控除対象者認定書」の交付対象は、65歳以上かつ「寝たきりの高齢者」や「知的障がい者に順ずる症状がある」などに定められています。最終的な認定は自治体によって異なる場合もあるので、お住まいの市町村の窓口へご確認ください。

まとめ
今回ご紹介した控除や制度で共通しているのは、自身で確認して申請しないと活用できないということです。
申請だけでなく、医療費や介護保険自費分の領収書の保管など手間もかかるので、まずはご家族や専門職と相談しましょう。
対象になる方が、どの控除や制度を活用するか検討して、その手間を含めた費用対効果も考えることは、長い介護生活において非常に大切です。
現在は、生活上必要な物が値上がりして家計を圧迫しています。そんな今だからこそ、制度を理解して、上手に活用すれば少しでも負担を軽減できるかと思います。
利用可能な制度は、対象者の居住地や属している保険組合などでも違いがあるので、事前に窓口へ相談しておきましょう。
自身が対象かどうかを知っておくだけでも、今後対象になった場合にスムーズに手続きができるでしょう。ぜひ前もって確認しておくことをおすすめします。