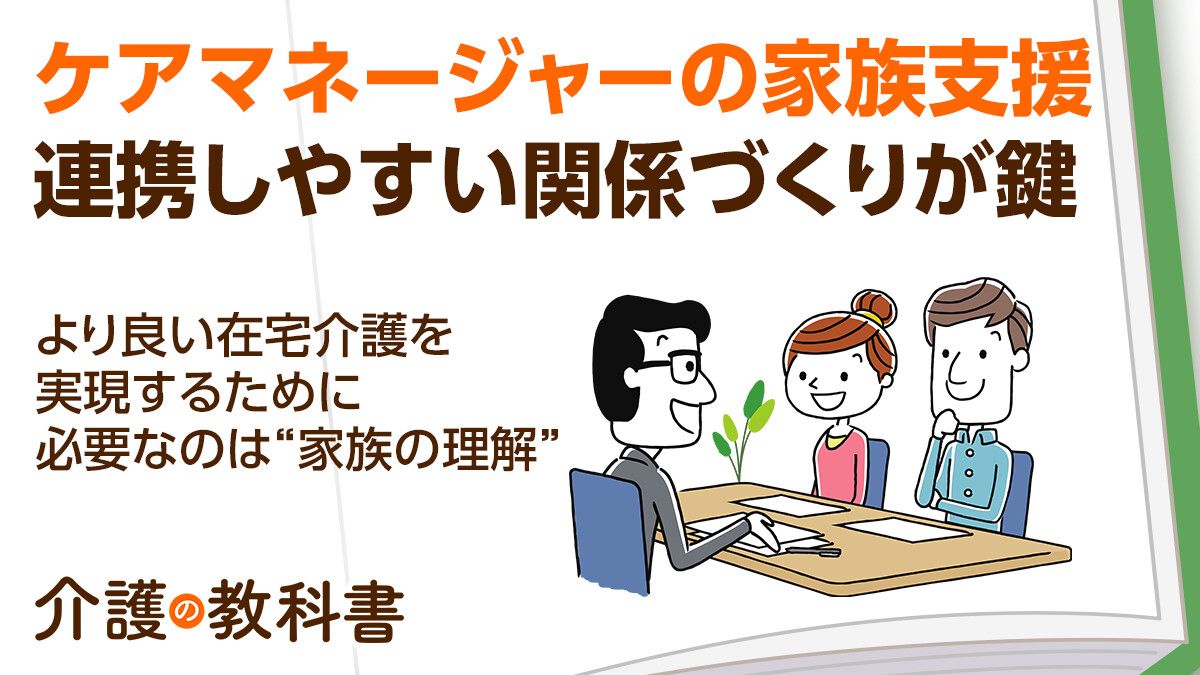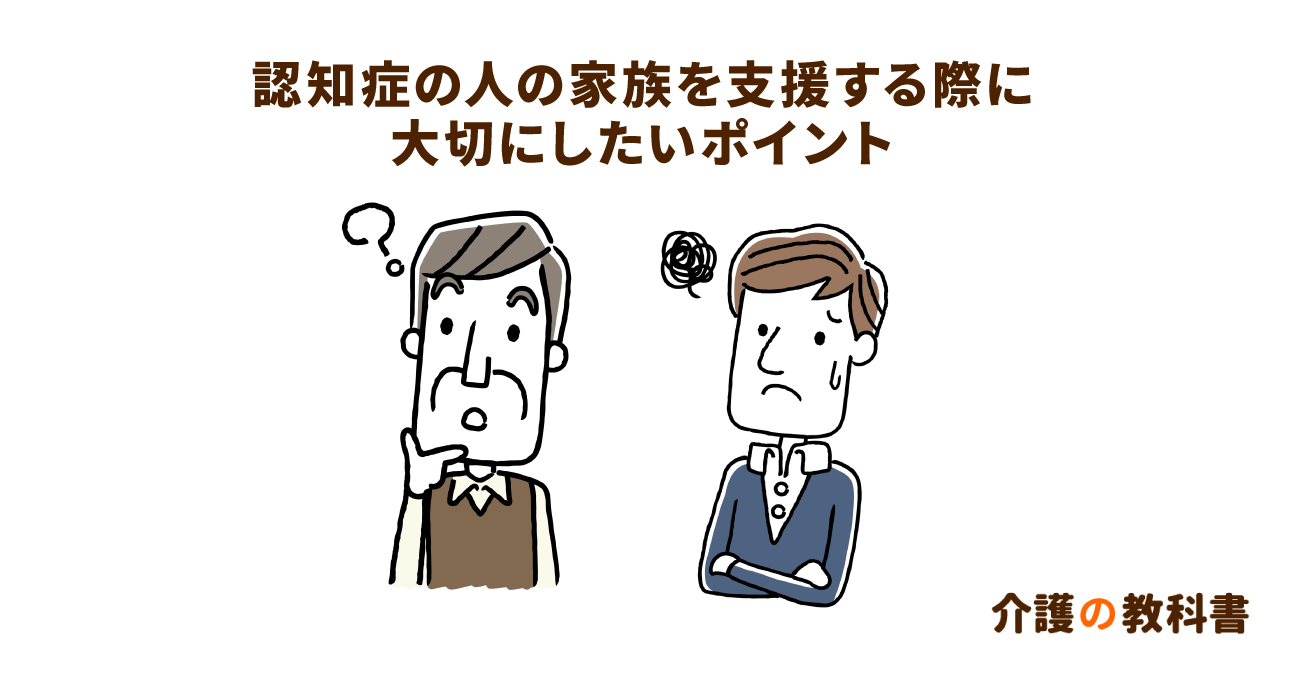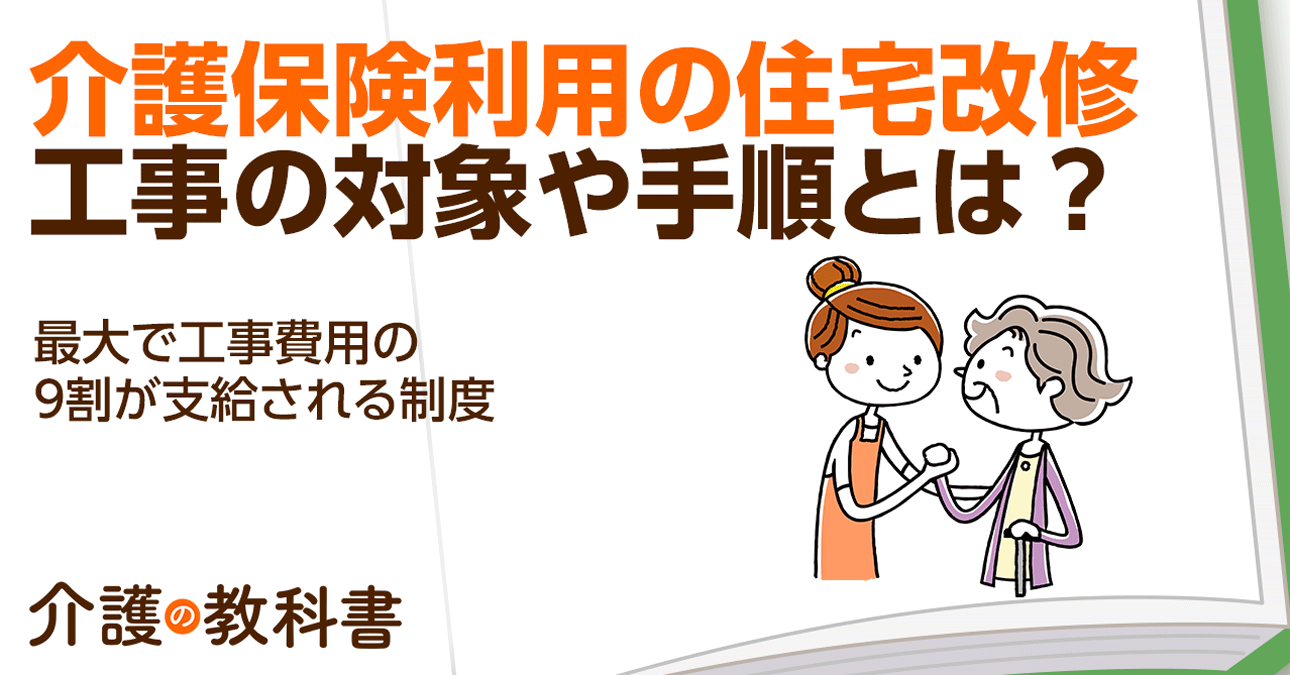ケアマネジャーの業務として一番重要なのは利用者本人に寄り添うことです。しかし、実際に支援をしていく中で大切になるのが「家族側の理解」です。
例えば、金銭管理を家族が行っているケース。介護保険のサービスを実際に利用することになったとき、経済的な面では家族との相談が必要になります。
そこで今回は、ケアマネジャーが家族に対して実際に行っている支援について解説していきたいと思います。
ケアマネジャーと家族の連携による支援事例
家族の形態は実にさまざまです。例えば、要介護者と同居しているけど、仕事の関係で帰りが遅かったり、シフト制の仕事で休みが不定期なご家族もいます。
ほかにも、近所に住んでいて週に何度も要介護者宅を訪問するご家族もいれば、遠方に住んでいて年末年始やお盆休みでないと帰省できないご家族もいます。なかには事情があって疎遠になってしまっているケースも…。
こうした家族の形によって支援していく内容や相談内容も変わってきます。
私が実際に行った支援をご紹介いたします。
【終活支援のアドバイス】
まずは、私が現在担当しているAさんの事例です。Aさんは要介護1の認定を受け、末期がんの宣告を受けています。ただ、本人には病状について伏せている状況です。
Aさんは仕事の関係で家族とは離れた場所で一人暮らし。結婚歴もなく、定年まで勤めあげられました。Aさんには結婚していて子どものいる妹のBさんがいます。
Bさんは車で20分程度のところに住んでいましたが、Aさんの状況を見かねてAさんと同居することになりました。Bさん親子は、できる限り在宅で看取りたいといった意向です。
先日訪問に行ったとき、BさんからAさんがお亡くなりになった後に入る「お墓」についての相談を受けました。
できればBさんの自宅から近い納骨堂を探しているけど、どこかいいところを知らないか?という相談でした。
AさんもBさんも、新聞広告では見つけていたのですが、他の場所も気になる様子だったので、最終的には、自宅からは少し離れた、私の知り合いの霊園を紹介しました。
ケアマネジャーは、こうした「終活」についての相談を受けることもあります。
【貯金が家族によって浪費されている…】
「要介護4」の認定を受け、ほぼ寝たきりの状態のCさん。夫には先立たれていて、知的障がいのある息子と同居していました。
Cさんは認知症がひどく、糖尿病の持病もある方でした。ただ、血糖値が400を超えるほど悪化しているのに、受診を拒否されていました。
自宅の中は物であふれかえり、足の踏み場は何とか確保できている状況。車で約1時間のところに住んでいるCさんの姪親子が週に1回ほど訪問し、買い物などの支援をしてくれていました。
Cさんは、若いときから息子のために貯金をしていて、当時の貯金額は1,500万円ほど。しかし、気づいたときには貯金が300万円まで減っていました。
現場で対応しているヘルパーさんなどの話によると、姪親子が買い物に行く際の交通費と称して、金品を持ち帰っているとのこと。
そのため、知り合いの弁護士に相談し、成年後見制度を利用して、Cさんの金銭管理を行ってもらうようにしました。
また、息子の支援については、障がいの相談支援専門員がついていたので、そちらに支援してもらうことにしました。その後Cさんはお亡くなりなりましたが、息子さんは障がい者施設に入所する運びになりました。
このように、同居している息子が知的障がいなど、家族の意向を明確に把握できない事例もありますし、ご家族によって金品が浪費されてしまうようなケースもあります。

【兄弟の折り合いが悪く、連携がうまくいかない…】
次は認知症を発症して「要介護1」の認定を受けた一人暮らしのDさんの事例です。
すでに金銭管理や服薬管理もままならない状態でした。
息子が二人いますが、兄弟仲がとても悪く、どちらかが支援しようとしたら、どちらかが疎遠になるといった関係です。
そのため、本人宅に訪問してきているのかも不明でした。また、一度長男と電話で話をしたことがありますが、非常に感情的な口調で言われる方なので、それ以来コミュニケーションが取りづらい状況になっています。
その後、地域包括支援センターに相談して、何かあれば対応してもらうように依頼しました。
最近わかったことですが、親戚の方がたまたま福祉用具貸与事業所に勤めていて、その方が訪問したとき、立ち座りなどでふらつきがひどい状況に気が付いたそうです。
そこでDさんの意向を聞いて、福祉用具で手すりをレンタルすることになりました。それ以来は親戚の方が訪問してくれるようになり、以前よりは支援がしやすい状況になってきています。
このように、要介護の方に適切にサービスを利用してもらうためには、家族の理解が必要になってきます。
ケアマネジャーと家族との関係が大切
ケアマネジャーは、介護保険制度のプロです。状況に応じて、家族の介護負担を軽減するためにショートステイの利用を勧めたりするなどの支援を行っています。
また、利用者さんの身体状況や病状に応じて、施設入所を勧めたりすることもあります。
ただ、それだけでは済まないケースもたくさんあるのです。特に在宅介護の現場では、ニーズが多岐にわたるため、柔軟な対応力が求められます。
ケアマネジャーは、介護保険制度以外のあらゆる制度や、さまざまな異業種の方と連携を図っておく必要があります。

ケアマネジャーは、定期的に研修等を受けており、その中で常々言われるのは、介護保険のサービス(フォーマルサービス)とそれ以外のサービス(インフォーマルサービス)を結びつけるということです。
インフォーマルサービスの中には、もちろん「家族の支援」というのも含まれます。
利用者さんが住み慣れた自宅で自立した生活を送るためには、家族の理解や協力が必要です。
利用者さんは高齢で、持病を抱えている方がほとんどですが、急変時はご家族の判断を仰がないと、勝手にサービスにつなげることはできません。
在宅介護では、ケアマネジャーと家族の双方が協力し合える関係を築くことが大切なのです。