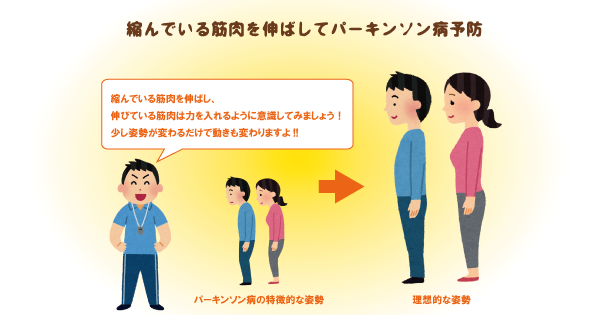こんにちは。「カラダブログ」を運営し、「多くの人が病院に行かないような文化を作りたい!」をテーマに活動している理学療法士の吉田直紀です。
介護者であるみなさん自身が健康であり続けるためのトレーニングや、ご両親やご家族に元気になってもらうためにスキルをお伝えしていきます。
第5回目となる今回は、「脳梗塞で片方の手足が動かない…」そんな家族を見ていて「私にもしてあげられることはないか?」というあなたに「家庭でもできる簡単全身ストレッチ」をお伝えします。
ストレッチの効果

寝たきりになると全身の血液循環が悪くなり、体がむくみやすくなります。加えて、体を動かさないことで関節が固まって動きにくくなる「拘縮」を引き起こす原因にもなってしまうことはご存知でしょうか。
まずは第1章で「ストレッチの効果」を知っておきましょう。要介護者のモチベーションを上げるためにも、ストレッチをして上げる前に伝えられるといいですね。
ストレッチの効果
- 副交換神経*を優位にするリラクゼーション効果
- 血流を促進する
- 関節の可動域を維持、拡大する
- 筋肉の緊張を和らげる
※副交感神経とは…リラックスをしている時に働く神経のこと。昼間の活動で疲れた体を修復するのが役割。
ストレッチの強さ加減とオススメ時間

自分でストレッチを行う分には痛みや伸ばす具合を加減しながらできます。しかしストレッチをする側になると、どれくらいの強さで行えばいいのか?どれくらいの時間を行えばいいのか?という疑問が出てきますよね。
明確な指標はないので、あくまでストレッチする側の主観になります。まずはゆっくり、そして優しく伸ばしてあげることがポイント。勢いよく反動をつけて痛みの出るようなストレッチは逆効果なので要注意。
痛みを伴ってしまっては、身体機能の改善が見られたとしても要介護者のモチベーションが下がってしまいます。「痛い?」「もう少し強くしても大丈夫?」など、常にコミュニケーションを取ることを忘れないでください。
オススメのストレッチ時間
- 体が温まっているお風呂上がり時
- 朝起きて体が動きにくいからこその起床時
- 運動の前後
- 体が疲れている時
※「食後」以外であれば特に問題はありません。食後は、消化のために内臓に血液が集中するため好ましくありません。
ストレッチは約20~30秒伸ばした状態を維持します。ストレッチをしてもらう人の呼吸が止まらないように呼吸を促しましょう。20~30秒たったらゆっくりと関節を戻して少し休ませてあげましょう。これを2~3セット繰り返します。
下半身のストレッチ ~足・膝・股関節、体幹編~
- 足関節のストレッチ
- <POINT>
足関節のストレッチは第1回目「カラダが硬くならないストレッチ~足関節編~」で紹介した、足首の背屈・底屈という動きです。ふくらはぎ周りの筋肉を刺激して血流を良くするために重要なストレッチです。 - 膝関節のストレッチ
- <POINT>
膝関節は曲げ伸ばしができる関節です。特に寝たきりの方は膝が伸びにくくなります。痛みのない範囲で膝を伸ばす運度を中心に行いましょう。 - 股関節のストレッチ
- <POINT>
股関節は曲げる・伸ばす・開くなど様々な方向に動く関節。満遍なく股関節を動かすことが大切になります。 - 体幹のストレッチ
- 体の中心のストレッチです。今回は仰向けで行うストレッチを紹介します。
上半身のストレッチ ~手・肘・肩関節、肩甲骨編~
- 手関節のストレッチ
- <POINT>
手首もそうですが、手の指が伸びにくくなっていることがあります。痛みが出やすい部位でもあるので少しずつ伸ばしてあげましょう。 - 肘関節のストレッチ
- <POINT>
肘は伸びにくくなることがほとんどです。主に肘関節を伸ばす方向にストレッチを行いましょう。 - 肩関節のストレッチ
- <POINT>
肩関節は股関節と同じ形をしていてとても動きやすい関節です。股関節と異なる点は「不安定」という点です。相手の関節可動範囲を無視したストレッチは肩を痛めてしまうため慎重に行いましょう。 - 肩甲骨のストレッチ
- <POINT>
肩関節の土台になる肩甲骨です。肩関節のストレッチよりも安全で肩周りの動きを良くする方法です。肩甲骨周りにはたくさんの筋肉をがついているので大きく動かしてあげることが大切です。
<素人の危険・安全なマッサージ>
- 押す
- 揉む
- 叩く
寝たきりや動く頻度が少ない人は体の血行が非常に悪くなります。しかし素人の方が安易に「マッサージ」を行うことは危険を伴います。素人の方が行うマッサージにありがちなのは「強すぎる」ことです。
以上の3つの方法を使うマッサージはプロの方に任せた方が安心です。
筋肉や靭帯、骨の場所が的確にイメージできて触ることができればよいのですが、素人の方には難しいです。押す・揉む・叩くが強すぎると組織を潰して炎症を起こすことがあります。
特に脳梗塞を起こしている方は薬を内服している人がほとんどだと思います。血液をサラサラにするような薬を飲んでいる人は注意しましょう。強いマッサージで皮下出血を起こすこともあります。
もし行う場合は安全にできる軽くさするようなマッサージを行いましょう。上記にお伝えしたストレッチとマッサージを併用すると全身の関節の動きと血流が良くなります。
本日のまとめ
- とにかくストレッチやマッサージは安全にできること
- 自信がない方は専門家の意見を聞くこと
- 介助者が無理のない範囲で行うこと
大切なことは介助者側が無理なく行うことです。介助者側が体を痛めないよう、ライフスタイルに無理が生じない程度に継続することがポイント。
ランニングと同じで一回で10km走るよりも1日5分でいいから走ることを続けることが大事。ストレッチやマッサージも同じです。習慣化させてあげることが大切になります。
動画も参考にしながらぜひ実践してみてください。
繰り返しになりますが…
「要介護者に楽しんでもらう!」これが1番大事だと思います。「お孫さんと外で遊べる!」「また自分の足で歩ける!」「自分でお箸を使ってご飯を!」その気持に応えてあげたいですね!
在宅介護は大変だと思いますが、「介護の教科書」・「カラダブログ」を通してサポートしていきます。
次回もお楽しみに!