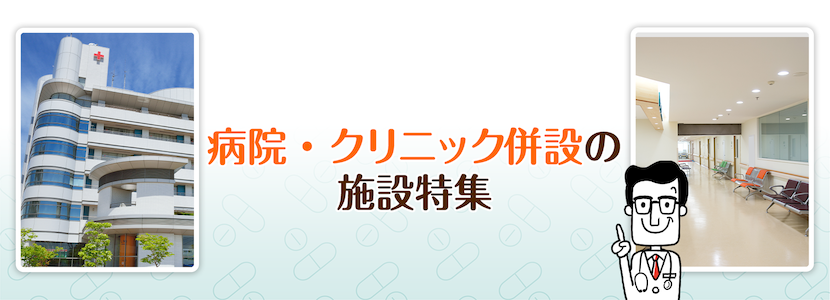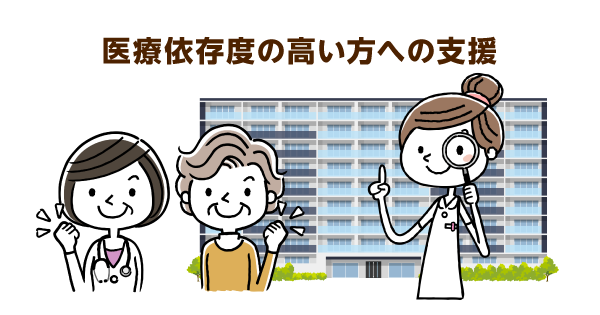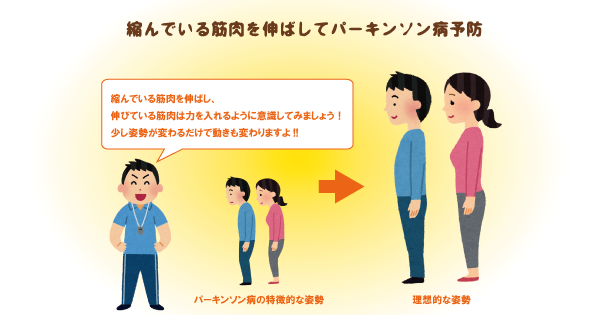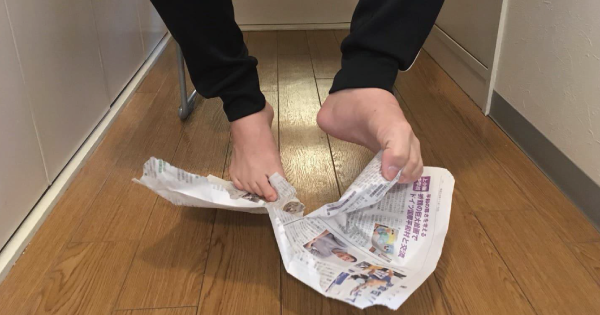はじめまして。理学療法士ブログ「リハ塾」を通じて専門的な体の知識を発信している、運動指導の専門家・理学療法士の松井洸です。
本記事をご覧になっている皆さんは呼吸について考えたことはありますか?
普段、私たちは当たり前のように呼吸をしていますが、肺炎や慢性閉塞性肺疾患(COPD)といった呼吸器疾患は増加傾向にあります。また、呼吸器疾患でなくても「深呼吸をしてください」と促すとできない方が多くいらっしゃいます。
今回はそんな呼吸についての知識とうまく呼吸をするためのポイントをご紹介します。動画もあるのでぜひご自宅で実践してみてください。
呼吸疾患は死因の上位 呼吸器疾患は死のリスク大

2016年に発表されている厚生労働省による死因別の死亡者数の統計を見ると、肺炎は第3位になるほど死亡者数が多いことがわかります。COPDは男性の死因の第8位となっており、これもまたかなり多い死亡者数となっています。
また、これら呼吸器疾患は今後さらに増加していく疾患は今後さらに増加していくと言われています。
その背景には呼吸器疾患よりも死亡率が高い心疾患や感染症など他の原因による死亡数の減少に伴なって呼吸器疾患の死亡者数が増加していくということ。
心疾患で死亡した方の中にも肺炎やCOPDで死亡した方が含まれているため、診断がより精度を高めるとともに呼吸器疾患で死亡された方が増えていくということがあります。
さらに、非喫煙者に比べて喫煙者の方が呼吸器疾患を発症する確率が3倍近くとなっており、現在喫煙していなかったとしても過去に喫煙歴があっても同等の値となっています。
喫煙してもすぐに発症するというわけではなく、20年以上の時間差で発症するので若年層の喫煙率が高くなっている日本では今後ますます呼吸器疾患患者数は増加していくことが懸念されています。
また、団塊の世代がこれから高齢者となることで高齢者数は一気に増加しますが、その中には過去に喫煙歴のある方も多く含まれているため、若年喫煙率の増加と喫煙歴のある団塊の世代の高齢化が大きな問題となると予測されます。
これだけ呼吸器疾患の死亡率が多いことは意外と皆さんご存知ないのではないでしょうか?
自分は絶対大丈夫とは言えませんし、生きていく上で呼吸は切っても切り離せない関係にあるのでこの機会に呼吸についての知識を深めていただけると幸いです。
なぜ呼吸が必要なのか? 生命維持には呼吸が一番重要

そもそもなぜ呼吸が必要なのでしょうか?
人は肝臓、腎臓、あるいは上位脳が損傷されても数日間は生き延びることはできますが、呼吸及び循環が約5分停止すると組織の酸素欠乏によって死に至るとされています。
当たり前のことではありますが、呼吸が止まると人は死んでしまいます。当たり前すぎて深く考える機会がないかもしれませんが、重要なことなのでよく考えてほしいのです。
死ぬまではいかなくとも、呼吸によって酸素を体内に取り込み、その酸素を全身の組織へ供給して循環しています。この酸素の取り込み・循環が滞ると筋肉や臓器も本来の働きを発揮できません。
それが長期的に見ると、肺炎やCOPDなどの呼吸器疾患をはじめ、筋力低下によって関節の障害や脳卒中などの脳の障害を引き起こすことも予測できます。
つまり、呼吸がうまくできないことは呼吸器疾患だけではなく、関節疾患や脳疾患を引き起こす可能性があるのです。
大げさかもしれませんが、組織が働くためには必ず酸素が必要です。その酸素が十分に供給されないことは組織のパフォーマンスを低下させることにつながります。自分の呼吸はうまくできているのか、考えてみてほしいのです。
呼吸のメカニズム 横隔膜を意識した呼吸

確認ポイント
- 胸郭の動き
- 横隔膜の働き
簡単に言えば、呼吸=呼気(息を吐くこと)+吸気(息を吸うこと)と表すことができます。呼気は安静時は自動的におこなわれており、肺が膨らんだ後にしぼむ力を利用して呼気が起こります。
ゴムのようなものだとイメージしてもらうと分かりやすいかもしれません。ゴムを引っ張って離すと勝手に縮みますよね? 肺も同じような特性を持っており、吸気によって肺に空気を取り込むと肺は広がり、吸気をやめると広がった肺は元に戻ろうとするため肺の中の空気が押し出されるというわけです。
吸気は横隔膜と外肋間筋という2つの筋肉が主に働き、その7割を横隔膜が担っています。横隔膜はあばら骨の一番下の内側にあり、吸気で横隔膜が下がることで肺により多くの空気を取り入れることができます。この時お腹が膨らむ形になります。
外肋間筋はあばら骨とあばら骨の間にあり、あばらの間を広げる働きを持っています。吸気の7割を横隔膜が担っているので、吸気に関しては横隔膜の機能が非常に重要です。
さらに、横隔膜の働きによって肺に空気を取り入れ、肺がしぼんで空気を吐き出すためには、肺や横隔膜といった組織を覆っている胸郭の動きも十分にあることが必要となります。
あばら骨が左右12対あるのですが、それらをまとめて胸郭と呼びます。胸郭はあばら骨と胸の真ん中の胸骨と呼ばれる骨、背中の背骨とそれぞれ関節を作っています。
つまり、この関節の動きが悪くなると胸郭は広がったりしぼんだりできなくなるため、呼吸にも影響が出てしまうのです。
呼吸をスムーズにするための運動療法(動画)
より多くの空気を取り入れ、吐き出すこともスムーズにできるようになるための運動をご紹介します。
これをすることによって、胸郭の動きを良くする、横隔膜の働きを促すことができます。
- 胸郭を広げるトレーニング
-
- ①あぐらまたは座位になる
- ②胸骨(胸の真ん中の骨)の中心をトントンと叩く
- ③そこの奥、胸と背中の間に空気を入れるイメージで鼻から吸って胸郭を広げる
- ④胸は膨らませたまま鼻から息を吐く
- ⑤3~4を3回繰り返す
- ⑥2~6を繰り返す
- <POINT>
- 胸郭を前後左右に膨らませる
- 背中側は膨らませにくいので特に意識して膨らませる
- 肩がすくまないように注意
- 横隔膜を働かせるためのトレーニング
-
- ①あぐらまたは座位になる
- ②へそから指4本分下のをさわる
- ③その奥、お腹と腰の間に空気を入れるイメージで鼻から吸って下腹を膨らませる
- ④お腹は膨らませたまま鼻から息を吐く
- ⑤3~4を繰り返す
- ⑥鼻から息を吐いて脱力
- ⑦2~6を繰り返す
- <POINT>
- お腹を前後左右に膨らませる
- 簡単なトレーニングなのでぜひご自宅でやってみてください。普段なかなか動いてくれない要介護者の方も、動画を見ながらだと動いてくれるかもしれませんよ。
本日のまとめ
重要ポイント
- 呼吸器疾患は年々増加傾向で今後も増加していくことが予測されている
- 呼吸は生命維持のために必要
- 呼吸が悪くなると、組織の酸素が不足してしまい、関節疾患や脳疾患になる可能性もある
- 呼吸には胸郭の動きと横隔膜の働きが重要
いかがでしたでしょうか?呼吸の重要性を少しでもお分かりいただければ幸いです。
呼吸が悪くなると、筋肉や臓器、脳への酸素供給が滞ってしまうため、筋力低下による関節疾患や脳梗塞など脳疾患を発症してしまうことも予測できます。呼吸は毎日欠かすことなく誰もが行っているものですが、意外と呼吸についてはよく分からない場合も多いです。
これを機会に自身の呼吸を見直してみてはいかがですか?最後までお読みいただきありがとうございました!