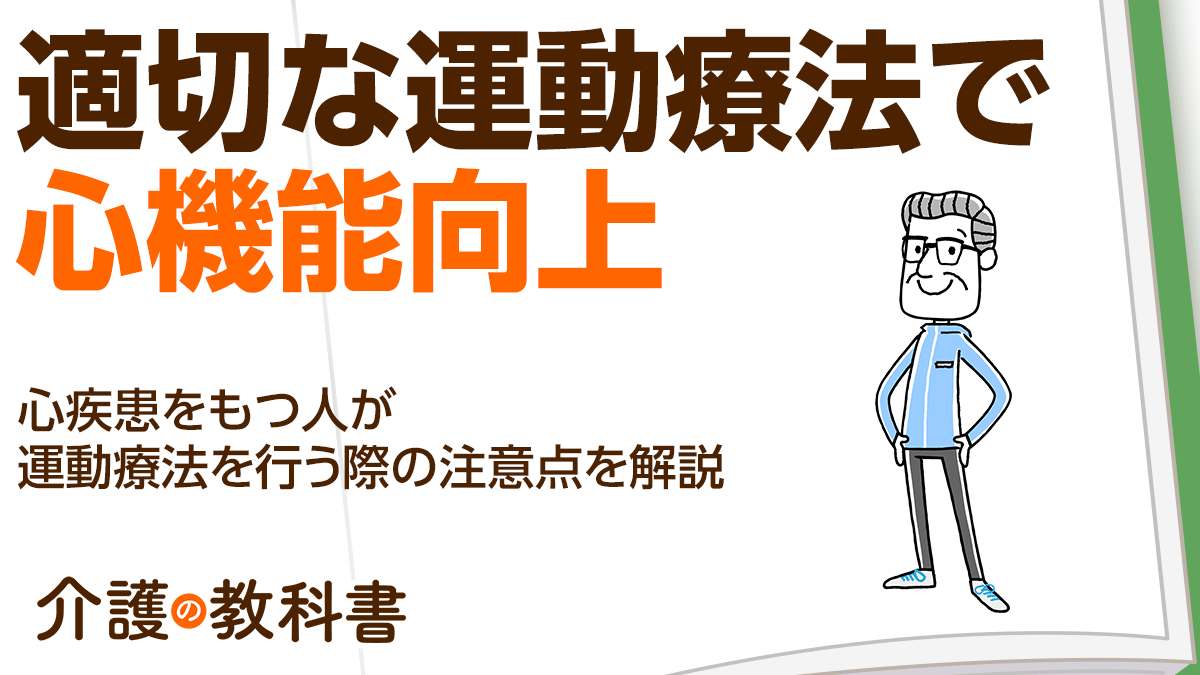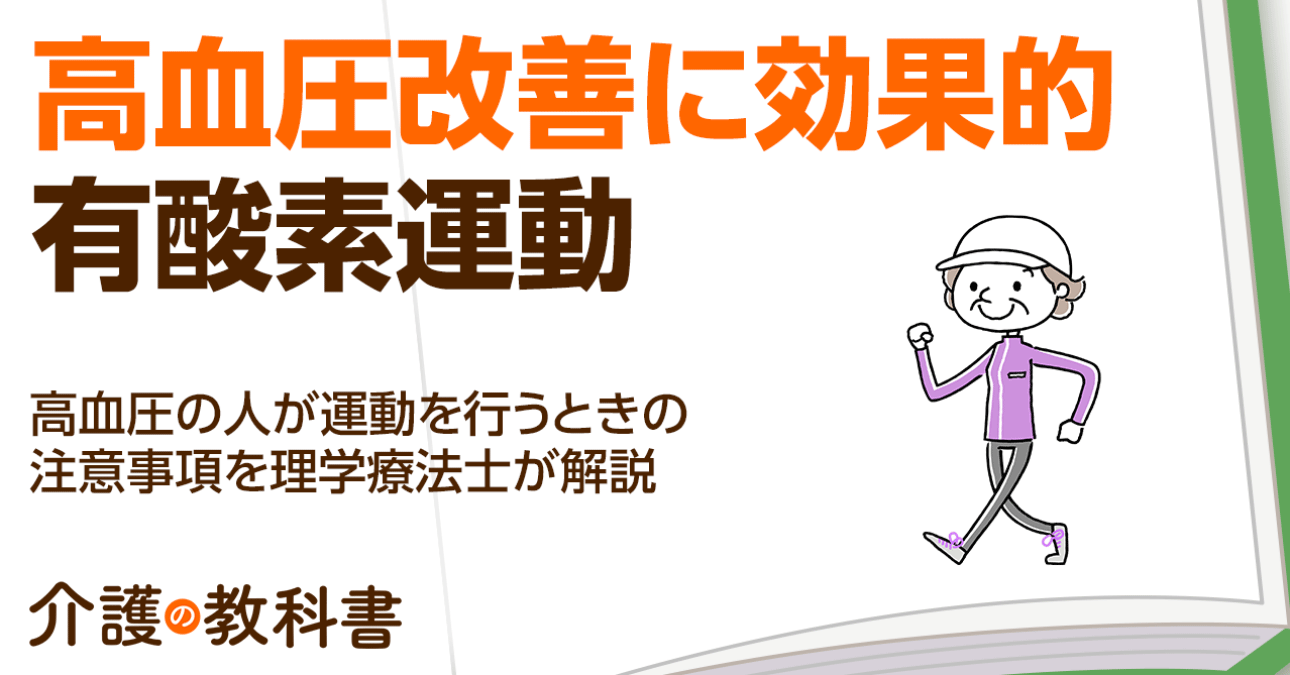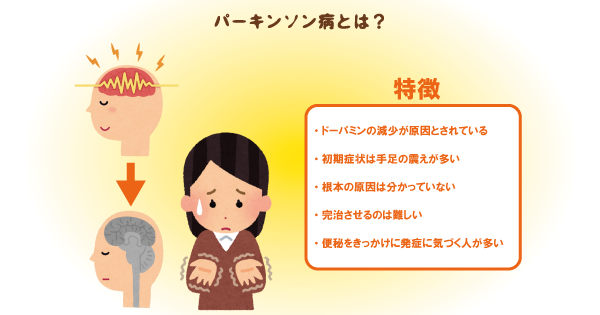心疾患を抱えると、活動量に制限がかかりやすくなる一方で、運動療法の実施が重要なことをご存じでしょうか。運動療法を行うことで心機能や持久力が向上し、生活の質(QOL)を高められる可能性があります。
この記事では、心疾患の方に対する運動療法の内容や注意点についてご紹介します。適度な負荷の運動習慣を身につけることで、心疾患の改善が期待でき、今よりも活動の範囲が広がるようになるでしょう。
心疾患の種類
心疾患にはどのような種類があるのでしょうか。代表的な心疾患についてみていきましょう。
虚血性心疾患
虚血性心疾患とは、心臓に血液が流れなくなることで起こる病気です。虚血性心疾患では、おもに「狭心症」と「心筋梗塞」に分かれます[1]。
狭心症とは、心臓の血管が狭くなって血液の流れが悪くなった状態のことです。狭心症を発症すると突然締めつけられるような胸痛が起こり、数分から十数分程度で発作が落ち着きます。
心筋梗塞とは、血栓(血の塊)などの原因によって心臓に血液が流れなくなった状態のことです。激しい胸痛のほかに、呼吸困難や吐き気などの症状が数十分、長くて数時間に及ぶことがあります。心筋梗塞は、場合によっては突然死するケースもあります[2]。
心不全
心不全とは、全身の血液を循環させる働きのある心臓の機能が低下する状態のことです。心臓は左右(左心系・右心系)によって役割が異なり、それぞれ以下のような働きがあります。
- 左心系:血液を全身に送る
- 右心系:全身から戻った血液を肺に送る
心不全は左右どちらかの機能が低下しているかによって、症状が変化するのが特徴です。例えば、左心系の心不全であれば全身に血液を送れないため、息切れや「ゼーゼー」といった喘鳴(ぜんめい)などが表れます。右心系の心不全だった場合、血液が心臓に戻りにくくなるので、むくみや体重増加などの症状が起こりやすくなります[3]。
不整脈
不整脈とは、脈のリズムが乱れている状態のことです。不整脈には大きく分けて「頻脈性不整脈」と「徐脈性不整脈」「期外収縮」の3種類に分かれており、それぞれの特徴と症状は以下の通りです[4][5]。
- 頻脈性不整脈:心拍数が100回/分以上の状態(症状:動悸やめまいなど)
- 徐脈性不整脈:心拍数が50回/分未満の状態(症状:息切れやめまい、倦怠感など)
- 期外収縮:脈が急に飛んだり、止まったりする状態
期外収縮は正常な方でも起こるとされており、とくに目立った症状が表れずに経過する方もいます。一方で、他の種類の不整脈は命にかかわるような症状が表れるケースもあるので、適切な処置が必要となることも珍しくありません[6]。
先天性心疾患
先天性心疾患とは、生まれつき心臓の働きや構造に異常がある状態のことです。生まれた子どもの100人に1人は先天性心疾患を持っているといわれており、発症する明確な原因はわかっていません[7]。
先天性心疾患にはさまざまな種類があり、代表的なものは以下の通りです[8]。
- 心室中隔欠損症:「心室」と呼ばれる心臓の部屋の間にある「心室中隔」に穴が開くこと
- 心房中隔欠損症:「心房」と呼ばれる心臓の部屋の間にある「心房中隔」に穴が開くこと
- 動脈管開存症:大動脈と肺動脈をつなぐ「動脈管」が自然に閉じずに開いたままになること
症状は種類によって異なりますが、呼吸がしにくい、汗をかきやすくなる、体重が増えないなどが表れます。
心疾患に対する運動療法の効果
心疾患を持つ方が運動療法をするとき、どのようなメリットがあるのでしょうか。運動療法による効果をみていきましょう。
心機能の改善
運動の実施によって心臓の機能の改善につながるとされています。心機能が改善すれば、血液の循環や酸素・二酸化炭素の換気が良好となり、症状の軽減につながるでしょう。また、虚血性心疾患や不整脈などの発作の軽減、そのほかの心疾患の発症・再発予防も期待できます[9]。
持久力・筋力の増加によるQOLの向上
運動療法によって持久力・筋力が高まるので、QOL(生活の質)の向上が期待できます[9]。持久力・筋力が増加すれば、今まで苦しいと感じていた動作も楽に行えるようになるでしょう。長時間の活動でも疲れにくい身体になれば、これまでよりもできることの範囲が広がります。
メンタルの安定
運動療法は身体的な面だけでなく、精神的面にも効果があります。心疾患にかかると身体や将来に対する不安感が強くなるため、うつ症状が表れる方もいるでしょう。運動を継続することで、不安や気分の落ち込みなどのうつ症状が軽減されるといわれています[10]。また、運動療法による効果で身体機能が改善すれば、その分メンタルの安定化につながります。
心疾患の方に行う運動療法の内容
心疾患を持つ方には、どのような運動がおすすめなのでしょうか。それでは心疾患の方によく行われている運動内容についてみていきましょう。
有酸素運動
低負荷の運動を一定時間行う有酸素運動では、心機能や持久力の改善・向上が期待できます。有酸素運動にはさまざまな種類があり、そのなかでもウォーキングやエルゴメーターなどがおすすめです。
運動の頻度は1回30~60分、週に3~5回が目安とされています[9]。人によって心疾患の症状は異なるため、状態にあわせて無理のない頻度に調節することが大切です。運動の強度は「ややつらい」と感じる程度にとどめて、それ以上負荷を強くしないように注意しましょう。
また、有酸素運動をする前のウォームアップとしてストレッチを行うことで、筋肉の柔軟性を高めてケガの予防につながります。
筋力トレーニング
有酸素運動だけでなく、筋力トレーニングをすることで筋肉量の増強が期待できます。筋力トレーニングで行う内容の例は以下の通りです。
- 立った状態での腕立て伏せ
- スクワット
- 膝伸ばし
- かかと上げ
- あお向けの状態でのお尻上げ
- あお向けの状態での腹筋
- うつ伏せの状態での背筋
このようなトレーニングを週に2~3回、1セット8~15回ずつ行い、1~3セット繰り返します[9][11]。適度な回数や頻度は症状によって異なるので、医師と相談しながら調整してみましょう。
運動療法の実施中に気をつけるべきポイント
運動療法は心機能や持久力の改善が期待できる一方で、負荷が強すぎると心疾患の悪化につながる恐れがあります。そのため、運動療法を行う前は必ず医師に相談し、運動の種類や時間、中止すべき基準についてアドバイスをもらいましょう。
心疾患におけるリハビリに関するガイドラインで示されている運動療法の中止基準について、一部抜粋したものが以下の通りです[11]。
- 運動時に胸の違和感やめまい、頭痛などの症状が表れる
- SpO2が90%未満に低下、または安静時から5%以上の低下がある
- 最高血圧が80mmHgより下回る、最高血圧が250mmHg以上あるいは最低血圧が115以上に上昇する
- 脈拍が40回/分以下となる
そのほかにも、心疾患の種類ごとに注意すべきポイントがあります。例えば、狭心症の場合は心不全や致死性の不整脈を誘発させないように、血圧と心拍数の過度の上昇に注意する必要があるでしょう。
慢性心不全の場合、負荷量が大きいと血液の循環が悪くなり、体重の増加がみられる可能性があります。そのため、自覚症状や血圧だけでなく、体重の変化にも注意しましょう。
運動療法を避けるべき心疾患の方
なかには運動療法を避けるべき方もいる点に注意しましょう。心疾患におけるリハビリに関するガイドラインにある、積極的な運動療法が禁忌となる症例を一部抜粋してご紹介します[11]。
- 過去3日以内に心不全の症状が悪化している
- 不整脈のコントロールが困難となっている
- 精神的、身体的な障害によって安全な運動が行えない
- その他の疾患によって運動療法が禁忌となっている
- 発熱や貧血などが表れている
このような状態が当てはまる方は、自己判断で運動を行わず、医師に相談するようにしてください。運動療法を行える方も油断せずに、負荷量の調整には十分に気をつけましょう。
心疾患のリスクに注意しつつ安全に運動を継続しよう
心疾患の方が運動療法を行うことで、心機能や持久力の改善が期待できます。その一方で、運動は心臓に負担がかかりやすいため、その方に適した負荷量で実施することが大切です。
運動療法を行う前は必ず医師に相談して、どのような内容・負荷量で行えば良いのかを確認しましょう。自身の心疾患のリスクや適切な負荷量に注意しつつ、安全に運動を継続してみてください。
【参考文献】
[1]国立循環器病研究センター「虚血性心疾患」
[2]厚生労働省(e-ヘルスネット)「狭心症・心筋梗塞などの心臓病(虚血性心疾患)」
[3]大阪南医療センター「心不全(高血圧性心疾患、心臓弁膜症、先天性心疾患、心筋症、心筋炎)」
[4]広島大学「不整脈とは」
[5]近畿中央病院「不整脈とは」
[6]大阪医療センター「不整脈とは」
[7]済生会熊本病院「先天性心疾患」
[8]千葉大学大学病院医学研究院・医学部「先天性心疾患 [9]「16.心疾患における運動療法」伊東 春樹 日本内科学会雑誌 第101巻 第9号・平成24年9月10日
[10]日本心臓リハビリテーション学会「運動療法を紹介」
[11]日本循環器学会「心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン」