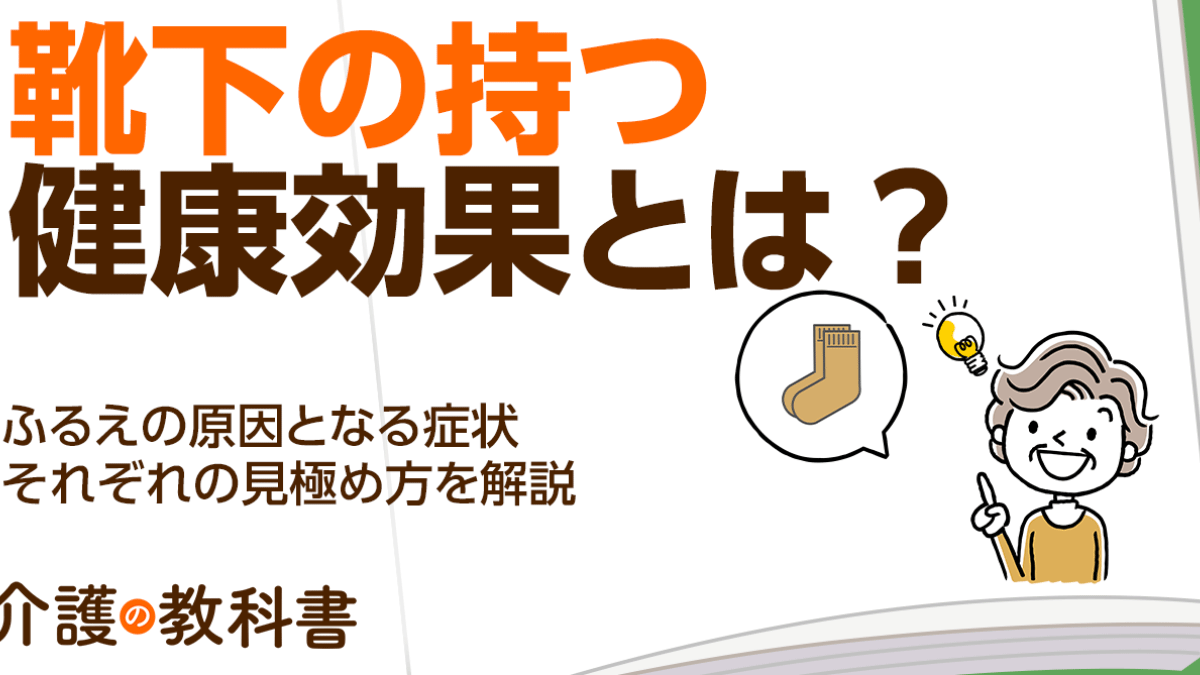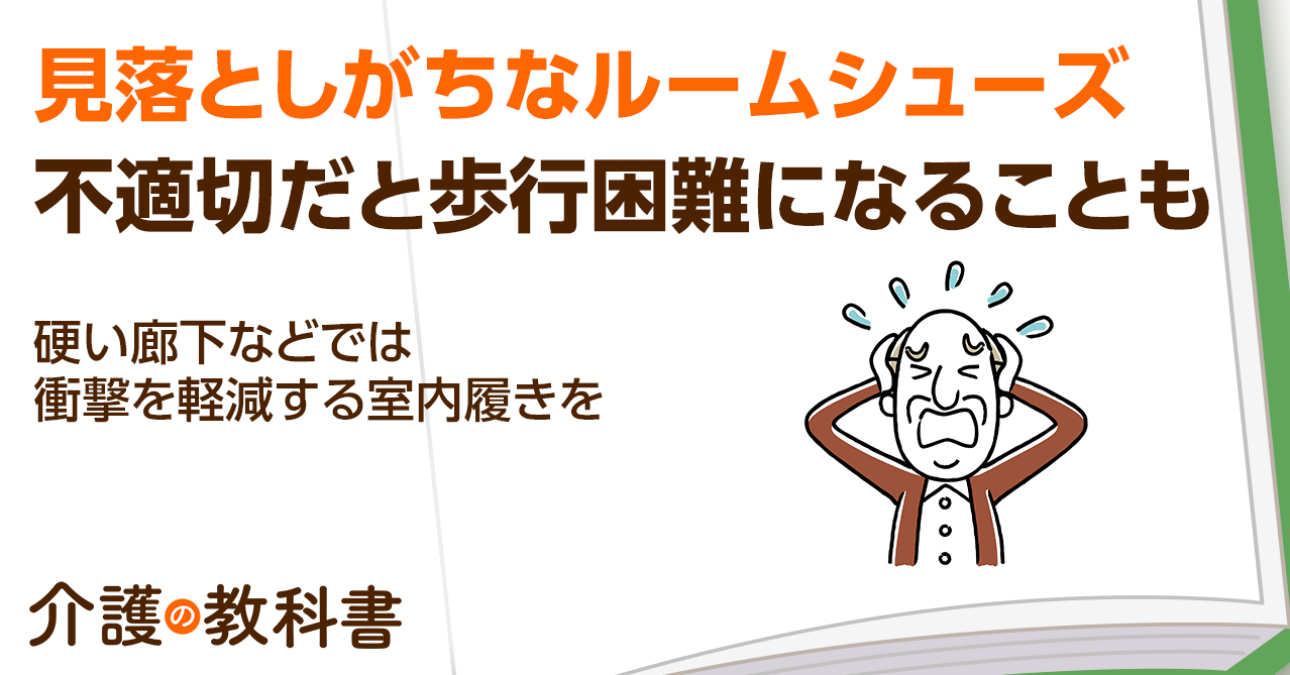靴下を履かずに、裸足で過ごしたほうが良いというイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、靴下は足を守る大事な道具です。
そこで、靴下にはどのような機能があるのか、そして、皮膚がデリケートであったり、持病があったりする高齢者の方に気をつけていただきたい点をご紹介します。
靴下が持つ3つの役割
靴下は一見どれも同じように見えるかもしれません。しかし、種類によってさまざまな機能を備えているので、用途に合わせて選ぶことが大切です。
では、どんな役割があるのか見ていきましょう。
足の保護・摩擦保護、クッション
歩行時には、足は体重の2~3倍もの衝撃を受けます。靴下はこの衝撃を緩和してくれます。さらに、靴と皮膚が直接触れてしまうと摩擦が生じてタコや角質が固くなるといったトラブル予防や、外傷を防ぐことができます。
吸湿・保温・抗菌、防臭
埃や汗を吸い取り、体温を保持します。また、抗菌成分が織り込まれた素材で菌の繁殖を抑え、防臭効果を備えたものもあります。
むくみ予防・血栓予防
足の血液は重力に逆らって下から上に心臓に向かって流れます。この流れをソックス(ストッキング)の圧迫によって促進します。
また、血流の促進を目的にした医療用弾性ストッキングなどもあります。静脈血管内に血流が滞らないようにすることで、心筋梗塞や脳梗塞などのもとになる血栓の予防にもなります。
一方、皮膚がデリケートな方や足の感覚が鈍くなっている方(糖尿病性神経障害の方など)は、靴下の縫い目などのちょっとした圧が重大なトラブルの引き金になることがあります。そのため縫い目がなく、足首の締め付けも適度につくられている靴下もあります。
ほかにも、一般的な筒状のもの、5本指、足袋形など形もさまざま。5本指靴下は縫い目や布が指の間に入る分、足趾が横に広がりやすい欠点もあります。
医療現場では当たり前になっている弾性ストッキング
靴下は私たちの肌に直接触れるものなので素材や形、つくり方によって機能が異なります。医療現場のような命を守る場で、下肢静脈瘤の症状緩和やベッド上の安静、術後の方々の血栓予防を目的に医療用弾性ストッキング(靴下の形状)を利用していただいています。
実際、弾性ストッキングによるリスク低下率は57%とも報告されています[1]。また、ドイツでは糖尿病患者のようにセンシティブな方でも安心して履ける縫い目のない靴下が製造販売されています。
このことからも、靴下やストッキングなどのウエアを変えるだけで健康を守れることがわかります。
ただ、医療用弾性ストッキングは医師の指示のもとで着用しなければならないため、受診が必要になります。
靴下が原因でトラブルになることも?
靴下には健康効果が期待できるものの、使い方や選び方によっては逆効果となることもあるので注意が必要です。ここでは、私たちにとって誰にでも起こり得るトラブルをご紹介します。
靴下が合わずに痛みが強まることも…
Aさんには巻き爪があり、日頃から痛みが現れないよう気を配っていました。爪の切り方なども気にされていたため、ご相談いただきました。
とても寒い日が続いたある日、Aさんが「先日、新しい靴下を下ろしたら爪先がきつく、巻き爪が痛くて大変で!出先でしたが、あまりの痛さに靴下のつま先を切ったんです」とエピソードを話してくれました。迷わず対処したことで、幸いにも炎症は避けられたそうです。
靴下は履いてみないと、締め付け感やサイズ感がわかりにくいことがほとんど。初めて購入する靴下の場合は気をつけなくてはいけません。
高齢者や小さな子どもは人にうまく伝えることができないので、身近な方が本人の表情や歩き方をよく観察し、問題ないかを確認する必要があります。
まとめ
靴下は足を守るだけでなく、私たちの健康を守る大切なフットウエアです。
目的に合う形で活用できれば、むくみの予防やスポーツ時の衝撃緩和など、さまざまなシーンで私たちを助けてくれる可能性があります。
むくみは転倒の要因にもなりますので、医療用でなくとも着圧ソックスなどの活用が有効かもしれません。
寒暖調整や外傷予防だけではない役割を持った靴下を、生活場面でぜひご活用いただけたら嬉しいです。
【参考文献】
[1]股関節全置換術患者を対象にしたランダム化比較研究
[2]一般社団法人日本血栓止血学会HP.わが国における静脈血栓塞栓症の予防ガイドライン作成・発行
[3]山田典一ら「弾性ストッキングの現状とエビデンス: 深部静脈血栓症・肺血栓塞栓症の予防」静脈学,2012 (23) 3, 233-238.