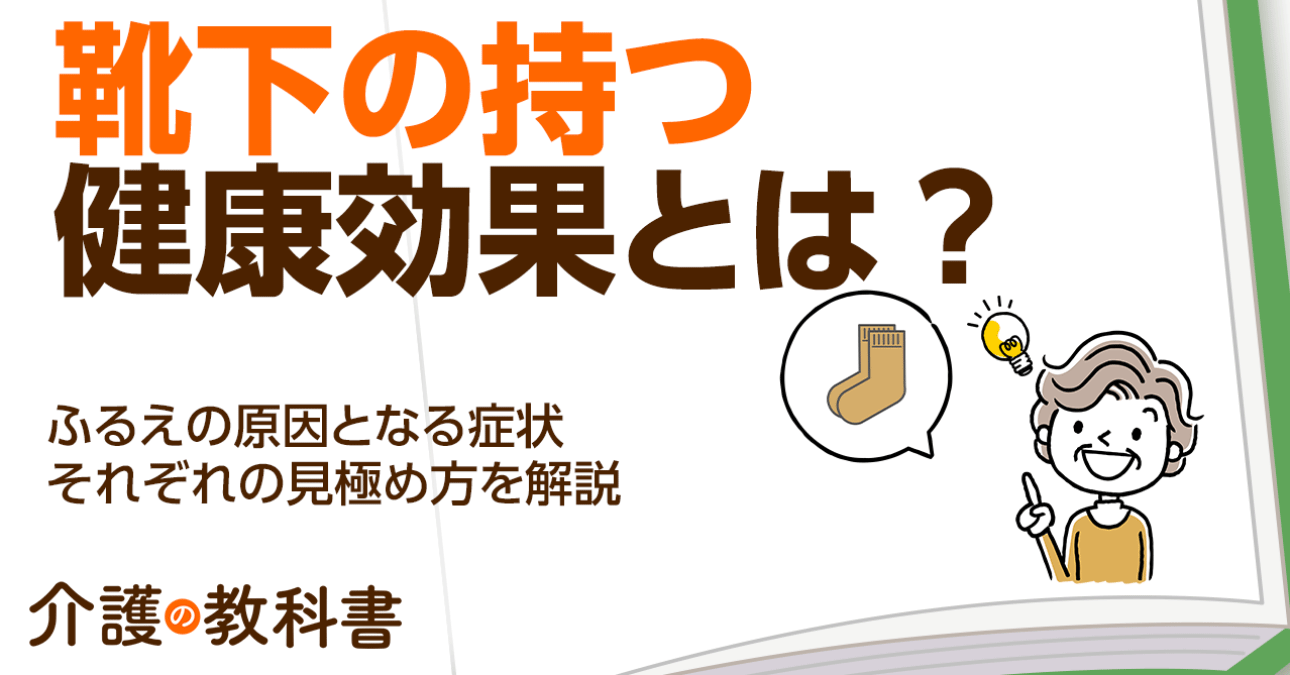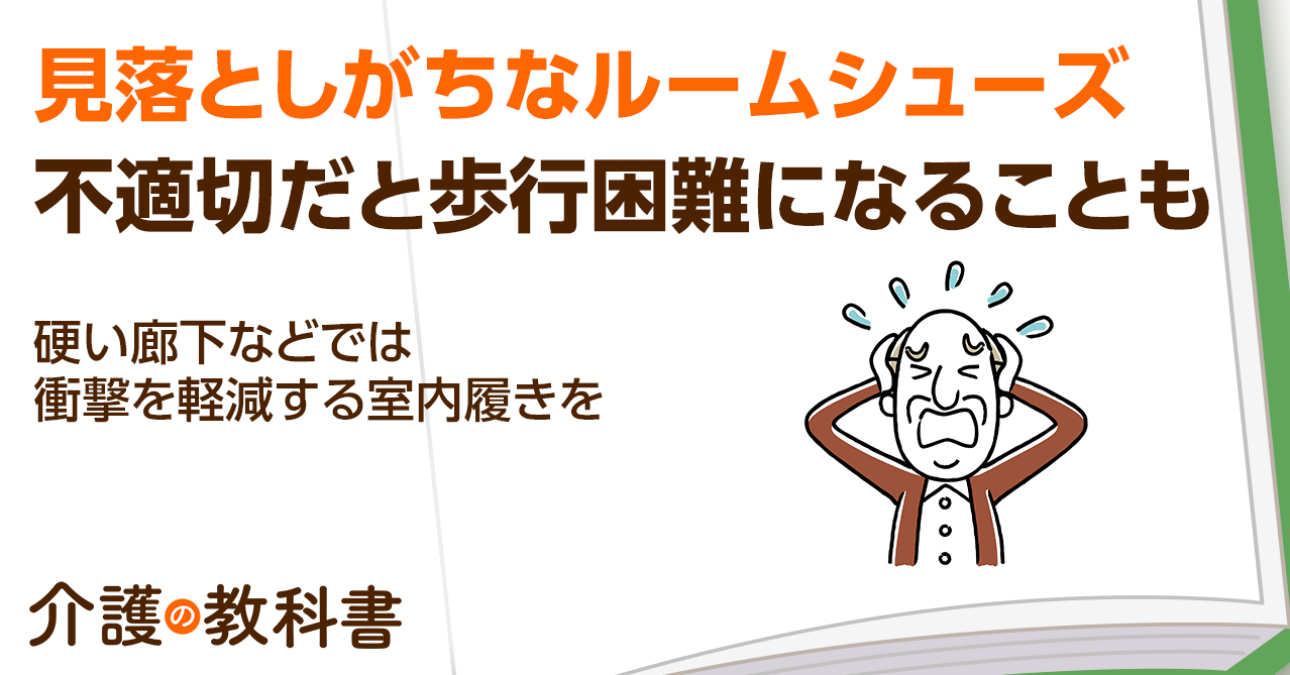タコやウオノメは、痛くならなければつい見過ごしてしまいやすいものです。
しかし、ないはずのものができるのは、意味があります。
足にできるタコやウオノメが体からの大切なサインなのです。本記事を読んで、これから気にかけていく機会になればと思います。
タコやウオノメは皮膚が反応した産物!
生まれたときから、タコやウオノメがある人はいません。タコもウオノメも人生のどこかでつくられてしまったものなのです。
では、なぜできてしまったのでしょうか?
原因が何もなくてできることはありません。「硬いものができている」「痛い」という変化は、「体がここを守ろう」と無条件に反応した結果なのです。
原因は一つとは限りません。例えば、以下のようなことが考えられます。
- 立ち方・歩き方の癖
- 骨格・足の形状
- 関節の動き
- 足裏の脂肪層の厚さ
- 皮膚の乾燥
- 足のアーチ(土踏まず)が低下
- 靴、靴の履き方
- 靴下の着用の有無 など
さらに、足の一部分へ継続的・断続的に圧や摩擦が生じることで形成されます。このような摩擦や圧の皮膚ストレスに対して皮膚が厚くなって身体を守っており、体が「ここは注意!」のサインを示していると言えます。
タコやウオノメは1日にして成らず
立ったり、歩いたりする際に足への摩擦や圧力が負荷として継続的・簡潔的にかかることで、局所にタコやウオノメができます。つまり、その部分に圧力がかかっているのです。

この原因が何かを探り、適切な対応をすることで、タコやウオノメは繰り返し発生しにくくなります。
ご存知かもしれませんが、タコとウオノメの違いは、圧のかかる場所の下に骨がなければタコ、骨があればウオノメになると言われ、タコは皮膚の上に厚く盛り上がるようにできるのに対して、ウオノメは体の内側に向かってできます。タコの中にウオノメができているケースもめずらしくありません。
これらは身体的変化や日常の習慣が影響していることが多く、極端なことを言えば、1日おかしな歩き方をしたとしても急にできることはありません。
ただ、「若い頃と何も変わっていないのに、急にできるようになった」というご相談をいただくこともあります。
以前からできていたが痛みが伴うようになってきて最近意識し始めたり、最近靴を変えたり、怪我などといった何らかの理由で歩き方が変わったことが考えられます。
年齢とともに避けられない身体的変化、関節の動きや筋肉量、足裏の脂肪層の厚さなどが知らないうちに変化し、歩き方も変わることがあるのです。こういった長い時間をかけて、少しずつ体は反応しています。
注意していただきたいのが、たかがタコやウオノメだと思わないこと。放置しておくと、痛みが増強し転倒にもつながることもあります。
また、糖尿病などを抱えた方にとってタコやウオノメ、水虫などの身近なものから大きなトラブルに発展することも少なくありません。痛みの有無にかかわらずきちんと対処することをおすすめします。
【事例】90代女性・Aさん
足の裏にタコやウオノメができて痛くて歩けないと、訪問看護師からご相談をいただきました。
本来だと足の裏は歩行の衝撃を吸収してくれる柔らかい脂肪がついていますが、Aさんの足は脂肪がほとんどなく、足裏の皮膚の下はすぐ骨が当たる状態でした。
Aさんはとてもお話が好きで社交性もあり、活動意欲が高いので「買い物へ行きたい」と言っていましたが、足裏の痛みでリビングですら数歩しか歩けませんでした。

そこでタコやウオノメを除去し、薄くなった脂肪層の代行として厚い靴下と靴の中のクッション性のある履き物へ変えました。足の状態からタコやウオノメはすぐにできてしまいましたが、足裏の脂肪層に変わる代用品をご利用したことで、日常の苦痛が和らぎ足が楽になって「羽ができたようだ」と笑顔で話してくださいました。
「たかが」と思われがちな足のタコやウオノメですが、Aさんのように本来できることができなくしてしまったり、自信を奪われてしまったり、趣味などを失ってしまうことがあるのです。
まとめ
タコやウオノメは痛くなる前にお手入れするとともに、どうしてそこにできたのか、専門家などに相談し対処することをおすすめします。
特に痛みを伴う場合、繰り返さないようにしたり、できるサイクルを長くすることで生活の質を改善することにつながります。
適切な処置をして、いつまでも生き生きとした日々を送りましょう。