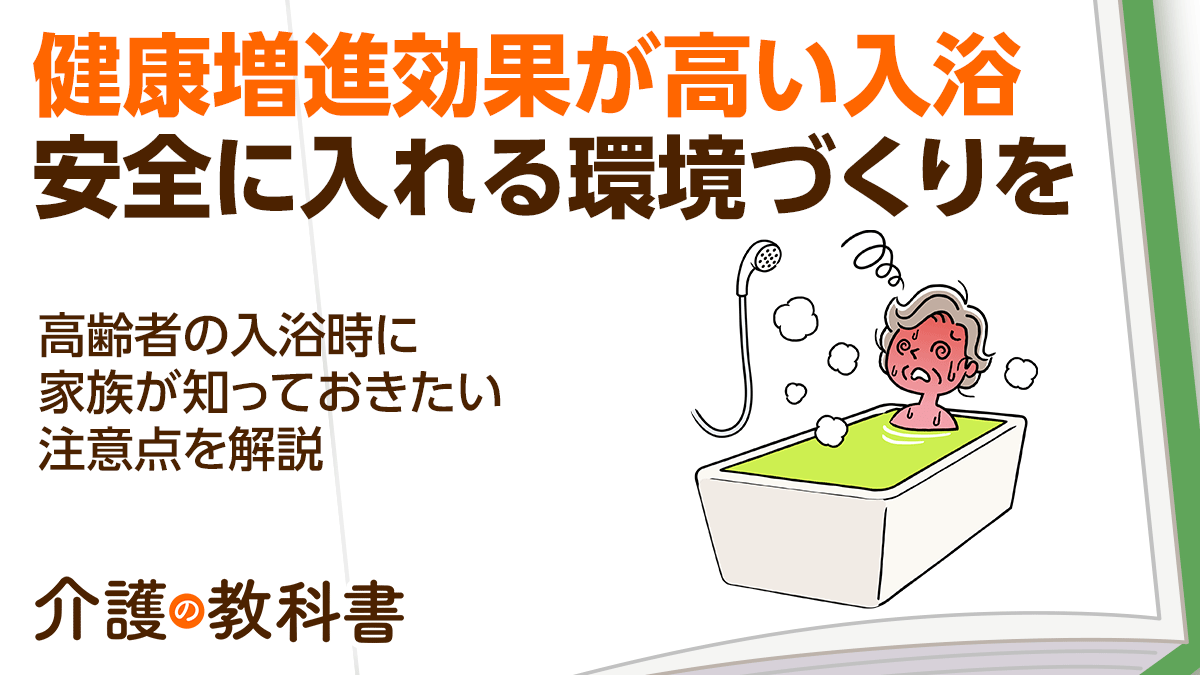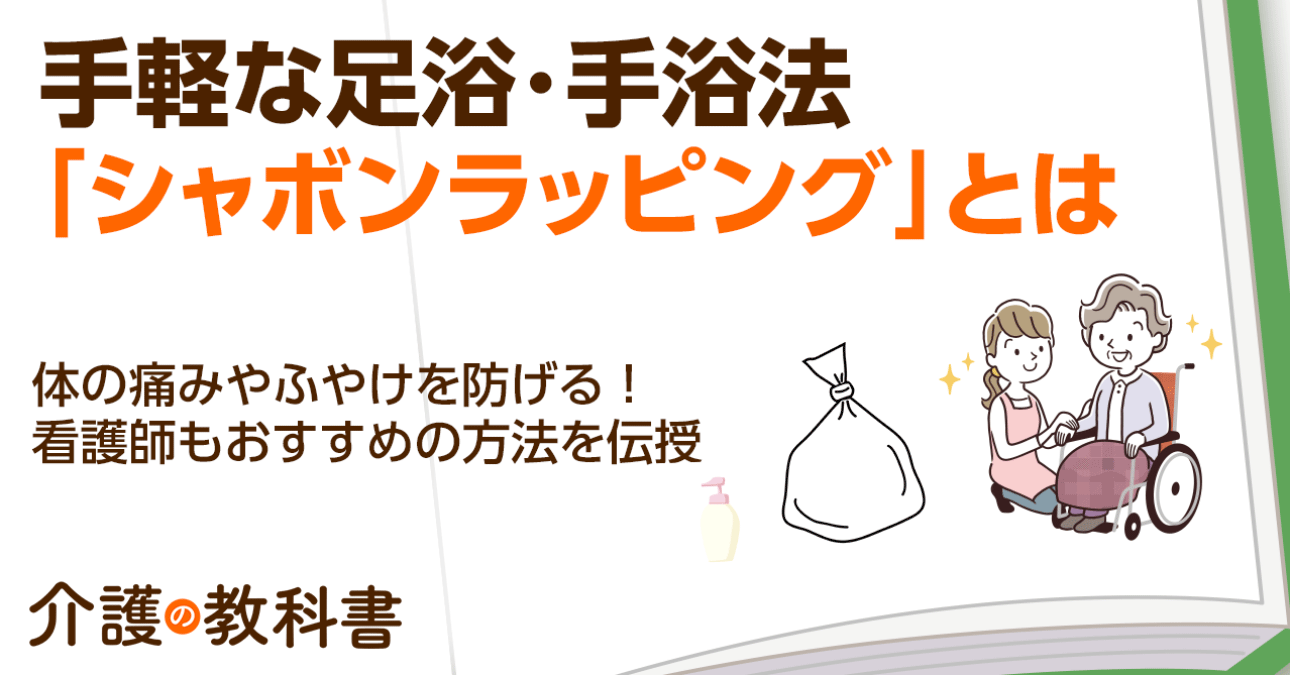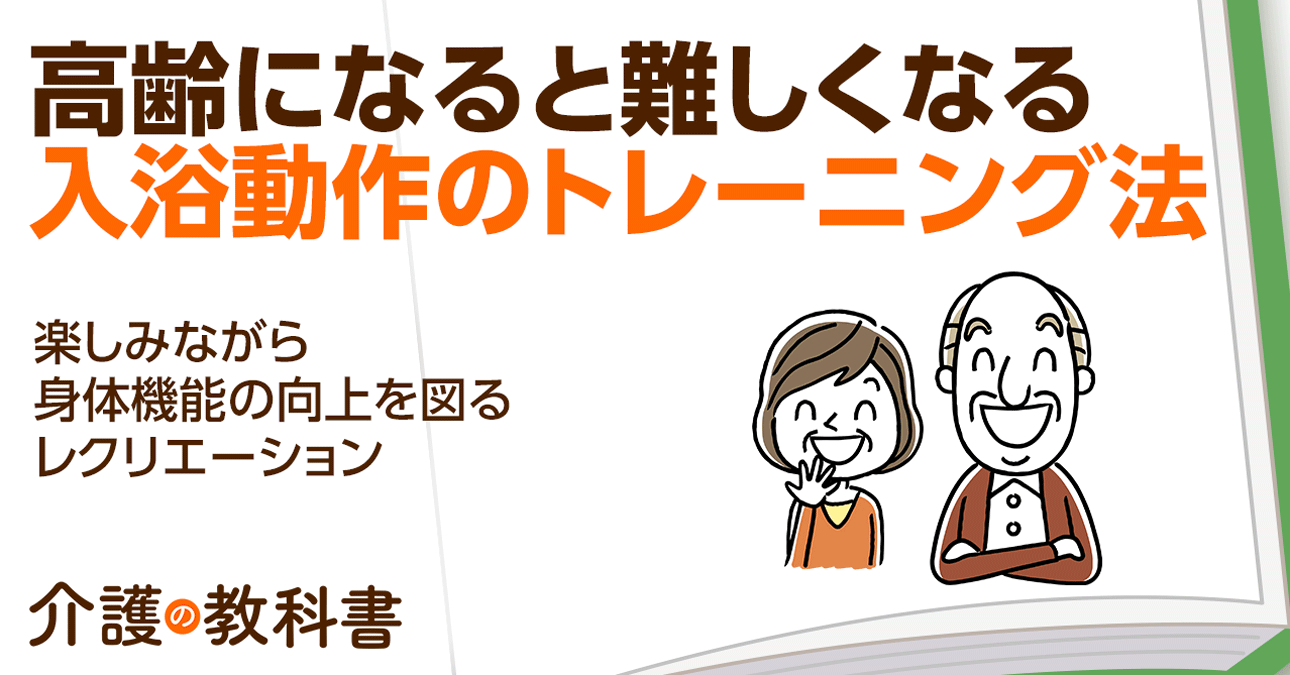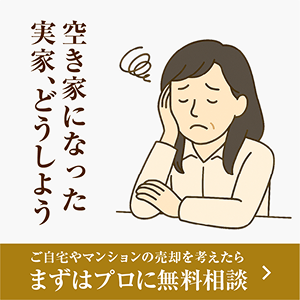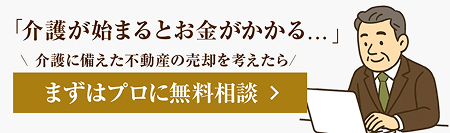入浴の動作には、リハビリの効果があることをご存知でしょうか。
健常者が自然と行っている入浴ですが、実はさまざまな体の部位を動かしており、健康に良い影響があると考えられています。
ただ、高齢者の入浴には危険が伴います。加齢によって身体状況が変化するため、高齢者だからこそのリスクが潜んでいるのです。
今回は、入浴のリハビリ要素と注意点を理学療法士の視点からまとめてみましたので、参考にしてみてください。
高齢者の入浴はリハビリになる
健康な成人が何気なく行っている入浴動作ですが、高齢者にとっては良いリハビリになります。
入浴そのものであったり、入浴に関連する動作には健康につながる要素が多く含まれているためです。
入浴はエネルギーを消費する
国立健康・栄養研究所は「ジャグジー風呂に入る」という行為が1.3メッツという単位の運動になると公表しています。
メッツとは、運動の強度を示す単位であり、静かに座っている状態を1メッツとして、どれくらいエネルギーを消費するかを表しています。
1.3メッツという運動強度は、静かに座っているときよりもエネルギーを消費するため、軽い運動をしている状態だと言えるでしょう。
一方、自宅で入浴介助をしていると「お風呂に入る動作は大変。軽い運動だとは思えない」という方もいるのではないでしょうか。
状態によっては、静かに座っていることも難しい要介護者もいるでしょうから、そのような方が入浴する場合は軽い運動とは言えません。
運動強度の計り方は、メッツのみではありません。ほかにも、自覚的運動強度(RPE)と呼ばれるものがあります。
RPEは、近年筋力トレーニングの指標として用いられています。そこで推奨されるのは「少しきつい」程度の運動です。
あくまで個人の自覚が指標となるため、「少しきつい」という感じ方は一様ではありません。
入浴動作が「楽だ」と感じる方もいれば「きつい」と感じる方もいます。つまり、入浴が以前より大変だと感じている方は、より運動としての効果を生んでいるとも考えられます。
お風呂に入るときに必要な動作がリハビリになる
次に、もっと細かい視点で入浴動作に含まれているリハビリ的要素を考えてみましょう。
入浴するときの動作は、具体的に以下のようなことが挙げられます。
- 着替え
- 段差の上り下り
- 浴槽のまたぎ動作
- 体や髪を洗う動作
これらすべての動作がリハビリに関連しています。
例えば「段差の上り下り」は、自分の体をバランスを保ちながら段差を越えるので、支える筋力が必要になります。また「着替え」の動作では、肩の関節を大きく動かしたり、片足立ちになるバランス能力を発揮することが考えられます。
お風呂にかかわる動作が運動になる
お風呂を使っていれば、浴槽や浴室は必ず汚れます。そのため、定期的に掃除をする必要があり、その行動自体がリハビリになります。
先ほど紹介したメッツという指標によれば、風呂掃除の項目は3.8メッツです。
ほかにも、掃除機がけは3.5メッツ、家財道具の片付けは3.0メッツとされており、お風呂に関連して掃除をしたり、物を動かしたりする動作自体が運動になるのです。
厚生労働省も掃除や洗濯などの家事を意識して体を動かすことを推奨しているので、入浴だけに注目せず、それにかかわるすべての生活動作がリハビリにつながっていると言えるのです。
高齢者が入浴するときに考えられるリスク
一般的に入浴は、健康に良いとされていますが、良い面だけではありません。高齢者が入浴する際は、リスクについて理解しておくことが大切です。

転倒
浴室は滑りやすいので、転倒リスクを伴います。転んでしまうと溺水などの重大な事故も起こりやすい場所でもあります。
さらに高齢者は、筋力やバランス能力、骨密度などが低下している可能性が高く、骨折などの大きな怪我につながる可能性があります。
脱水
高齢者は、さまざまな要因が関係して脱水が起きやすい状態にあります。高齢者が脱水を引き起こす要因は以下になります。
- 活動量が低下する
- 口が渇くことを感じにくい
- 腎臓の働きが弱くなる
- 体の水分量が低下する
高齢になるともともと脱水を引き起こしやすい状態であるうえに、口が渇いていることを感じにくく、水分摂取量が低下してしまうため、脱水になりやすいのです。
重症になってしまうと、脳や肝臓、腎臓などに後遺症を残すこともあります。また、命に関わる可能性も否定できません。
入浴の際には汗をかくので、さらに脱水のリスクが高まります。
溺死・溺水
65歳以上の高齢者の不慮の事故において「溺死・溺水」は3番目に多いとされています。これは交通事故よりも多い数値で、高齢者にとって非常にリスクの高い事故だと言えます。
東京消防庁の調査によると、冬場に溺れる事故が多く発生しているとされており、ヒートショックが溺死や溺水に至る原因として多いと推計されています。
やけど
高齢者は、温度感覚が鈍くなるため、やけどにも注意しましょう。
50歳以下では約0.5度の温度差がわかるのに対して、65歳以上では約1.0~5.0度の温度差がなければわからないという報告もあります。
人が低温やけどをする温度は約44度以上だとされているので、入浴に適している40度付近では、温度感覚の鈍さによってやけどを生じる可能性が十分にあるのです。
表皮剥離
表皮剥離とは、すりむき傷のことを指します。
入浴するときは肌を露出するので、服を着ているときに比べれば表皮剥離を起こしやすい状況になります。
また、皮膚は歳を重ねるごとに徐々に薄くなり、弾力性も低下します。そのため、高齢者は表皮剥離を生じやすいのです。
ヒートショック
急激な温度の変化にさらされると血圧が大きく変動することがあります。この温度差を原因にした血圧の変動によって起こる健康被害をヒートショックと呼びます。
もしかしたら「急激な温度の変化にさらされることはない」と考えている方もいるかもしれませんが、実は脱衣所と浴室の温度差だけでもヒートショックを引き起こすことがあるのです。
ヒートショックを原因として失神が起こり、浴槽内で溺れてしまうケースは決して少なくありません。溺れるまでに至らなくても、怪我にもつながるので、ヒートショックには十分に注意してください。
高齢者が安全にお風呂に入るためのポイント
最後に、高齢者が安全にお風呂に入るためのポイントを解説します。
転倒予防のために手すりや滑り止めなどを設置する
高齢者はバランスを崩しやすいうえに、浴室は滑りやすいので、転倒には十分注意する必要があります。
その際、以下のような福祉用具が役立ちます。
- 手すり
- 滑りどめ
- バスボード
- 介助用ベルト
- シャワーチェア
- シャワーキャリー
転びやすい状況はさまざまなので、すべての福祉用具を導入する必要はありません。
例えば、膝に痛みがある方は浴室の段差でバランスを崩しやすくなっていると考えられます。その場合は、段差の位置に手すりを設置すると良いでしょう。

また、脚の力が低下してバスチェアからの立ち上がりが難しくなった方は、肘掛け付きのシャワーチェアを使って立ち上がると効果的です。
ただし、適切な福祉用具の選択は簡単ではありません。リハビリ専門職などに相談して決めるようにしましょう。
お風呂や浴室の温度に注意する
皮膚の温度感覚が低下している高齢者の場合は、高温のお湯に浸かっても熱いと感じにくいことがあります。また、体温調整機能が低下していることもあるので、温度変化によって体調を崩しやすい点にも注意する必要があるでしょう。
安全に入浴するためには高温浴を避ける必要があります。42度以上の高温浴では、血圧が大きく上昇することがあり、失神のみでなく、脳出血を生じる可能性もあるとされています。
そこで、お湯の温度は39~41度ほどに設定しておくと比較的安全だとされています。また、温度だけでなく、浴室や脱衣所の温度にも気をつけるようにしましょう。
一般的には、10度以上の温度差があるとヒートショックのリスクが上がるとされているため、暖房などをうまく使って、温度差を抑えるようにしてください。
体調をチェックする
入浴時は体調を確認してから行うようにしましょう。
いつもと違うように感じたら、入浴を控えても結構です。体温や血圧、脈拍などを確認しながら危険を避けるようにしましょう。
血圧・脈拍・体温の正常値は以下の通りです。
血圧:120/80mmHg以下
脈拍:60~100回/分
体温36~37度
ただし、高齢者は体温平均が36.6度と一般成人よりも少し高かったり、血圧が高くなりがちだとされています。
さらに、バイタルサインは個人差も大きいため、普段の状況との違いを観察することが大事になるでしょう。
場合によっては、入浴して良いバイタルサインの基準について医師からの指示が出ることもあります。心配のある方は主治医に相談しましょう。
入浴にはリハビリや運動の要素があり、健康増進効果が見込めます。その一方で、身体機能が低下した高齢者ならではのリスクが高まるのも事実です。入浴を効果的に行うためには、十分な安全対策を行い、事故を防止する姿勢が重要です。
リハビリ専門のスタッフや主治医のアドバイスを求めて、安全かつ効果的な入浴を楽しんでください。