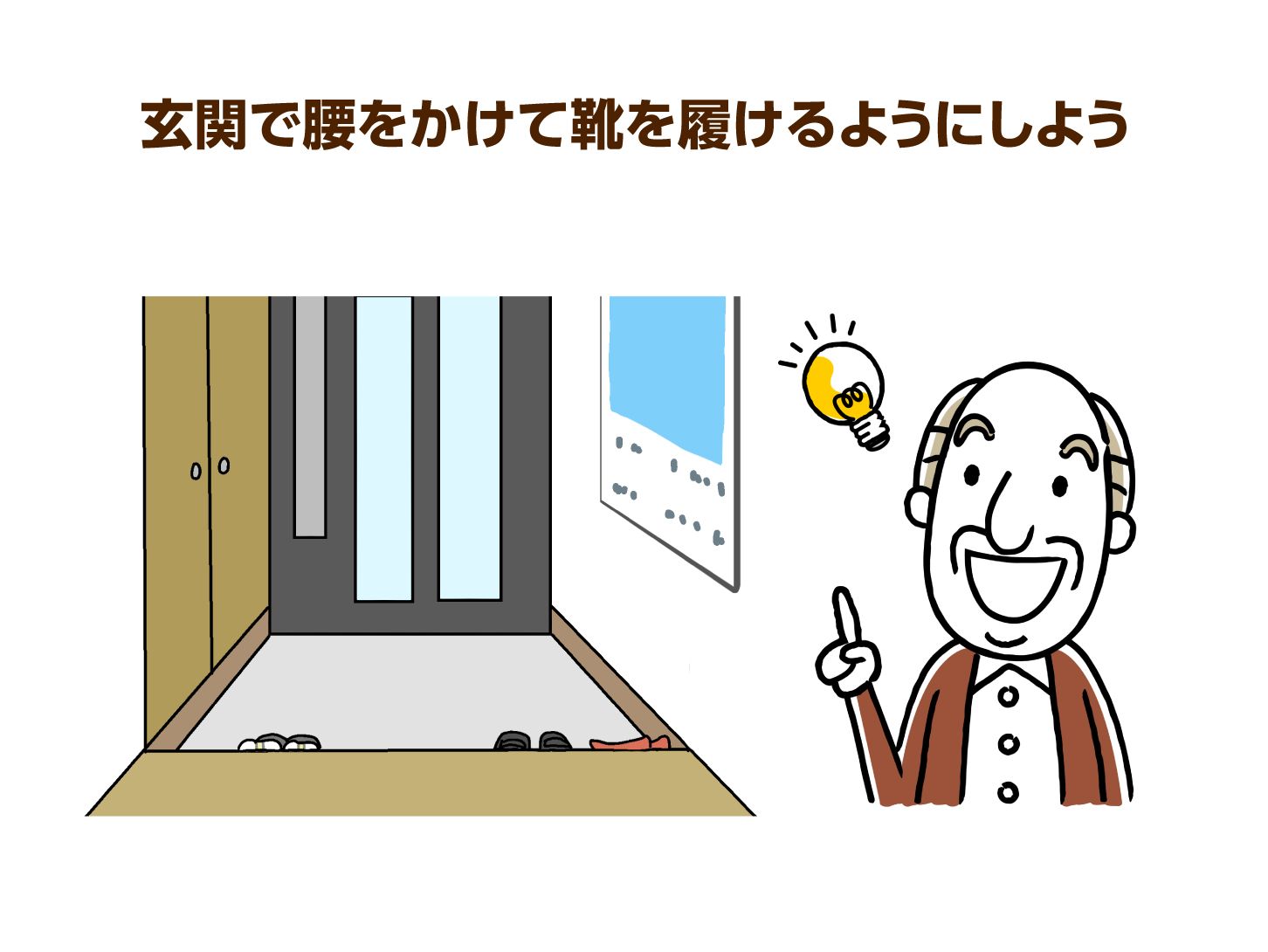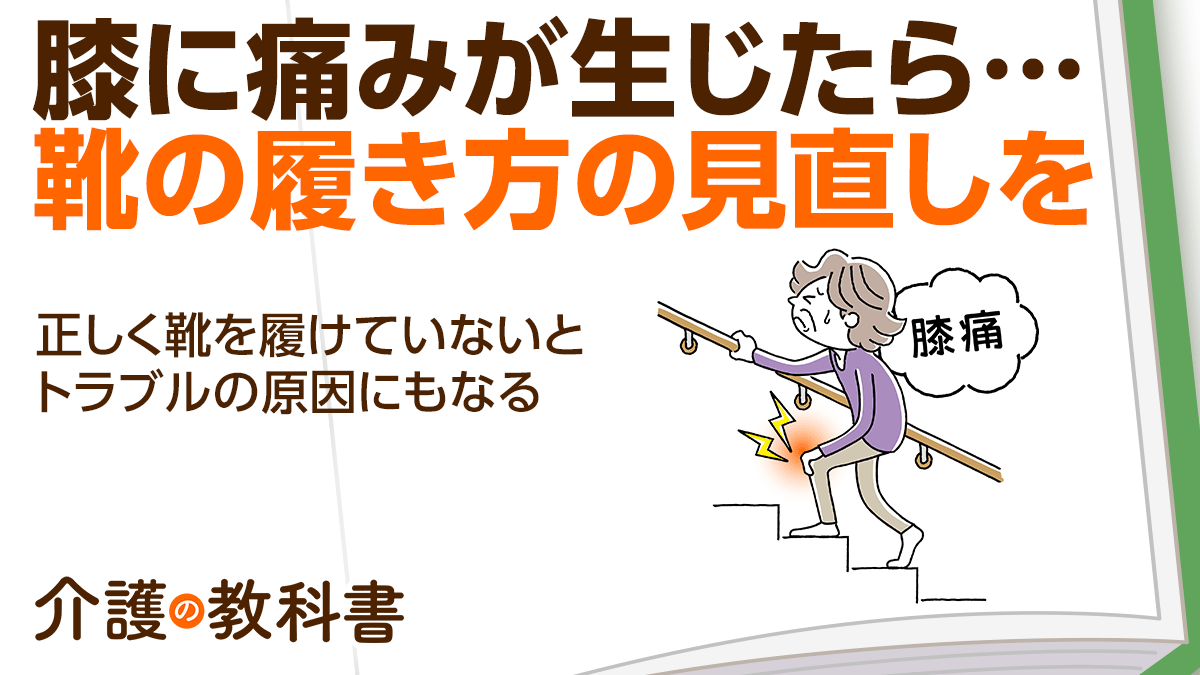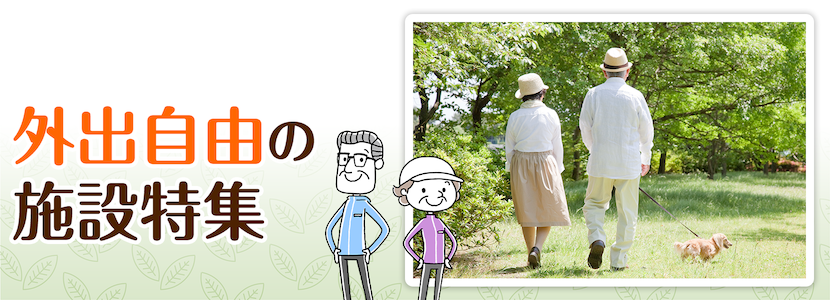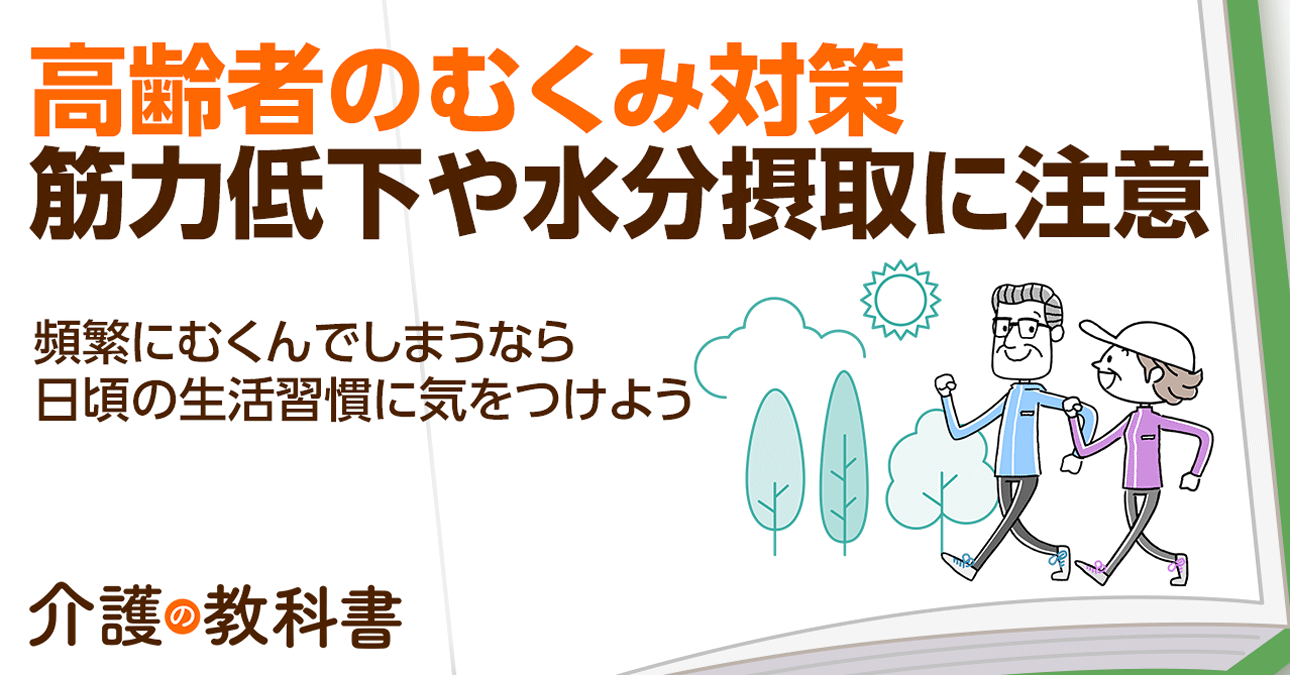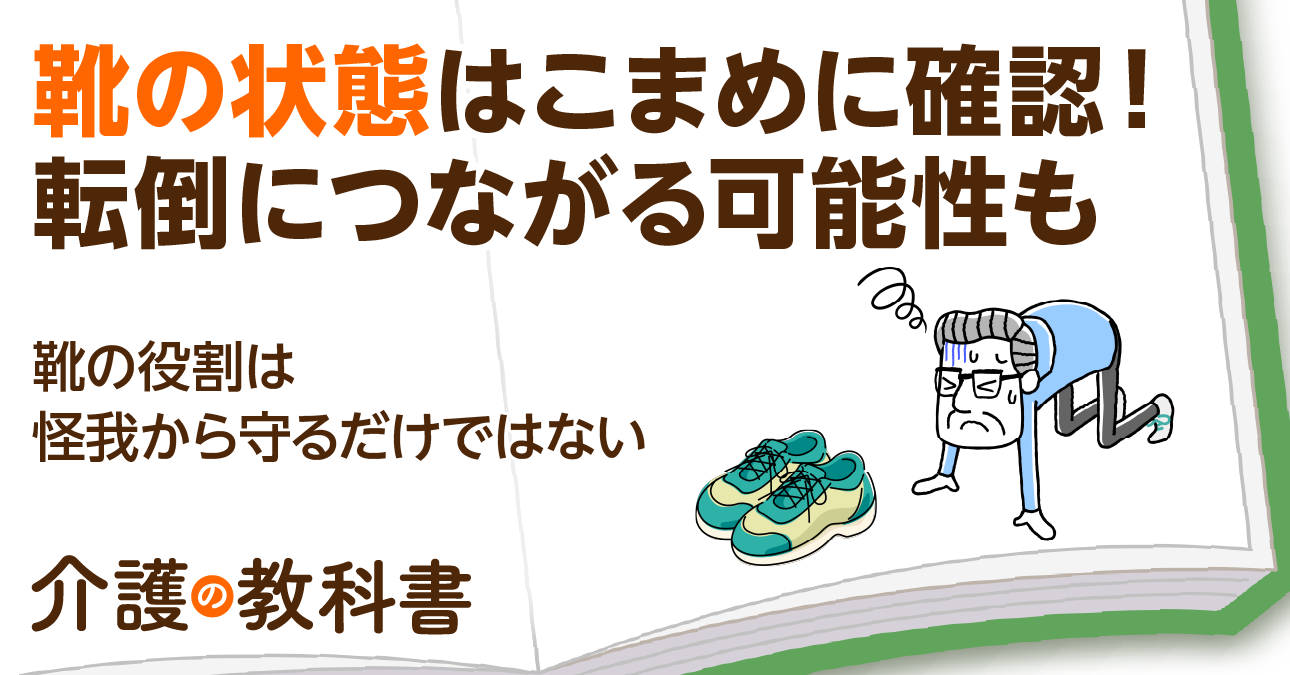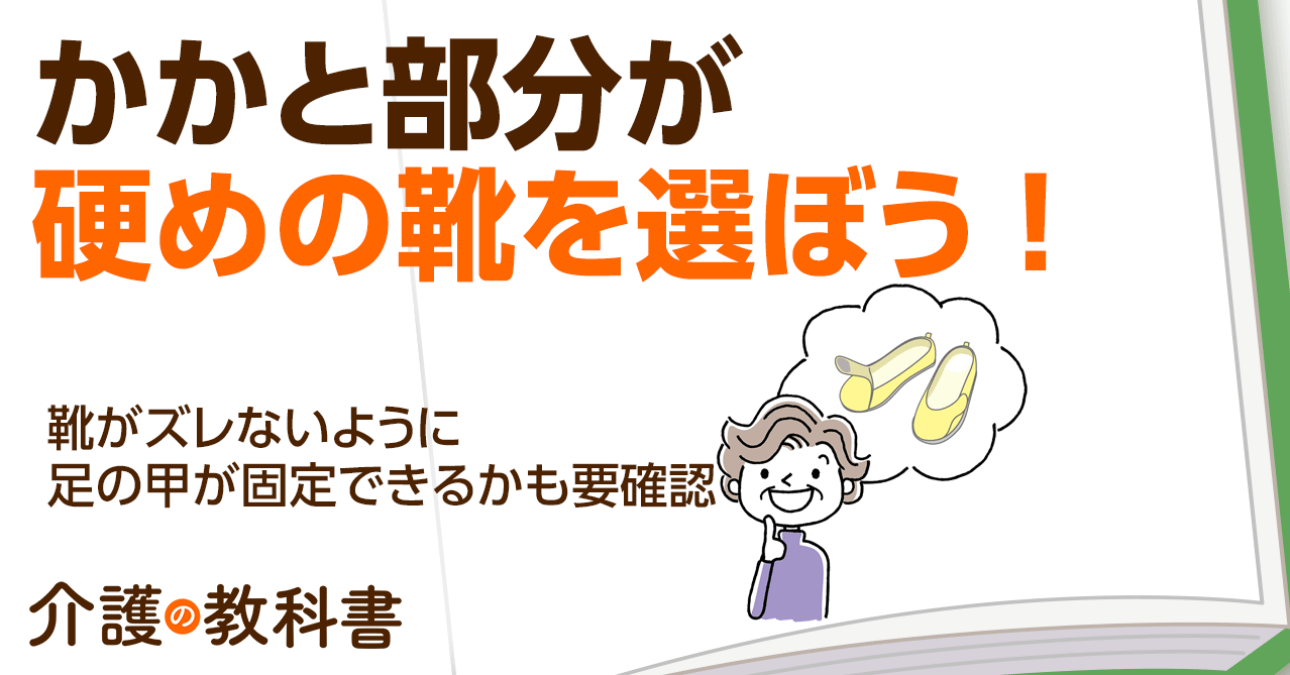「大は小を兼ねる」といいますが、靴についてはこの言葉に当てはまりません。それぞれ適切なサイズを適切に履くことが重要だからです。
履き方一つで今ある靴でも、履き心地や歩いた感覚、疲れ方、歩き方が異なり、歩行の安定感に差が生じます。
高齢者だけでなく、靴の履き方は足を健康に保つ基本なので、ぜひともこの機会に押さえておきましょう。
靴は踵(かかと)が命!靴と自分の踵を合わせて履こう
日本は歴史的に草履や下駄の文化が長く、靴を履くようになって100年ほどしか経っていません。それもあってか靴の適切な履き方が普及しているとはいえません。
靴と草履(下駄)は備えている機能や履き方がまったく違います。きっと「そんなのわかってる」と感じている方も少なくないことでしょう。しかし、実生活では、大半の方が靴を草履と同じように脱ぎ履きしているかもしれません。そのせいでタコや魚の目で痛みが生じたり、疲れを助長していることが少なくないのです。
靴の脱ぎ履きには、足と靴との部位の合わせ方がポイントになります。
靴の適切な履き方
①足の甲の部分を緩めて履き口を広げた状態にして足を入れる

②靴に足をいれたら足首を曲げ、かかとをトントンして、足と靴のかかと部分を合わせる

③踵を90度に曲げた状態で甲の部分をしっかりと留める

紐とファスナーが付いているタイプの靴でも紐が緩んできてしまうので、3日に1回くらいは紐を縛り直しましょう。
適切な履き方ができると、足の指を自由に動かすことができ、靴の中でのズレや摩擦を最小限に抑えられます。その結果、タコや魚の目、巻き爪などの足トラブルの予防や改善も期待できます。
靴は歩行を助ける道具の一つ
日本は欧米とは異なり、日常的に靴の脱ぎ履きをしています。長く愛用されてきた草履や下駄の脱ぎ履きは、こうした文化とよくマッチしています。
一方、靴は足を保護するだけでなく、足とのフィッティングと適切な履き方で歩行を助けて足の機能を支持する役割を担います。
例えば、視力矯正を目的にメガネを購入したとしましょう。
- おしゃれな眼鏡フレームを購入してもサイズが合わない
- レンズの度が合ってない
- フレームもレンズも合っていても適切にかけていない
もし、このような状態だと視力は矯正されずに眼鏡をかける意義がありません。
実は靴も同じなのです。眼鏡のフレームは靴、レンズは中敷、かけ方は履き方だと考えるとわかりやすいでしょう。
もし、オーダーシューズをつくったとしても履き方が不適切だと、その有用性は最大限に発揮されません。特に甲の部分を緩くしてあって、紐やベルクロをいじらずに脱ぎ履きできる状態は長靴を履いているのと大差ありません。

そのため、無意識に靴が脱げにくいよう足に余計な力を入れてしまっています。脱ぎやすい=脱げやすいのです。
踵をトントンと合わせてから靴を履くことで、足と靴が一体となり靴の中で動くことがなくなり、靴本来の足の動きをサポートする機能が発揮されます。
例えば、踵から地面に着地したときに足への衝撃を靴が受け止め、足の無駄な動きや力が要らなくなるので疲れにくく歩きやすくなるのです。
高齢者の膝の痛みも改善!
高齢者の方はよく「足が疲れやすい」「膝が痛くなる」と言います。そうしたとき、私は必ず靴のフィッティングの確認とともに靴の履き方を確認しています。
比較的多い問題は、主に次の3つです。
- 足の長さに対する靴の長さが合っていない
- 足の踵の横幅が合っていない
- 適切な靴の履き方をしていない
スニーカーを長年スリッパのようにつっかけて履いていた方の中には、適切な靴の履き方を知っていても面倒なので他の手立てがないか相談にこられる方もいらっしゃいます。
しかし、靴の履き方は健康な足をつくり、維持するための基本中の基本。履き方を差し置いてどうにもなりません。
足に合った靴を適切に履くと、驚くほど足が快適になり、疲れやすさや痛みが軽減することもあります。実際、私のもとにも膝の痛みがなくなったという声が届いています。
靴は踵を合わせて履くようにつくられている
そもそも靴は踵をしっかりと合わせて、甲を留めて使うようにつくられています。
そのため、踵を踏んで履いていると、靴の機能をまったく活かしていないとも言えます。そればかりか身だしなみとしても問題があります。
靴は適切に履くことで、筋骨格の動きと足の負荷を緩和します。そして、疲労感の緩和や効率的な歩行の安定にもつながりますので、運動によって膝を痛めるようなことも少なくなります。
健康的に自分らしく生き生きと歳を重ねていくために、ぜひ靴の履き方を見直してみてください。そのためには玄関に腰かけられる場所の有無も大切になりますので、整理整頓をしておきましょう。