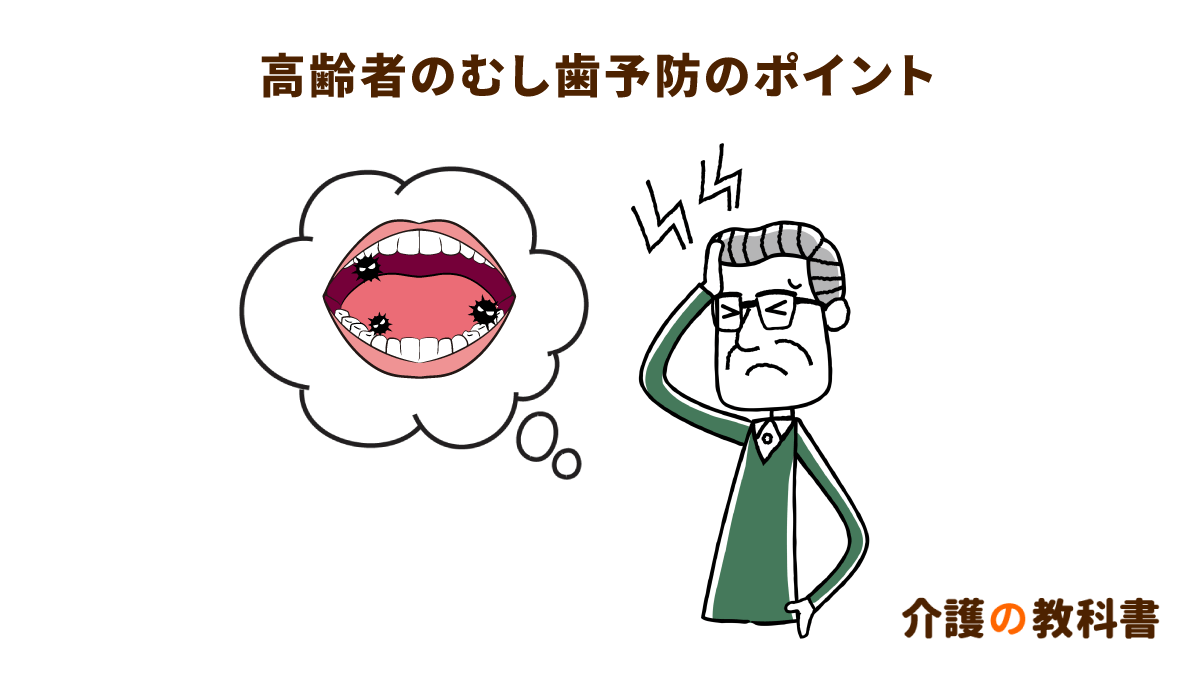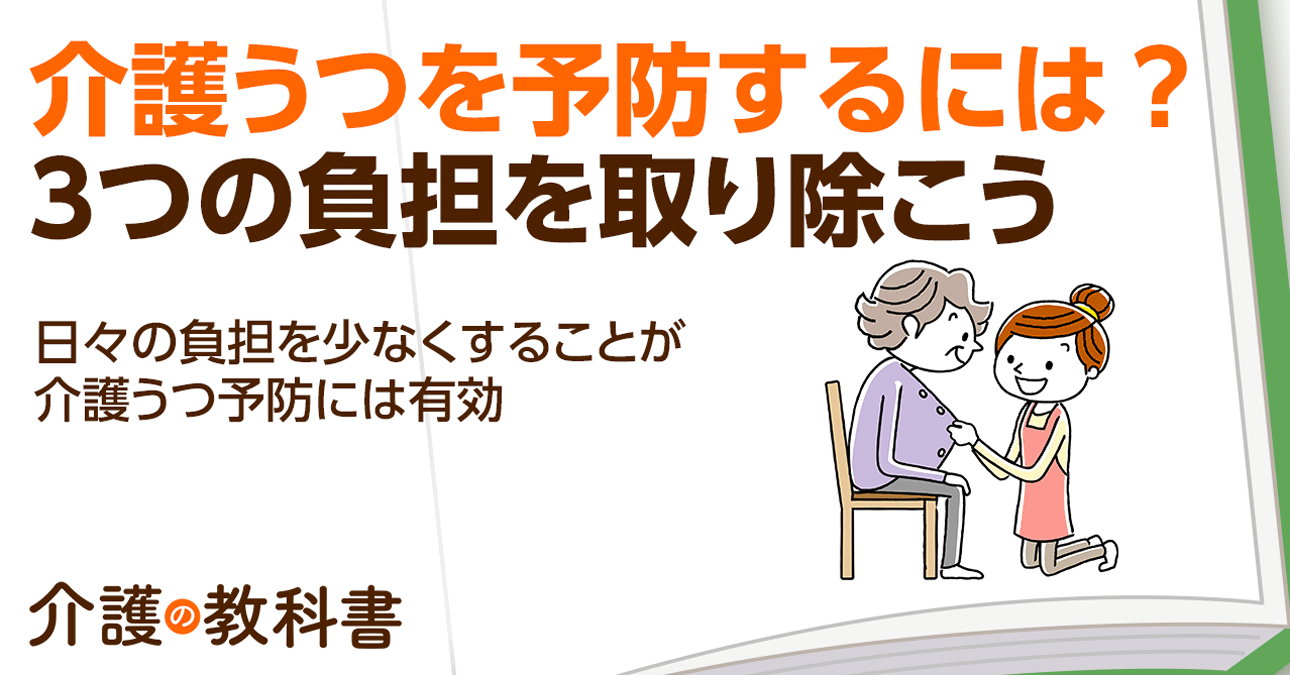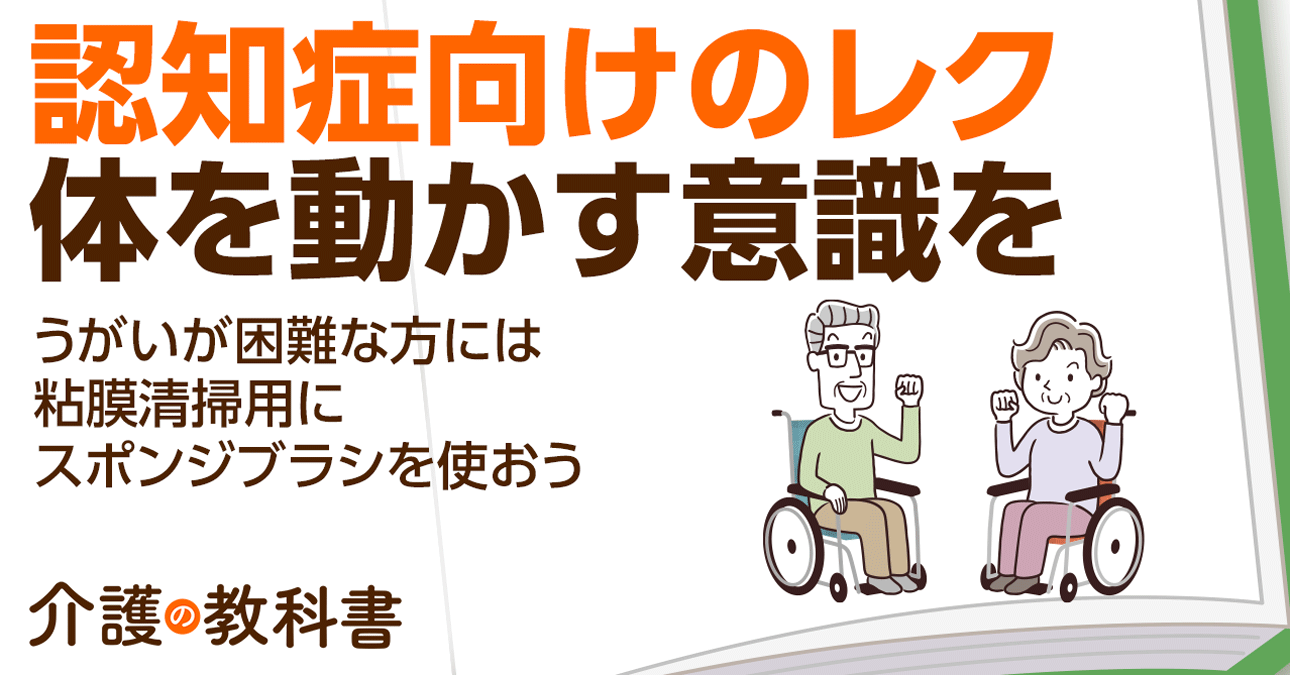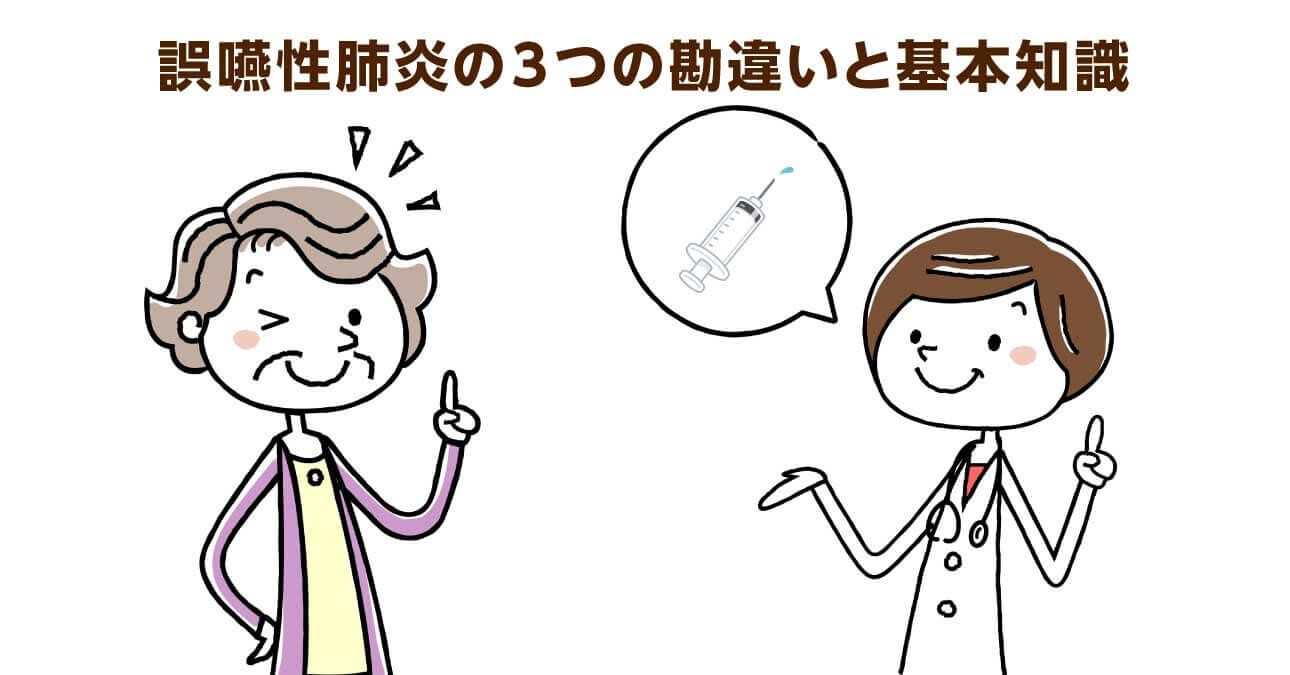厚生労働省の『平成28年歯科疾患実態調査』によると、80歳になっても歯が20本以上ある「8020」を達成した人の割合は51.2%だとされています。
80歳以上の2人に1人以上が歯を保てていますが、同時に高齢者の虫歯が増加してきていることもわかっています。
高齢者が歯を喪失する原因の多くは、歯周病と虫歯がです。そのため、歯周病予防とともに虫歯予防が大切になります。
そこで、高齢者の虫歯の要因と予防法について紹介いたします。
高齢者が虫歯になりやすい理由
最近は口腔衛生指導などで、若年者で虫歯がある人は減少傾向にあります。しかし、76~84歳で虫歯がある人の割合は、約90%と増加傾向にあります。高齢者の虫歯が増加している要因を解説します。
歯は加齢の影響を受ける
歯は歯髄(歯の神経で根っこの部分)と呼ばれる神経部分を象牙質が覆い、その上をエナメル質が覆う構造になっています。
また、歯は硬いエナメル質が覆うため、虫歯菌は容易に象牙質に進行することはできません。
しかし、高齢者の場合は、加齢の影響と、長年のブラッシングや咀嚼により、エナメル質が薄い状態にあります。そのため、虫歯菌が容易に、象牙質・歯髄まで到達してしまいます。
加えて、加齢による歯の器質的な変化が、象牙質と歯髄にも生じます。加齢に伴い、象牙質全体にある細い管の内面が石灰化され、象牙質は硬くなり、透過性も低下します。
これらから、高齢者の歯は虫歯が進行しやすく、治りにくいという特徴を持っていることがわかります。
歯髄が石灰化すると、細菌に感染しやすくなって虫歯が治りにくくなるため、歯の強さが失われます。

口腔ケアと治療
加齢とともに、さまざまな要因で歯肉(歯茎)が下がりやすくなり、歯の根元が露出するようになります。この露出した根元の部分を根面といいます。多くの高齢者は、根面が虫歯になることが知られています。
硬いエナメル質に覆われていない根面が露出すると、虫歯菌が直接歯の根元を攻撃し、虫歯になりやすくなってしまうからです。
そのため、根面の虫歯を予防するケアが重要になります。特に、効果的にブラッシングを行うことが大切です。
ブラッシングは、硬すぎないナイロン製の歯ブラシを使用して強すぎない力で行うのがポイントです。歯ブラシを新調して、1ヵ月も経たないうちに毛先が広がってしまうような人は、磨く力が強すぎる可能性があります。
強い力でゴシゴシしないと、磨いた気がしないという人もいるかもしれませんが、最適なブラッシング圧は、100~200gです。これは、リンゴを歯ブラシでこすったときに、皮に傷がつかない程度の弱い力です。
適切な圧でブラッシングを行い、根面の虫歯を予防していきましょう。
また、歯の根本部分が露出してくると、冷・温水で痛みを感じるようになります。
そうすると、うがいを十分に行わずに終えてしまうことも多くなります。うがいの際には、冷たすぎたり、熱すぎたりする水を使用せず、ぬるま湯で、しっかりと口を動かして行いましょう。
今までの歯科治療の経験のなかで、「神経を抜く」という治療をされている方もいるのではないでしょうか。
このような治療経験があると、痛みが生じないため、虫歯の進行に気づかず、歯がぐらぐらしてきて初めて気づくこともあります。
そうすると、治療が困難となり、抜歯が必要になることもありますので、特に定期的な歯科健診を受診するように気をつけましょう。
高齢者が生じやすいオーラルフレイル
加齢による歯への機能的な影響に、オーラルフレイルがあります。
加齢に伴い心身の機能は徐々に低下し、体が弱く病気になりやすくなります。この状態を「フレイル」と呼びます。つまり、オーラルフレイルは、「口のフレイル」という意味です。
オーラルフレイルは、生活環境の変化が生じたときに、口腔保健への意識が低下するところから始まるといわれています。
例えば、仕事をしている間は規則正しく食べ、食べた後の口腔ケアを欠かさず行っていたのに、仕事を辞めて人と会う機会が少なくなると、口腔ケアへの意識が薄れてしまうといったケースです。
口腔ケアへの意識が薄れると、食べた後も歯みがきをせずうがいだけですましたり、1日で行う口腔ケアの回数が減少しやすくなります。
また、オーラフレイルがはじまると、日常生活において滑舌低下、噛めない食品の増加、むせといったささいなトラブルが生じやすくなります。
このようなトラブルは、舌の動きや口周りの動きの低下傾向を示しています。
口の中や周りの動きが悪いと、唾液が十分に口の中で循環せず、虫歯の要因につながります。
唾液には、抗菌作用、pH緩衝作用、自浄作用など、虫歯を予防する機能があるからです。
薬剤などの影響を受け、唾液分泌が低下しやすい高齢者が口の動きまで低下すると、唾液を口腔内にめぐらすことが難しくなり、さらに虫歯の危険性が高くなります。
そのため、虫歯予防のためにも、口腔機能を維持し、唾液を有効に活用したオーラルフレイル予防が大切です。
オーラルフレイルの予防について
社会活動などに参加し、人と会う習慣をつける
オーラルフレイル予防は早期の対策が大切になります。対策することで口の機能低下を緩やかにし、失われつつある口腔機能を回復させる可能性があるからです。
対策の一つが、人と会って、社会活動に定期的に参加することです。
社会参加することで、食事や歯みがきの習慣がつきやすく、口腔保健への意識が高まりやすくなるからです。
社会参加活動は、心の豊かさや生きがいが得られること、自身の健康にもつながるともいわれます。
地域によっては、さまざまな市民講座が開催されていたり、コミュニティグループの活動があります。市民広報などをチェックして、社会参加活動を意識していきましょう。
口腔機能を保つ習慣をつける
虫歯予防のための口腔機能を保つには、食事や運動の習慣が大切です。食事では、筋肉の維持に大切なタンパク質などを含んだ食べ物を摂取することがポイントです。鶏肉や卵など良質なタンパク質を食事を心がけましょう。
また、口腔周囲の筋肉を日頃から動かしていくことが重要です。
顔を洗った後に「あいうべ体操」第32回参照などを取り入れてみてください。
適度に首を回したり、肩を上げ下げするような体操を日頃から行うなど、日常生活にちょっとした運動を取り入れてみましょう。

高齢者は加齢の影響などを受け、虫歯が増加しやすく、また、治りにくくなっています。
虫歯予防のためにもオーラルフレイル予防が大切です。オーラルフレイルを防ぐことで、虫歯予防に繋げていきましょう。