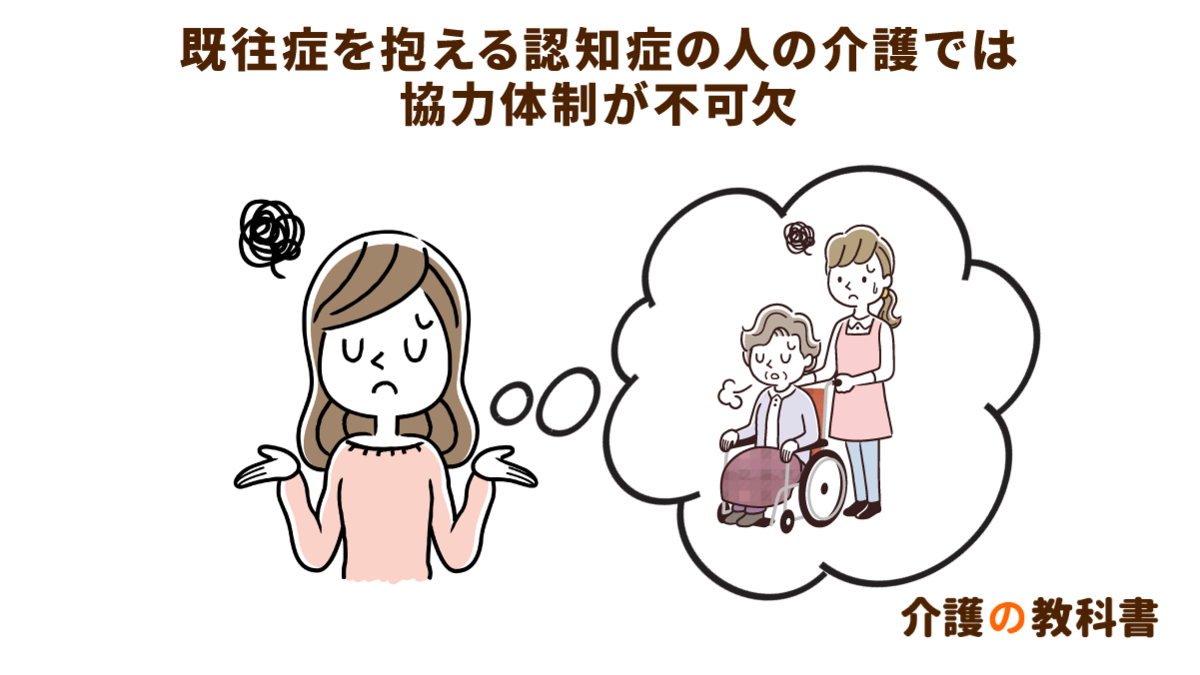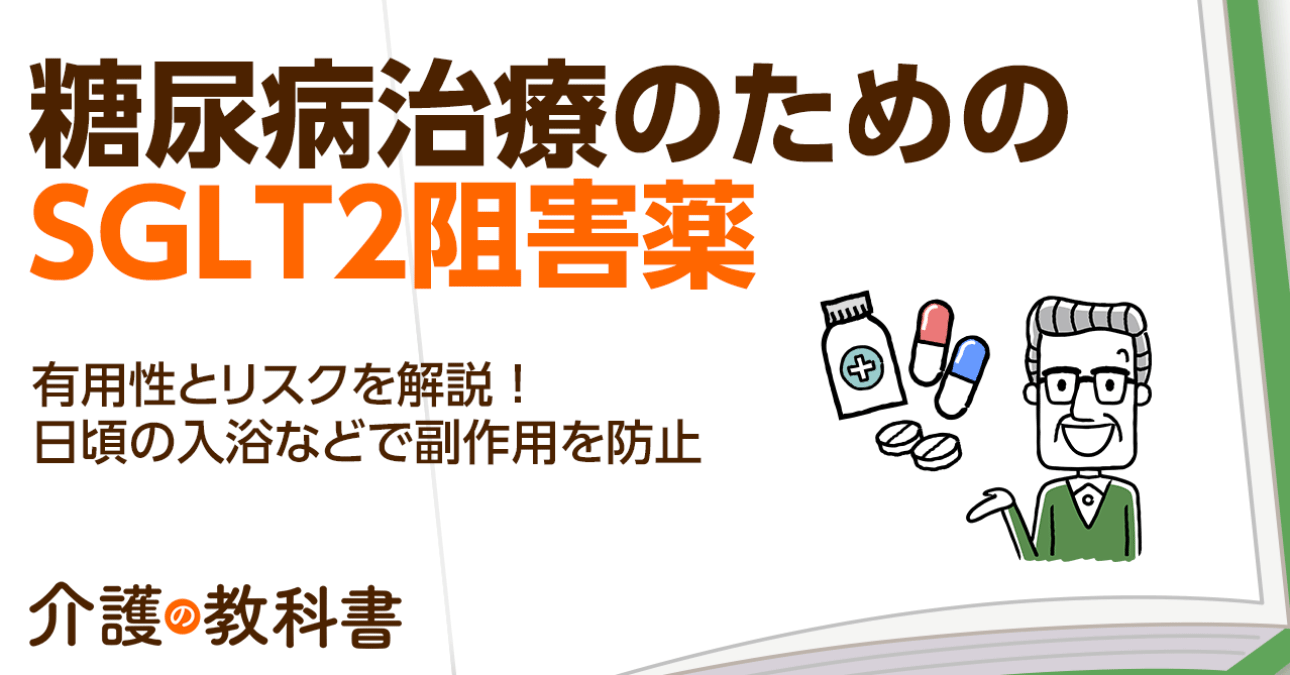介護者メンタルケア協会代表、橋中今日子です。
介護が必要となる疾患の第1位は「認知症」です。誰でもなる可能性のある疾患ですが、必要以上に恐れる必要はありません。認知症になったからといって、何もできなくなるわけではないからです。介護保険サービスや周囲の人のサポートを受けながら、自宅で生活されている方もたくさんいらっしゃいます。
しかし、持病がある方が認知症を発症した場合、家族の負担が増加することもあります。
特に糖尿病は、骨折や心臓病、脳血管疾患(脳梗塞や脳出血)のリスクが高まるため、生活習慣、運動、食事制限、服薬や自己インシュリン注射などの薬物療法をあわせた継続的な治療が必要です。
そのうえ認知症を発症すると自己コントロールが困難となりますので、家族などの介護者にはその負担が大きくのしかかります。「私がサポートしなければ」という責任感から、精神的に追いつめられることも多いのです。
【事例】糖尿病の母親が認知症を併発して自己コントロールが困難に
【50代 女性 Aさん】の事例
Aさんの母親は、糖尿病を患いながらも一人暮らしをしていました。しかしある日、自宅で倒れていたところをご近所さんに発見されて緊急入院。検査の結果、糖尿病の病状が悪化していて、急激な低血糖で意識障がいを起こしたことがわかりました。さらに、アルツハイマー型認知症とも診断されました。母親は記憶や認知機能の低下で、服薬や自己インシュリン注射が困難になっていたのです。
退院後に問題になったのが、毎日のインシュリン注射でした。Aさんは主治医から「本人だけでは服薬や注射のコントロールができないので、家族の協力が不可欠です」と説明を受けました。インシュリン注射は医療行為にあたるため、本人、家族、看護師や医師しかできないのです。
Aさんは、訪問看護サービスを利用したいと考えましたが、母親は「何も困っていない!余計なことをするな!」と、介護保険の申請すら嫌がります。このため、Aさんは片道40分かけて、毎日実家通いをしなければなりませんでした。
高齢の糖尿病患者は、服薬やインシュリン注射をきちんと行っていても、容態が安定しないことが多いのです。3ヵ月後、母親は再度、低血糖と脱水症状で緊急入院します。Aさんは「私が実家に戻らなければ、母が死んでしまうかも…」と思いつめてしまいました。
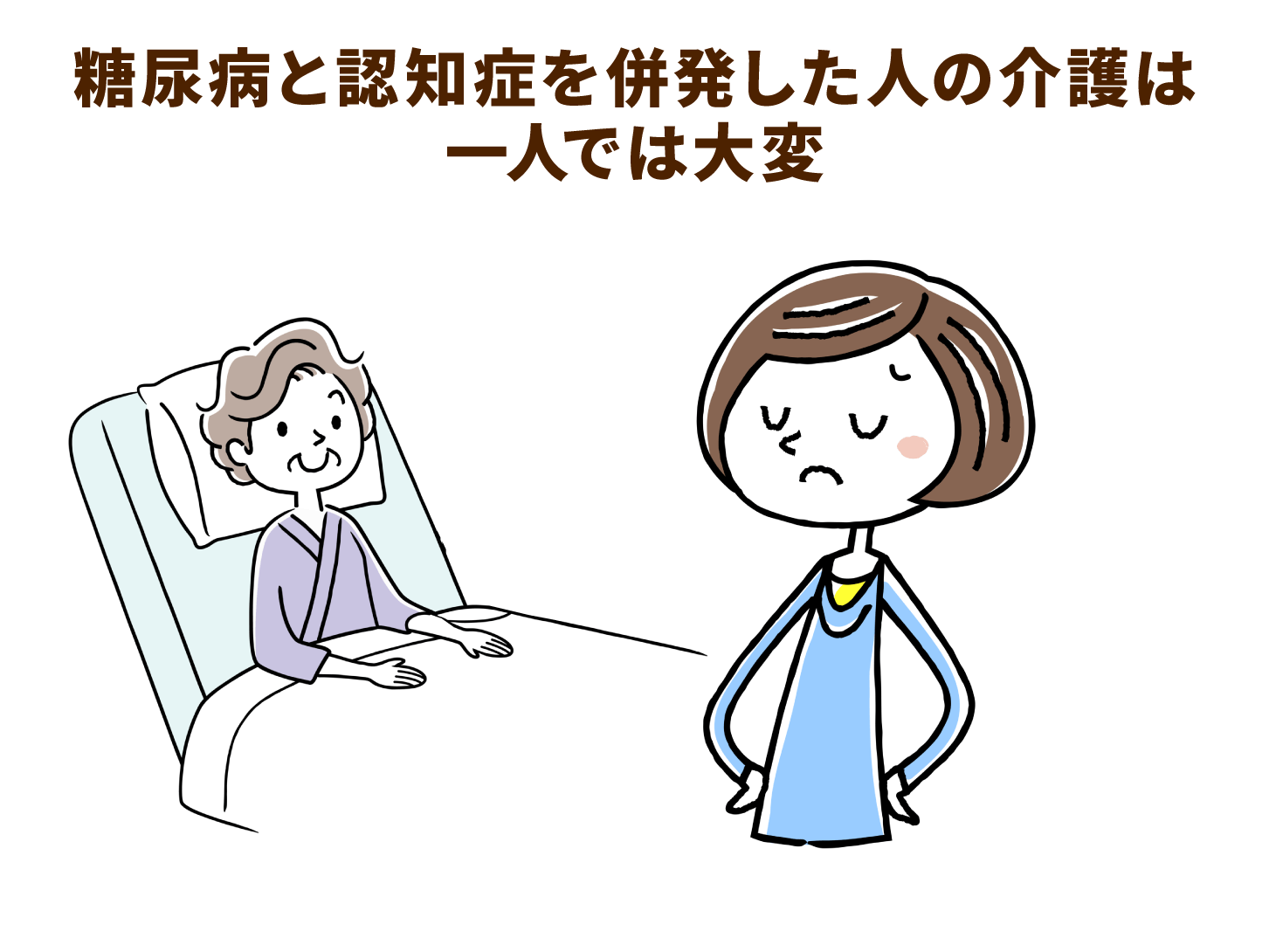
ピンチを救ったのはソーシャルワーカー
Aさんのピンチを救ったのは、病院のソーシャルワーカーでした。「もう娘さんだけでは対応できません。介護保険の申請をして、お母さまが安心して生活できるように介護保険サービスを使った協力体制を作りましょう」と強く勧められたことで、母親が介護保険の申請を受け入れたのです。
サービスを強く拒んでいる人も、入院中にソーシャルワーカーや医師の助言を受けると、気持ちが和らぐことがあります。母親は要介護1と認定され、週2回の訪問看護サービスの利用が始まりました。
訪問看護サービスの導入で、Aさんは連日の実家訪問から週に2回は開放され、落ち着きを取り戻しました。その後は徐々に、訪問介護、デイサービス、ショートステイと少しずつサービスの種類を広げていくことができ、今では週に1~2度ほど顔を見に行く程度になり、施設への入居も視野に入れているそうです。
Aさんは「私一人では、サービスを拒む母を説得できませんでした。入院はピンチだったけれど、ある意味チャンスだったかもしれません」と笑って話してくれました。
協力体制を築いて介護者の心理的ストレスを和らげる
実質的な負担を軽減することも大事ですが、それ以上に大事なのは「私が介護をするしかない」という責任感が引き起こす心理的ストレスへの対処です。
まずは、介護サービスを利用して、複数人の専門家による協力体制を築いていきましょう。サービスをフル活用したとしても、負担をゼロにすることはできません。しかし「何かあったときに、一緒に考えてくれる専門家がいる」という安心感は、介護者を追いつめる過剰な責任感を緩和することができるのです。
Aさんも、ケアマネージャーや訪問看護・介護スタッフと情報交換を含めた話し合いの場で愚痴や悩みを言えるようになり、心がずいぶん楽になったと言います。
また、ここ数年で、インシュリン対応ができるショートステイの施設が増えました。新しい情報は専門家が一番よく知っているのです。「介護者自身に不測の事態が起きたとき、頼れる人や場所がある」というセーフティーネットを整えるためにも、協力体制は不可欠です。
「私がやらなければ」「私しかいない」という考えが頭によぎったときは、「今、限界になっている!」と気づくきっかけにしてください。そして、「まだ使っていないけれど、助けてくれそうな人、物、サービスは何か?」と、協力体制を広げる意識を持つようにしてみましょう。

苦しいときは新しい知識や情報を得よう
コロナ禍によって見通しの立たない状況の中で、緊張を強いられる生活が続いています。自由に人に相談したり、協力を求めたりすることがままならないときだからこそ、新しい知識、情報を得て苦しい状況を打開しましょう。
『介護の教科書』には、メンタルヘルス、メンタルケアの情報も多数掲載されています。過去の記事と合わせて、ぜひ活用ください。
橋中からの直接のお返事、対応はできませんが、『みんなの介護』の記事や当協会が配信している無料メルマガで解決策についてお伝えしていきます。
皆さんが介護で経験されていること、対策を取られていることを介護者メンタルケア協会の問い合わせフォームでぜひ教えてください。お困りごとやご相談には、こちらの『介護の教科書』の記事でお答えできればと考えています。
「職場が介護の状況を理解してくれない」「何度も同じことを言われて怒鳴ってしまう」といった日々の介護の悩みについては、拙書『がんばらない介護』で解説をしています。ぜひ、手にとって参考にしていただきたいです。