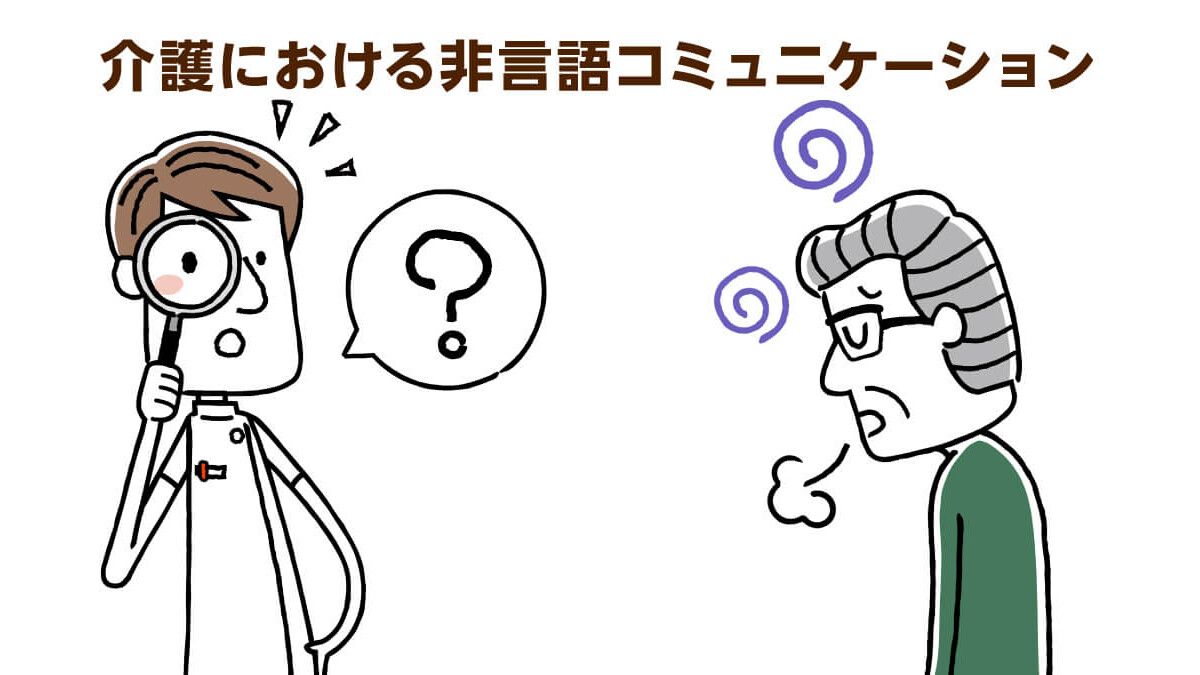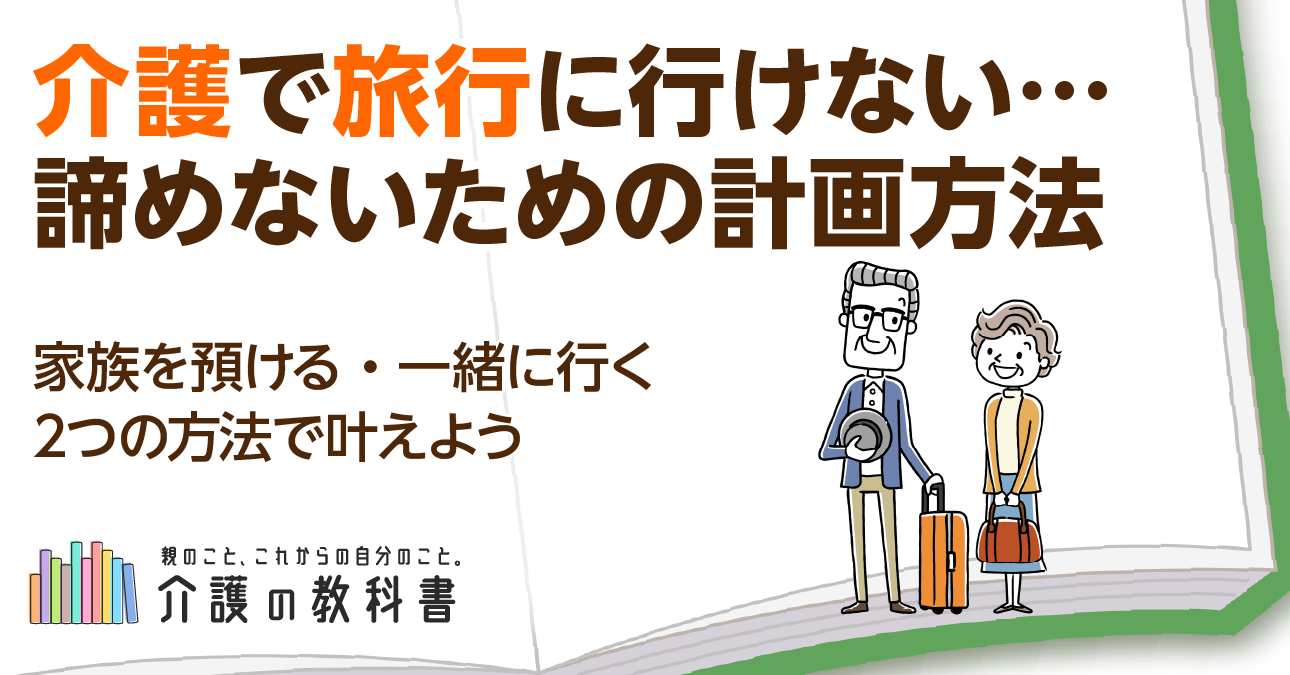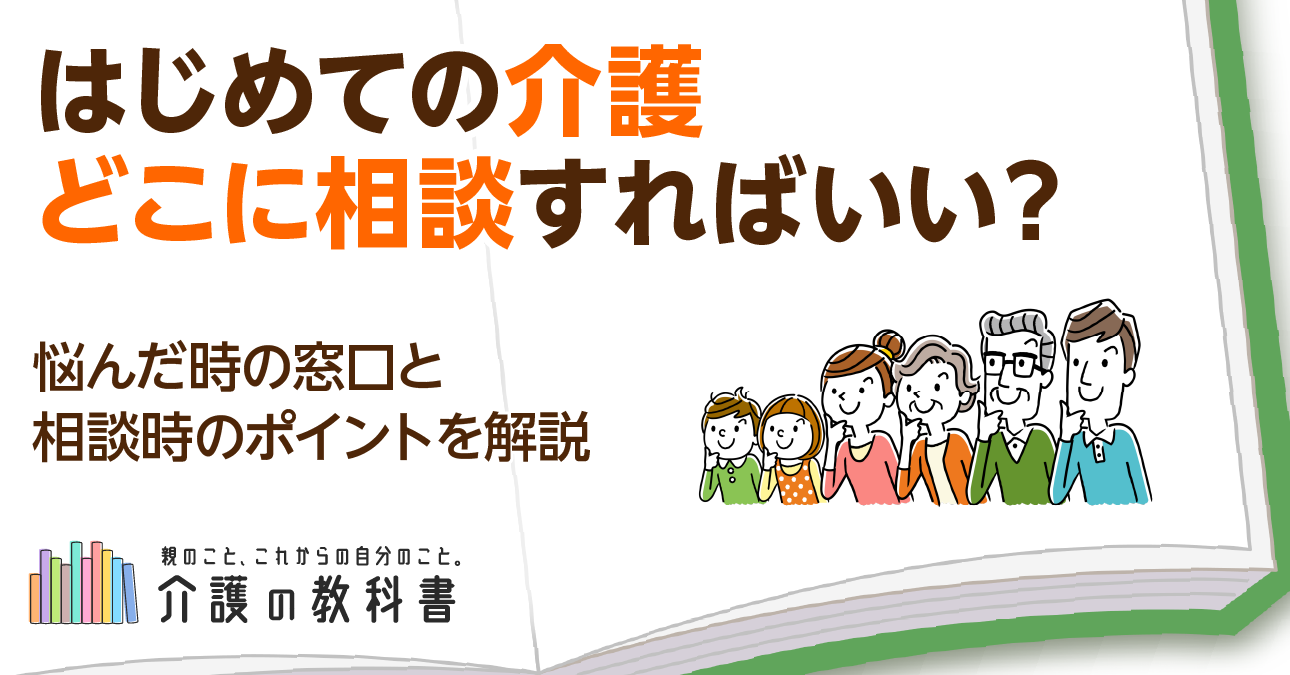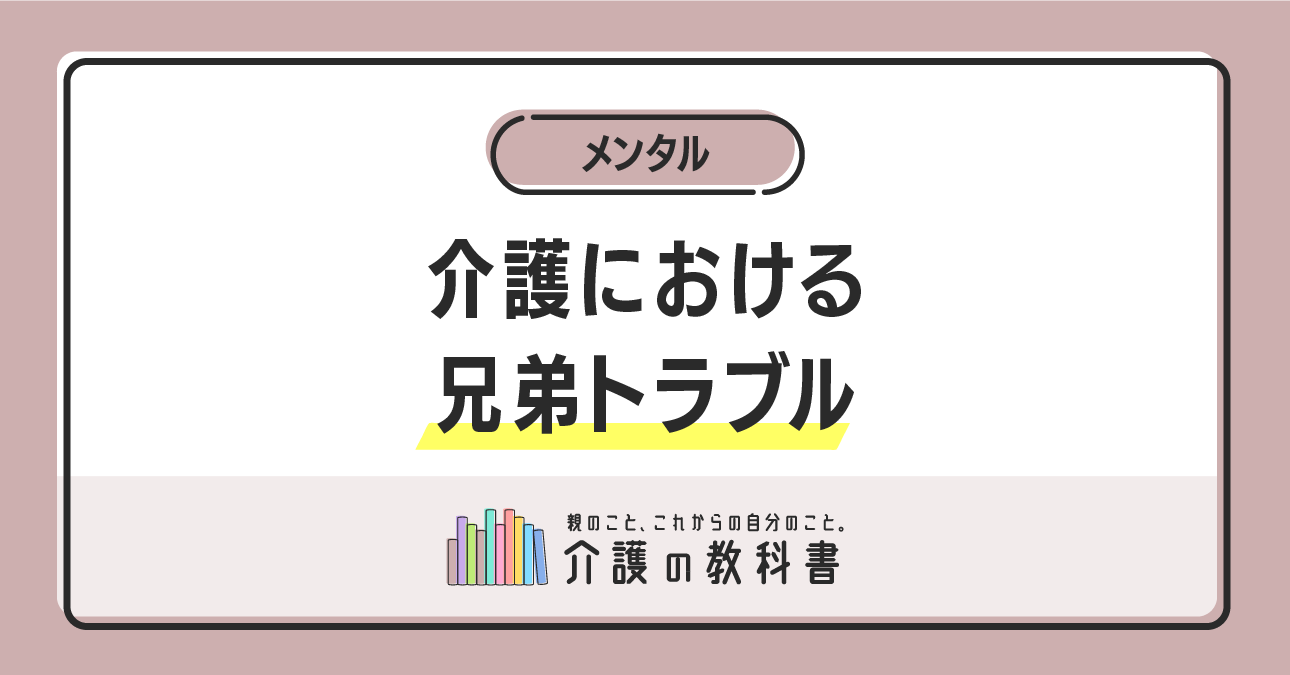皆さんこんにちは。陽だまりのnekoの夢のmaruこと井上百合枝です。
今回は、「介護における言語コミュニケーションと非言語コミュニケーション」についてお話していきます。
対話で用いるツールは言語だけでない
皆さんは「どのようにコミュニケーションを図るのか」と聞かれたとき、どんな手段を思い浮かべますか。多くの方が、「言語によるコミュニケーション」を思い浮かべると思います。
ただ、実際の介護現場でコミュニケーションを言語のみに頼っている場合、介護者から「あの人(被介護者)は認知症が進行していて何を言っているかわからない」とか、「(被介護者が)何も言ってくれないからわからない」などという言葉をよく耳にします。これは、介護する側にもされる側にもとても苦しいことだと思います。
しかし、コミュニケーションは言葉のみでは成立しません。「言語によるコミュニケーションは、コミュニケーション全体の10%程度」と言われることもあります。意識する・しないにかかわらず、私たちはあらゆるものでコミュニケーションを図っているのです。これを「非言語コミュニケーション」といいます。
では、私たちは言語以外のどのような手段でコミュニケーションを取っているのでしょうか。いくつか例を挙げてみます。
- 声のトーン
- 視線の動き
- 表情
- 身振り・手ぶり
- ものを動かす音
- 姿勢
- 体の距離・接触
- 匂い
- 服装
- 持ちもの

非言語コミュニケーションの2つの事例
一人暮らしのAさん(70代)の場合
Aさんは社交性が高く、週に3回ほど地域の公民館に出向いては、健康体操やダンスなどのサークルに参加していました。サークルでは開始時間の10分前には到着して準備を手伝っています。表情はいつもはつらつとしていて、明るい色の服装を着ていることが多く、新規の参加者には積極的に声をかけていました。しかし1ヵ月ほど前からAさんは浮かない表情をしていて、サークルにも遅れてくるように。口数も少なくなったり、暗めの色の服が増えてシャツのボタンもちぐはぐになってることもありました。
皆さんは、このAさんから発せられているコミュニケーションの発信をどのようにキャッチしましたか?「実際に見たわけじゃないし、これだけじゃわからない」という意見もあるかもしれませんね。では、もう1例見てみましょう。
自宅で介護されているBさん(80代)の場合
在宅介護を受けているBさんは近頃認知症が進み、言葉によるコミュニケーションが取りづらい状況になりました。1人で歩行や立ち上がりができないので、ソファーに座っていることが多くなっています。しかし、ときどき大声で「おーい、おーい」と介護者を呼んでお尻をもぞもぞさせます。「なーに?」と介護者が声をかけてもBさんは答えることはできません。
介護者が離れると、ほどなくして「おーい、おーい」と呼びます。そのような日は、1日中その繰り返しです。ときには、1人で立ちあがって衣類を全部脱いだり、おむつを外してしまうこともあります。介護者は、自分に嫌がらせをしているのではないかと感じることもしばしばです。
非言語コミュニケーションの意味を客観的に捉えること
コミュニケーションは、よくキャッチボールに例えられます。一方からの投げかけでは成立しません。ボールを投げる(被介護者)、受けとめる(介護者)、投げ返す(介護者)、受けとめる(被介護者)ができるようになると、コミュニケーションが成立します。
AさんもBさんも、非言語的なコミュニケーションの「ボール」を介護者や周りの人にたくさん投げかけています。では、被介護者から投げられた非言語のコミュニケーションボールを、介護者がどうキャッチして投げ返すことができるのか考えてみましょう。

Aさんの例
Aさんからのボール
- 顔色:はつらつ→表情が浮かない
- 服の色:明るい色→暗い色
- サークルの場所への到着時間:10分前にくる→遅れてくる
- 身だしなみ:シャツのボタンがちぐはぐ
周囲や介護者からの返球例と対応のヒント
| 気づき | 返球例・対応のヒント |
|---|---|
| あれ、以前とは異なる変化が見られるぞ | 「何かあったかな?」「体調に変化はないかな?」などと声をかけてみる |
| 気持ちの状態が悪いのかな? | 「何か考えていることがある?」「何か不安なことがある?」と声をかけてみる |
Bさんの例
Bさんからのボール
- ときどき「おーい、おーい」と介護者を呼んでお尻をもぞもぞさせる
- 介護者が離れると同じように声を出して呼ぶ
- ときに1人で立ちあがって衣類を全部脱いだり、おむつを外したりする
周囲や介護者からの返球例と対応のヒント
| Bさんの気持ちの予測 | 返球例・対応のヒント |
|---|---|
| 排便・排尿をしたいのでは? | 訴えを受け入れ、排泄介助をする |
| 不安になっている | 「ここにいるよ、安心して」と声をかけ、しばらく手足をさする |
| 座る時間が長くてお尻が痛そう | お尻や背中にクッションを挟んだり、座る場所を変えたりしてお尻の痛みを軽減する |
| 「おーい」と呼べば介護者が自分の方を向いてくれると認識している | 過剰に反応せず、Bさんと介護者が実行できる別のコミュニケーションを探す |
| 「私(介護者)は、あなた(被介護者)を大切に思っている」というメッセージを伝える | |
| お風呂に入りたい | 「まだお風呂が沸いていないので、お風呂が沸くまで服を着ていてね」と諭す |
| 気温が暑いと感じている | 衣類を1枚減らす、少し窓を開ける |
| 体がかゆい | 全身の皮膚状態を確認し、皮膚科等の受診を検討する |
| 衣類の接触が心地悪い | 本人の肌が苦手な繊維が肌に接触していないか確認する |
| ゴムがきつくないか確認する | |
| 衣類にしわが寄っていないか確認する | |
| 衣類そのものがきつくないか確認する | |
| だぶついて身体の動きを妨げていないか確認する | |
| 排泄があった | 排泄介助を行う |
| 出かけたい | 衣類を着せて、少し外に出る |
「ときには1人で立ちあがり、衣類を全部脱いだり、おむつを外したりする」行動は、本人にとってどのようなときかを客観的に捉えて、声かけ・介助をしましょう。
仕草やさまざまな変化からご本人の気持ちを捉えよう
いかがでしたか。今回は介護における言語以外の非言語コミュニケーションについてお話して参りました。言葉以外の非言語コミュニケーションを理解することで、介護する方・される方のお気持ちや介護生活が少しでも楽になれたらと思います。