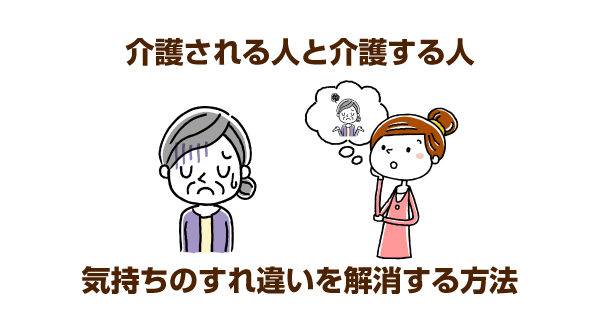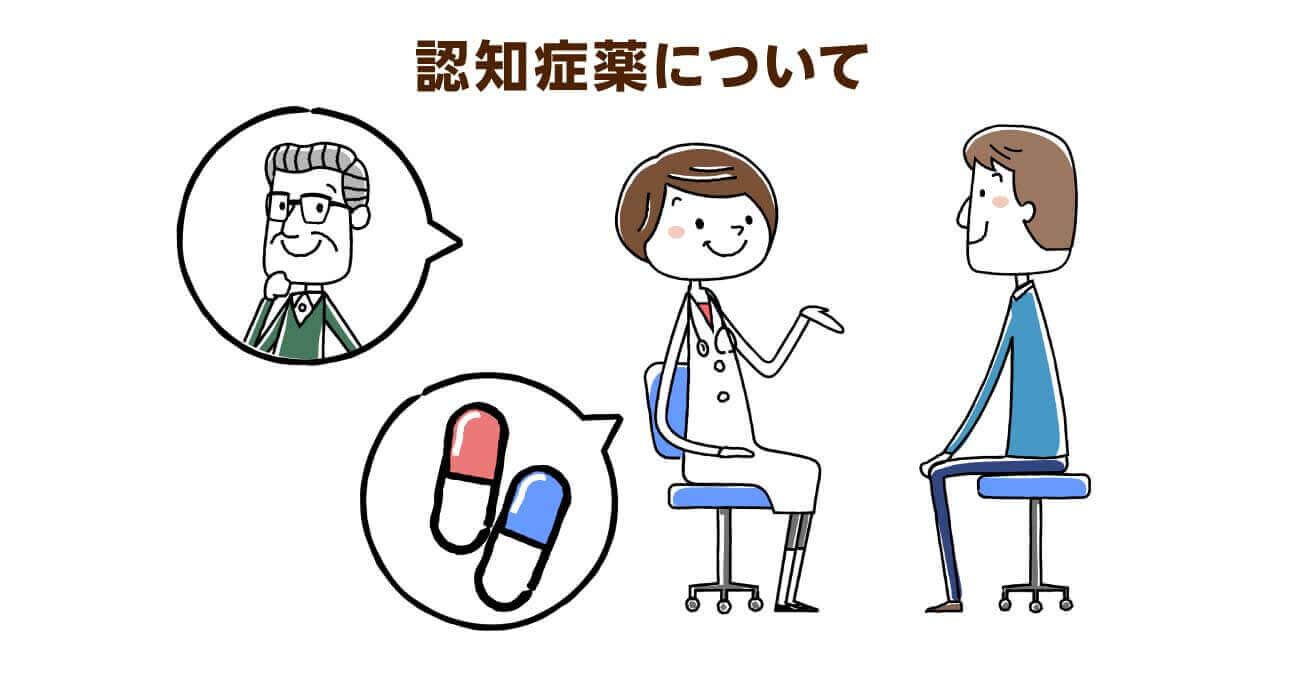こんにちは。「メンタル」の科目を担当している、介護者メンタルケア協会代表・心理カウンセラーの橋中今日子です。
「両親との関係がぎくしゃくしている中で介護が始まってしまった」、「大事にしてもらえた記憶がないのに、なぜ私が介護しなければならないの?」など、心にわだかまりを抱えながら、介護を続ける苦しさを訴える相談が後を絶ちません。
介護そのものの負担はもちろんのこと、「介護なんてしたくない」「でも“介護しない”なんて言えない」という気持ちの中で疲弊している人がとても多いのです。
今回は、嫌いな親の介護をしたくない。だけれど、せざるをえない。そんな葛藤で苦しんでいる気持ちを楽にする3ステップをご紹介します。
ステップ1:相反する気持ちに名前をつけて独立させる
まず「介護をしたくない自分」と「介護はしたくないけど、“しなきゃいけない”と思っている自分」にそれぞれ名前をつけましょう。
「どういうこと?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。「名前をつける」ことは、異なる意思や目的を持った気持ちを擬人化し、分けて整理するための方法です。
例えば、「介護したくない自分」には「本当は文句を言いたい自分」「怒っている自分」などです。「したくないけど、“しなきゃ”と思っている自分」については、「責任を感じている自分」や「後悔したくない自分」といった感じで名前をつけてみましょう。
どうしても名前がつかない場合は、「A」「B」と記号で分けても良いです。ここで名前をつけることが最終ゴールではないので、ピンとこなくても「(仮)」と書いて、まずは名前をつけてみてくださいね。
ステップ2:それぞれの「自分」の言い分を聞き、ねぎらいの言葉をかける
続いて、名前をつけた「自分」たちの、それぞれの言い分を書き出してみます。両親や家族にこれまで言えなかったことなどです。
仮に「本当は文句を言いたい自分」の言い分を書き出したとしましょう。
「本当は文句を言いたい自分」の言い分
- 「そもそも、私を大切にしてくれなかったじゃない!」
- 「『お姉さんなんだからしっかりしなさい、我慢しなさい』ってばっかり!
- 「『進学したい』って言ったのに、許してくれなかったじゃない!
- 「子ども生まれても、妹の方ばかりかわいがって!」
ある程度書き出せたら、次に「これを言えなかったことで、どんな気持ちだったのか?」を書き出します。つらい、苦しい、悲しい、寂しい……など、奥に秘めてきた「感情」を書き出すのです。ただし、文句だけを並べていると興奮状態になってしまいますので、必ず感情を言葉にしてみてください。
- 言えなくて「つらかった」
- 話を聞いてもらえなくて「悲しかった」
- わかってもらえなくて「苦しかった」
感情を書き出せたら、両親や家族に本当は言ってほしかった“ねぎらいの言葉”を、自分自身にかけてあげましょう。
- 「だからつらかったんだね」
- 「だから苦しかったんだね」
- 「そんな中で、本当に介護を頑張ってきたね」
ねぎらいの言葉を自分へプレゼントすることは「自己受容」「自己共感」と言って、ストレス解消やメンタルヘルスで大事なステップなのです。

1人目の「言い分」と「感情」を書き出すことができたら、同じ方法を使って別の「自分」の言い分を聞きます。
「後悔したくない自分」の言い分
- 「だって、両親もあと何年生きられるかわからないもの」
- 「大切にされなかったと言っても、育ててもらった恩があるんだから」
- 「最期のとき、後悔したくないでしょう」
- 「今しかできないことがあるんじゃない?」
- 「もっと大変な人もいるし、まだ大したことはしてないじゃない」
義務や自分を説得するような言葉が出たら、「なぜそう思うのか」質問を続ける
「後悔したくない自分」や、「○○を回避したい自分」の場合、義務やその人自身に対する説得の言葉が並ぶことが多いです。そのときには、「なぜそう思うのか?」とさらに突っ込んで質問してみましょう。
- 「最期ぐらい、家族らしい時間を過ごしたい」
- 「お父さん、お母さんの笑顔を見たい」
もう1人の自分の言い分を聞き出せたかどうかを判断する目安は、言い分をすべて「〇〇したくない」から「〇〇したい」に変換できるかという点です。
ここまで書き出せたら、「本当は文句を言いたい自分」のときと同様に、共感とねぎらいの言葉をかけてあげましょう。
- 「そっか、家族らしい時間を過ごしたいんだね」
- 「お父さん、お母さんの笑顔を見たいんだね」
- 「でも、なんだかうまくいかなくてつらいんだね」
- 「その中で、長女としての責任を果たそうと頑張ってきたんだね」
「〇〇な自分」が2人以上いる場合は、全員分同じステップを繰りかえしてください。
ステップ3:「〇〇したい自分」と改名して、目的を明確にする
最後は、それぞれの自分に「ふさわしい名前」を再度選びなおしてください。
例えば、「怒っている自分」は「自分を大切にしたい自分」に、「後悔したくない自分」は「両親の笑顔を見たい自分」などですね。「〇〇したい自分」と書き直すことで、目的が明確になります。
目的が明確になると、頭の中でごちゃごちゃになっていたものが整理でき、「だから嫌だって思ってたんだ」「だから、“介護しなきゃ”と思っていたんだ」と、自分の中で納得感が生まれやすくなります。
自分の「目的」を明確にしたあとは、「明日はどんな時間にしたいか」「この一週間がどういった時間になれば、2つの異なる『自分』の双方が満足できるか」を書き出してみましょう。
例えば、疲労感を覚えている人の場合には、一週間だけ「自分を大切にしたい自分」を優先して、実家に帰る回数や滞在する時間を短くしてみる。その翌週に通院の付き添いをしなければならないときには、「自分を大切にしたい自分」に少し協力してもらって「両親の笑顔を見たい自分」を優先する回数を増やす、などです。
すべて自分の気持ちではありますが、気持ちの整理が難しい“チームメンバー”の協力を得るという、「マネジメント」の気持ちで取り組んでみてください。
自分の心の葛藤への対応が上手になってくると、ストレスが軽減するだけでなく、心身の回復力も増すことがわかっています。また、意見が異なる他者とのコミュニケーション力もついてくるので、今回紹介しました「対立する自分の気持ちのマネジメント術」をぜひ試してみてくださいね。
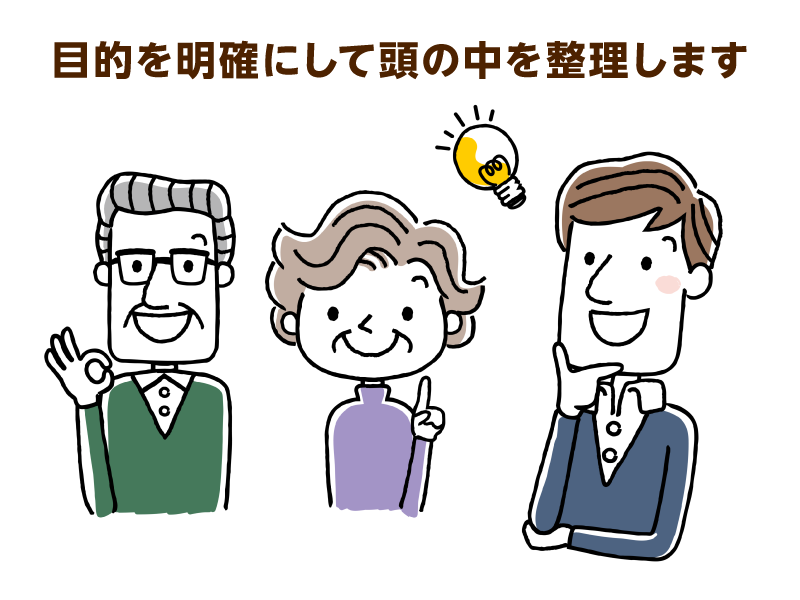
気持ちを抑えこむのではなく、少しずつ受けいれていきましょう
最後にお伝えしたいことは、「葛藤があるそのままの状態でいい」ということです。嫌な気持ちを抱えたまま介護をしてもいいですし、「〇〇のことが嫌いだ」と思っても良いのです。
「“嫌いだ”なんて考えちゃいけない」「“介護したくない”なんて思っちゃいけない」といった、自分の中で湧きおこる気持ちを無理やり押さえこもうとすることは、私たちの心身に大きなダメージを与えることが研究でわかっています。見たくない自分の心を受けいれるには時間が必要かもしれませんが、「“嫌いだ”と思っていい」「“介護なんてしたくない!”と言っていい」と、少しずつ自分に許可を出す回数を増やしてみてくださいね。
介護に関するお一人お一人のご相談にお答えすることは叶わないのですが、皆さんから寄せられたお声を元に必要な情報を記事にしてまいります。もしよろしければ、何について困っておられるのか、どのような情報をお求めなのかを相談フォームから是非お寄せください。
介護者メンタルケア協会が発行している無料メルマガ「介護に疲れたとき、心が軽くなるヒント」でも、心の葛藤の解消法やストレス対策の具体的な方法をお伝えしています。ぜひ登録してみてくださいね。