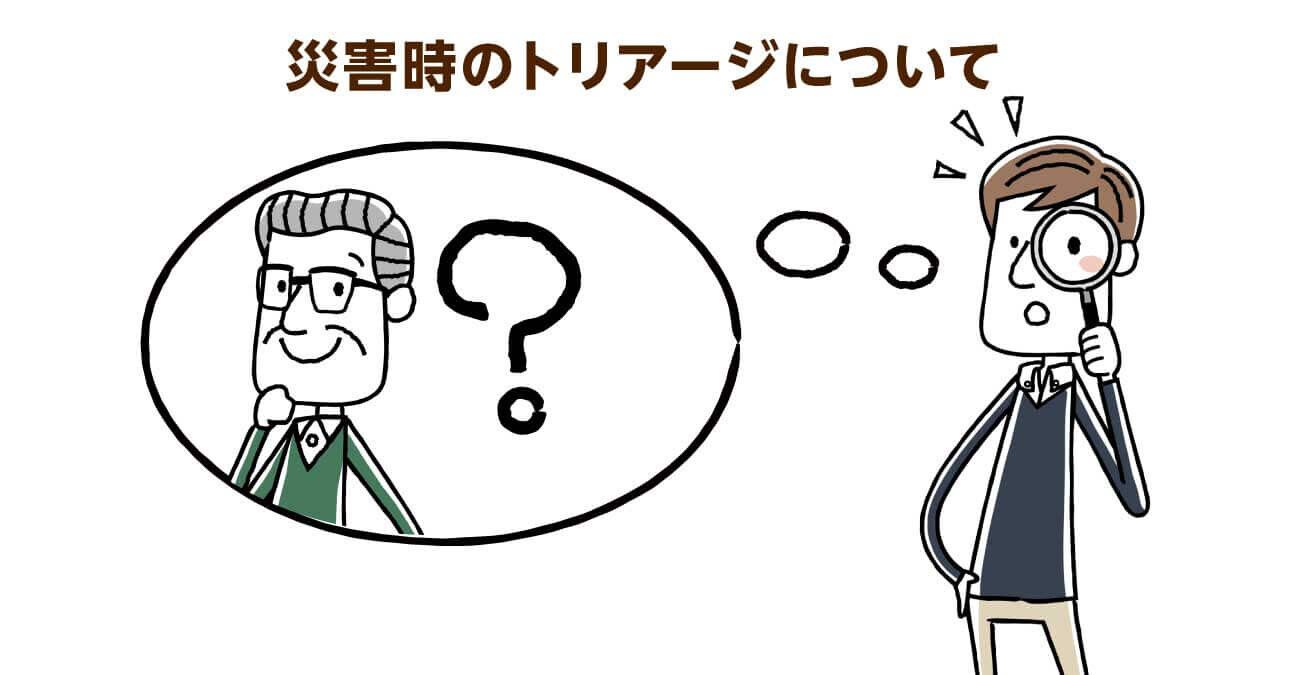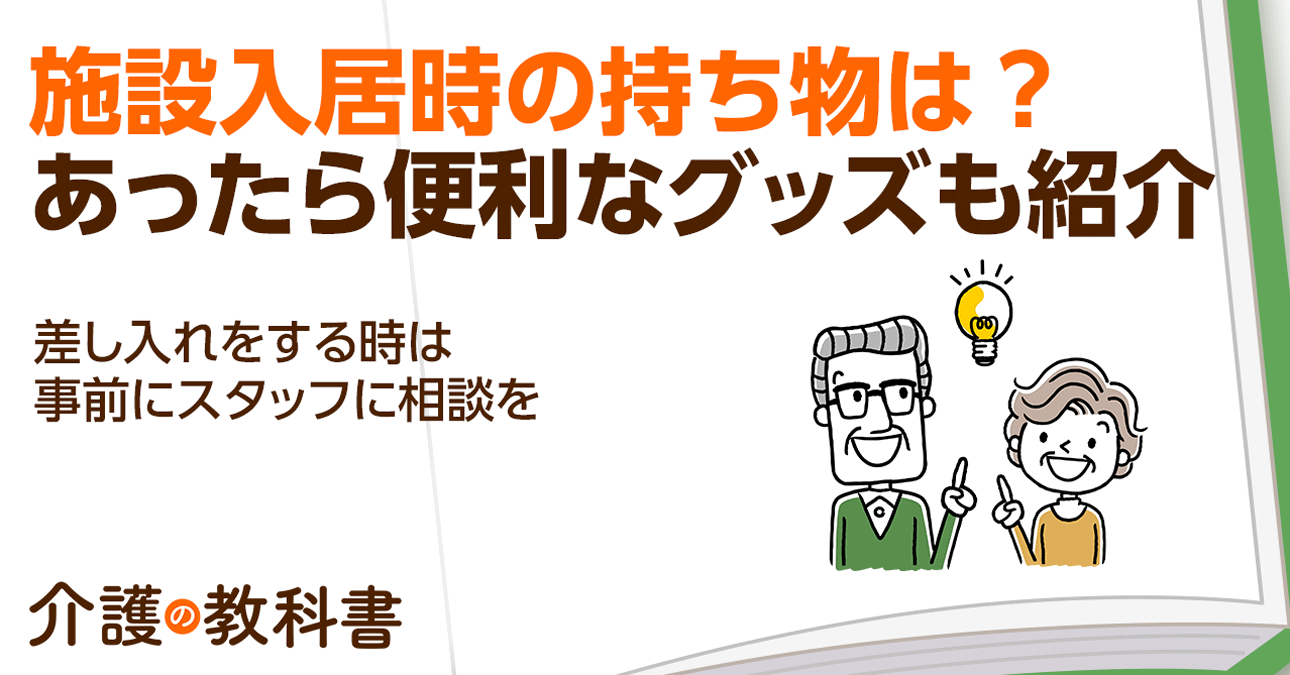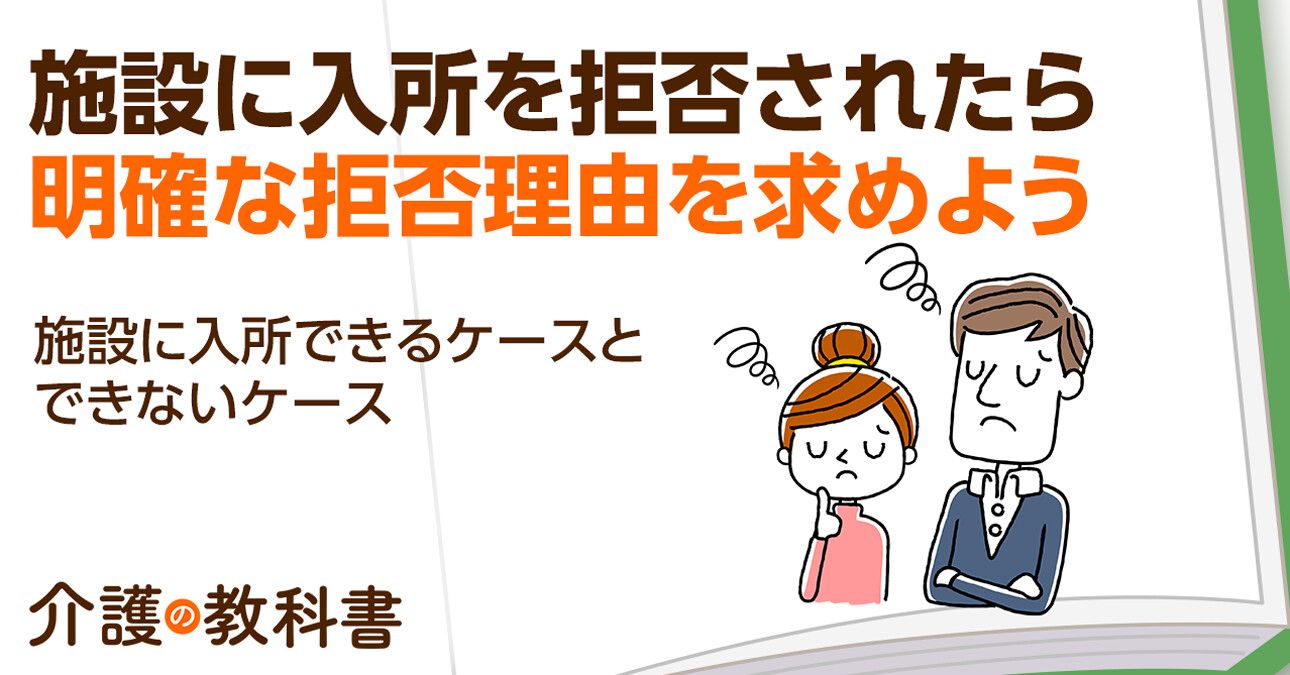皆さん、こんにちは。(公社)大分県栄養士会の栄養ケア・ステーションを担当している管理栄養士の濱田美紀です。
今回は、「ミールラウンドの際のチェックポイントと対策」についてお話ししたいと思います。
ミールラウンドで食事が取れているかを確認
「ミールラウンド」とは、実際の食事の食べ方を確認して、しっかりと食べて飲み込めているかを評価することです。「食事を行う」とは、具体的には以下の2工程を指します。
- 料理を毎回口の中で噛みくだいて(咀嚼:そしゃく)むせることなく飲み込む(嚥下:えんげ)
- 体内に必要な栄養素を吸収して元気に過ごす
これらの当たり前の行為を、高齢化や脳卒中などの病気や事故、認知症などで忘れてしまう方がいます。そのような方は、生きていくための食事ができなくなってしまう場合があるのです。
一人ひとり状態や症状が違いますが、そのような方に必要な料理を提供し、食べているかを確認するのがミールラウンドです。ミールラウンドを行う場合、注目すべきポイントは介護施設・在宅で生活されているときで異なります。今回は、それぞれのポイントと簡単な対処法をお話ししていきます。

介護施設における確認すべき8つのポイント
- 1:食事を食べものだと理解できているか認知機能を確認
- 理解できていなかった場合は、目の前で食事を見ていただきながら説明し、認識してもらいましょう。
- 2:テーブルが食事しやすい高さに調節されているか
- 料理が見える高さにテーブルがセットされているかを確認しましょう。
- 3:食事の姿勢はきちんとしているか
- 前かがみや後ろにのけ反ったりしていないかを確認します。体に麻痺などがあり、椅子に座っていても姿勢が斜めになっている場合は、クッションなどを当てて垂直に座れるように奨めましょう。
- 4:箸やスプーンなどの食具はどれが適しているか
- 麻痺がある方でご自身で食事を取る方は、どのようにして食事をされているかを確認し、必要であれば介護自助具を準備しましょう。
- 5:咀嚼・嚥下機能を評価して食事形態を確認
- 咀嚼・嚥下機能の悪い方は言語聴覚士などに評価してもらい、本人にあわせた食事形態やとろみづけを栄養士などと相談してください。

- 6:食事をおいしそうに食べているか、食事を全部食べているか
- 全体を観察し、提供した食事をすべて食べているか残食調査を毎回行いましょう。ニーズにあった食事提供ができているかを確認することが目的です。
- 7:排泄(尿・便)はきちんと出ているか
- 排泄のチェックを行い、便秘などがある場合は看護師に相談しましょう。
- 8:毎月の体重変化を確認し、活動量と食事摂取量が適切かを多職種で確認する
- 体重の増減は摂取したエネルギーと運動量に大きな差があるか、病気による可能性もあるので多職種で対処法を検討してください。
介護報酬改定で栄養マネジメントにおける加算を強化
施設では、必要に応じて医師や看護師、歯科衛生士、言語聴覚士、栄養士などの多職種でミールラウンドを行うことが大切です。
来年度の介護報酬改定では、これまでの「栄養ケアマネジメント」が施設サービスに包括化され、「栄養マネジメント強化加算」が設定されています。この加算は、低栄養リスクの高い方へ管理栄養士が週3回以上のミールラウンドを行うことが条件です。なので、介護職員の方は勤務している施設の多職種の方と、ミールラウンドの方法について確認されると良いと思います。ほかにもさまざまな条件がありますので、厚生労働省の資料を確認してください。
在宅における確認すべき4つのポイント
介護施設でのミールラウンドでお話しした7項目目までは同じです。在宅介護のみで気をつけるべきポイントは、以下になります。
- 1:定期的な定住測定や血液検査など
- 定期的に体重測定や受診での血液検査を行いましょう。顔色なども確認して、必要な場合は主治医や福祉サービスの方へ相談してください。
- 2:必要な栄養を摂取できる環境は整っているか
- 買いものや料理をつくれる人がいるかを確認します。整っていない場合は福祉サービス(買いもの支援・調理支援)をお願いすることも必要です。
- 3:主治医からの食事について指示があるか、それには対応ができるか
- 在宅で食事療法を継続することは、とても大変だと思います。栄養士の方に、在宅での食事療法について相談してみてください。
- 4:訪問介護や通所事業所と連携を取っているか
- お住まいの地域にある「地域包括支援センター」に相談し、地域で元気に過ごせるような支援を受けていただければと思います。

持病のある人は特に注意
在宅では糖尿病や腎臓病などの治療食を必要としている方や、食べもので「むせ」がひどく誤嚥性肺炎の恐れがある方は特に注意が必要です。しっかりとミールラウンドを行うことで体調管理を行いましょう。
ミールラウンドは健康状態の確認のためにも重要
ミールラウンドとは、食べることだけを見るのではなく、その方が元気で過ごせるように過ごされているかを見ることだと思います。本日お話ししたポイントだけでなく、その人にあったチェックポイントを見つけてほしいと思います。