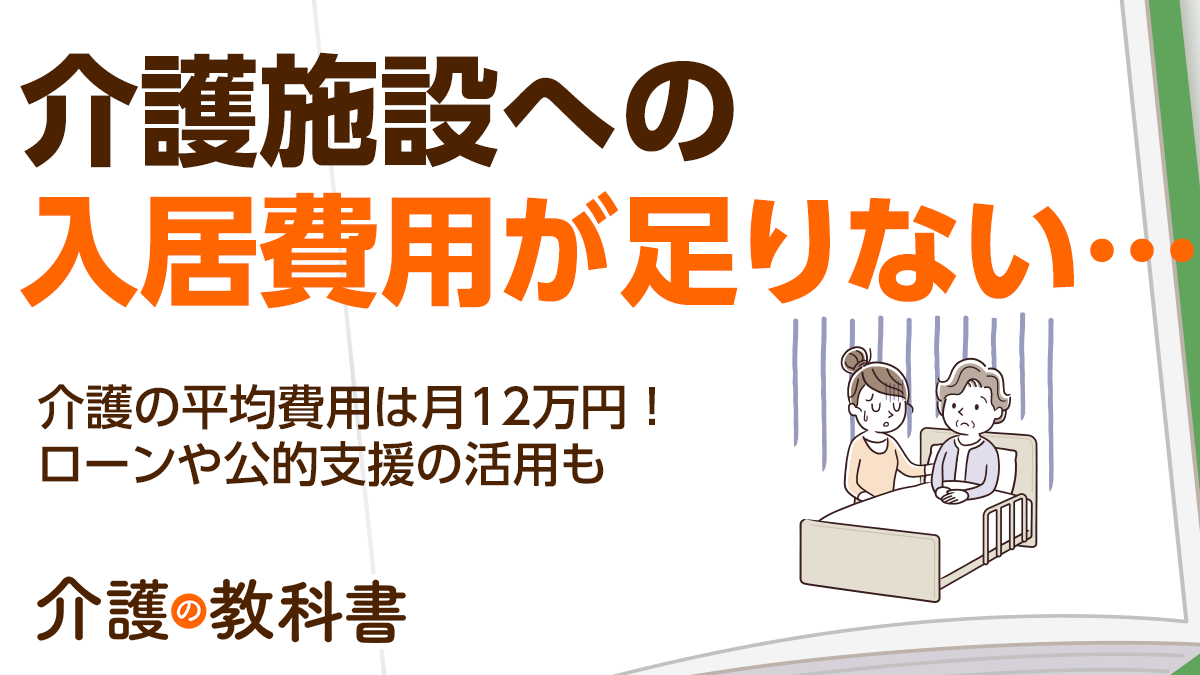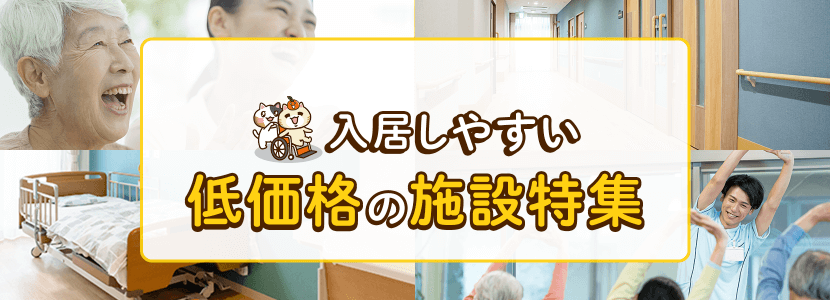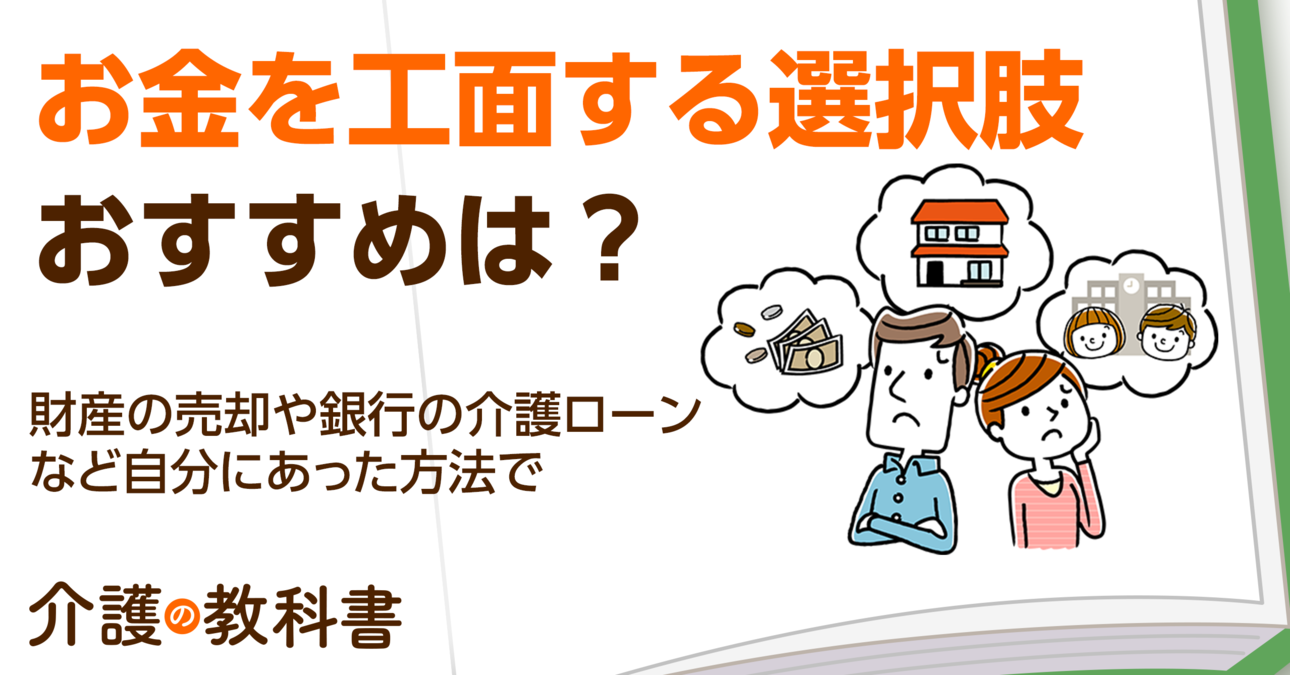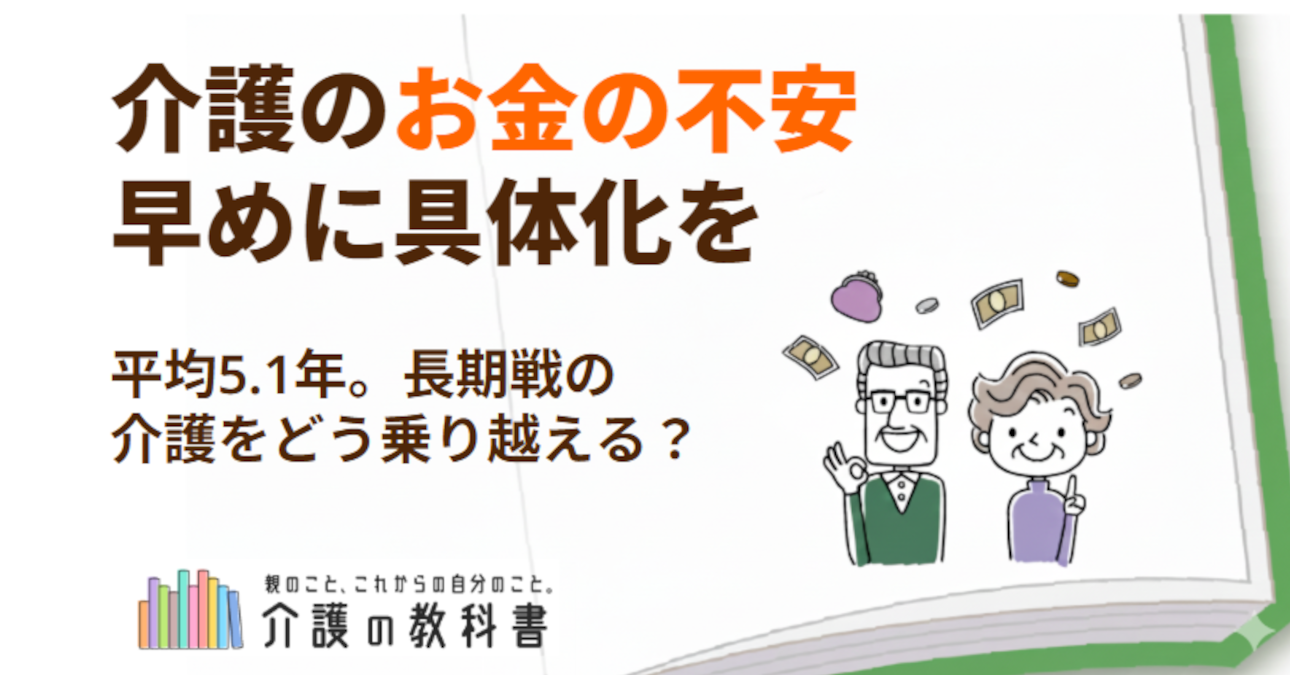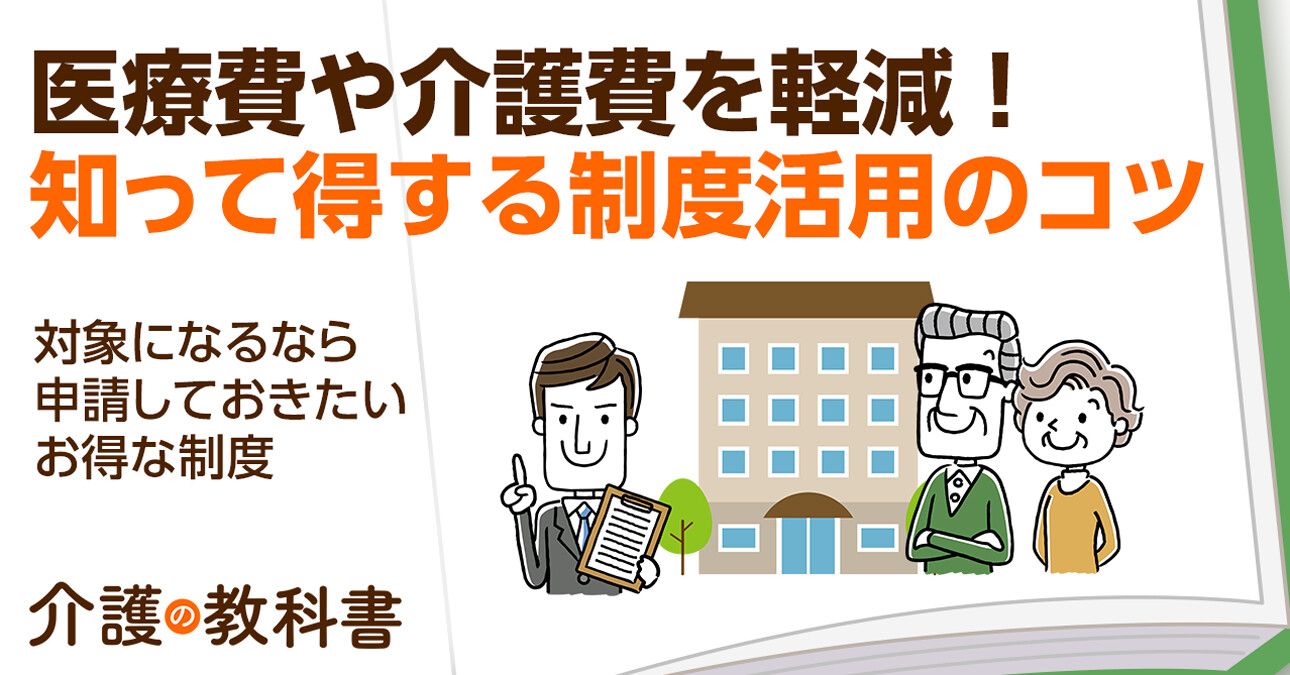要介護者が介護施設へ入居する場合には、契約時に「初期費用」を支払った上で毎月「月額費用」を支払うことがほとんど。
特別養護老人ホームや介護老人保険施設などの公的施設であれば、初期費用がかからなかったり費用が安かったりする傾向にありますが、入居希望者も多いため、なかなか入居することができません。いくら介護保険で費用負担を軽減できるとはいえ、施設入居のためのお金が不足することも考えられます。
そのような場合、介護ローンを利用して資金を調達するか、在宅介護で費用を抑えるか迷うところです。
今回は、一般的に介護費用がどのくらいかかるのかや、費用が不足した場合の介護ローンや公的制度、その他の方法などについて見ていきます。
介護にかかる平均費用は?
介護に関する年数や費用については、人それぞれ異なります。
ただし、一つ確実なのは、介護には「それなりにお金がかかる」という点です。
介護保険による介護サービスを利用したとしても1~3割の自己負担費用がかかりますし、支給される給付額には限度額もあります。
公益財団法人生命保険文化センターの「2021(令和3)年度生命保険に関する全国実態調査」では、次のような調査結果が報告されています。
①過去3年間の介護に要した費用の平均(公的介護保険サービスの自己負担費用を含む)
- 住宅改造や介護用ベッドの購入費などの一時的な費用の合計は、平均74万円
- 月々の費用は、平均8.3万円(在宅では平均4.8 万円、施設では平均12.2万円)
②介護を行った期間(現在介護を行っている人は、介護を始めてからの経過期間)の平均
- 平均61.1ヵ月(5年1ヵ月)、そのうち4年を超えて介護した人が約5割
このように、介護は、平均で5年以上もの間、介護保険を利用しても月額8.3万円もの費用がかかることがわかります。
介護保険の仕組み
介護保険とは、要介護状態や要支援状態になった方に対して給付を行う公的な社会保険の一つです。
介護保険による介護サービスを受けられる介護保険の被保険者は、原則として65歳以上の第1号被保険者だけです。
なお、40歳から64歳までの医療保険の加入者である第2号被保険者は、特定の16疾病により介護認定を受けた場合に限って、サービスが受けられます。
介護保険で受けられるサービスは、以下になります。
- 居宅介護支援
- ケアプランの作成や、介護をする家族の相談対応など
- 居宅サービス
- 訪問介護などの訪問型サービスや、デイサービスなどの通所型サービスや、ショートステイなどの短期滞在型サービスなど
- 施設サービス
- 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設などの入居費用の助成など
- 福祉用具に関するサービス
- 介護ベッドなどのレンタルや、福祉用具の購入費の助成など
- 住宅改修
- 手すり、バリアフリーなどの工事費用の補助金など
介護保険の介護度における支給限度額
介護保険からの介護サービスの給付ですが、全額支給ではありません。介護保険は、被保険者の所得に応じて1~3割の自己負担があります。
また、介護保険は要介護度ごとに支給限度額が決まっています。
支給限度額を越える介護サービスにかかる費用は、全額自己で負担しなければなりません。
介護度における支給限度額は、以下になります。
| 介護度 | 給付限度額 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
介護ローンとは?
このように、介護費用には、多くの費用がかかります。
特に、介護施設へ入居していたり入居しようと考えている場合には、在宅介護よりも費用がかかります。
そのため、介護費用が不足している場合には、介護ローンを借りるという方法もあります。
介護ローンとは、目的ローンの一つであり、資金使途は基本的に介護にしか使えません。
介護ローンを取り扱っている金融機関は少なく、代表的な金融機関は、以下になります。
- 千葉銀行の介護ローン
- ろうきんの福祉ローン
- 山梨中央銀行の介護ローン
- 大垣共立銀行のライフプラン介護ローン
- 常陽銀行の医療介護ローン
介護ローンを取り扱っていない金融機関の場合は、資金使途が自由なフリーローンを利用するという手もあります。
ただし、フリーローンは資金使途が自由ということもあり、資金使途が決まっている介護ローンよりも一般的には金利が高くなります。
生活福祉資金貸付制度の活用も視野に
介護費用が不足した場合に、公的制度を利用するという方法もあります。
都道府県社会福祉協議会が実施主体の貸付制度として、生活福祉資金貸付制度があります。
生活福祉資金貸付制度の対象や種類は以下のようになっています。
①貸付対象
- 市町村民税非課税程度の低所得者世帯
- 身体障害者手帳などの交付を受けた者の属する障害者世帯
- 65歳以上の高齢者の属する高齢者世帯
②貸付資金の種類
- 総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)
- 福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
- 教育支援資金(教育支援費、就学支度費)
- 不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金)
この中で、介護費用として借り入れできるのは、福祉資金の福祉費です。
福祉資金の福祉費の資金使途の一つに、介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費とあります。
③貸付限度額
福祉資金の福祉費の貸付限度額は580万円以内、最長償還期限は据置期間経過後20年以内ですが、資金の用途に応じて上限目安額と償還期間が設定されています。
介護サービス、障害者サービスなどを受けるのに必要な経費や期間中の生計を維持するために必要な経費の上限目安額と償還期間は、以下になります。
- 療養期間が1年を超えないときの上限目安額は170万円
- 療養期間が1年を超え1年6ヵ月以内であって、世帯の自立に必要なときの上限目安額は230万円
なお、据置期間は6ヵ月で、償還期間は5年になっています。
④貸付金利子
- 連帯保証人を立てる場合は無利子
- 連帯保証人を立てない場合は年1.5%
⑤連帯保証人
原則必要ですが、保証人なしでも貸付は可能です。
まとめ
このように、介護にかかる費用は、介護施設へ入居している場合は平均月約12万円、介護期間は平均約5年です。月12万円を5年間の場合、単純計算で720万円もの費用がかかることになります。
介護ローンや公的制度の利用をする方法もありますが、在宅介護に切り替えるという方法もあります。
在宅介護の場合、居住費がかからないため介護費用を抑えることができるものの、介護は肉体的にも身体的にも負担が大きいため、本当に可能かをよく考える必要があります。
家族で協力できるかをよく検討してみて、家族全員が納得できる介護方法を選択するようにしましょう。