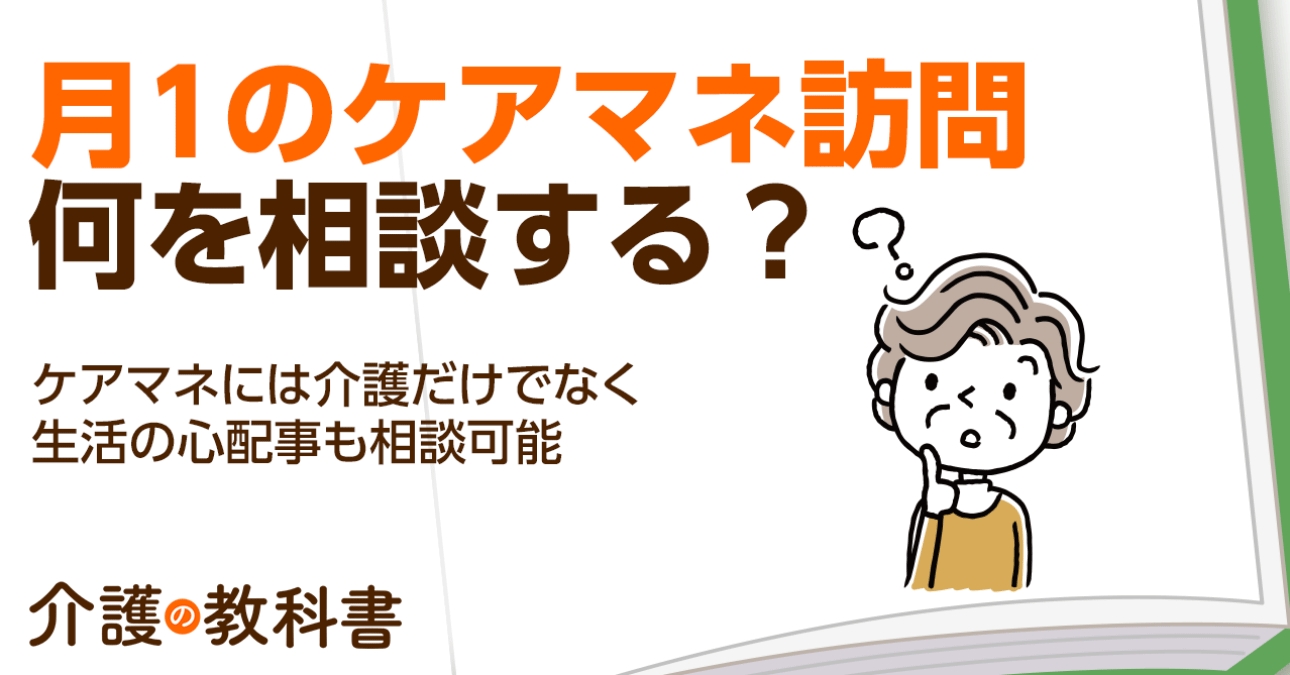みなさん、こんにちは。終活ジャーナリストの小川朗です。
「今の介護保険法は介護される側のための法律であって、介護する人のためには作られていません」
昨年、30代の半ばから始まった19年間に及ぶ介護生活が終わったAさんの言葉です。
Aさんは実母が認知症と診断され、1999年に介護離職。その翌年に始まったのが介護保険法でした。
介護を受ける方の支援は充実してきましたが、介護者のための支援はまだまだ不足しています。
今回は介護うつになったAさんの事例を用いて、介護者のための支援を充実させていく必要性についてお話ししていきます。
介護保険法の目的は“介護を受ける人の支援”
私は終活カウンセラーとして講師をしているのですが、終活カウンセラーの初級検定で最初に学ぶのは、この介護保険法の基本的な考えです。
介護保険法の第一条には、介護保険法の目的が示されています。
条文ならではの硬い文章ですが、あえてここでご紹介しますね。
介護保険法第一条
この法律は(中略)要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について(中略)自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保険医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため(中略)介護保険制度を設け、(中略)国民の保険医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする
内容を噛み砕いて説明すると、年を取ってお風呂やトイレ、食事などの介護が必要になった方々が、自立した日常生活に戻ることができるようにサポートするための制度を設け、保険医療と福祉を向上させることが介護保険法の目的だということです。
介護保険法の目的は、条文からもわかる通り“介護を受ける方の支援”です。
要介護状態になった方のための制度は、この法律の施行を受けて随分と充実してきたと思います。
システムが整備され、ケアマネージャーやケアワーカー、ホームヘルパーという耳慣れない職業が、新世紀とともに誕生します。
しかし、在宅介護をする家族のための支援は、今よりもっと充実させていく必要があるでしょう。
それでは具体的に、家族にどのような支援が必要なのかについて考えていきますね。
介護うつになったAさんのケース
第91回と同様に、Aさん(30代男性)の事例を用いてお話しします。
前回のおさらい
Aさんは30代のときに母親が倒れ、介護をすることになりました。
時間や経済面の負担に追われながらも、母親の在宅介護を続けていたAさんですが、時代は介護保険法の成立当初。
専門職も戸惑いのなかにあり、Aさんは充実したサポートを受けられず孤独に陥っていきました。
このAさんのお話には、続きがあります。
Aさんの実母は認知症だと診断され、その翌年、今度は奥さんの実母が足を骨折して歩けなくなりました。
この出来事により、Aさんと奥さんはそれぞれの実家で介護に専念することを余儀なくされました。
夫婦で別居を始めたAさん。その頃から母親に、認知症の問題行動が頻発するようになりました。
心中を考えるほど追い詰められたAさん
いきなり暴れるなどの問題行動を繰り返す母親に、Aさんは疲弊していきます。
「24時間、気の抜けない状態が続きました。睡眠も十分にとれなくなり、今度は自分が体調を崩してしまいました」。

医師からは、「このまま行くと、あなたが死ぬよ」とまで言われ、Aさんはついに母親との心中を考えるまでに追い詰められます。
何がAさんを、そこまで追い詰めたのでしょうか。
「話を聞いてもらえる人がいなかったことだと思います。当初、母を精神科に連れて行っても、薬は出してもらえてもこちらの状況が理解してもらえず、対応がグダグダ。さらに介護保険の施行当初は、介護に携わる人たちも手探り状態。誰も頼りにならない、と孤立感ばかりが深まりました」
この後、母親の病気は認知症ではなく、肝性脳症だったことが判明。
肝機能が低下すると血中アンモニア濃度が上昇し、それが脳に達して脳症を発症する病気です。
認知症は判断が難しいとはいえ、完全な誤診でした。
原因の判明により、Aさんの母親は症状が改善しましたが、入院生活は続きました。
介護うつから立ち直ったのは理解者の存在が大きかった
心中まで考えた状況から、Aさんはどうやって脱出したのでしょうか。
きっかけは、母親が入院することになり、完全看護(病院がすべての看護をする状態のこと)になったことです。
Aさんは奥さまと再び同居できるようになり、実母が入院している病院にも通いながら、奥さまの実家で義母の介護を分担するようになりました。
夕方になると精神的に安定しない母親のために付き添って夕食をとり、付き添いから家に帰ると、今度は奥さんと交代して義母を介護。
いつも朝方6時ごろ就寝する生活でしたが、それでも7時間程度の睡眠時間をとることができるようになりました。
ひとりで実母の介護していたAさんにとって、状況を理解してくれている奥さまと再び暮らし、互いを労わりながら義母の介護を分担できたことは大きな変化でした。

病院では同じような境遇の方と仲良くなり、家から作ってきたおかずを交換することも。
同じ境遇であるからこそ、わかりあえることが多く、癒しにもなったと言います。
同じ状況を分かち合える理解者ができたことが、Aさんが危機的状況から脱出するきっかけのひとつと言えます。
介護者のための制度を充実させる必要がある
Aさんは実母で8年、義母の介護を奥さんと分担しトータル19年間、介護に勤めました。その介護生活も、2018年に義母が亡くなったことで終わりました。
3年間かけて資格も取り、ようやく社会復帰となったAさんは、今何が必要なのかという問いに、こう答えてくれました。
「介護なんかで辞めやがって、という風潮はまだあります。介護している人を物心両面から支える制度と、介護離職から復職できる環境整備が必要です」
心中を考えるまでに追い詰められたAさんは、精神的なサポートと、身体的な介護負担を軽減するようなサポートの両方が必要だったと思います。
デイサービスなどの利用により、介護者が一時的に介護から解放される瞬間は確かにありますが、仕事と両立していくためにはまだ十分とは言えないことが、離職者の数からもうかがえます。
介護保険法は介護される側の人の自立支援をサポートする法律ですから、介護をしている人の問題に対応できない部分もまだまだあります。
要介護者のために充実させてきた介護制度の整備を、これからは介護者のために並行して行っていくことが必要です。