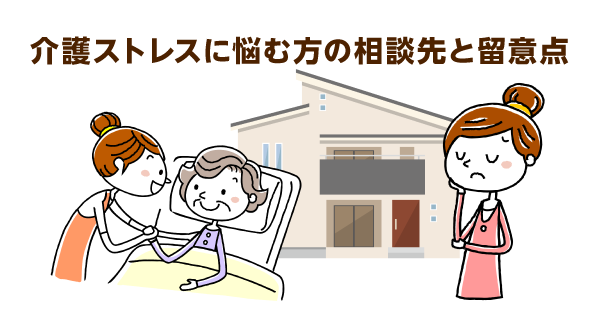こんにちは。「認知症介護よりそいケアアドバイザー」の石川深雪です。
みなさんは「ダブルケア」という言葉を耳にされたことはありますか?「ダブルケア」とは、介護と子育てを同時に担うことです。
2016年の内閣府の調査によれば、ダブルケアをする人が全国で少なくとも25万3,000人にのぼるということがわかっています。
この調査における「育児の対象」は未就学児のため、小学生まで含めればさらに人数が増えるのです。
私自身の経験や、身近な人の体験談などをもとに、ダブルケアの負担を少しでも軽くする方法について考えてみたいと思います。

ダブルケアの実態
先ほどご紹介した2016年の調査結果をもう少し詳しく見てみましょう。
ダブルケアを行う約25万人のうち、女性が約17万人、男性が約8万人と、女性が男性の約2倍となっています。
その年齢は男女ともに30~40歳代が8割を占めているのです。
つまり、働き盛りの人が直面している問題と言って良いでしょう。
特に、「介護と育児と仕事」の3つを抱えている人のなかには、仕事を続けられずに休職したり退職したりする人も多くいます。
しかしながら、ダブルケアを行う人には金銭面の負担も大きく、介護度にもよりますが、育児費用と介護費用にかかるお金は月8万円以上とも言われているのです。
次からは、実際にダブルケアを行う人の事例をご紹介しましょう。
介護、育児、仕事をこなすSさんの事例
Sさん(36歳)は、現在90歳の義理のお父様(認知症・要介護2)と同居中です。
お子さんは小学2年生。
Sさんは、私と会うたびに「眠たい~」と言っています。
「お父さんが夜中に何回もトイレに行くの。付き添わないと転んだら大変だし…」「今日は一人で外に出ていこうとしていたのでびっくりした」「子どもを連れて実家に帰りたいけど、長期間家を空けられない」と毎日話しているのです。
ご主人は休日に子どもの相手はしてくれるようですが、普段の育児、家事や父の介護は彼女の負担が大きいとのことでした。
ショートステイサービスを使いたくても、ほぼ毎日デイサービスを利用するため介護保険サービスの利用限度額いっぱいになってしまっているそうです。
一人で抱え込んでしまった私の事例
続いて、私自身の話をしましょう。
私は長男が生後7ヵ月の頃に義理の父と同居を始めました。
義父は脳梗塞の後遺症で左片麻痺があります。
私の義父は、身の周りのことはできますが、自分で重いものを持つことや長時間歩行は難しい状態でした。
そのため、私は小さい子を抱えながら自分の休日に義父の買いものの付き添いや通院の送迎をしていたのです。

その頃私の主人は仕事が忙しく、休日もほとんど家にいない状態でした。
義父はプライドが高く、気難しい人です。
精神的にもかなりの波があるため、毎日私は顔色をうかがって自由に外出できない日々が続いていました。
毎日とても苦しく、そのストレスを子どもにぶつけてしまうことも多々ありましたし、私自身も心のバランスが崩れていくのを感じていました。
それでも、私は3年以上の間、その悩みを誰にも話せませんでした。
その理由は「良い妻」「良い嫁」「良い娘」でありたかったから。
私自身のその考え方がさらに自分を追い詰め、その結果、限界を感じた私は子どもを連れて夜逃げ同然で家を出ました。
当時長男は4歳、次男は生後3ヵ月でした。
どこに相談したら良い?
ダブルケアは「子ども」「介護」どちらにもかかわってきます。
「子ども」と「介護」の各分野についての相談窓口や、ダブルケア専門の相談窓口についての情報を集めましょう。
ダブルケアについて集めるべき情報
- 国やお住いの自治体でどんな支援活動が行われているか
- 仕事をしているなら、職場でのダブルケア支援制度があるか
- 近くに当事者の集まり、ネットワークはあるか
具体的には、すでに介護保険のサービスを使われている方であれば担当のケアマネージャーさん、お子様が保育園に通っているのであれば保育士さんなど、あなたが相談しやすい人に相談してみてください。
まだ介護認定を受けていなかったり、身近な人だと話しにくいのであれば、地域包括支援センターや、市町村の子育て支援課などの相談窓口があります。
ここまでダブルケアの相談窓口を紹介してきましたが、一番大切なのは家族間で話をすることです。
(私はここをまったくしてこなかったために、大変な思いをすることになってしまいました)
私は家を出たあとに主人や実の親に話をして、ときには愚痴を聞いてもらうことやいろいろな面でサポートしてもらうことができ、今では義父とも良い関係を築いています。

大切なのは「一人で頑張らないこと」
現段階では、「ダブルケア」という言葉自体がそれほど社会で認知されておらず、ダブルケアを支える制度もありません。
私自身も、家を飛び出したあとで育児と義理の母親の介護に悩む友人と話しているときに、「もしかして自分もそうなのかも?」と気づいたほどです。
しかし、確実にダブルケアにかかわる人は増えており、独自にダブルケアのサポート体制を整えていっている自治体もあります。
まずは当事者が声をあげていくことで、「ダブルケア」の大変さを伝え、そのサポートの必要性を周囲の人をはじめ公的機関にも認知してもらうことも重要です。
「育児」と「介護」、どちらか1つをとっても制度やその負担が社会問題になっています。
その2つが重なったら、さらに大変になるのは誰が考えてもわかることです。
自分一人や家庭内だけでなんとかしようとせずに、早めに相談をしてくださいね。