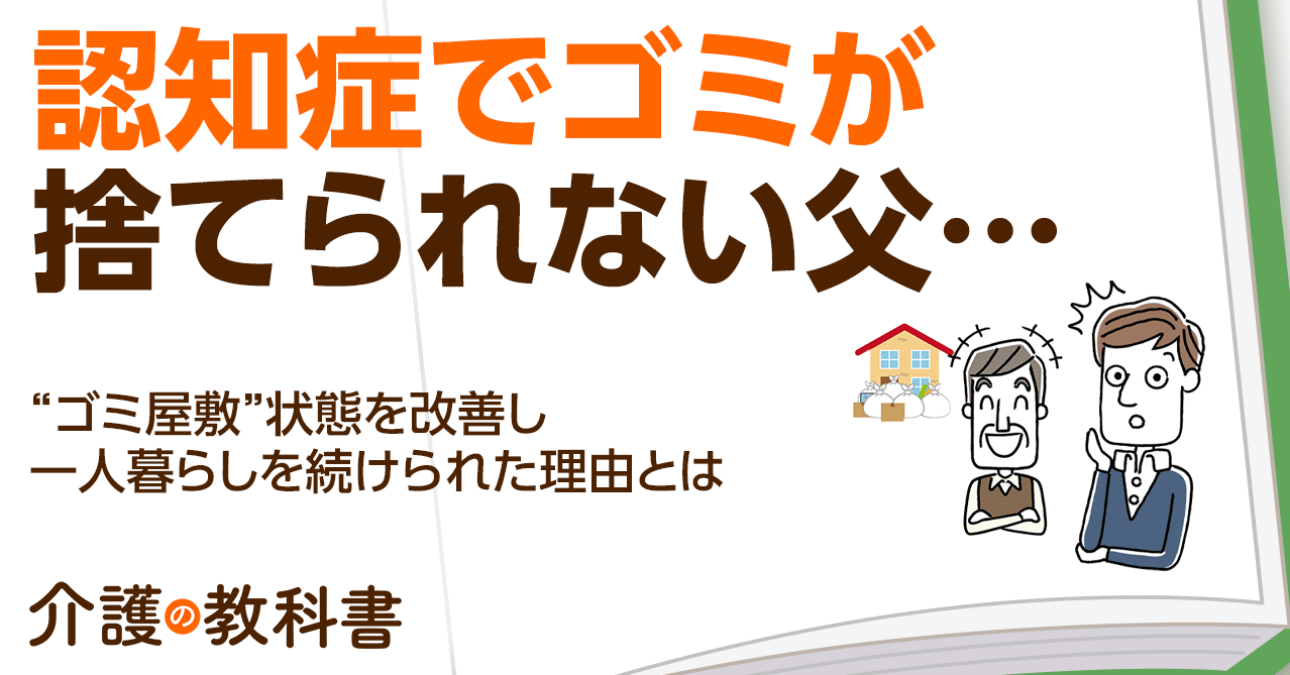みなさん、こんにちは。高木亨です。
「自立支援」や「(要介護状態の)重度化防止」という言葉が介護業界で一般的になり、支援者も当事者も、これら2つの支援に取り組むようになりました。
しかし、自立支援や重度化防止の定義はまだ漠然としており、今より議論をされる必要があると思います。
「老」はほとんどの人に生じますし、「死」は平等にどんなに人にも起こります。
自立支援と重度化防止の定義やゴールが見えていないと、介護状態になってはいけない、重度化したらおしまいだ、ということになりかねません。
今回は、自立支援と重度化防止についてお話ししていきますね。
自立支援の内容は専門職の倫理観に委ねられている
まず、現在の自立支援の在り方についてお話しします。
介護福祉士の倫理綱領には、自立支援について以下のようにあります。
利用者本位、自立支援
介護福祉士はすべての人々の基本的人権を擁護し、一人ひとりの住民が心豊かな暮らしと老後が送れるよう利用者本位の立場から自己決定を最大限尊重し、自立に向けた介護福祉サービスを提供していきます。
この内容から考えると、自立は“基本的人権”の考え方に根差しているようですね。
しかし、介護における基本的人権を「具体的にどこまで擁護するのか」、自立を「どのような状況と定義するのか」ということまで深く議論されることは、まだまだ少ないのです。
そのため、基本的人権の擁護についての範囲も、自立支援の範囲も、サービスを提供する専門職の“倫理観”に委ねられているのが現状だと考えられます。
本人の意志によってジレンマが発生する
それでは、どうして自立支援や重度化防止について、定義やゴールを決める必要があるのでしょうか。
それは自立支援や重度化防止が、基本的人権と対立することがあるからです。
介護現場では、本人の意思を尊重することで、自立支援と重度化防止に歯止めがかかることがあります。
例えば、要介護状態のAさんが「自宅に戻りたい」と言っているとき、自宅に戻ることで要介護度が悪化することが客観的に見て明白だったとします。
そのような場合に、自立支援や重度化防止のために本人を無視することは、基本的人権を無視し、介護福祉士として倫理に反することになってしまいます。
当然ながら「自立支援や重度化防止のためであれば本人意思を無下にしてよい」と記載しているものはどこにもありません。
このように、自立支援と重度化防止について「どこまで行うのか」を定義していなければ、本人の意志と介護福祉士としての在り方にジレンマが生じてしまうのです。

介護現場では日常的に、このようなジレンマが起こっているため、「本人の意志」を尊重しながら「自立」策を調整しているのです。
また、認知症の場合はもっと難しくなります。
「どこまでが本人意思か」「いつの本人意思か」を慎重に汲み取るところから「(介護状態の)重度化防止」に取り組む必要性があるからです。
例えばBさんが認知症により、本来の性格からは考えられないような意志を示した場合、今の意志を取るべきか、かつてのBさんの意志を取るべきかで現場では常に葛藤に苛まれています。
もちろん、こうした矛盾を解消する方法のひとつとして「成年後見制度」があります。
しかし、制度の利用や理解はまだ進んでおらず、後見人がいる場合であっても、医療行為への同意権が付与されていなかったり、居所指定権(本人の住む場所を決める権利)などは本人の意思に委ねることとされているため、やはりジレンマが解消できない場合があるのです。
「老い」を受け入れられる社会にする必要がある
自立支援と重度化防止は確かに重要で、その観点は大切だと考えています。
しかし、自立支援と重度化防止に強くこだわりすぎると、「老い」を受け入れられない状態になりかねません。
例をひとつ挙げてみましょう。
認知症になったらおしまいだと思っているCさんの事例
Cさんは地域の「認知症予防」のため、公民館や公会堂等でせっせと「予防体操」や「手指運動」を指導していました。
そして現在は、その習慣だけが強く残ったまま、重度の認知症症状に陥っています。
本人はそれを自覚することができず、認知症になってたまるかと、今でも数十秒前に行った「予防体操」や「手指運動」を周囲に押しつけます。
休むことなく延々と。
Cさんは「認知症になるくらいなら死んだほうがマシだ」「認知症になったらおしまいだ」という意思を示し続けています。
Cさんは、介護予防や重度化防止に捉われるあまり、認知症という「老い」を受け入れられない状態のまま、認知症になってしまったのだと思います。
「老い」、そしてその先にある「死」を受け入れるためには、それらをいつまで行うのかを決めることが大切です。
80代で重度化防止ができたら、次は90代、次は100歳になっても…と、高齢福祉の現場では、目指すべき期間が延々と伸びています。
このまま議論が進まず、「自立支援」「重度化防止」の掛け声だけが大きくなると、ただ高齢者の方に「老いるな」と言うような状態になるかもしれません。
「老い」を受け入れられない社会になると、100歳を越えて要介護状態になった方に「それはお前の努力が足らないからだ」という考え方になる可能性もあります。
当たり前ですが、「生涯現役」を強要することは福祉と言えないのです。

私たちは、「自立支援」とはどこまで行われるべきで、「重度化防止」はいつまで実施されるべきかを、振り返って考えてみる必要があるのではないでしょうか。