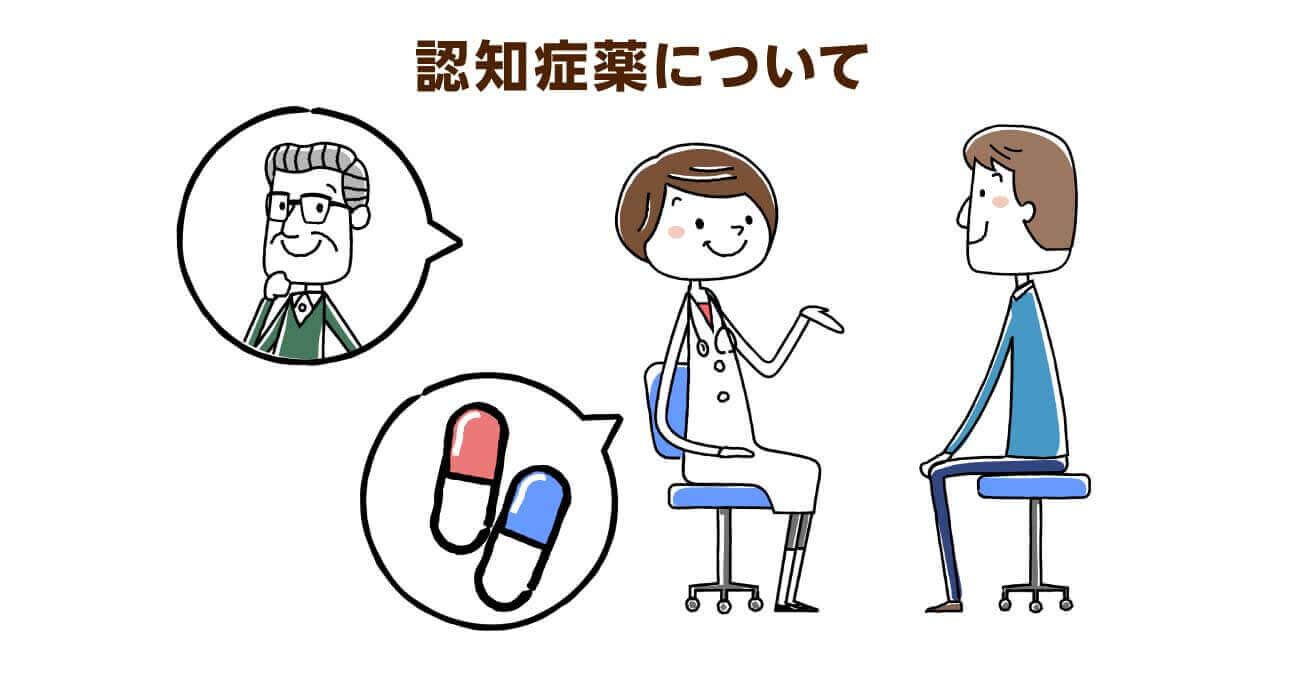こんにちは。大阪在住のフリーライターで、要介護4の祖母の在宅介護6年目の奥村シンゴです。
今回は、「高齢者虐待」をテーマに書いていきます。
「平成28年度高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果が公表されました。
養護者(老人ホームや介護老人福祉施設などの養介護施設の業務に従事する者、在宅で高齢者を養護、介護する家族、親族、同居人を指す)による高齢者虐待が1万6,000件以上にのぼっています。
高齢者虐待にはいくつか種類があるのをご存知でしょうか?
暴力などの身体的虐待、無視したり叱りつける心理的虐待、年金などを勝手に使う経済的虐待、劣悪な環境で放置する介護・世話の放棄・放任といった虐待があります。
しかし、これらすべてが虐待に含められてしまうと、介護者としては「自分も虐待をしているのではないか」と不安を抱く方もたくさんいるのではないでしょうか。
私は、被介護者に対する愛が深ければ深いほど責任を感じ、精神的に追い詰められて虐待してしまうことがあると考えています。
私の経験も踏まえて、高齢者を虐待してしまう介護者の実情についてお話していきますね。
虐待をしてしまった経験について
私は心理的虐待、経済的虐待、介護・世話の放棄・放任に該当する虐待をした経験があります。
1.心理的虐待
祖母が十分な食事を済ませた後で、夜中や早朝に「あんた、お腹空いたの。なんか甘い食べ物ちょうだい」とおねだりをしてくるときがあります。
祖母はここ2年程で体重が10kg以上増え足腰に負担が大きくなったり、動脈硬化予防の薬を服用しているので、食事の量を控えなければなりません。
もちろん「ばあちゃん朝ご飯あるから我慢しよ」と説得していますが、納得してくれなかったり、忘れてすぐに同じ事を繰り返して言ってきたりするので、無視をする以外にどうしようもないのです。
2.経済的虐待

認知症の方の年金を勝手に使うことが虐待に含まれることを、私はおかしいと感じています。
例えば、私の祖母は元々お金遣いが荒く、すぐに1着数十万もする洋服を購入してしまうことが多々ありました。
私や母は「こんな高い服を買って着る機会あるの?着ないなら返品してこよう、ばあちゃんの生活費はそんなにたくさんあらへんで」と説得します。
しかし祖母は、「私のお金なのになんで指図されないといけないの?ほっといてちょうだい」と聞いてくれません。
祖母には貯金がほとんどなく、食費・光熱費・家賃などの生活費はもちろん、介護サービス費用も月々かかっています。
そのうえ高額な買い物をされてしまうと、足りなかった分のお金は私たちが肩代わりすることになるのです。
このようなケースに、年金を使わずしてどう対応しろと言うのでしょうか。
また、「認知症になると通帳やカードを隠すようになるから、どこにあるかわからなくて困るの」と在宅介護をしている人たちからよく聞きますが、私の祖母も同様でした。
タンスの引き出しやカバン、ポケットの中、さらには知人に預けていたりと、私や母親は通帳やカードを探し出すだけで半日近く費やしたこともあります。
これらのことが3年近く積み重なると、祖母自身も自分で管理できないことを自覚し始めたのか、「絶対他の誰にも渡しちゃだめだよ」と言いつつも、ようやく私が管理することに同意してくれました。
こうした経緯から、認知症の方の年金を勝手に使ったり、管理したりすることが経済的虐待と言われてしまうと、介護が成立しないと私は考えています。
3.介護・世話の放棄・放任
介護・世話の放棄・放任については多くの介護者が陥りやすく、私も放棄・放任したことがないかといえば嘘になります。
ある日、突然祖母が倒れたときのことです。
慌てて救急車を呼んで病院へ行きました。診察結果は「尿路感染で2週間の入院が必要」というもの。
尿路感染とは、おしっこの通り道(尿路)から、膀胱内に細菌が進入して感染してしまう病気です。
医者は「この時期ね、どうしても水分が不足しがちでね。ときおりお年寄りが尿路感染で運ばれてきますよ。排泄機能が鈍くなってきているので、本人が申告するよりコップ一杯多めの水分を摂取させてあげると感染予防になりますよ」と水分補給の重要性を指摘されました。
そのうえで「1日1~2回で良いから股間を綺麗に拭いてあげるとさらに良い予防対策になります」とアドバイスを受けました。
そのとき私は「しまった、油断してた。自分では十分な介護をしてると思っていた」と、自分の至らなさを痛感しました。
それ以来、オムツを替えるときはなるべく股やお尻を拭いたり、特に夏場は水分を多めに摂取させたりするようになりました。
この経験から私は、一生懸命に介護しているつもりでも、介護・世話の放棄・放任をしてしまうことがあり、それは誰にでも起こり得ることだと思うのです。
身体的虐待が一番多い
厚生労働省が発表した「平成28年度老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業報告書」によると、身体的虐待が66.6%と最も多く、次いで心理的虐待が41.1%、介護・世話の放棄・放任が20.8%、経済的虐待が20.0%となっています。
この報告書によると、虐待の件数としては一番多いものの、私の経験として身体的虐待は一度もありません。
まるで就職活動の面接で「嘘をついたことがありません」と外面よく答えているようですが、本当に思い当たりません。
ただそれは、私が環境に恵まれているということだと思います。
近所でこういう出来事がありました。
近所に住んでいた、40代男性のお話です。
彼の父親は認知症と脳出血による下半身麻痺、母親は認知症でした。
そのお宅からは、頻繁に物が飛んでガラスが割れる音、壁をドンドンする音、「お前こら、何回失敗しとんじゃ、ちゃんとそこでせえ言うとるやろうが」という息子の怒鳴り声、「キャーキャー、もうこれ以上やめて」という悲鳴が聞こえてきていました。
朝から晩まで、多いときでは一日5~6回もそんな一騒動が起こっていたためか、あるときついに警察が来ました。
隣人に通報されたようで、息子は手錠をかけられ連行されていきました。
周囲からは「あの人は両親を一人で介護してるんだって。施設に入れればいいのに迷惑だわ」「あそこまでして家でみるなんてよくわからない人やね」といった冷ややかな声。
彼の両親は状況を理解することができなかったようで、ただただ息子の名前を呼びながら泣いていました。
この騒動のあと息子は自宅に戻り、それからしばらく騒音は聞こえなくなりました。
おそらく両親を施設に入所させたのだろうと思います。
ところが、一ヵ月くらい経過したある日。
再び同じような音、大声、悲鳴が聞こえてきました。
息子は、警察や役所のすすめを断って在宅介護を再開したそうですが、なんとまた警察に逮捕されました。
その後は両親を施設入所させ、在宅介護を終わらせたそうです。
息子は介護サービスを一切利用せず、一日中両親の面倒をみていたのだと聞きました。

このケースから、介護はすればするほど、被介護者を愛すれば愛するほど、責任を感じて自分を追い詰めてしまうことが伺えますね。
虐待を防ぐためにできること
介護サービスはなるべく活用した方が良い
私の場合、祖母のケアマネージャーが着任した当初から「なるべく介護サービスは利用する方が本人と介護者のお互いが楽になると思います。ずっと一緒ではしんどいですから」とアドバイスを受けていました。
私は介護サービスを目いっぱい利用しています。
私の祖母は要介護4で、利用しているのはお泊りデイサービスやショートステイ、週2回のデイサービス、週1回1時間の訪問看護など。
費用は毎月15万円ほどかかりますが、仕方がないものだと考えています。
6年間で介護施設に行かざるを得なかったののは数えるほどで、介護職員、ケアマネージャー、訪問看護の方々に日々助けられていることに感謝感謝です。
ここまで周囲に恵まれていることは稀なのかもしれませんね。
介護から解放される時間をつくる

私の休日のストレス解消法は、介護や祖母のことは極力忘れて、好きなことができる時間を思いっきり楽しむことです。
家で午前中から夕方まで寝たり、友達と飲みに行ったり、一人で映画や買い物へ行ったり、恋人と2時間ぐらい電話したり。
そのように、被介護者から離れる時間をきちんとつくることで、一人で思い詰めるという精神的負担を減らすことができます。
ここまでのお話で、虐待をしてしまう介護者の現状を理解してもらえたでしょうか。
在宅介護をするにあたって、まったく虐待が起こらない方が不自然だと思います。
自分で一生懸命、介護をしている方ほど虐待をしてしまうのかもしれません。
もし「自分がしていることは虐待ではないか」と不安に思っている方は、ケアマネージャーなど専門家に相談してみましょう。
あなたは一人ぼっちではないのです。
今回のテーマまとめ
- 1人で介護しようと思わず、介護サービスを利用するようにしましょう
- 被介護者から離れてリフレッシュする時間をつくりましょう
- 悩んだ時は、ケアマネージャーや専門家などに相談しましょう