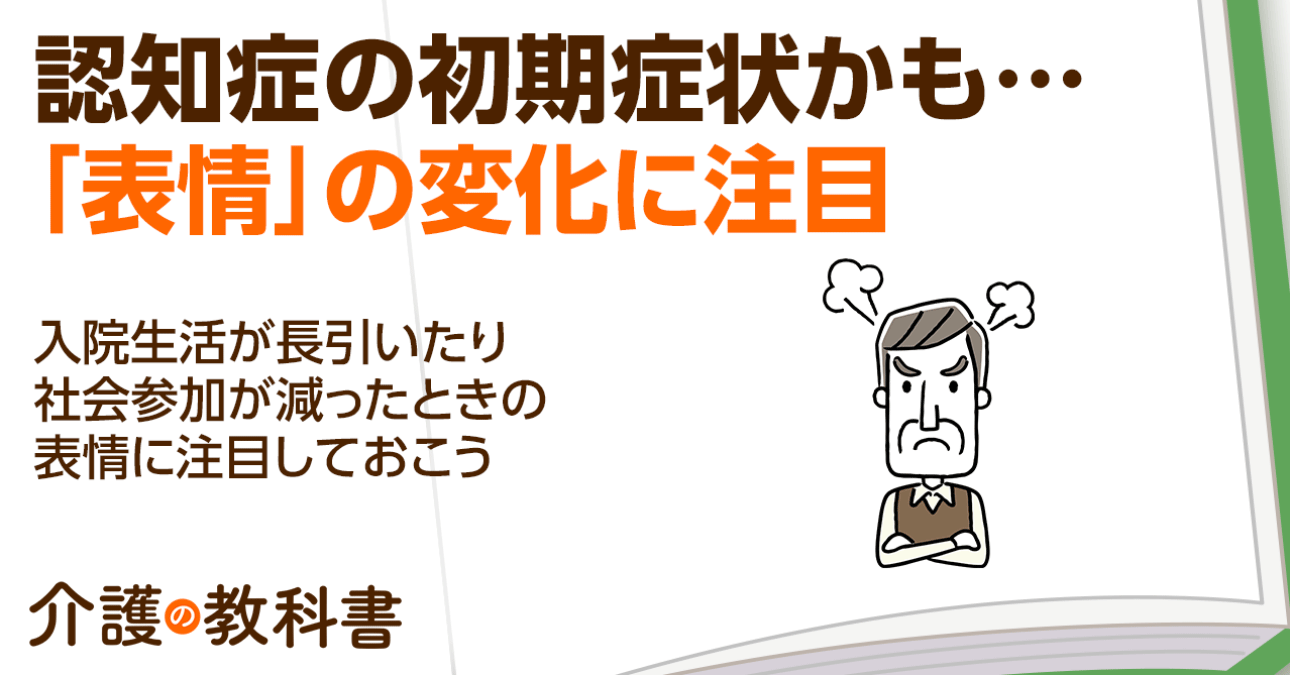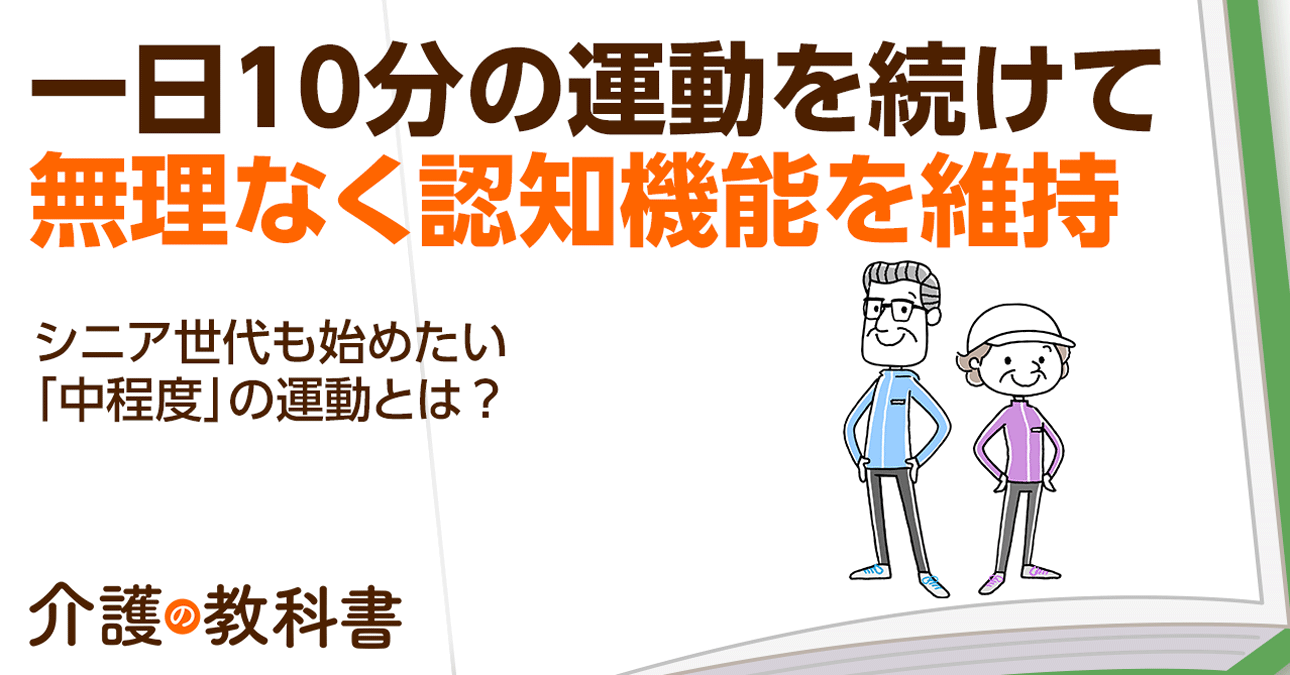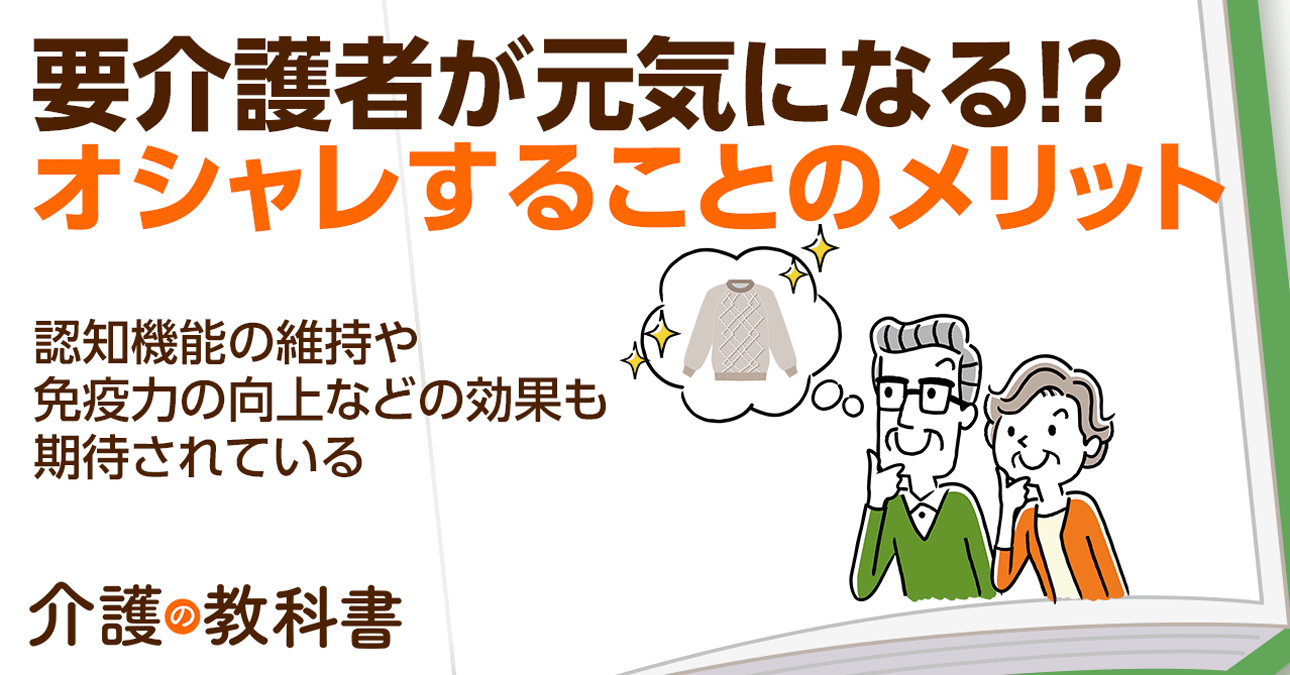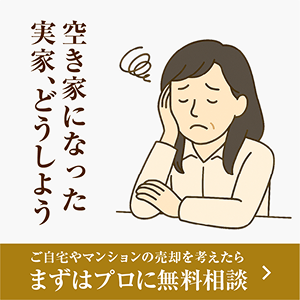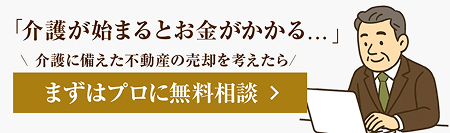人工知能(AI)やICT分野における技術革新は、介護の効率化や高齢者の健康維持・向上に役立つと言われています。
なかでも、家庭でも比較的活用しやすいのがコミュニケーションロボットです。人間の言葉や動作に応じて、会話やジェスチャーなどを返してくれるロボットで、コミュニケーションを円滑化する効果があると考えられています。
そこで今回は、国内ですでに流通している代表的なコミュニケーションロボットをご紹介いたします。
コミュニケーションロボットがもたらす効果の研究
世界中でコミュニケーションロボットの開発・研究がされています。
国内で有名なのが、神奈川県のさがみロボット産業特区です。ここでは、生活支援ロボット開発の一環として、介護に役立つコミュニケーションロボットを用いた実証実験などが行われています。
例えば2015年に首都大学東京が実施した、人型コミュニケーションロボットPALROを用いた実証実験では、認知症の方の認知機能改善などの効果が認められ、体操などのパートナーとして活用することで運動機能の向上などにも効果をもたらすことが明らかになりました。
今後増加すると見込まれている一人暮らし高齢者や介護施設における職員の負担軽減など、さまざまなシーンでの活用が望まれています。そんなコミュニケーションロボットについて、以下に紹介していきます。
人型コミュニケーションロボット
①PALRO

PALROは、会話とコミュニケーション力が特徴の二足歩行ロボットです。人を認識すると自分から「何とお呼びすればいいですか?」「僕と友達になってくれますか?」などと人懐っこく話しかけて関係性をつくっていきます。
高度な顔認識機能を備えており、100人以上の顔を覚えることができるほか、誰とどのような会話をしたのかも記憶して「〇〇さん、こんにちは!この前はしりとりをしましたね」「お久しぶりです」などと、その人に合ったトークをしてくれます。
また、童謡、歌謡曲、演歌、J-POPなどの歌を歌ったり、ダンスを踊ったりすることが得意で、人を楽しませることが大好きです。
【適合するケース】
歌やダンス、健康体操などが得意なため、介護施設のレクリエーションの時間などに活躍しています。また、専用アプリ「 PALRO つながリンク」を活用すればPALROと利用者の出来事が共有されるため、家族が高齢者の方をゆるく見守るのにも適しています。
【効果】
それまでの会話データやインターネット上のトピックスなどをもとに、その人にあった会話を提供し、身振り手振りなども交えつつテンポよく返事をするなど、人との快適なコミュニケーションが行えるように設計されています。その会話力により、高齢者のQOL向上や生活機能改善に効果が期待されています。
また、施設に導入する場合、レクリエーションや体操の時間をPALROが担当することによって介護職員の負担も軽減も狙えます。
②Sota

世界的に有名なロボットクリエイター・高橋智隆氏デザインによる親しみやすいキャラクターデザインで知られるロボットです。言葉や身振り・手振りを使った自然な対話を実現する卓上サイズのコミュニケーションロボットで、人型ではありますが、足の部分は台のようになっており、動き回ることはありません。。カメラやマイク、スピーカー、ネットワーク機能などを搭載し、IoTデバイスやクラウドAIなどと高度に連携することが可能です。
【効果】
ユーザー登録をすることで、家族の顔と名前を覚え、話し相手になることができます。コミュニケーションの機会を家族全員に提供します。また、Sotaは小さな子どもやペットの見守り機能も搭載されています。
【適合するケース】
オフィスや店舗、公共施設などで商品の案内やプレゼンテーションなどを人の代わりに行うことができます。
ビジネスシーンで活用されることが多いロボットですが、介護施設の見守りシステムの一部として活用されるケースもあります。例えば、NTTデータの「エルミーゴ」では、居室にSotaを配置して利用者の会話を喚起しているほか、スタッフがSotaを通じて遠隔で声かけをすることも可能です。
③ロボホン

ロボホンは、シャープが開発したモバイル型ロボットです。Sotaと同じく、ロボットクリエイターの高橋智隆氏がデザインを手がけています。話したり歩いたり踊ったりして、人間とコミュニケーションを取ることができます。
「ロボホン」の名の通り、電話通話ができるのが他のコミュニケーションロボットと大きく異なる点です。「電話をかけて」と話しかけ、かけたい番号を伝えることで発信することができます。Androidをベースに開発されており、背中のディスプレイからスマートフォンのように操作することも可能です。
【適合するケース】
一人暮らしの方や留守番をしているときなど、一人でも楽しく過ごせるような機能が搭載されています。また、「予定を覚えて」と呼びかけることで利用者のスケジュールを把握し、リマインドをしてくれる機能もあります。
そのため、通院や宅配便の受け取りなどの予定を忘れてしまいがちな一人暮らし高齢者の生活のサポートなどにも適していると考えられます。
動物型コミュニケーションロボット
④PARO

PAROは「人の心」をケアするアザラシ型ロボットとして開発されました。本物のタテゴトアザラシの赤ちゃんの鳴き声をたくさん使っているほか、瞬きをするなどの表情の変化や動作のリアルさが特長です。
驚いたり、喜んだり、あたかも心や感情があるかのように振舞う自律型ロボットです。本物の動物と同じように触れ合うことで、人の心を元気づける・ストレスを軽減する・コミュニケーションを活性化するなどの働きかけを行います。
医療・介護・福祉施設での精神的ケアのツールや、自宅で本物のペットが飼えない方のパートナーとして選ばれています。また、ギネスブックに「Most Therapeutic Robot(世界で最もセラピー効果のあるロボット)」として認定されています。
【適合するケース】
セラピーやトレーニングのツールとして適しています。具体的には、認知症、発達障害、精神障害、PTSD、脳機能障害、がん患者などに利用されています。また、ペットを飼うことが困難な高齢者や動物に対するアレルギーがある方、住宅事業によりペットを飼うことができない方などにも適しています。
高齢者や特定の疾患を持つ人々のQOL向上や生活機能改善に役立つでしょう。また、最新テクノロジーを搭載しており、誰でも簡単に安全に扱えるのも特徴の一つです。
⑤aibo


ソニーが手がける全長約30cmの犬型ロボットです。1999年発売の初代「AIBO」は惜しまれつつも2006年で販売終了になりましたが、2018年に、よりリアルな犬に近いデザインの「aibo」として後継機が発売になりました。aiboは子犬に似た動作が特長で、四足歩行が可能です。
ユーザーと周辺環境をセンシング技術によって認識し、その情報を基に具体的な行動をAIが制御します。人を識別することができ、優しくしてくれる人には懐いたり、甘えたりします。
お手やハイタッチ、ボール遊びなど、本物の犬らしいふるまいをするほか、音楽に合わせたダンスなども披露してくれます。
【効果】
近年、ペットの飼育は心身の健康に好影響を与えるという研究が多数報告されていますが、aiboは同様の効果が期待できるロボットです。犬と同じように人に愛され、人と心を通わせて向き合っていく存在であり、そのために人を理解することを大切にしています。人工知能をもつaiboは、療養中の子どもとのセッションを通じ、より他者とのつながりを促進したり、抑圧している感情を表現する支援者として、効果があるという結果が出てきています。
【適合するケース】
家庭の中で家族の一員として愛情を注がれながら育つ自律型ロボットです。宇宙船での特殊な環境下でのトレーニング中や病院に入院する子どもたちなどが、aiboの存在によって神玄関係や生活環境にポジティブな影響を与えたとされています。
その他
⑥LOVOT

LOVOTは人間を癒すことに特化して開発された。名前を呼ぶと近づいてきて、抱っこをねだります。触れると本物の生きもののように柔らかく、ほんのり温かいのが特長です。また、6層の映像をアイ・ディスプレイに投影することで、“目が合う”“見つめると、見つめ返してくれる”瞳が実現しています。鳴き声は声帯をシミュレーションしたシンセサイザーでリアルタイムに生成されており、日本語での会話はできないものの、生きもののような“意思を感じる”ロボットです。
【効果】
人と会う機会が減ってしまった高齢者などと暮らすことで、精神的なケアに役立つとされています。また、神戸市の「CO+CREATION KOBE Project」による実証実験により、LOVOTとのコミュニケーションは認知機能低下抑制に効果があることが明らかになっています。
【適合するケース】
介護施設や家庭でのメンタルケアや認知症予防に適しています。また、アプリを活用することで、LOVOTと利用者のふれあいの様子が確認できるほか、モニター機能などを活用することで、離れて暮らす家族をゆるく見守ることもできます。
⑦chapit
chapitは高性能な音声認識エンジンを搭載しており、離れた場所からでも人の言葉を聞き取ることができるコミュニケーションロボットです。一文字ずつゆっくり話しかけるのではなく、すらすらと普通に話しかけても認識をするので、友達感覚で会話することができます。
【効果】
日常的な雑音がある環境下でも人の声を聞き取ることができるので、高齢者の会話相手にもなることができます。「クイズモード」「計算モード」「暗記ゲーム」「チャレンジモード」などのレクリエーション機能もあるので、認知機能のトレーニングなどにも役立つでしょう。
【適合するケース】
インターネット接続なしで使えるため、接続環境がない場所でも利用できます。介護施設などにも持ち歩くことができるので、日常生活のさまざまなシーンで活用できます。
⑧Qoobo

Qooboはしっぽのついたクッション型のロボットで、そっと撫でるとふわふわと、たくさん撫でるとぶんぶんとしっぽを振って応えてくれます。
本物の動物と同様に寿命があり、約2年(しっぽ約7万往復分)で動かなくなります。ペットを飼う場合と同じく命の大切さを感じることができるほか、高齢者が一緒に暮らす場合、ご自身の万が一の際の引き取り手を探す心配も軽減されます。
【効果】
言葉のいらないコミュニケーションを提供することを目的に開発されています。その存在が、高齢者の心を癒し、発語や撫でるなどの行動を促し、他者との活動と参加を促すきっかけになることでしょう。
【適合するケース】
Qooboは、毎日の生活に癒やしを求める人や、ペットを飼いたくても飼えない人に向いています。
⑨Romi

MIXIが独自に開発した、「会話」特化型の手のひらサイズのロボットです。既存のロボットの会話は、人間が会話内容をあらかじめ登録していましたが、Romiは最新のAIがその都度会話内容を作り出しており、予測不可能で自然な会話が魅力です。目覚まし機能や、リマインダーなどで利用者をサポートしてくれるほか、脳トレや歌、山手線ゲームなど100種類以上の豊富なコンテンツで楽しませてくれます。
また、人の声や顔に反応して振り向き、豊かな表情や動きでコミュニケーションができます。
【適合するケース】
どんな話題にもついていくことができるので、ひとりの時間が多い高齢者にとってなんでも話せるパートナーになりえます。
また、専用のプログラミングツールを無料公開しているので、子どものプログラミング教育にも活用されています。