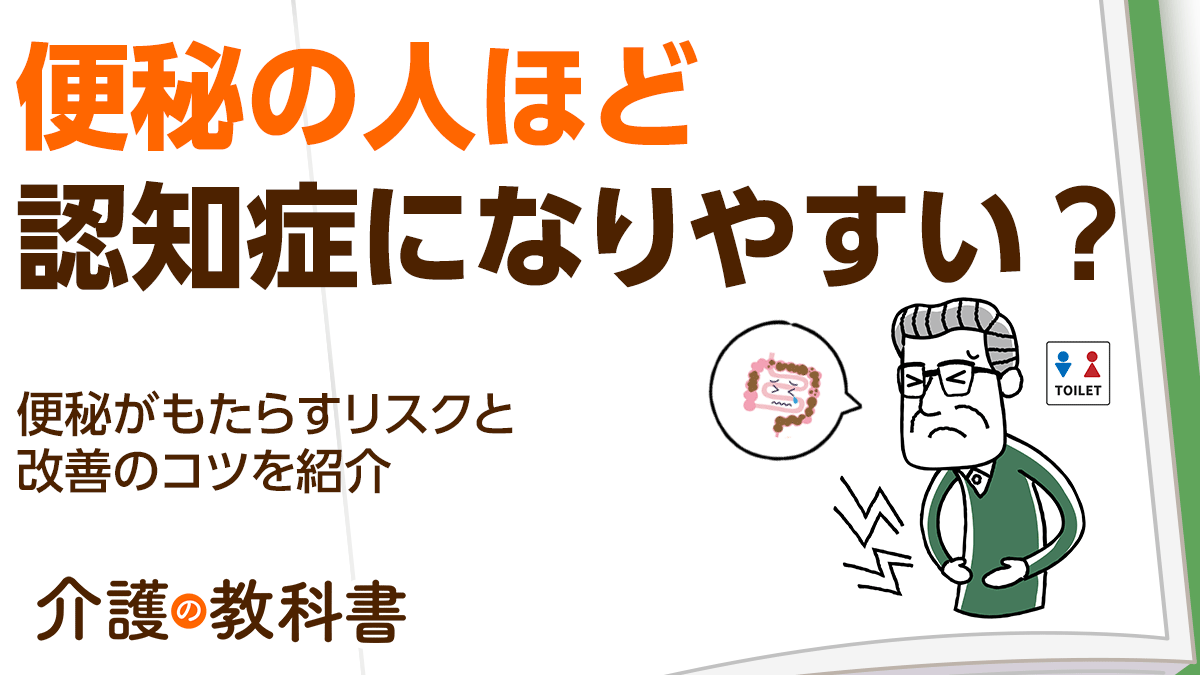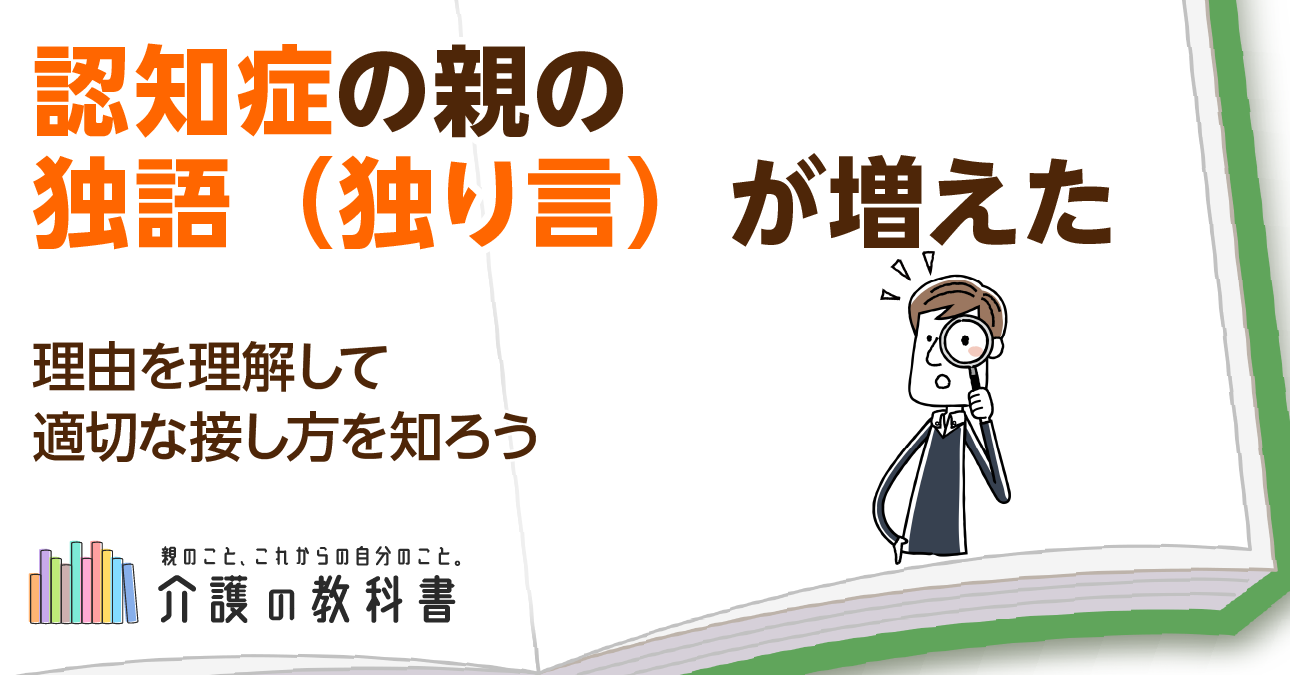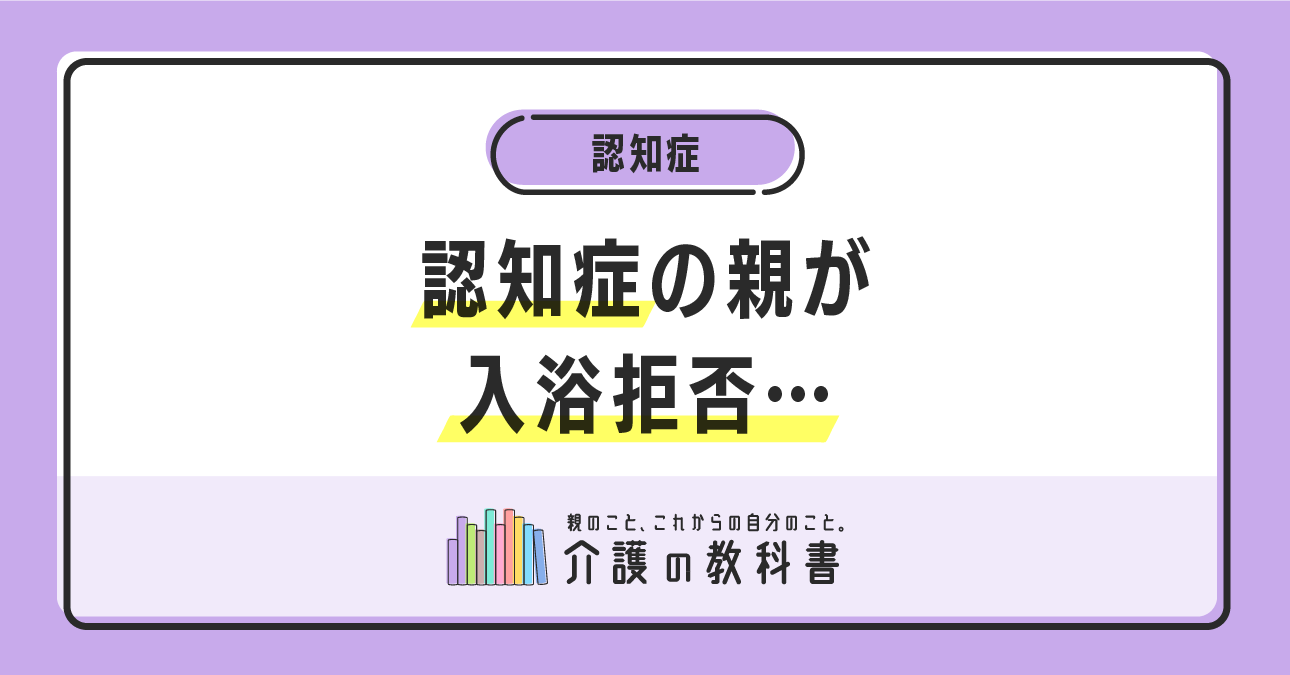国立がん研究センターの研究によると、中年期以降の便秘や硬い便が認知症リスクを高める可能性があるそうです。
ですが、高齢者は食事量が低下したり、身体機能が衰えたりして便秘になりやすいとされています。
今回は高齢者の便秘がもたらすリスクと対策について解説いたします。
国立がん研究センターの研究報告
脳と腸の働きはお互いに関連している
これまでの研究によって、脳の機能と腸の機能には相互に関連があることがわかっています。認知症は脳の認知機能への障害によって生じるため、腸内環境が何らかの影響を及ぼすとも考えられます。
そこで、国立がん研究センターでは高齢者の排便習慣や便の硬さに注目。50~79歳の男性約19,000名、女性約23,000名を2000~2016年の間追跡調査し、排便習慣と、認知症発症との関連を調査しました。
排便頻度と硬い便による認知症リスク
その結果、排便頻度が毎日1回のグループに対して、週3回未満の男性では約1.8倍、女性では約1.3倍認知症のリスクが高くなり、排便頻度が少ないほど認知症リスクが高くなることがわかりました。
また、便の硬さについて、「普通の便」と回答したグループに対して、「硬い便」と回答した男性では約1.3倍、女性では約1.2倍、「特に硬い便」と回答した男性では約2.2倍、女性では約1.8倍認知症のリスクが高くなり、便が硬いほど認知症リスクが高くなりました。なお「下痢便」と回答したグループは約0.8倍と低くなっています。
便秘と硬い便が認知症リスクを上げる理由
国立がん研究センターによれば、排便頻度の低さと便の硬さは、便が腸管を通過する時間が遅れていることと関連しているとしています。
腸管を便が通過する時間が長くなると、腸内細菌がつくる短鎖脂肪酸を減少させることがわかっています。短鎖脂肪酸が減少すると、酸化ストレス※を引き起こし、認知症リスクを高める可能性が考えられます。
※体内で起こる酸化反応によって引き起こされる有害な作用。活性酸素と抗酸化物質のバランスが崩れることで起こるとされている
また、短鎖脂肪酸が減少すると免疫が活性化して、全身に炎症を広げて認知症リスクを高めるのではないかと報告しています。
便秘の予防ケア
それでは、どのように便秘を改善するべきなのでしょうか。
便秘を予防・ケアするポイントは、腸を刺激して運動しやすくすることと排便習慣を身につけることです。以下のような対策が有効だとされています。
トイレの習慣をつける
夜間寝ている間は、腸がぜん動運動をして便を直腸に送りやすくなります。そのため、一般的には朝起きたときは排便しやすいタイミングです。
朝は、便意がなくても毎日決めた時間に5分間座ってみてください。その際、排便の前にウォシュレットで肛門を刺激するとマッサージとなって排便しやすくなります。
また、朝食を摂ってからトイレに行くのも良いでしょう。食べ物が腸に入ることで、前日に溜まっていた便が動きやすくなるからです。
それでも排便できない場合は、手洗いや洗顔をすることも効果的です。冷たさを感じると自律神経が反応して便意を催すことがあるからです。
水分をよく摂取する
硬い便は水分が不足した状態です。そこで水を飲むと便がやわらかくなり、出しやすくなります。冷たい水よりも常温のほうが効果が高いという指摘もあります。
発酵食品を食べる
納豆やチーズ、ヨーグルトに代表される発酵食品には、多くの有益な菌が存在します。これらの菌は、腸内で善玉菌として働いて排便を助けてくれる役割をしています。
お腹を冷やさない
お腹を冷やすと、腸の運動が鈍ってしまいます。そのため、できる限りお腹を冷やさないように工夫をしましょう。寒い季節には腹巻きなどもおすすめです。
まとめ
高齢者は身体機能の低下などによって、腸内環境が崩れて便秘になりやすいとされています。ですが、便秘は認知症の発症リスクにも関連しているのです。こうした不調を防ぐためには、規則正しい生活を身につけ、決まった時間にトイレに向かう習慣づけが大切です。
そのためには朝起きたときに、太陽の光を浴びて体内時計を毎日リセットすることも有効だとされています。人間の体内時計は1日25時間程度のサイクルで回っているとされ、太陽の光を浴びることでそのズレを修正してくれるともいわれています。
これから次第に寒くなっていきます。体が冷えると便秘気味になりやすいので、できる限り温かい環境で過ごし、腸をいたわるような行動をとりましょう。
【参考文献】
排便習慣と認知症との関連(国立がん研究センター)2023/10/5
冬は便秘の季節 ~冷えた身体と腸内環境を整えよう~(山梨県厚生連)2023/10/5
便秘(健康長寿ネット)2023/10/5