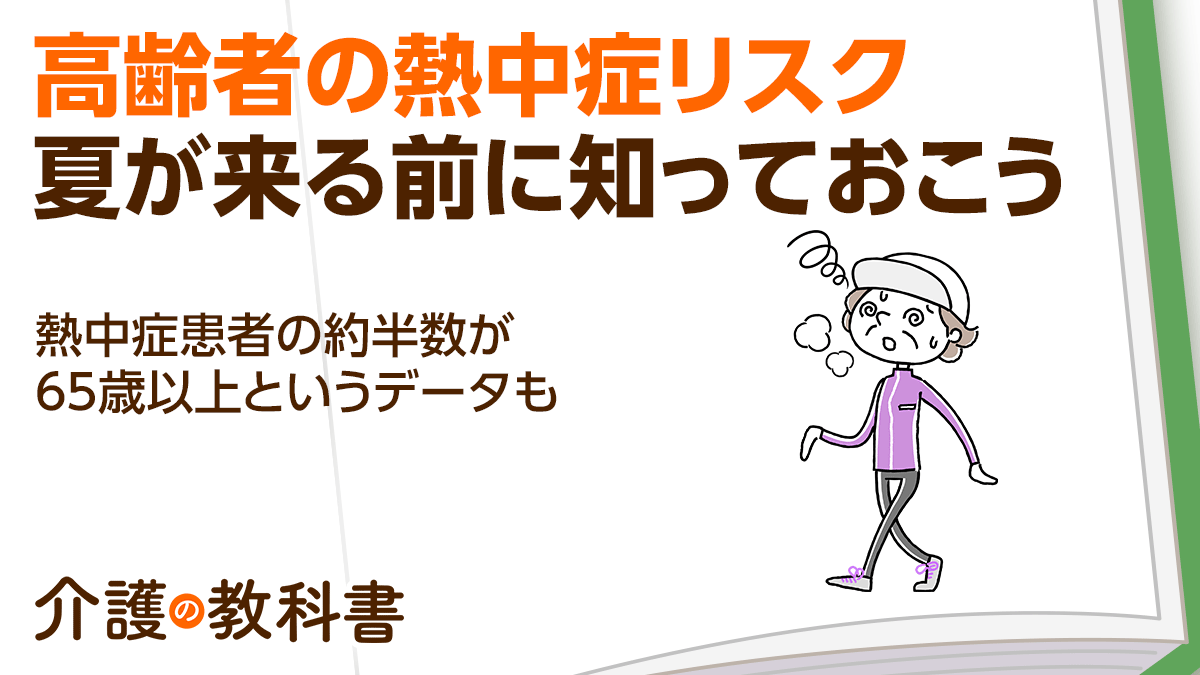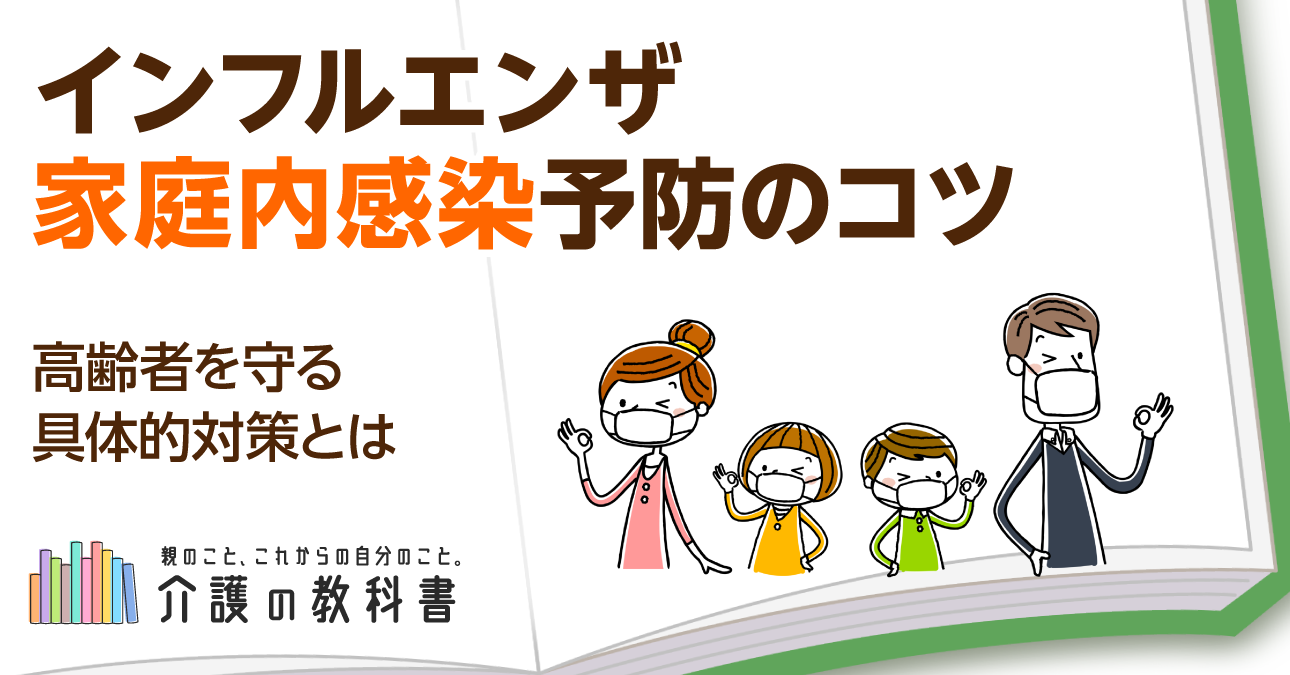「高齢者が熱中症で救急搬送された」
「室内で倒れていた高齢者が熱中症で亡くなった」
毎年気温が高くなり始めると、このようなニュースに触れることが多くなるのではないでしょうか。私も周りに高齢者が多いため、決して他人ごとではありません。
実際に高齢者は成人よりも熱中症にかかりやすいと言われ、ときには命に関わります。熱中症は暑い日の外出中だけでなく、室内や夜間にも熱中症のリスクは潜んでいるのです。
この記事では高齢者が熱中症になりやすい原因を中心に、予防法や対処法などをご紹介します。
高齢者が熱中症になる原因
厚生労働省の資料によると、熱中症患者の約半数が65歳以上の高齢者だといわれています。
気象庁と環境省のデータによると、2021年の熱中症による死亡者のうち、東京では8割、大阪では7割が65歳以上の高齢者でした。
公的機関のデータから見ても、高齢者は熱中症にかかりやすいことが分かります。主な理由を下記に示しました。
- 体温調節機能が低下している
- 汗をかきにくい
- 暑さやのどの渇きを感じにくい
- 体内の水分量が少ない
- 冷房に抵抗を感じる方が多い
高齢者は体温を調節する機能が低下しており、体に熱がたまりやすいことが1つ目の理由です。
それだけでなく、汗をかきにくいとも言われます。人間は汗をかき、それが蒸発されることで体温を下げる働きを持っています。汗をかきにくいということは、体温が下がりにくいということであり、やはり熱がこもりやすい状況になるのです。
高齢者は放熱しにくく、暑さやのどの渇きを感じにくいということを知っておきましょう。何度もトイレに行くことへの不安から、水分を控える傾向もあるのです。
また、体内の水分量が少ないことも原因です。子どもは体内の75%、成人は体内の60%が水分であるのに対し、高齢者は50%程度と、成人より2割ほど水分量が少ないのです。
そのため脱水症状も起こしやすく、熱中症にもなりやすいのです。
体が冷える、電気代がかかるなどの理由から、エアコンを使った冷房に抵抗を持つ高齢者も多いので、これも原因の1つと言えるでしょう。
高齢者向け熱中症の予防方法
高齢者はなんといっても熱中症の予防が大切です。ここでは、主な予防方法を3つご紹介します。あるデイサービスでの取り組みも紹介しますので、参考になさってください。
1.こまめな水分と塩分の補給
熱中症予防のために大切なのは、こまめな水分と塩分の補給です。人間は知らず知らずのうちに汗をかいて水分と塩分を失っています。それに加えて、高齢者は成人より体の中の水分量が少ない状況です。
水分と塩分を同時補給するには、スポーツドリンクや経口補水液、お味噌汁や昆布茶などがおすすめです。ただしこれらを水の代わりにはしないでください。塩分や糖分を取りすぎてしまう危険性があります。
3食ごとや起床後、入浴の前後、就寝前など、こまめに水分補給をすることが大切です。夜寝ているときも熱中症の危険があるので、枕元にお水やスポーツドリンクなどのペットボトルを用意しておくことをおすすめします。

心臓や腎臓に持病がある方の場合は、水分摂取量に関してかかりつけ医に相談しましょう。
高齢者デイサービスでの取り組み
あるデイサービスセンターでは、水分補給の時間を決めていました。来所時・入浴後・昼食時・レクリエーションの休憩時・おやつのときです。それ以外のときでも、利用者さんには自由にお水やお茶を飲んでもらっていました。夏場のおやつは、ゼリーやアイスなど冷たくて、水分がとりやすいものを提供していました。
1日の水分摂取量が決まっている利用者さんに対しては、お水ではなく細かくした氷を提供していました。製氷皿の氷1個を水30㏄として、1回の水分量100㏄のときに氷3個をお出ししていたのです。氷にした理由は、水よりもゆっくり口に含められて少ない量でも満足感を得られるためです。毎回氷ではおなかを冷やす可能性があったので、レクリエーションの休憩時などにお出ししていました。
2.適切な冷房
温度計や湿度計で室温や湿度を確認しながら、エアコンや扇風機で空間を冷やしましょう。
高齢者は暑さを感じにくいので、肌感覚に頼ると冷房をつけることなく、暑い部屋で過ごし続ける可能性が高くなります。そのため、客観的な数字を見て冷房の判断をしましょう。
室温は28℃以下、湿度70%以下が目安とされています。
エアコンの冷房に抵抗がある場合は、冷気が直接体に当たらないように風向きを調整するとよいでしょう。または扇風機を使うのもよい方法です。理由は2つあります。
- 風が体の熱を逃がす
- 体の周囲の空気が、熱を含まない空気に入れ替わる
このため扇風機を使うことは、体を冷やすことにつながるのです。
停電などの緊急時には、冷たいタオルで体を拭くことでも体を冷やすことができます。
3.涼しい服装
半袖の服、ゆったりとした服、通気性や吸湿性の高い素材の服を着るなど、服装での熱中症予防も大切です。
洋服の色も大事です。黒っぽい色の服は熱を吸収しやすいので、体の中に熱がこもる可能性があります。特に外出時は白や、色が薄めの服を選ぶとよいでしょう。
外出時には日傘や帽子も使うと、直射日光に当たることを防げます。
直射日光に当たり続けると、体に熱がこもり熱中症のリスクが上がるので、できるだけ避けるのが望ましいです。
また、認知症の方の服装は特に注意が必要です。
認知症が進むと、今の季節が分からなかったり、暑さが判断できなくなる場合があります。また、服を脱いだり着たりすることが難しくなります。
加えて、なじみのある服を着ていたいといった、本人ならではのこだわりもあるでしょう。なじみの服が厚手のものであれば、気温が高い日でも厚着になってしまいます。
この場合、無理に脱がすのは逆効果です。「ちょっと暑いですから、1枚脱いでみましょうか」など、さりげなく提案するとよいでしょう。脱ぐのが大変そうでしたら、手伝います。
それでも脱がない場合は、冷房をつけて調整します。
熱中症にかかった場合の症状と対処法
熱中症の症状はⅠ度・Ⅱ度・Ⅲ度の3段階に分かれます。重症化すると脳や肝臓、腎臓の機能に異常をきたす場合があるので、早い対応が求められるのです。
Ⅰ度(軽症)
I度の症状としては、めまいや立ちくらみ、こむらがえり、大量の発汗などが挙げられます。
対処法としては、安静にして体を冷やす、スポーツドリンクや経口補水液を少しずつ飲んでもらうといったことが挙げられます。ただしこれは、本人に意識があり、口から水分をとれる状況の時に限られるので注意してください。
Ⅱ度(中等症)
頭痛、吐き気、おう吐、体のだるさなどの症状が出てきます。
必ず誰かが付き添った上で、Ⅰ度での対処法を続けましょう。
吐き気が強い、もしくは吐いてしまうといった症状があれば、すぐに医療機関を受診してください。
Ⅲ度(重症)
意識障害やけいれんなどの重い症状になります。昏睡状態になり亡くなる場合もあります。
対処法
一刻を争うので、速やかに救急車を呼びましょう。救急車が到着するまで、体を冷やしながら声をかけつつ、状況の変化を見守ります。
体を冷やすことは、重症度問わず必須の対処法です。主なものとしては以下のようなものが挙げられます。
- 首やわきの下、太ももを保冷剤などで冷やす
- 日陰や冷房の効いたなどの涼しい場所に移動する
- 衣服をゆるめて、うちわや扇風機で風を送る
まとめ
この記事では、高齢者の熱中症について解説しました。高齢者は成人よりも熱中症になるリスクが高いので予防しておくことが重要です。
涼しい服装とこまめな水分補給を意識し、適切に冷房を使って体温の上昇を防ぎましょう。
しかし、さまざまな原因で高齢者自身が予防法を適切に行えない可能性もあります。
「節電のためにエアコンは我慢する」
「トイレが近いから水を控える」
このような高齢者も少なからずいらっしゃいます。そのため、周りにいる人も熱中症の予防や対処法に関する正しい知識を持つことが必要なのです。
もし身近な高齢者に熱中症の症状が現れたら、早めに対処し、それでも治らないようでしたら急いで医療機関を受診しましょう。