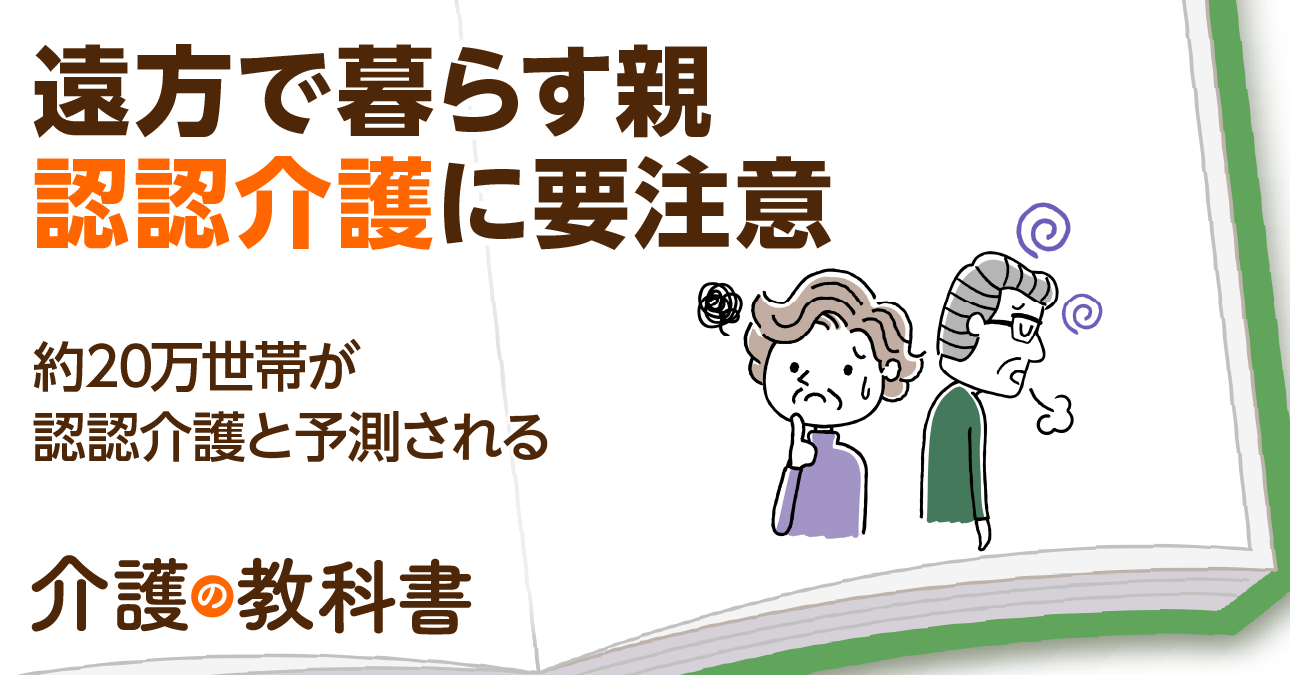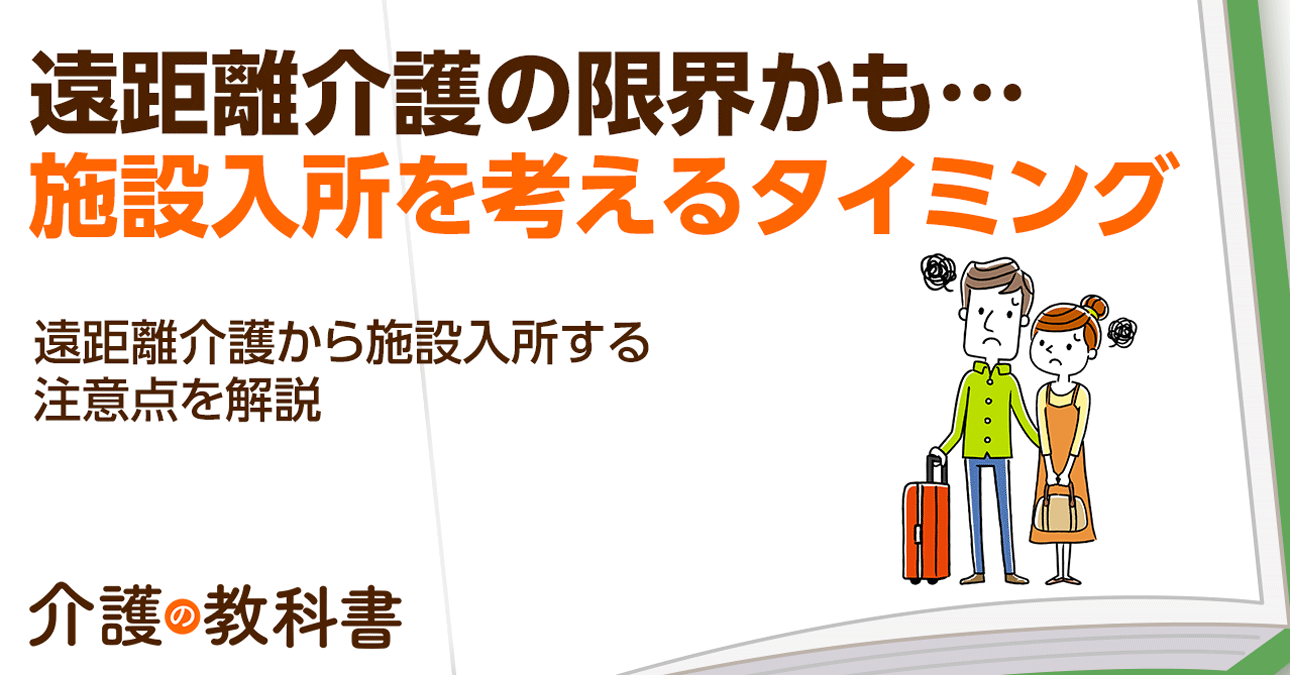「高齢の親と離れて住んでいるけど、元気にしているかがいつも気になる」
「親と一緒に住んでいるけど、日中は仕事で家にいないので、その間が心配」
そのように考える方も多いのではないでしょうか。自分自身が年を重ねると、もちろん親も高齢になります。健康状態の悪化や認知症を発症するなど、心配することも増えてくるでしょう。
そんなときに役立つのが、高齢者見守りサービスです。高齢化により、最近はさまざまな見守りサービスが増えてきました。
この記事では高齢者見守りサービスの種類や選び方についてご紹介します。
高齢者見守りサービスとは?
高齢者見守りサービスは、離れて住む家族に代わって、高齢者の様子を見守るためのサービスです。
主に、1人暮らし高齢者宅や高齢者夫婦世帯で利用されています。
訪問や電話で直接状況を確認するものや、カメラや人感センサー、スマホアプリを使って、間接的に見守りを行うものがあります。
メインは健康状態や日常生活状況の確認ですが、サービス業者によっては、急病やけがのときに救急車を要請するなどの緊急時対応も可能です。
見守り時の状況は、離れて住む家族に伝えられるので、本人・家族も安心ですね。

高齢者見守りサービス6種類を比較
高齢者見守りサービスにはさまざまな種類がありますが、ここでは、以下の6種類について解説します。
| 種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 訪問・宅配型 | 直接顔を合わせるので、状況が分かりやすい | 訪問日が決まっている 緊急時向きではない |
| 電話型 | 訪問が苦手な人にも受け入れられやすい | 表情が見えないので、詳しい状況が分かりにくい |
| アプリ型 | 比較的操作が手軽 | スマホを持っていない高齢者は利用できない |
| カメラ型 | リアルタイムで状況が分かるので家族が安心できる | 監視されているという印象を持たれやすい |
| センサー型 | 監視されているという印象を与えにくい | 緊急時対応が難しい |
| 緊急通報型 | 緊急時対応にすぐれている | 毎日の見守り向きではない |
1.訪問・宅配型
訪問型は、専門スタッフが高齢者の自宅を訪問して見守りを行うものです。
主なものとしては、郵便局や新聞配達店などのサービス機関による訪問、民生委員や地区のボランティアによる訪問があります。
宅配型は、お弁当や買い物の品を高齢者の自宅に直接届けることで、生活状況や安否確認を行うサービスです。
宅配専門業者が行うほか、市区町村の高齢者福祉サービスとして導入されている場合もあります。
メリット
高齢者本人の顔を見られるので、状況を確認しやすいのが大きなメリットです。
また、他の人とコミュニケーションがとれるため、孤独感解消にもなるでしょう。
配食業者によっては、栄養バランスやその人の身体面に合わせた献立(減塩食や低カロリー食など)に対応できるケースもあるので、栄養管理にも役立ちます。
デメリット
訪問日が決まっていることが多く、毎日の安否確認が難しいことがデメリットです。
また、訪問スタッフが介護・医療の専門家ではないことが多いため、緊急時の対応には向かないでしょう。
2.電話型
サービス提供会社のスタッフや市区町村のボランティアが高齢者宅に電話をかけて、安否確認を行うサービスです。
サービス提供機関によっては、テレビ電話を利用して行うところもあります。
メリット
訪問が苦手という高齢者にとっても、比較的受け入れやすいのが特徴です。電話は普段から使っているものなので、抵抗感なく使える高齢者も多いでしょう。
デメリット
テレビ電話ではない限り高齢者の表情が分からないので、詳しい状況を確認しにくいのはデメリットです。なお、耳が遠い高齢者には不向きといえます。
3.アプリ型
高齢者と家族が持っているスマホに所定のアプリをインストールして、見守りを行うサービスです。
アプリ型見守りサービスの内容としては、以下のようなものがあります。
- 指定した時間になると高齢者のスマホにアラームが鳴り、高齢者がアラームを止めると家族のスマホにメールが届く
- 一定期間高齢者のスマホが充電されないと、家族あてにメールが届く
- 「家にいる」「元気です」「元気がない」など複数のメッセージボタンから自分の状況を選んで、家族に現状を伝える
メリット
比較的手軽な操作で見守りを行えます。また無料のものや安価なものが多く、経済的負担が少なくてすむのもメリットといえるでしょう。
デメリット
高齢者がスマホを持っていない場合や、機械の操作が苦手な場合には利用が難しいというのがデメリットになります。
また、高齢者がスマホやアプリを使える場合でも、外出時にスマホを忘れると、外出先での体調急変などが家族に伝わらない可能性があります。
4.カメラ型
高齢者宅にカメラを設置し、離れて住む家族が映像で状況を確認できるサービスです。
メリット
映像で状況を確認するため、離れていてもリアルタイムで状況が把握できます。そのため、電話やメールよりも家族が安心できるのが大きなメリットといえるでしょう。
お手持ちのスマホ等で手軽に様子を確認でき、工事も必要ないので手軽に導入できることもポイントです。
デメリット
家にカメラがあることで、「監視されている」という印象を持たれやすいので、本人が導入を拒否するケースもあります。プライバシーにできるだけ配慮し納得してもらったうえで設置するようにしましょう。
5.センサー型
高齢者宅に人感センサーを設置するタイプです。
「一定時間動きがない」など、高齢者宅で異変があったときに、家族に連絡が届きます。
自宅内にセンサーを設置する以外にも、冷蔵庫や電気ポット、リモコンなどの家電製品にセンサーが内蔵されているものもあります。
メリット
カメラと違い、高齢者本人に「監視されている」という印象を持たれずに利用可能です。
デメリット
リアルタイムでの状況確認を行えないため、緊急時の対応が難しいことがデメリットになります。
6.緊急通報型
主に警備会社が提供してる見守りサービスです。緊急時にペンダントやタブレットなどについているボタンを押すことで、専門スタッフがかけつけます。
急病やケガの際には救急車要請も可能です。
メリット
セキュリティ会社が提供しているサービスは、緊急時の対応に優れているので安心感があります。ボタンを押せば駆けつけてくれたりと、操作も簡単でわかりやすいのも特徴です。
デメリット
高齢者が意識を失ってしまうと、操作ができず対応に遅れてしまう危険性があります。また、毎日の見守りには適していないので、日頃から様子を確認しておきたいという方は別のサービスを検討した方が良いでしょう。
見守りサービスを選ぶときに大切な3つのポイント
見守りサービスは数多くありますが、親や子どもの状況にあったものを選ばないとせっかくのサービスが有効活用されません。それどころか、かえってマイナスになる場合もあるでしょう。
最後に、見守りサービスを選ぶときに大切な3つのポイントをご紹介します。
1.親の思いを聞いてから選ぶ
いくら子どもが「安心のため」と見守りサービスをすすめても、親が拒否する可能性もあります。「監視されているみたいでいやだ」、「自分にはまだ必要ない」と親には親の思いがあります。
親の思いを無視してサービスを開始することは、親にとっては不本意なことでしょう。場合によっては、親と子の間に溝ができる可能性もあります。
まずは親の思いを聞くことから始めましょう。その上で「お父さん(お母さん)のことが心配だから、見守りのことを考えてみた」と自分の気持ちも伝えます。
そうすることで、親の気持ちが変わり、見守りサービスを受け入れる可能性も出てきます。
サービス利用を親自身が受け入れた上で、「どのサービスなら利用してもよいか」の意見をきくと良いでしょう。
2.操作しやすいものを選ぶ
カメラやアプリ、センサーを使った見守りサービスでは、親子ともに何らかの操作が必要になるものもあります。
子ども側にとってはあまり問題はないと思いますが、親にとっては新しい機械の操作は予想以上に難しいこともあります。
機械を使う場合は、簡単に操作できるものや、親の操作が不要なものを選ぶということも考えると良いでしょう。

3.値段も考慮して選ぶ
基本的に、高齢者見守りサービスは利用料金が発生します。中には高額なサービスもあります。
利用料金を誰が支払うか、いくらまでなら支払えるかなども考慮して選びましょう。
ここでも親子・家族の話し合いが大切になってきます。
まとめ
6つのサービスを紹介しましたが、どれにもメリットとデメリットがあります。残念ながら、「これがあれば完璧に見守れる」というものがないのが現状です。
また、見守りサービスに利用に抵抗を示す高齢者もいます。
心配なあまり家族がサービス利用を先走ってしまうと、見守りのメリットよりも大きな問題が発生する場合もあります。それは「親子の間に溝ができること」です。
そのことで親子が疎遠になると、見守りそのものが難しくなってしまうかもしれません。
まずは親の思いを聴くことが望ましいといえます。
しっかりと家族で話し合い、お互いに納得して見守りサービスを導入することが大切です。うまく活用できれば、高齢者や家族を支える心強い存在になるでしょう。