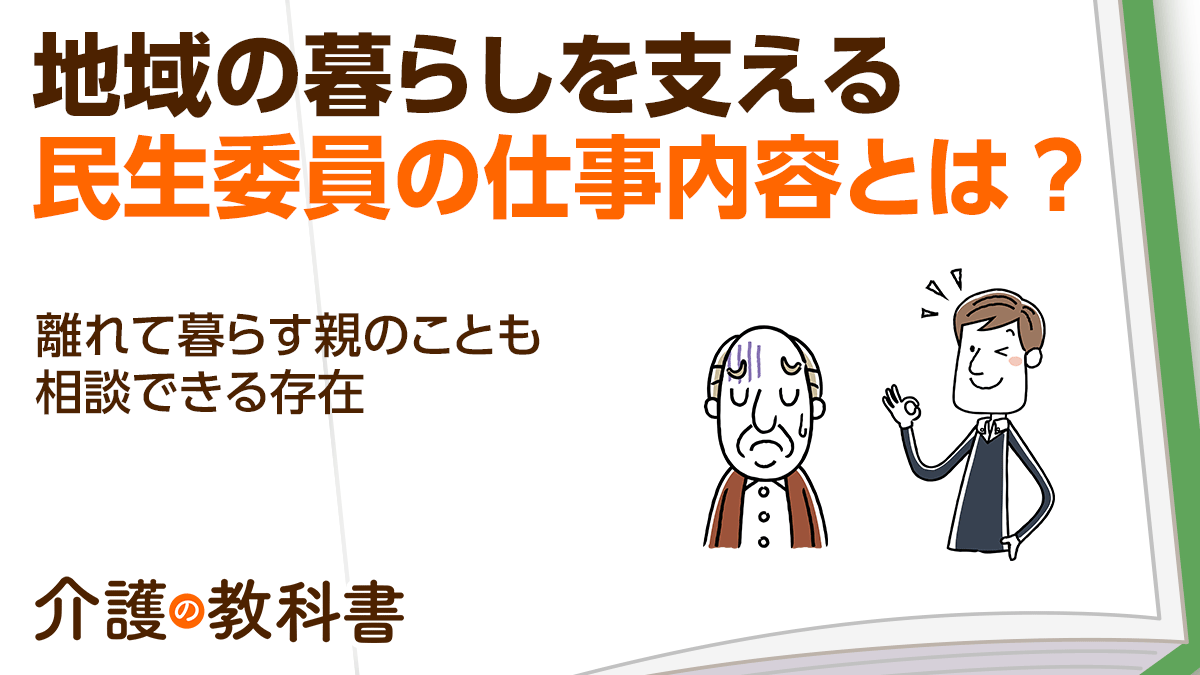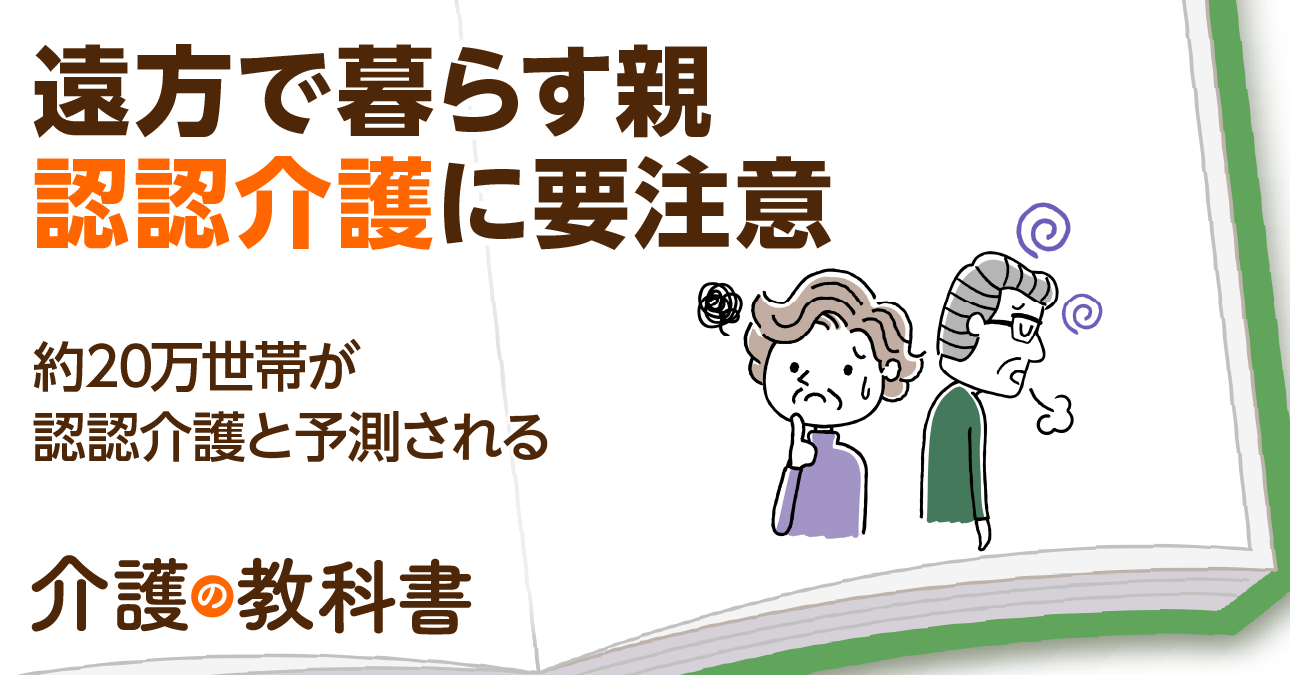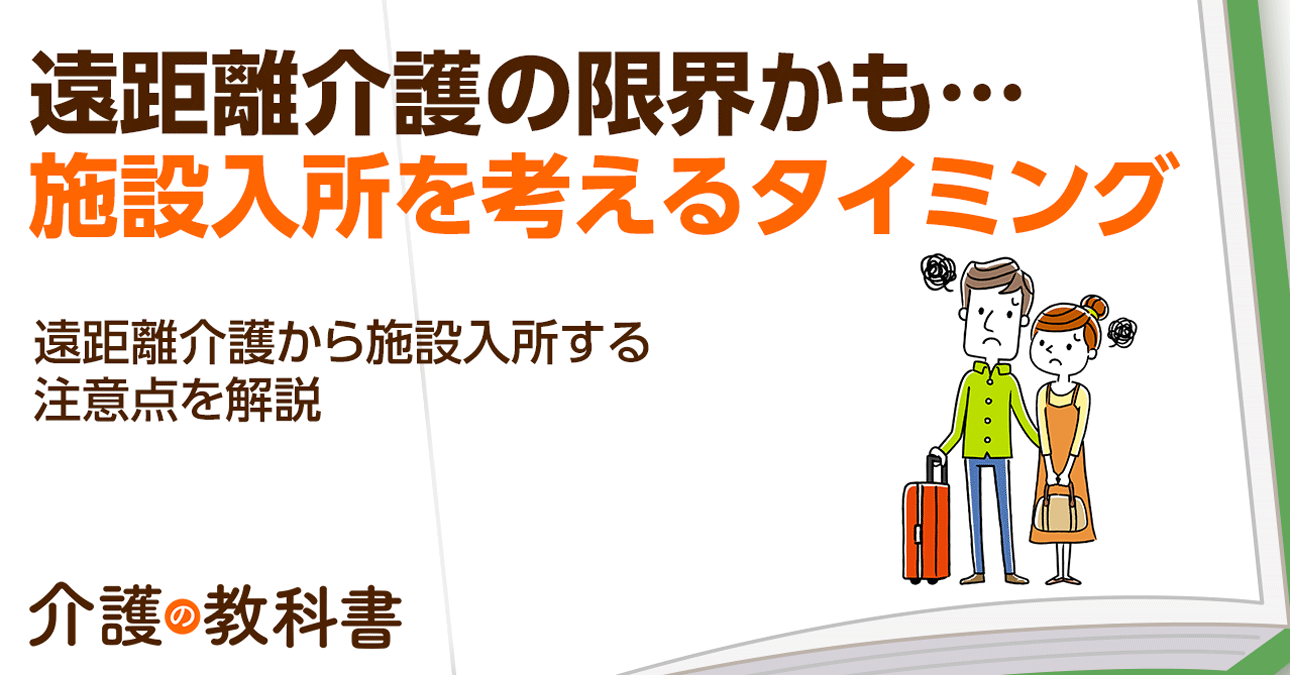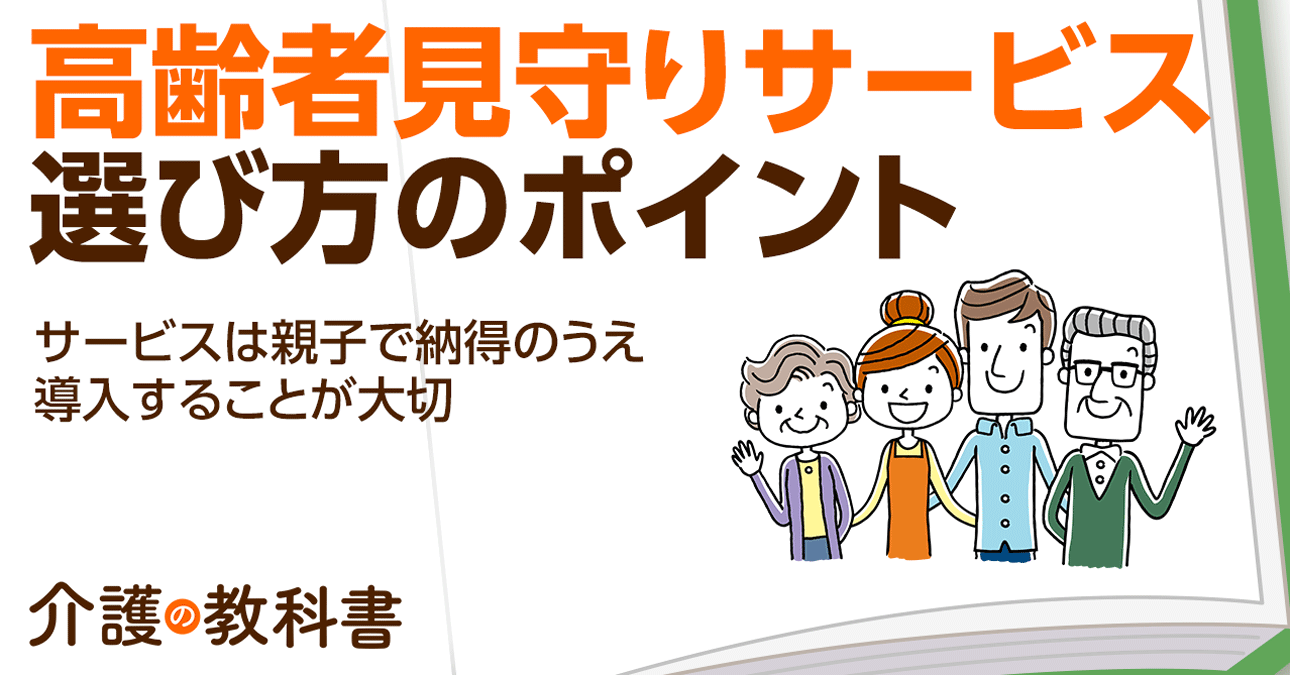高齢の親が1人暮らしをしている場合、ご本人だけではなく、離れて住んでいるご家族も不安を感じていることが多いのではないでしょうか。
急に具合が悪くなったらどうしよう、何かトラブルに巻き込まれたら自分だけでは対応できないなど悩みはつきません。そのようなときに心強いのが、民生委員の存在です。地域の民生委員は、住民を常に見守ってくれています。1人暮らし高齢者も例外ではありません。
この記事では、民生委員の仕事内容や、民生委員に相談できることなどを事例を交えてご紹介します。民生委員に相談したい場合の方法も解説しておりますので、参考になさってください。
民生委員って何をする人?仕事内容をご紹介
民生委員は、民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された非常勤の公務員です。地域住民の立場で、生活や福祉に関する相談や援助を行っており、核家族化が進んだ地域社会において身近な相談相手でもあります。
3年任期で再選されることも多い民生委員には、以下の7つの役割があげられます。
- 社会調査:担当している地区の住民がどのような問題を抱えているのか把握する
- 相談:地区の住民が抱えている困りごとの相談にのる
- 情報提供:住民の困りごとを解決するために役立つ福祉サービスなどの情報を提供する
- 連絡通報:住民の困りごとを行政や各関係機関に報告する
- 調整:住民と支援機関との連絡調整を行う
- 生活支援:住民の困りごとに対して具体的な支援を行う
- 意見具申:活動を通じて得られた問題点や改善策を行政や関係機関に伝える
民生委員に相談できることを具体的に知りたい
民生委員には、地域で生活していく中でのさまざまな悩みが相談可能です。そこには高齢者の介護に関する悩みも含まれます。
令和3年度福祉福祉行政報告例では、高齢者に関する相談が全体の59%を占めており、以下のようなことが挙げられます。
- 1人暮らしをしているが、急に具合が悪くなったらどうしよう
- 最近高齢者が詐欺にあうことも多いので、トラブルが怖い
- 家族の介護を1人で行っているが、心身ともに限界になってきた
- 1人暮らしの親の見守りが十分にできなくて心配
1人暮らしへの不安については、定期的な訪問による安否確認や福祉サービス利用に関する支援を行います。介護に関する相談であれば、介護保険制度の紹介及びサービス利用に向けての支援を行います。
民生委員が単独で支援する場合もありますが、行政や地域包括支援センターなど関係機関と連携をとったうえで対応することが多いでしょう。

また、病気や障害などで生活が困窮している場合の相談も可能です。
- 生活保護受給や申請について
- 生活福祉資金貸付制度について
生活福祉資金制度利用は民生委員への相談・支援が必須ですので、ご注意ください。
民生委員に1人暮らし高齢者の見守りをお願いできる?事例紹介
親と子が離れて住んでいる場合、自分だけでは充分な見守りを行えないので不安を感じている方も多いのではないでしょうか。特に親が1人暮らしであったり、介護保険サービス未利用であったりすると不安は大きいことでしょう。
そんなときには民生委員に相談することも選択肢の1つです。
自治体によっては、民生委員が65歳以上の1人暮らしの方への見守り訪問を行っているところもあります。(筆者在住の北海道札幌市では、1人暮らし高齢者の見守り活動を民生委員に依頼)
ここで、以前ある自治体で実際にあった3つの事例をご紹介します。
1.1人暮らしのAさん(男性80代)の場合
Aさんは、糖尿病や心疾患がある方です。近くに家族や親族、友人もいないため、急に具合が悪くなったらどうしようと不安を抱えていました。
話を聴いた地域包括支援センター職員が、緊急通報システム利用の提案をしました。その際に支援センター職員は民生委員に相談したのです。相談内容は、「緊急通報がなったときに、協力員として駆けつけてほしい」でした。
その民生委員は、他の方の協力員も担っていたこともあり、快く協力してくれました。このことをきっかけに、民生委員はAさん宅を随時訪問して見守りを行うようになったのです。
2.1人暮らしのB さん(女性80代)の場合
Bさんは、1人暮らしの女性です。訪問介護や通所介護などの介護サービスを利用しながら、在宅での生活を続けていました。しかし、経済状況がよくないため、サービス利用を断るときもあったのです。
そんなおり、持病の糖尿病のコントロールが悪くなったため、急きょ入院することになりました。退院前に、ケアマネジャーや介護サービス担当者など関係者が集まって、本人を交えた会議を開きました。今後の方向性を話し合うためです。
Bさんから出たのはお金の不安でした。そこで出されたのが、生活保護受給に関する提案です。
ケアマネジャーが民生委員に相談して、退院直後Bさん宅を訪問し、生活保護の申請につながりました。生活保護受給が決まったBさんは、中断していた介護サービスを再開します。そして新たに、訪問看護サービスも入ることになりました。
3.老々介護のBさん夫婦(ともに80代)の場合
1人暮らしではありませんが、実際に民生委員が関わった事例としてご紹介します。
夫のBさんと妻のCさんは2人暮らしです。子どもがいなく、他の親族も遠くに住んでいました。この数年で夫の認知症が少しずつ進んできました。しかしAさん夫婦は生活保護世帯で経済的にも余裕がなく、介護保険サービスの使い方や申請方法も充分に理解していませんでした。
Bさん夫婦の近くに住む民生委員から、地域包括支援センターに相談がありました。そこで支援センター担当者は民生委員とともに家庭訪問し、介護保険サービスについて説明し、サービス利用につなげました。
サービス利用後は、担当のケアマネジャー・民生委員・生活保護担当ケースワーカー・地域包括支援センター職員でBさん夫婦を支援しています。
民生委員に相談したいときはどうするとよい?
ここまで、民生委員に相談できることや、実際の事例をご紹介しました。では実際に「親の見守りのことを民生委員に相談したいときの方法」について解説します。
最初に、市区町村役場の福祉担当窓口に相談しましょう。親の住んでいる地区を伝えると、担当の民生委員名と連絡先を教えてくれます。自治体によっては、広報誌や公式ホームページに一覧表が載っている場合もあるので、そこをチェックするのもおすすめです。
民生委員には守秘義務があるので、他の人に秘密はもれません。安心して相談しましょう。
民生委員に相談する前には、事前に親にも話しておく方がよいでしょう。もし急に民生委員が自宅に訪問(または電話)してきた場合、親は驚くと思います。それだけではありません。親を思う子の心が親子トラブルに発展する可能性もあるからです。
親は必要ないと思っている、でも心配。そういうときは、「お父さん(お母さん)のことが心配だから話だけでもしておくね」というひと言があるといいですね。民生委員に相談するときも、「親は大丈夫と言っていますが心配なので」と添えておくとよいでしょう。
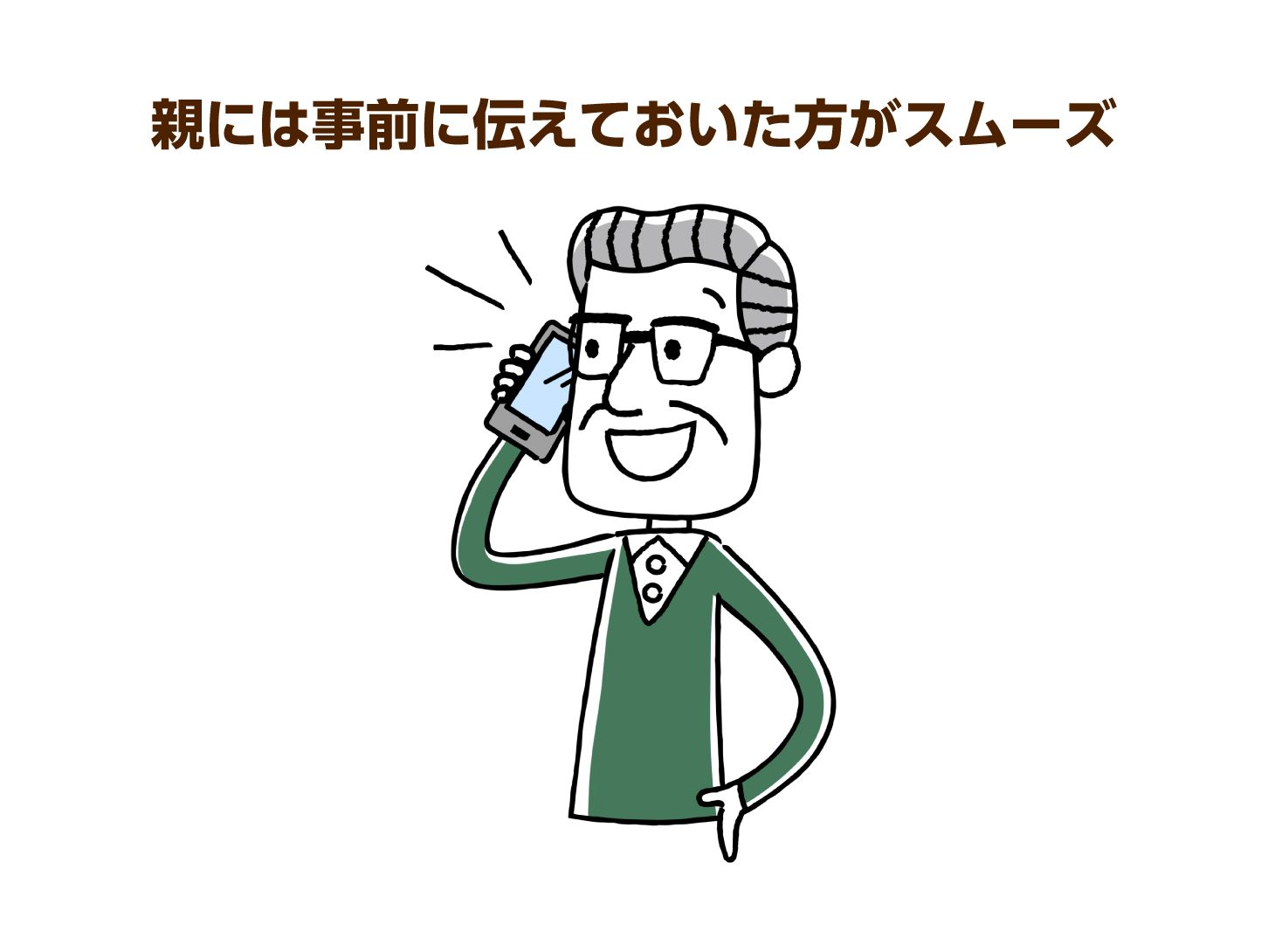
この記事では、民生委員に関する内容を事例を交えて解説しました。地区に住む民生委員は、1人暮らし高齢者はもちろん、地域住民と行政窓口・介護福祉サービスとの架け橋と言えます。
民生委員に相談することがきっかけで、地域での暮らしがより良くなっていく人も大勢います。まずは、「私の地区の民生委員は誰だろう?」と知ることから始めてみてはいかがでしょうか。きっと助けになることでしょう。