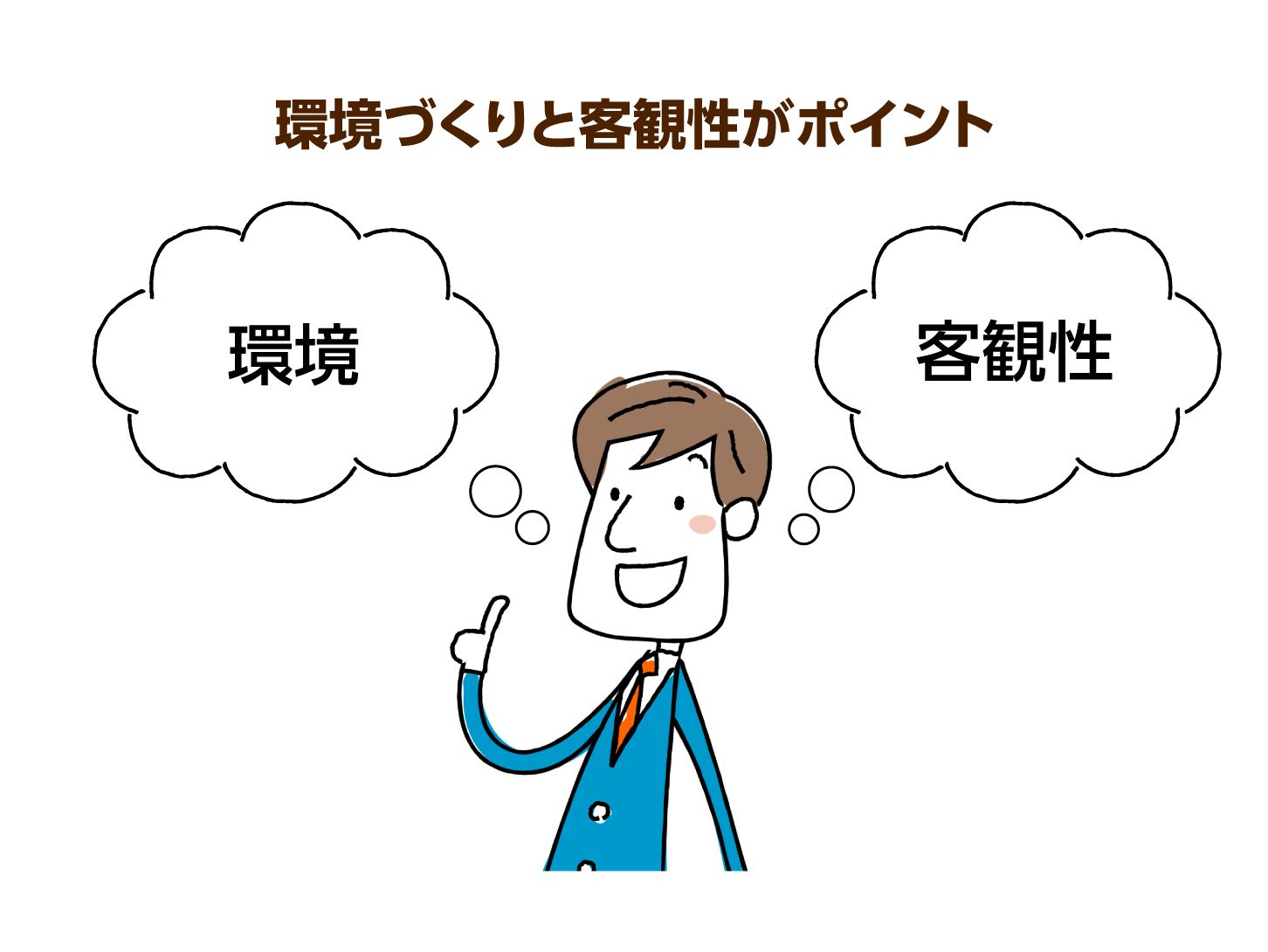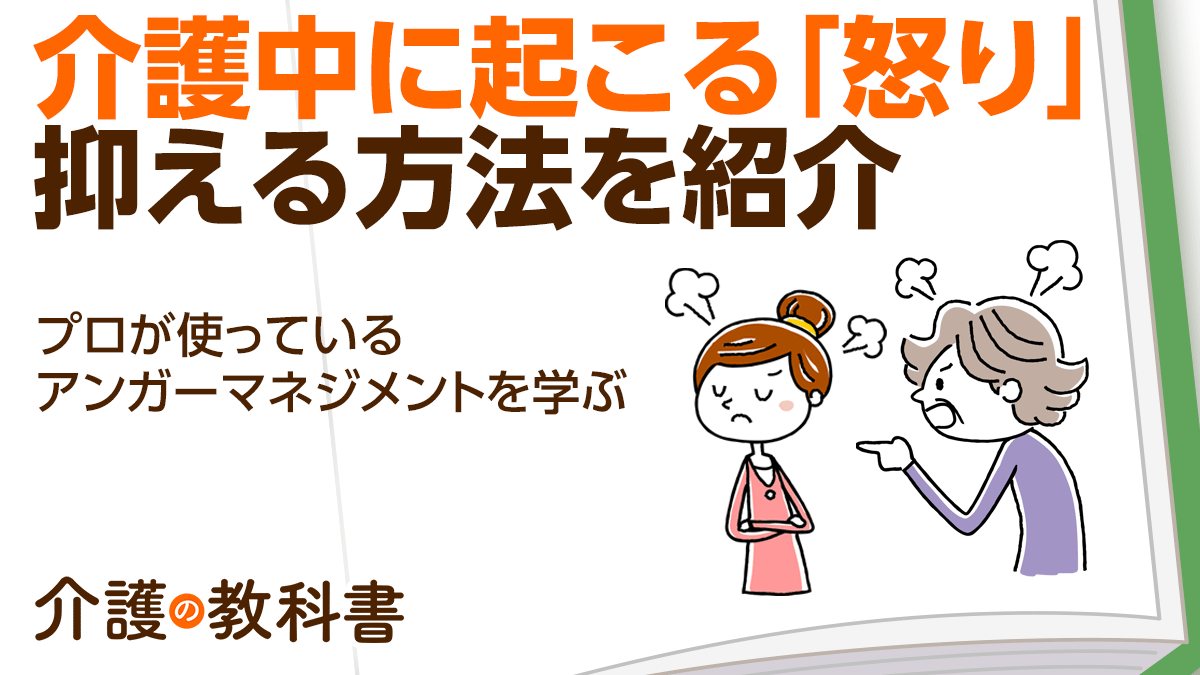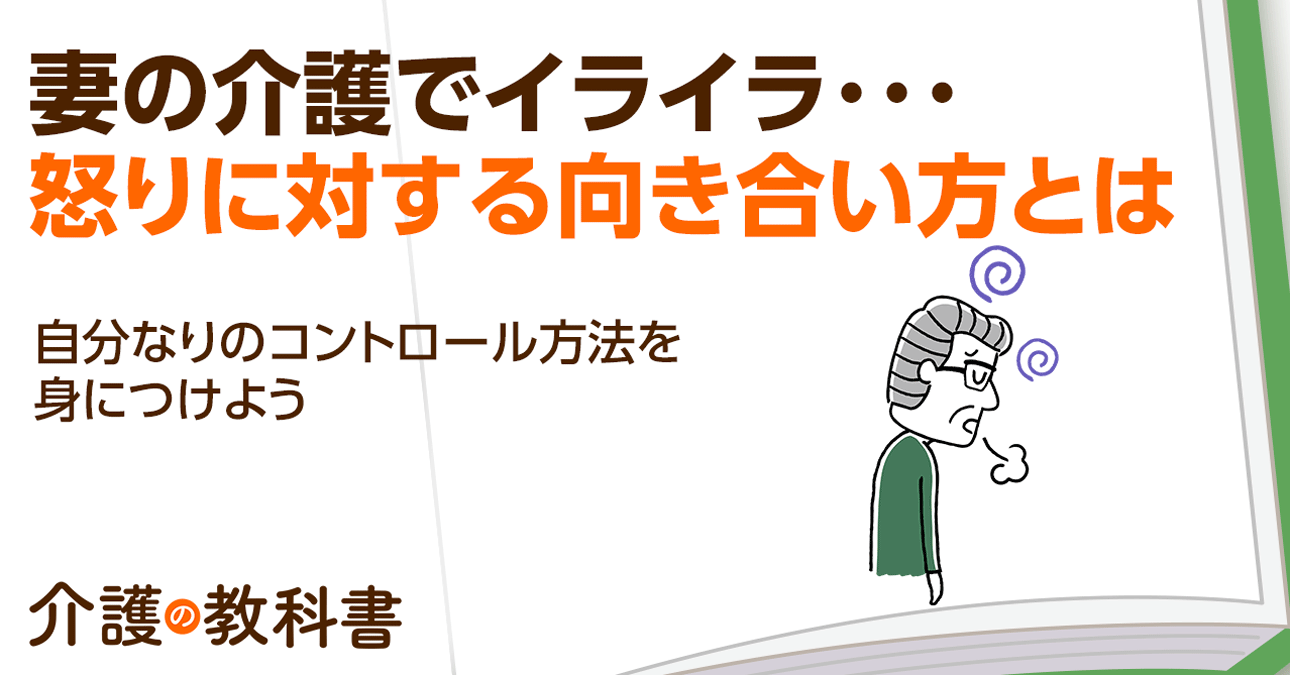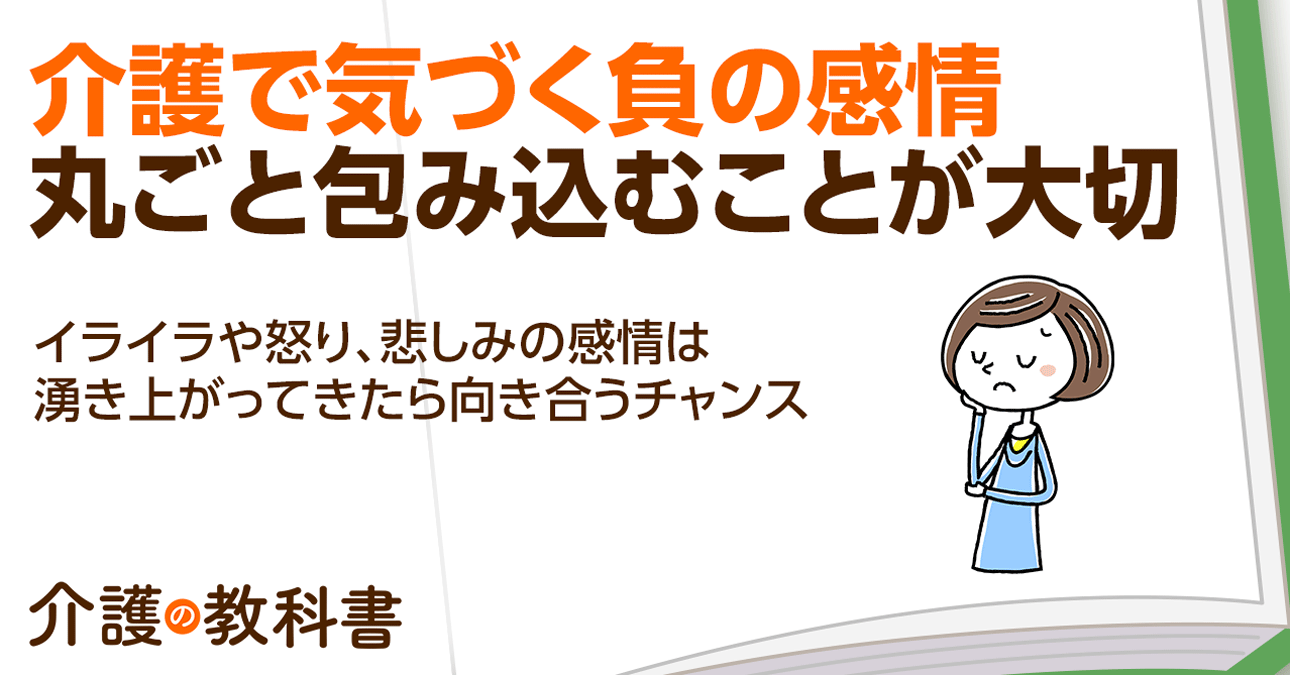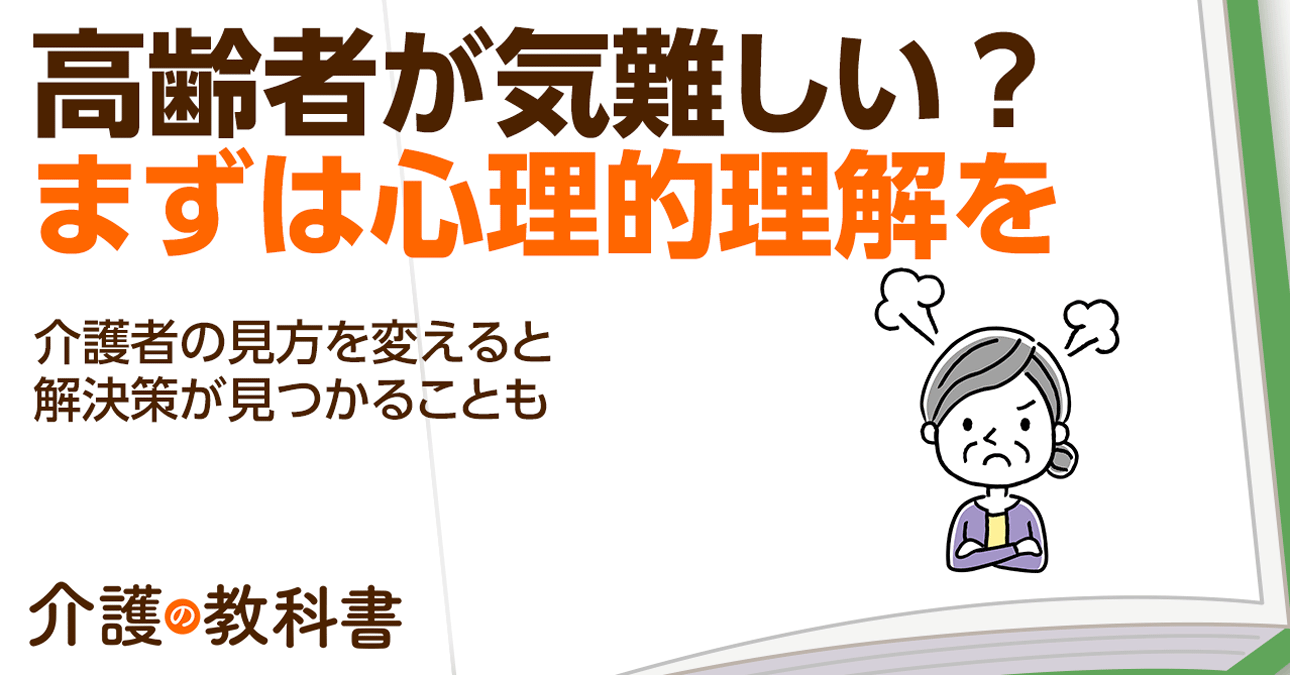在宅介護をしていて、次のような思いをしたことはありませんか?
「イラッとして思わず不機嫌な態度をとってしまった」
「言わなくてもいいことをつい言ってしまった」
「うまくコミュニケーションが取れずストレスが溜まっている…」
今回は介護しているときに感じるイライラや怒りの感情をマネジメントしていくアンガーマネジメントについてお話しします。
アンガーマネジメントとは?
アンガー(anger)とは日本語で「怒り」を指します。アンガーマネジメントとは、マイナスの結果を引き起こしやすい怒りの感情に正しく対処して、健全な人間関係を築く知識や技術のことです。
決して怒りをゼロにする技術ではありません。なぜなら、怒りは生きていくのに不可欠な感情で、なくすことはできないからです。
怒りのプロセス
怒りは以下のような流れによって発生するとされています。
- 出来事に遭遇:何かの出来事があったり、誰かの言動を見たり聞いたりする
- 出来事の意味づけ:その出来事がどういうことなのかを考え、意味づけをする
- 怒りの発生:意味づけの結果、自分が許せないものであれば怒りが発生する
同じ出来事が原因で誰もが怒ることがないように、怒りには個人の価値観が反映されていています。同じ出来事に遭遇しても、その出来事の意味づけによって反応が変わるということです。
アンガーマネジメントの実際
では、アンガーマネジメントはどのように行われるのでしょうか?大きく2つの方向性があります。
行動の修正:怒りのままに行動しないこと
怒りによるマイナスの行動を起こさないように修正していく方法です。
- ストップシンキング
- とっさに余計なことを言わない
- ディレイテクニック
- 怒りを感じたらゆっくりと深呼吸をする
反射的に怒りを表出してしまわないよう気をつける方法だといえるでしょう。
認識の修正:頭の中を怒りにくい仕組みにすること
自分自身の怒りを客観視してよく知ることから始めます。
- スケールテクニック
- 怒りの強さの段階を0から10までで評価する
- アンガーログ
- どういった状況で怒りを感じたかを記録し見える化する
自分の怒りの感情を俯瞰的に捉えることで、冷静に行動するようにしていく方法です。
とはいえ、方法論だけを知っていても実践できないと意味がありません。怒りの感情はとても強いものですから、それを客観的に見つめるということは大変なことです。
しかし、一つひとつ実践することが大切です。まずは「怒りのまま行動しないようにすること」「頭の中を怒りにくい仕組みにすること」が重要なポイントです。そのことを意識することから始めてみましょう。
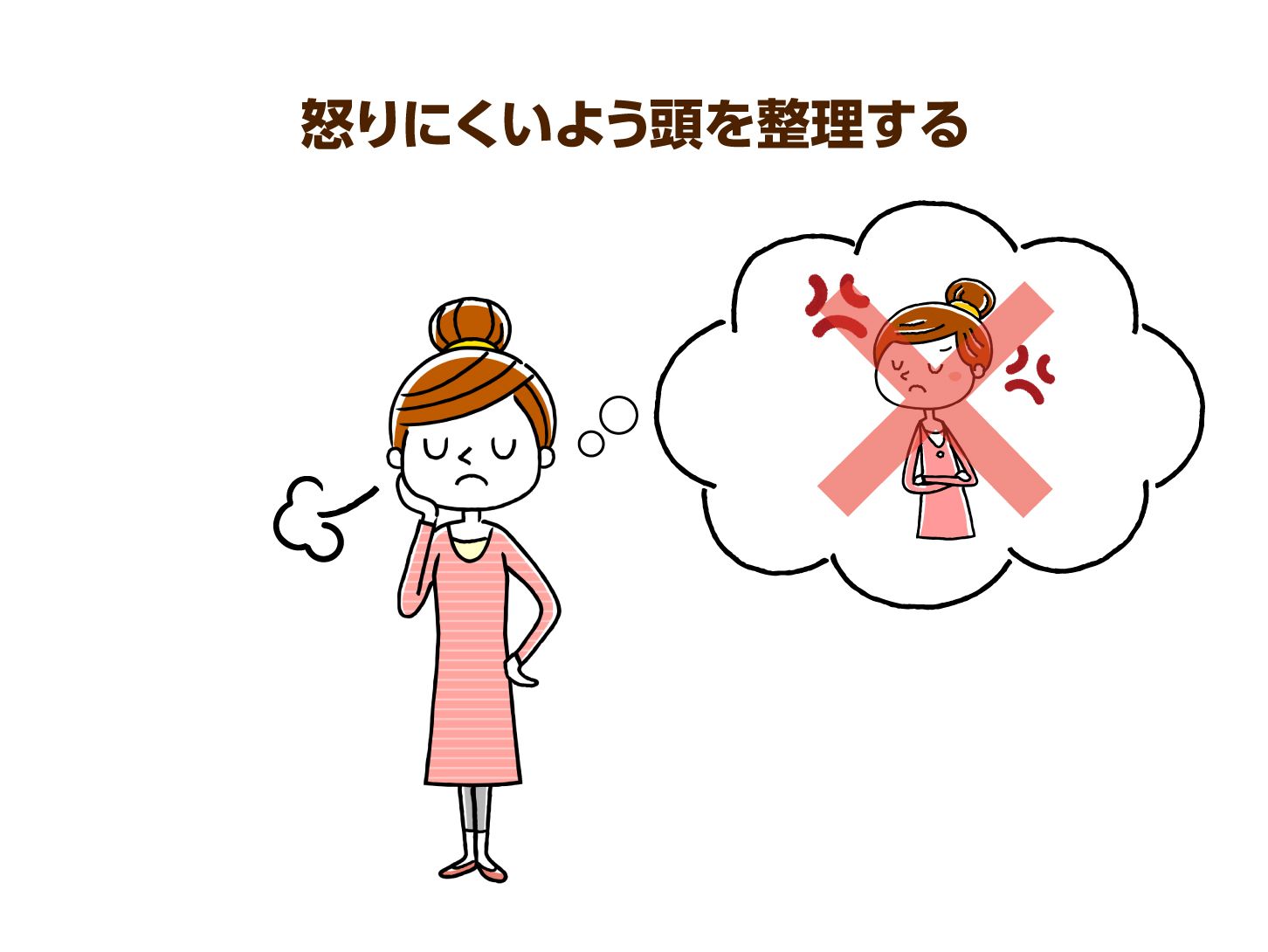
介護者が不機嫌になっていたら「怒り」は発動しやすい
アンガーマネジメントを実践していく中で、介護者自身がそもそも怒りやすい環境になっていないかも確認しておきましょう。
積み重なるストレスや、介護する相手とのコミュニケーション不足は怒りやすい状態を生み出します。
これらを解決するためには以下のような方法が考えられます。
- 休養をしっかりとること
- 息抜きできる環境を整えること
- 介護する相手とのコミュニケーションを密にとること
これらをアンガーマネジメントの土台として生活に取り入れてみてください。何より介護者であるあなたが少しでも楽に介護ができることが重要です。
怒りを悪者と決めつけず、介護生活を豊かにするきっかけに!
介護する相手が配偶者や家族などの近しい関係性の場合、頭では理解しているつもりでも感情が優先されてしまうことがあります。
そんなときは今回のアンガーマネジメントの方法を一つでも試してみてください。「怒り」の感情は悪いものと決めつけるのではなく、これからの介護生活を豊かにするきっかけにしてもらえればと思います。
そのためのポイントは次の2つです。
- 不機嫌でない自分であるための環境づくり
- 自分自身の価値観を客観的にチェック
このポイントを忘れずに、日々の介護生活を少しでも余裕があるものにしていきましょう。