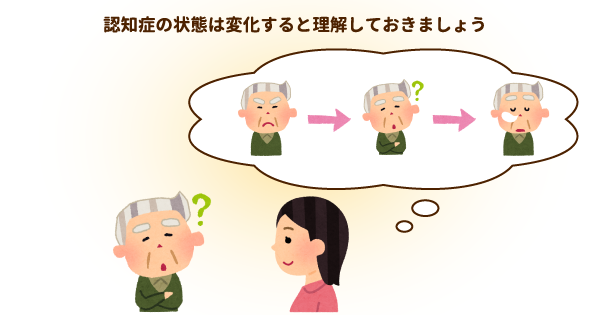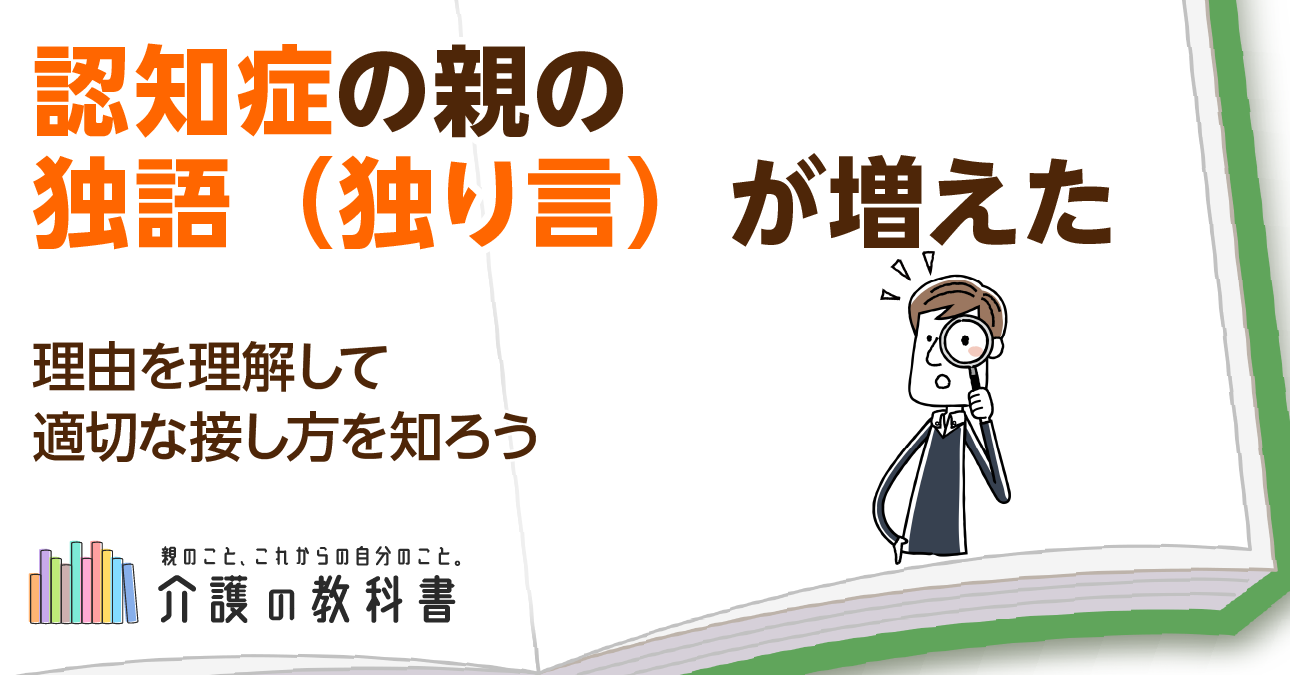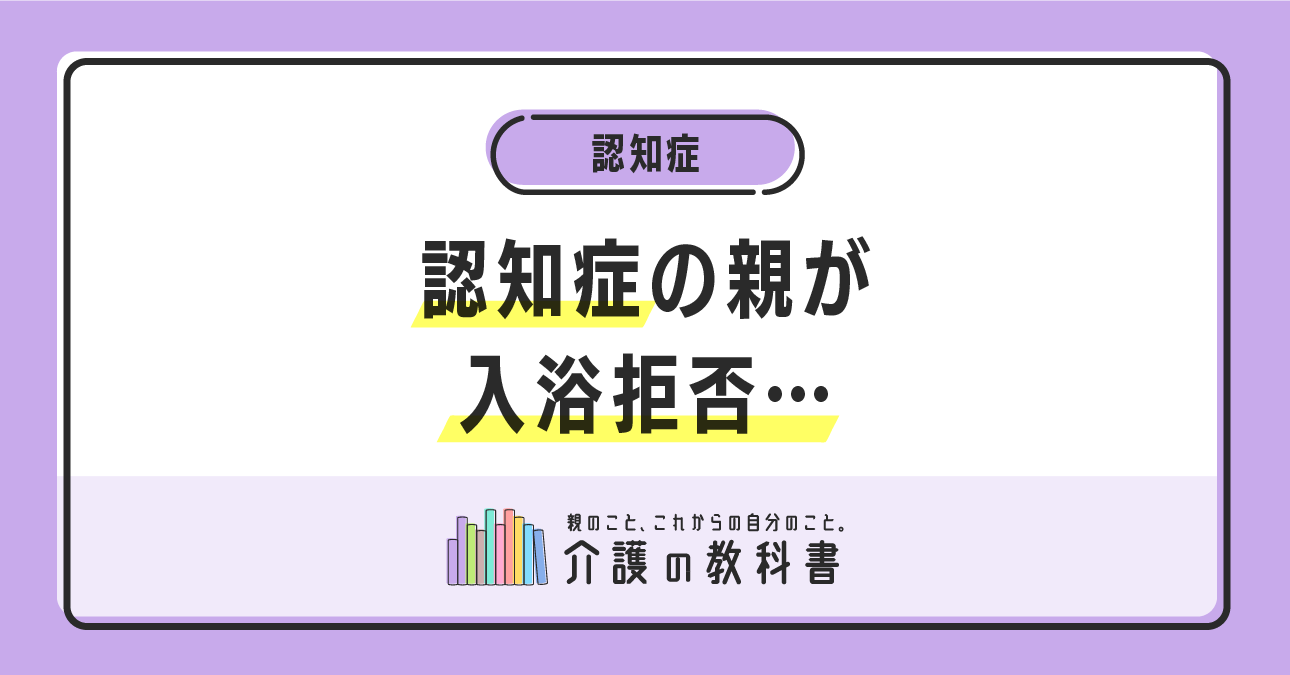庭や家の中の様子を注意深く観察しましょう
庭の様子
まずは庭です。庭の管理は緊急性が低く、広ければ広いほど大変です。コロナ禍前はきちんと整理されていたのに、荒れてしまったのであれば、身体的な不具合を隠していたり、無関心や無頓着になっている可能性があります。
ほかにも、経済的・身体的な理由のほか、フレイル(心身虚弱)や高齢者うつ、認知症が進行中である可能性もあります。
2階や階段・はしごの上にある部屋
階段を上がった先にある部屋の様子にも気を配ってみましょう。
生活上必要でない部屋にほこりがたまっていれば、段差を上るのがきつくなっていたり、生活空間以外への関心が向かなくなっている可能性があります。
単純に「誰も使っていないから」という理由も考えられますが、使用されていない部屋は傷みやすく、換気もされていないことからアレルゲンや家屋の痛みの原因になることもあります。
車とガレージ
運転をよくする親であれば、自家用車の外装やガレージなどにこすり傷やへこみがないか確認しておくと良いでしょう。
ぶつけた跡があったり、こすった傷の上からさらにぶつけていたりするようであれば、空間認識の低下や見落としの慢性化、反射速度の低下などが考えられます。
また、それが修繕されているようであれば車やガレージの劣化を軽減できますが、そのまま放置しているようならもう少し観察した方が良いかもしれません。
問いただすような聞き方をしてしまうと事実を隠されてしまうこともありますので、「ちょっと直しておこうか」「カバーでもつけておこうか」といった提案するような言葉で良いと思います。
まったく関心がなかったり、ぶつけている事実に気づいていない場合は、認知症や高齢者うつといった別の疾患がある可能性もあります。
単身で生活していると気づけない身体的な変化
料理の味付けや好みの変化
料理好きだったのに、コンビニやスーパーの総菜、外食が多くなっていたら気にかけてみてください。
また、味付けが濃くなったり明らかに変化している場合は、何らかの感覚の変化が考えられます。常に一緒にいるとそうした変化は掴みにくいものですが、帰省して久しぶりに会ってこそ違和感に気づける可能性があります。
嗅覚や味覚は、視覚や聴覚と比べると見落とされがちです。目のかすみや耳が遠くなるという症状は自分自身でも気づけますが、味付けなどは他人でなくてはなかなか気がつけないものです。
さらに、これまでとは明らかに異なる偏食がみられるような場合は、何かしらの症状が出始めているか、今後疾患が現れる可能性があります。

むくみの有無や体重の増減
以前会った時より、身体が細くなった感じがする。あるいは体重が増えたように見える。そうした違和感に気づく事も大事です。
また、むくみや息切れが重なっているようであれば、心疾患が疑われるので、主治医に相談したかどうかだけでも確認してみてください。
本人からすれば普段からのことですので「歳だから」という理由だけで済ませているかもしれません。
同様に頻繁にむせたり、胸につかえる、胸やけといった症状がみられたら心不全や肺炎などの可能性が疑われます。
血圧測定器で脈の早さなども確認できればベターですが、他に症状がないときは、数値だけで一喜一憂することのないようにしましょう。
血圧の数値は常に変動しているので、家庭で計測した数値をあまり鵜呑みにしない方が得策です。もし心配なら、親の承諾を得てから主治医に相談すると良いでしょう。
睡眠状態が悪い
睡眠中の様子も可能であれば、チェックしてみてください。
睡眠の深さや寝つきの良し悪しはまだ自覚できますが、寝ているときの状態は本人では気がつきようがありません。
日中にうたた寝を頻繁にしていて、夜眠れないと訴え続ける方もいます。また、イビキとともに呼吸が止まる無呼吸症候群や、激しい寝言や寝相など自覚が困難なものも多くあります。
家族と一緒にいる時間があって初めて発覚する睡眠状況もあるのです。もちろん、寝ずに見張っている必要はありませんが、おかしいと感じることがあれば把握はしておきたいところです。
親の生活態度や行動の変化に気をつけよう
両親の力関係や性格の変化
両親の力関係や性格の変化は、何かしらの精神疾患や認知症の症状が隠れている場合があります。
生活が維持できている場合は慌てる必要はありませんが、喧嘩が頻繁に起きているようなら、近隣の方や地域包括支援センターなどに相談するのも一つの手段です。
「やたら夫(妻)が忘れっぽくて…」と訴えてきた場合、忘れている自覚がある方は、認知症よりも高齢者うつの可能性が高くなります。
また、逆に伴侶の忘れっぽさを指摘している側が「自分が記憶していないことに気づかず相手を責めている」ケースもあります。その場合は、指摘している側に認知症の症状が進行中である可能性が高くなります。
外出の減少
外出が少なくなる理由は、「面倒だから」「おっくうだから」という言葉で片付いてしまうために、疾患が隠れてしまう可能性があります。
決して緊急性が高いわけではありませんが、高齢になってからの引きこもりは心身のレベルが一気に低下するリスクがあります。違和感を抱くレベルであれば、今後の変化の兆しと捉えて、対策を講じておきたいところです。
言葉をよく聞きなおす
会話をしていて、「どういう意味?」「どういうこと?」といった聞き返しが繰り返されるようなら何らかの兆候かもしれません。
難聴ではないのであれば、精神疾患や認知症の症状が隠れている可能性があります。理解力や注意力の低下が聞き直しを誘発していることもあるのです。
とはいえ、親がまだ普通に暮らせているのなら、過度に心配するのではなく、かかりつけ医やかかりつけ薬局などの専門家に相談すると良いでしょう。

このように、親の変化は久しぶりに会うからこそ気づけることがあります。ただし、せっかくの帰省を台無しにしてしまわないためにも、親に対して強く問いただしたり、訂正しようとしたりするのはおすすめしません。
まずは、再会の喜びに浸っていただくことが何を置いても大切なことです。ここで挙げた項目は、あくまで参考程度に考えてください。
何らかの違和感を覚えたのなら、さりげなく観察し、また近々訪れる機会を設けましょう。万が一のため、親の主治医や地域包括支援センターを確認しておくと良いでしょう。