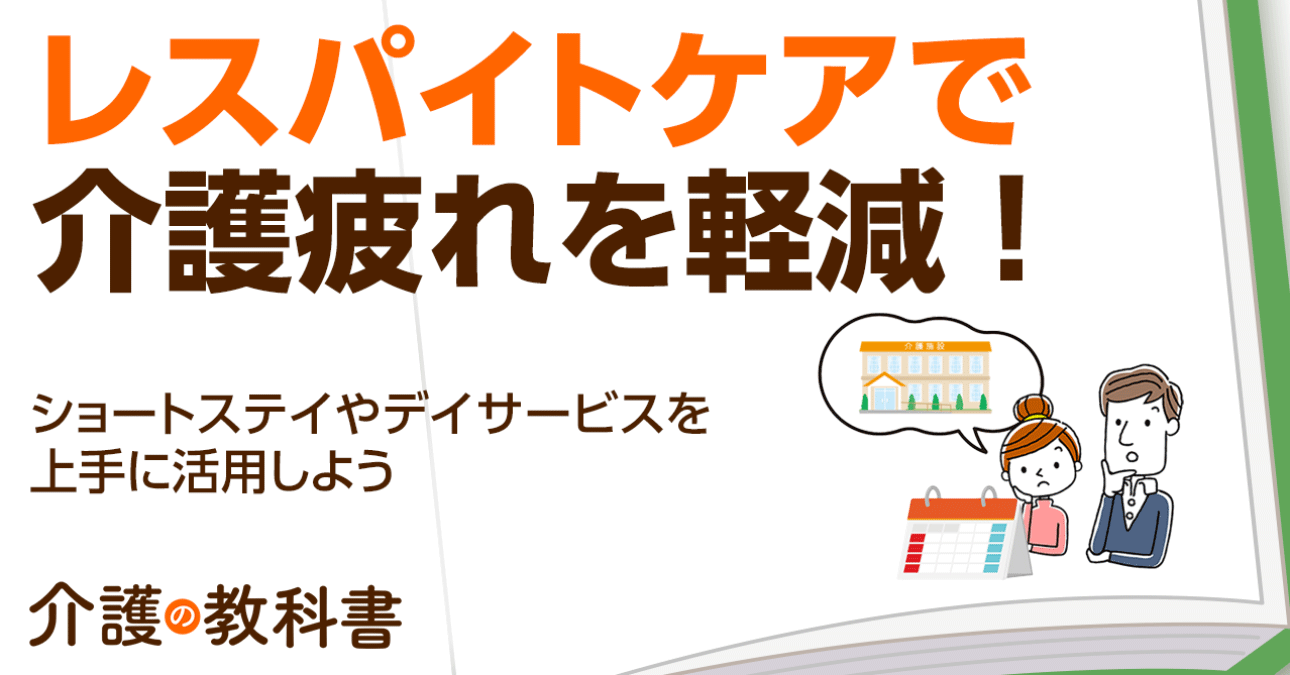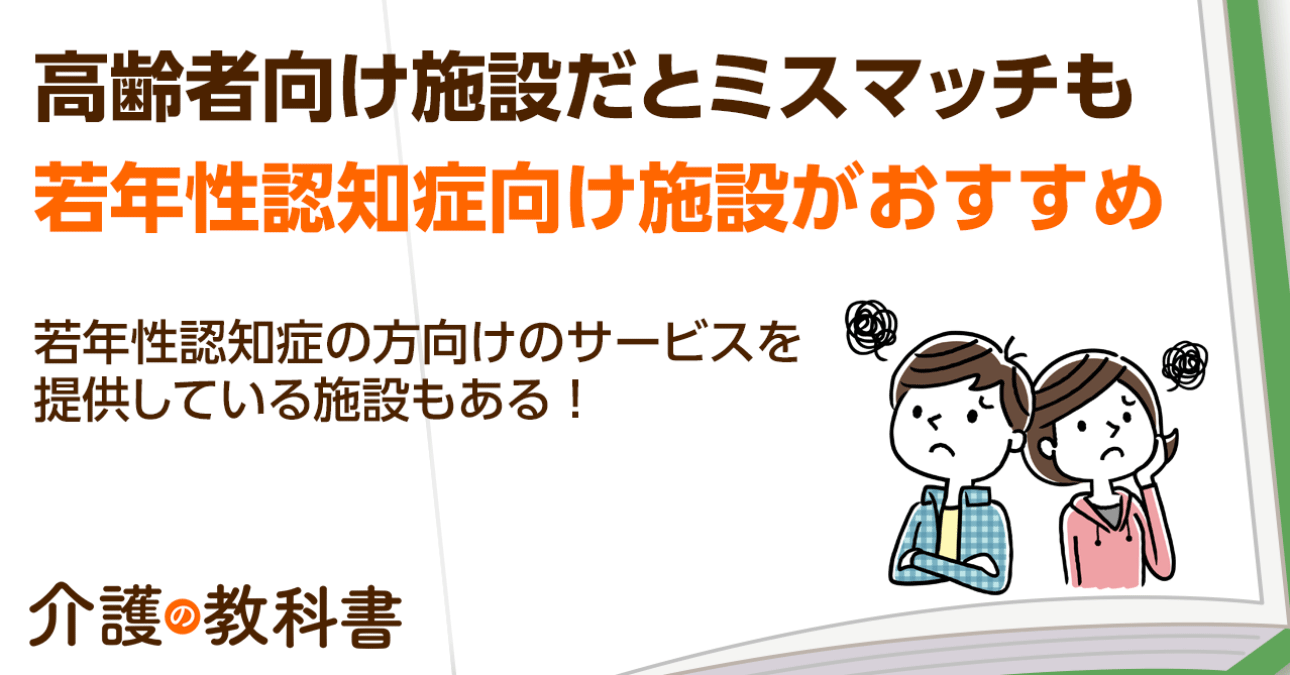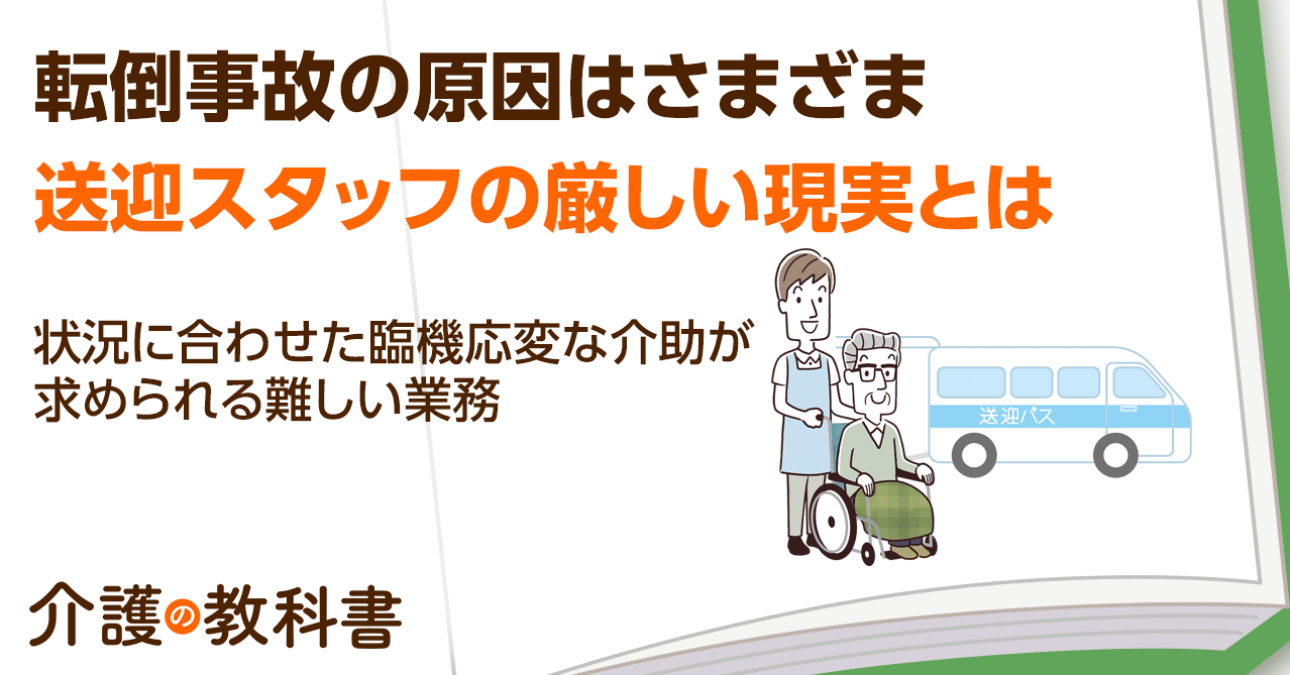終活カウンセラー協会認定講師でジャーナリストの小川朗です。
今回は利用者のクレームにまつわるデイサービスの現場の声を紹介します。
サービス内容に関するクレーム事例
最近増えつつある幼老複合施設の関係者が、利用者からクレームを受けた事例をご紹介します。
【ケース1】
Aさんは「幼稚園に勤めていたから、子どものいる施設が良い」と利用してくれていました。しかし「タバコを吸わせろ」など、徐々に強く要求するようになりました。ほかの利用者とケンカするなど、トラブルが頻発するようになったため「ほかの施設に移動されてはどうか」と提案しました。すると、Aさんの家族は「利用拒否だ」と反発し、区に申し入れました。施設側は区の査察を受ける羽目になり、区は都へも連絡。真相を理解してもらうまで、大変な労力を要しました。
利用者に問題があるケースでも、それを逆手に取って自治体に駆け込むモンスタークレーマー。こうした人たちが介護施設を窮地に追い込むケースは少なくないようです。
次のケースは、デイサービスのドライバーをしている方の体験談です。
【ケース2】
軽度の認知症のあるBさんを高層アパートの4階まで迎えに行っていました。奥さん、娘さんが交代で見送りと出迎えをしてくれて、デイサービスへの定期的なお出かけをとても喜んでいる様子でした。ところがある朝、いつものように迎えに行くと、奥さんが険しい顔で出てきて「おじいさんがかわいそうなので、もう行かせません」と突然のキャンセルになりました。
一体何が起こったのかとケアマネージャーに確認したところ、家でBさんと奥さんとの間に、次のような会話があったそうです。奥さんが「今日、どうだった?」と聞くと「何もしていないよ」との答え。「一日何も?座っているだけ?」と聞き返しても「そうだ」と答えるだけ。Bさんの奥さんはそれを鵜吞みにしてキャンセルしたのですが、もちろんそんなことはありません。連絡ノートにもその日のメニューが書かれていたのですが、それはまったく頭に入っていない様子でした。娘さんはわかっていたようですが、何ともやり切れない気分になりました。
小規模デイサービス施設では、こうしたキャンセルも大きなダメージになるはずです。

金銭トラブルの事例
また、金銭を巡るトラブルも、少なくないようです。
【ケース3】
Cさんは、認知症を患い、夜な夜な徘徊する症状がありましたが、本来は温厚で子ども好き。あまり手がかからない利用者でした。奥さんも施設を気に入っていて、大変にありがたがってくれていました。ところが、Cさんが心臓の病で突然亡くなられてしまいました。施設からは数人のスタッフがお通夜にも行きましたが、請求は少し時間を置くことになりました。落ち着いた頃を見計らって、請求書を持参すると、次男が「遅いので払えない」と強硬に主張。押し問答が続いた末、ようやく精算してもらったものの、余計な時間がかかり、後味の悪さも残りました。
【ケース4】
サービス利用終了に伴い、早めに精算の請求書を届けたんです。すると両親の年金で生活しながらDさん(母)の介護をしていた一人娘が突然怒り出して「昼食代が高過ぎる」「まずい」などと猛クレーム。Dさんを家に送り届けても留守が多く、その都度施設に戻って、改めて家に送ることになりました。そのときは娘さんにも感謝されたこともありましたが…。実はこの方、近所ではDさんへのDVで有名でした。後日、成年後見人を立てられ、しばらくしてから精算がありましたが、反論せずにじっと待ち続けるのも、辛いものがありましたね。
クレームやトラブルが発生する原因と対策
トラブルの原因として、家族がサービスの提供範囲を理解していないことや、サービスに過剰な期待をしているとの指摘も一部あります。一方で、事業所側のサービス内容の説明不足が原因で、利用者側の理解不足を招いているとの声もあります。
【ケース1】のように煙草を吸い、暴力を振るうなどのケースは、決して珍しいケースではありません。西東京の某市で居宅・訪問の介護事業所で代表を務めるEさんは、「こうしたケースは、良くありますね」と現状を明かしたうえで、講じている対策を話してくれました。
では、問題を起こす人への対応はどうしているのでしょうか。
想定されるあらゆる事態に備え、しっかり聞き取りを終えることが重要です。解決策として、「事業者側が利用者や家族などとの信頼関係を築くことが第一」との意見もありますが、利用者側の置かれた環境や、抱えている問題も千差万別です。まずはハラスメントを受けたと感じた時点で、すぐに先輩職員などと情報を共有し、迅速な対応を取ることが、トラブルを拡大させない選択肢のひとつといえるのではないでしょうか。

今回、介護の最前線で、利用者からのクレームにさらされ続けるスタッフの声を聞くことができました。その中で印象的だったのは「地域包括ケアシステム? 環境の整備はまだまだ進んでいません」という声が多数を占めたことです。
厚労省が「地域包括ケアシステム」の構築を目指す2025年まで3年あまりとなりました。小規模事業所の撤退や人員不足の裏にあるのは、クレーム対応に関する情報提供を含めた、行政側のサポート不足です。
さらに、これに拍車をかけるのが労働環境の過酷さと賃金の低さにあります。岸田政権は介護人材への賃金アップを掲げましたが、これだけでは不十分なことは明らかです。
クレーム対策などを含めた抜本的な待遇改善策に本腰を入れて取り組まない限り、地域包括ケアシステムは準備が整わないまま、タイムリミットを迎えることになりそうです。