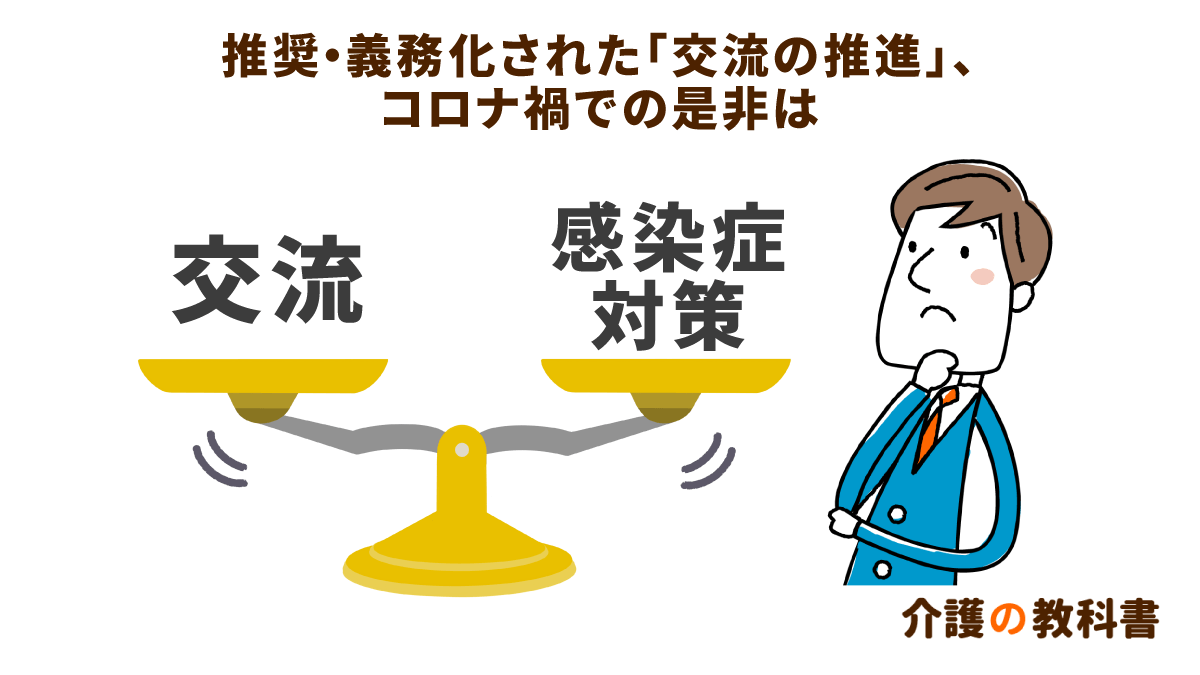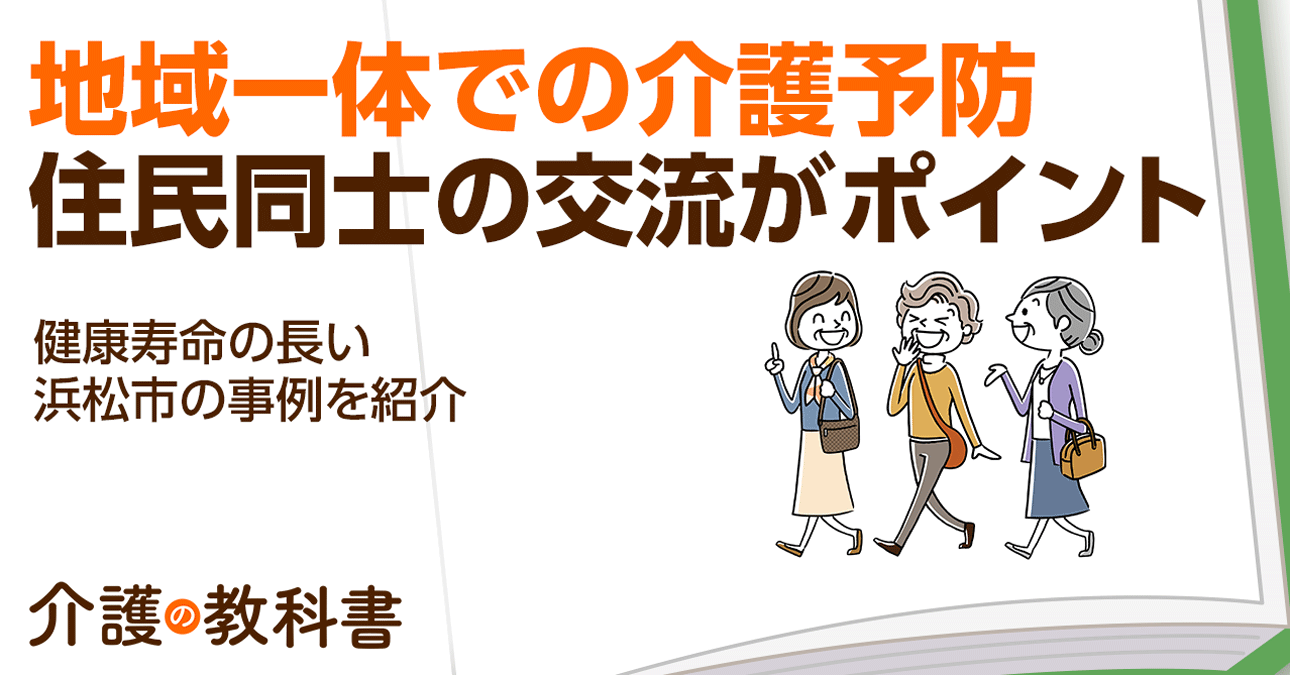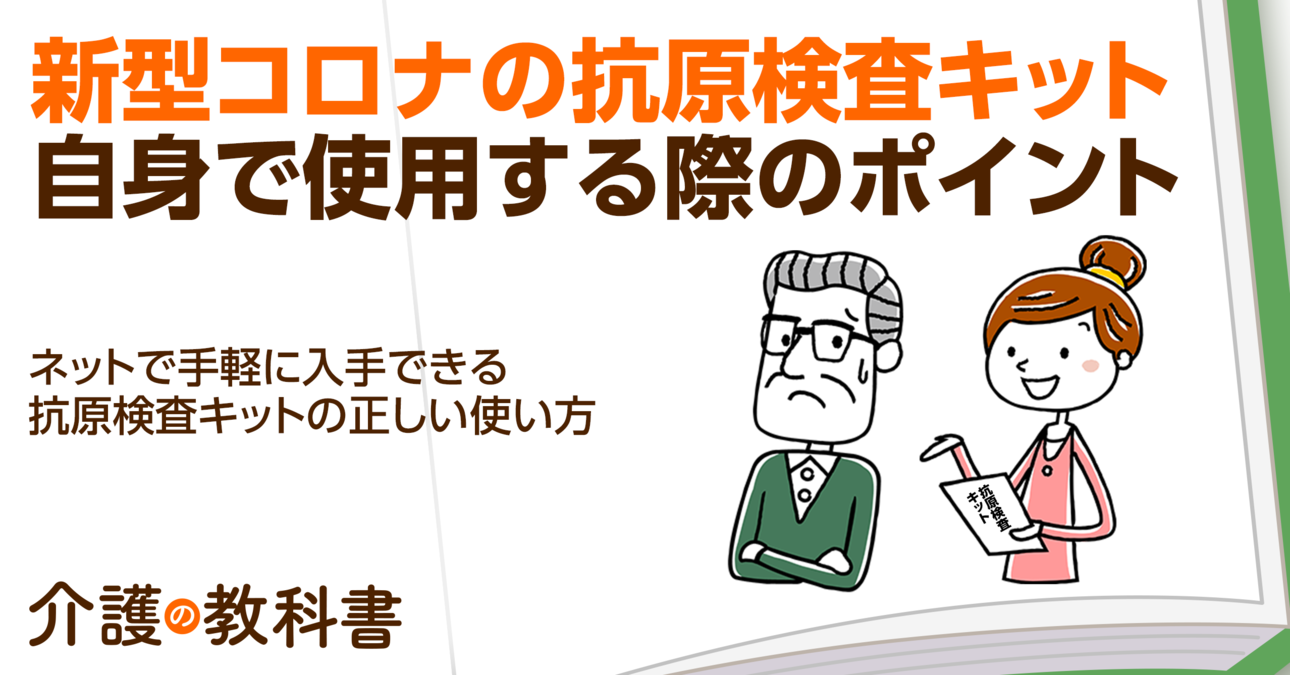皆さんこんにちは。株式会社てづくり介護代表取締役の高木亨です。
コロナ禍以前は当然だったことが、今では考えつかないようなことが多々あります。マスクにしても、コロナ禍以前は「マスクを外すのが礼儀」と言われていたものです。しかし、現在はマスクを着用したままのあいさつこそが礼儀となりました。今では素顔を見たことがない方さえいらっしゃいます。
こうした変化は当然、高齢者との交流にも大きな影響を与えました。介護事業者には「交流の推進」が推奨・義務化されており、思わぬ負担となっています。今回は、この問題についてお話させていただきます。
義務づけられた「交流の推進」、コロナ禍での在り方は
そもそも高齢者にとって地域交流や世代間交流は、認知症の予防やロコモティブシンドローム(加齢による筋力低下や、関節・脊椎の病気、骨粗しょう症などで運動機能が衰え、要介護状態や寝たきりになってしまったり、そのリスクが高い状態)の予防などの効果があると考えられています。さらには、数年後の死亡率の低下に至るまでポジティブな影響があることなどのさまざまなメリットが示されてきました。
そうした研究結果や考え方に基づき、各介護施設・事業所などでは各種交流の推奨や義務づけられてきました。しかし、この流れは新型コロナの感染拡大をきっかけに方針転換を余儀なくされました。交流はおろか、部外者の排除・徹底的な制限などが指示され、「行わなければならない」とされてきた交流事業が「してはいけない」レベルにまで激変したのです。
一方で、交流の大切さについては取り下げられることなく残されたままです。その代表的な例として、2021年の報酬改定では「地域密着型通所介護事業所だけでなく、通常規模以上の通所介護事業所にも利用者の地域における社会参加活動や地域住民との交流を促進する観点から、地域住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない」として義務付けられました。
既定路線で改定の内容が決まっていたとはいえ、出されたタイミングは最悪と言えましょう。時期的にはコロナ第4波が襲いかかりつつあったタイミングで三密回避の徹底、不要不急の外出を避けるよう推奨され、人流の低下を叫んでいた頃でした。
いわゆるダブルスタンダードと言えますが、コロナ禍の中でうやむやにされた感じすらします。結局どうすることが正しいのか具体的な指示は今もありません。クラスターが発生しようものなら、そのマイナス影響は測り知れないものがあるにもかかわらず、保証についてはまったく触れられていないのです。「各事業所毎に十分に気をつけつつ、交流には努めるように」という中途半端な内容になってしまっています。
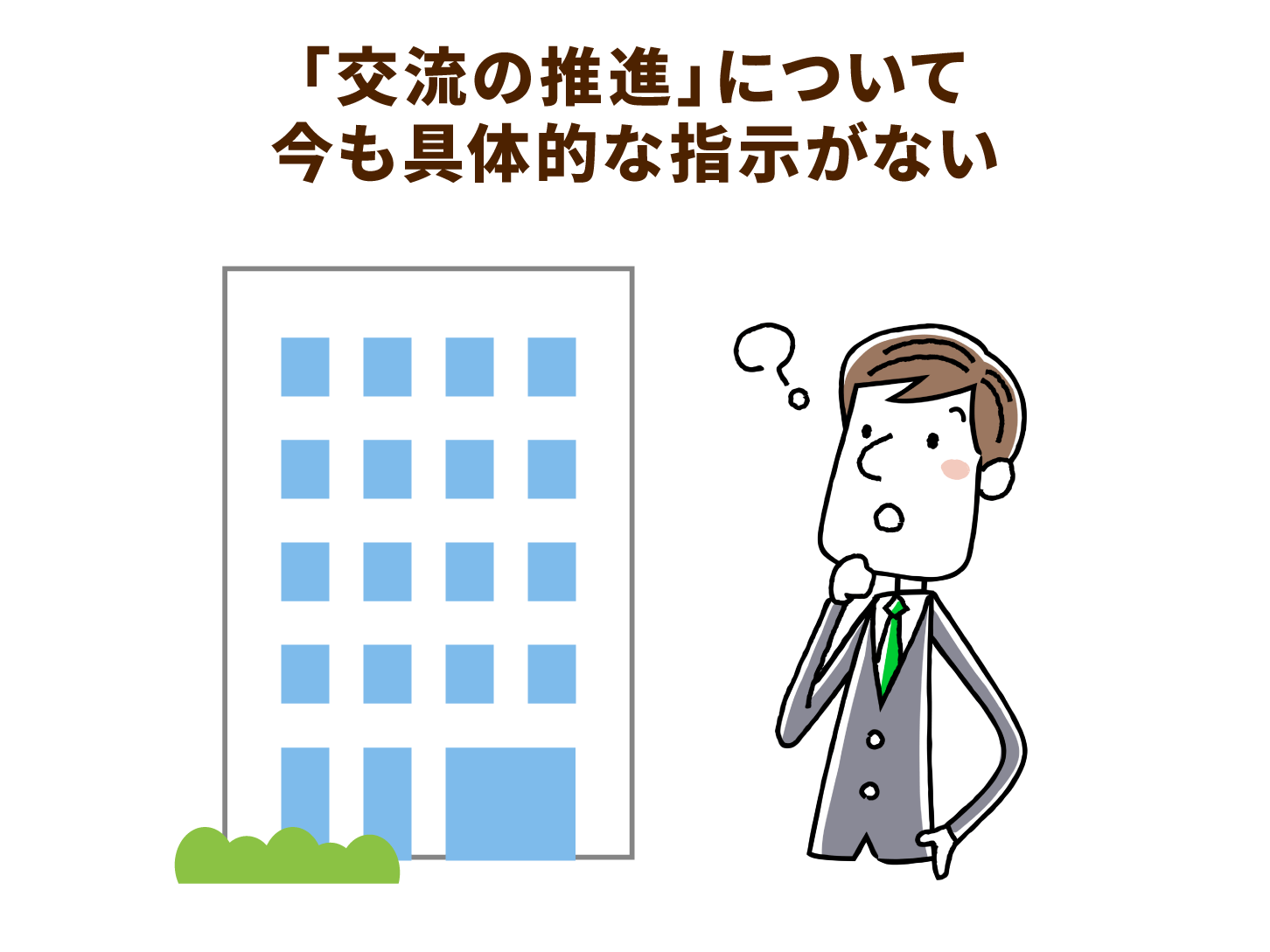
曖昧な介護報酬の評価は改善が必要
介護事業に限った話ではなく、我が国の社会保障制度そのものについて「お願いベース」で対策が取られています。それらは政策などではなく、単に国民の努力だとも言えそうです。「自粛と補償は別」という見解について各方面でも議論されましたが、「被害が出ても責任は持てませんが、交流はするように頑張ってください」という姿勢はなかなか理解を得にくいのではないでしょうか。
こうしたダブルスタンダードの指示が公然と出されてしまう背景には優先順位付けがそもそも間違ってしまっているように感じます。
生命、社会、経済…どれも大切であり重要ですが、緊急性が高いのは、やはり生命でしょう。生命を守るためには、ほかの大切なものを削る作業が必要になることもあります。地域交流や世代間交流は、ケアの優先度としては低くなり、災害時は除外されざるを得ません。
不要とは何が不要で、不急とは何を以て不急なのか具体的な線引きはされてこないまま、「社会的許容度」に任せて「感染防止に努めながら積極的に交流を」という曖昧な表現と基準を続けていては、何をもって良いケアと呼ぶのかもわかりません。
もちろん、「コロナ禍だから交流はできない」という消極的な介護事業者は少ないでしょう。コロナ禍以前のような触れ合いを通じた交流はまだしばらくは難しいでしょうが、さまざまな対策や工夫を講じ、交流に努めていることと思います。
そうした取り組みによってリモート形式やタブレット端末を用いるなど、画期的な交流方法も生まれています。無茶なダブルスタンダードを両立させるべく、前例のない発想・工夫や努力を絞り出し続けて最前線で頑張っている介護従事者の方々には頭が上がりません。国としては、実のある正しい評価を切に望みます。