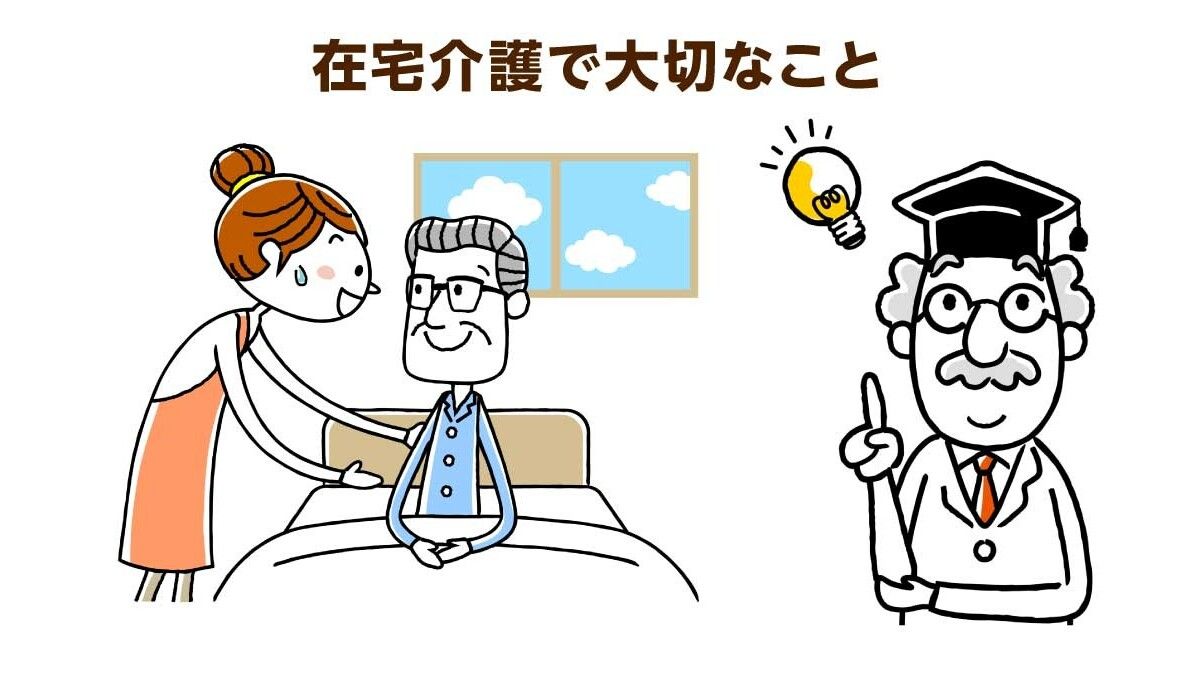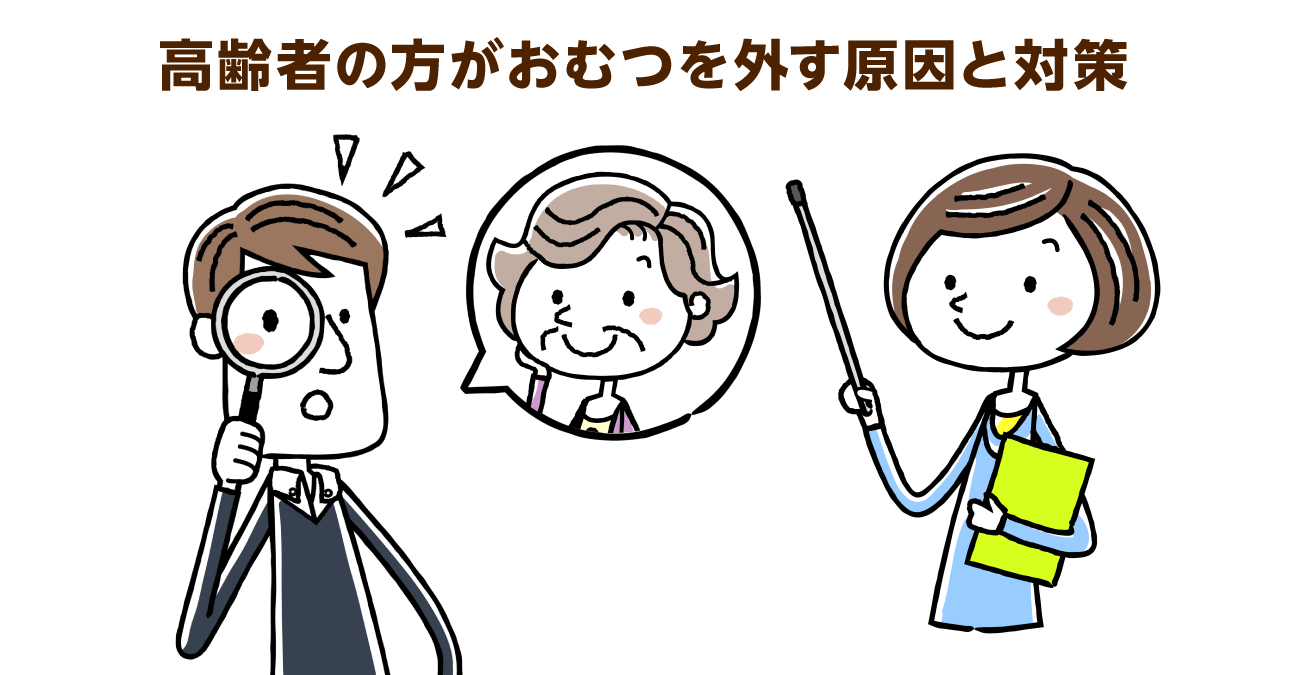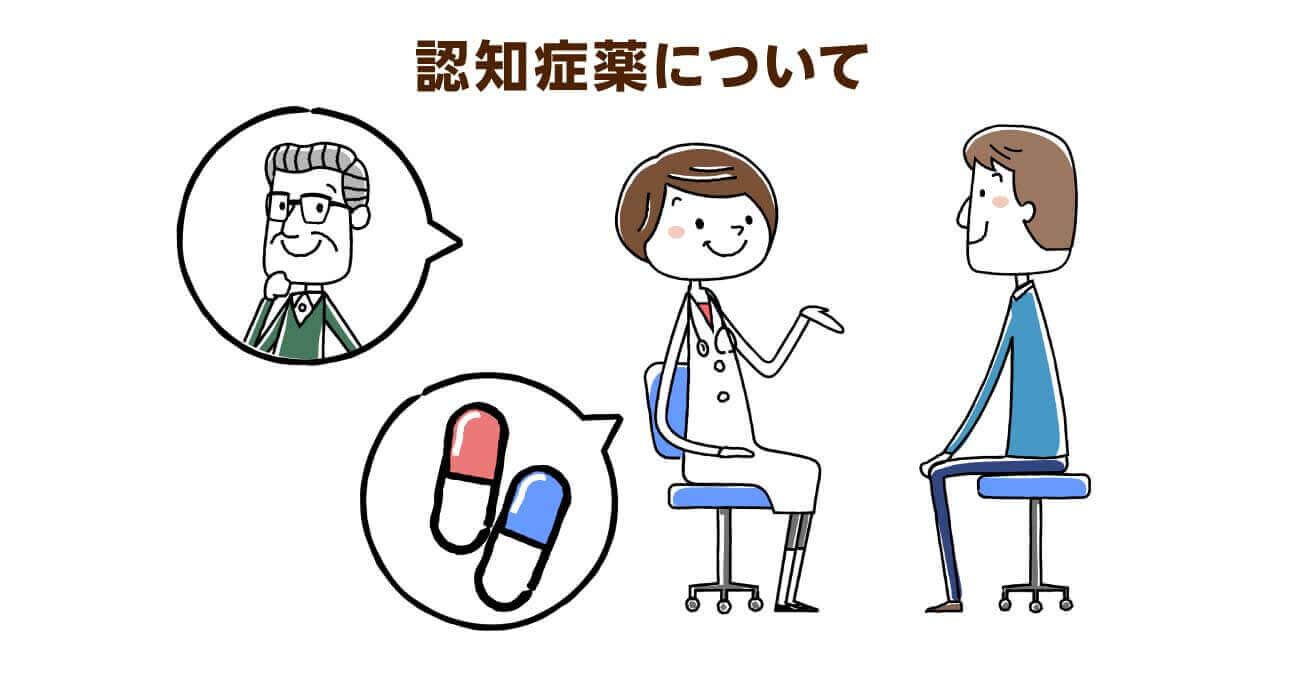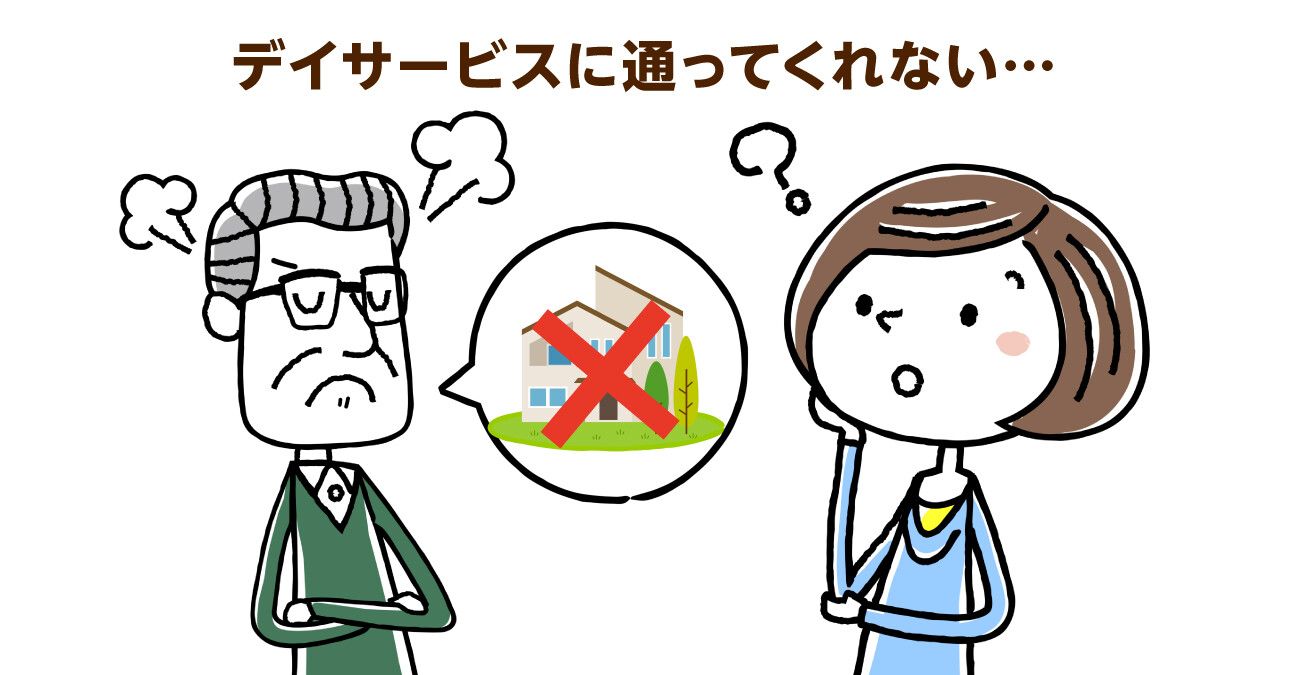皆さんこんにちは。株式会社てづくり介護代表取締役の高木亨です。今回は、在宅介護をする際に大切なことについてお話していきます。
在宅介護で「つらい…」とお感じになられている方に、特に伝えておきたいことは3つです。
- 完璧を目指さない
- 距離を取る
- 1人で介護にあたらない
介護者は被介護者の人生も背負っている状況です。かつて「介護は家族がするもの」という時代が確かにありました。しかし、現代では介護の環境や条件も変わり、社会的許容度にも変化がありました。
平均寿命が延びていることもそうですが、こと高齢者介護においては「平均余命(その年齢まで生きた方があと何年くらい生きるかの期待値)」で考える必要があります。その観点からみると、被介護者の寿命が100歳を越えていたとしても、それほど珍しくありません。
今現在、在宅で介護にあたっておられる方々は、「現代の介護」を意識し「介護がつらいのは当たり前」などと軽々と片付けないでいただければと思います。
完璧を目指さない
決して介護を甘くみた訳ではないでしょうが、「在宅で介護を行う」と選択された方が陥りやすい傾向として、以下があります。
- しっかりと介護しなければ
- ちゃんと面倒を見なければ
- なんとかしなければ
特徴として、語尾に「しなければならない」「しなくてはいけない」といった「義務づけ」がみられます。もちろんそれは立派なことですが、介護は「対人援助」なので、決して思った通りにならないものなのです。
また、「自分が頑張らなければ」という思い込みには大きな落とし穴があります。それは、「自分(だけ)が頑張れば良い」「自分(だけ)が頑張れば済む」という事態に陥りやすいということです。
実際には「自分だけが頑張れば良い」ということはあり得ません。介護は「対人」ですから必ず「相手」が存在します。この「相手」が常に協力的であるならば、介護はそもそも問題にはなりません。また、「介護者が頑張った結果、状態や状況が良くなる」ということも、高齢者介護の場合はほとんどありません。「あちらを立てればこちらが立たず」となる場合や、悪化することもあるくらいです。
実は能力的に優秀な方が、介護の負担を一人で背負ってしまう傾向にあります。さまざまなことができるが故に介護においても高得点を狙ってしまう傾向が強いというわけですね。在宅で介護を行う場合は及第点を狙う考え方をお勧めします。「赤点でなければいい」くらいの気持ちのうえでの余裕やゆとりを持つことが大切です。
特に、被介護者の言動からくる介護者の精神的な負担は介護者に重くのしかかってきます。一生懸命取り組んでいる中で辛らつな言葉や反論、抵抗などが押し寄せてくることが考えられるのです。
一方で、感謝やねぎらいの言葉が精神的な足かせとなることもあります。意識して余裕を持たないと、あっという間に介護うつやノイローゼに陥ります。しかも多くの場合、介護者本人はこの状態に陥っていることに気がつくことはありません。常に経済的・身体的・心理的な余裕を保っているかを意識してください。

物理的・時間的・心理的に距離を取る
介護を困難にしている原因の1つに、被介護者との物理的・時間的・心理的距離を取りづらいことが挙げられます。
例えば、私たちのような介護従事者はある一定の決められた時間内だからこそ、「良いケア」に努めているのであって、休むことなく延々と介護にあたっている訳ではありません。限られた時間に集中してこそ「良いケア」がはじめて実行できます。
在宅介護者も意識して、それぞれの「距離」をとれる状況の確保に努めてください。誰かにお願いしたり頼むことに抵抗があるかもしれません。しかし、自分自身の時間をつくることは介護における基本であり、義務と位置づけるべきです。「そんなことはもっと大変な状況になったら考えよう」と思われるかもしれませんが、経験上そうなってからでは手遅れだと断言できます。
被介護者は介護者であるあなた以外に手を掛けられることを嫌がるかもしれません。しかし、介護者が倒れたり、心身が病んでしまってはより不幸な結果を招きます。「まだ大丈夫」と思っている状況が続くことは、すでに大丈夫とは言えません。他人から見た視点が欠けていますし、「どうなったら大丈夫ではないのか」「どこの誰に助けを求めるのか」の基準が見えていないからです。
「今まで大丈夫だったから明日も大丈夫」とならないのが介護です。極端な話、明日から24時間眠れない状況になるかもしれません。そうなってしまったら、介護につきっきりの生活となります。
心理的距離の置き方としては、介護の場合は視点を変える方法があります。親子や嫁姑以外の関係性、男同士・女同士・男女、郷土の違いや育ちの違いなどをあえて意識して他人の感覚を取り入れるようにします。
心理的距離がずっと近いままですと、良かれと思ってしたことが裏目に出てしまう場合が多くなります。「これほど思っている」「大切にしているから良いことだ」と決めつけてしまうのです。
多くの場合、善意からの押し付けほど断わりづらく煩わしくなります。常に物理的・時間的・心理的距離の確保を意識してください。どれかが欠けているようであればもはや介護者だけでどうにかできる状況にはない、とお考えになった方が良いでしょう。

1人で介護にあたらない
介護の注意点において、特に重要なこととして「ワンオペ(1人ですべての仕事をこなす状況)」にならないことが挙げられます。
できれば周囲の家族や親族、近隣に協力を仰ぎましょう。難しいようであれば各種相談窓口を通じて介護サービスの利用を視野に入れてみましょう。とにかく多いのが、「周囲に迷惑を掛けられない」との思いから「1人でなんとかしなければ」と抱え込んでしまうケース。救いを求めるタイミングを失うと相談するハードルは高くなっていきます。コミュニケーションは介護の基本です。「相談(愚痴も含みます)も介護」とお考えください。

被介護者には「介護者」という人格で接すること
さて、介護の理想は多数の人間で当たることですが、在宅介護では「私(介護者)以外に介護人はいない」という場面は多くなります。そんな状況であっても「自分ではない誰かだったらどう介護にあたるか」をイメージしておくことが大切です。私はよく「役を演じる」という表現を使っていますが、私たちはそもそも意識するしないにかかわらず、時と場に応じて態度や行動を変えています。
介護においては、「介護の役割」を持った自分を意識すると良いでしょう。「自分自身に他人の視点を加える」という考え方です。そして役割を演じたら、しっかりとその役を「降りた」と思える瞬間をつくることが大切です。
素のままの自分で介護することは、丸腰で仕事に挑むようなものです。あっという間に感情にのまれ、通常では考えられない虐待行為や事件・事故を起こしてしまうことや、セルフネグレクト(自分自身へ虐待)に陥ってしまうことも、珍しくはありません。
感情を整理すること
比較的、介護がうまくいっていると「介護者はこれくらいで弱音を吐かない」だとか、「施設にいれることはしない」などと本来の素の自分を見失しない、固執してしまいます。毎日、衣類を交換するように、気持ちも着替えるイメージを持つようになさってください。
愚痴を声に出して呟いてみたり、日記に書き留めたり、録音・録画するなどして自身の気持ちや心理状態を客観視して、整理できるようにしておくと良いでしょう。繰り返しになりますが「まだ大丈夫」は「もう危ない」と思ってください。「今はこういう状況です」と打ち明けられる相手と状況を常につくりましょう。
月並みですが、以下については積極的に確保・調べるようにしてください。
- 素の自分をさらせる時間と場所はあるか
- 各種サービスに委ねられる部分はないか
- 気軽に相談できる人はいるか
- どこにどんな支援があるか
頑張る、という言葉は便利です。しかし、休息や息抜きなくして頑張り続けることは決して美徳ではありません。頑張れないときにどうするかを考えることも重要なことです。手を抜くことや休息をとることは介護においては非常に難しい課題となります。なかには離れることすらできかねるケースもあることでしょう。
しかし、介護をし続けるということは、「世間で認識されていること以上に、自分自身を壊しかねない難作業である」と意識し、ご自身の生活を確保することを忘れないでいただきたく思います。