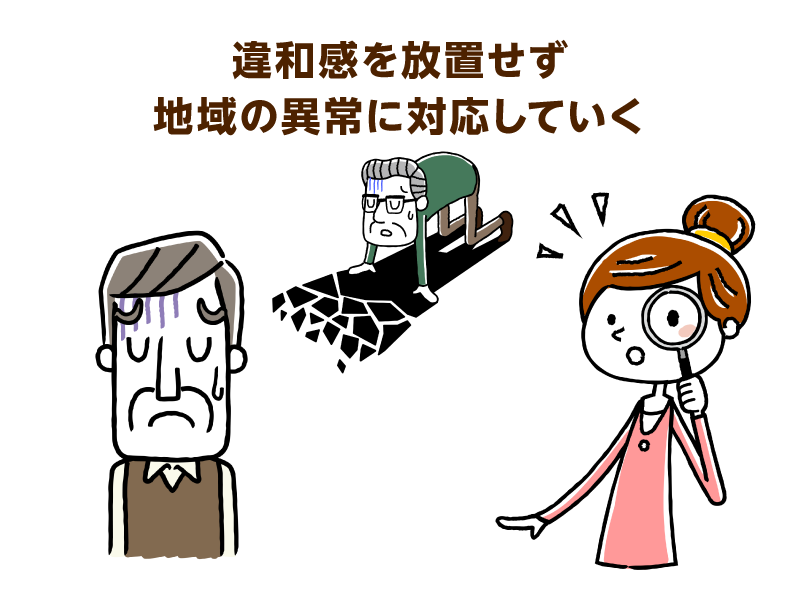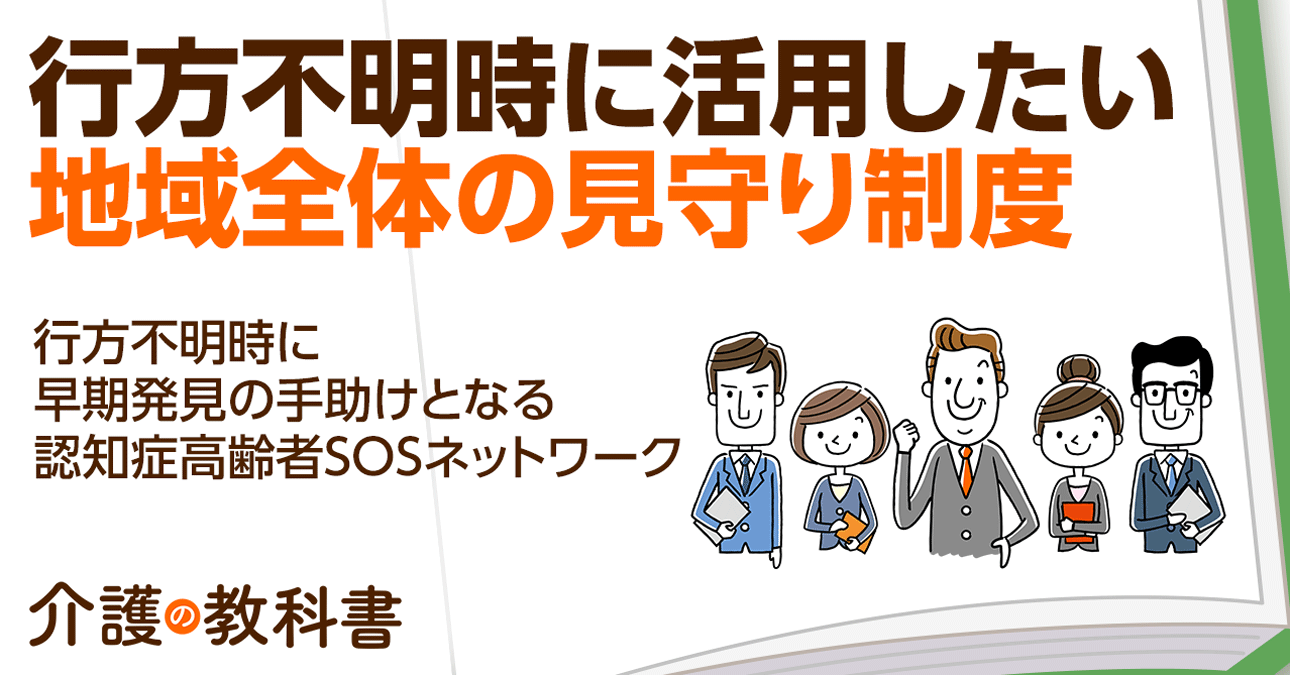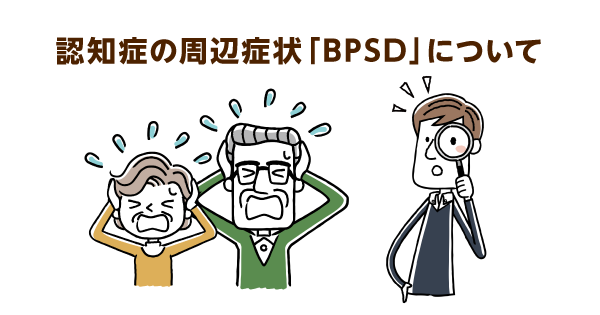こんにちは。千葉県の房総地域の地域包括支援センターで社会福祉士として勤務する藤野雅一です。今回は、「認知症徘徊模擬訓練」についてお話します。
高齢者を守る!「認知症徘徊模擬訓練」
私が勤める包括支援センターでは、2019年11月に「認知症徘徊模擬訓練」を行う予定でしたが、台風15号の影響で中止となってしまいました。また、2018年度下半期から認知症に関する相談が急増加しました。
認知症に関する相談の内容
- 認知症の症状が原因で「高額な布団を買わされる」という消費者被害に合った
- 認知症の方が毎日のように銀行に来て、銀行員の業務に支障が出ている
- 認知症の夫が妻に暴力を振るう
- 徘徊中に踏切内に入る
- 認知症状が急激に悪化したことが原因で、介護施設を抜け出した利用者がいる
- 急に落ち着きがなくなり、工具や縄を持って地域を歩き回っている
毎日のように、認知症に関する相談を受けました。
踏切内に立ち入ってしまうケースに関しては、地域の警察や区長、民生委員、福祉事業者、郵便局や金融機関関係者にも集まっていただき、対応策を検討してきました。
また、典型的なアルツハイマーのほかに、幻視や幻聴を伴うレビー小体型認知症や暴力が顕在化しやすいピック病と思われる対象者に関する相談、アルコール性認知症が疑われる方に関する相談などの相談もたくさんいただきました。
「私たちの地域で今、何が起こっているのか」ということをテーマに、「地域ケア推進会議」を各地で開催し、地域をあげて高齢者虐待や消費者詐欺被害などから高齢者を守っていく体制作りに注力しています。
徘徊が発生した際には、警察署や地元の郵便局と連携して、徘徊者を目撃した郵便配達員に画像を送信してもらうなどして、徘徊を早期終結できるような策を検討しています。この取り組みに関しては、認知症の方の徘徊が夕方や深夜、早朝に偏っていることから、郵便局員の就労時間と大きくかけ離れてしまうことやプライバシーの関係で、実現はかないませんでした。そこで、今度は「オレンジリングでつなぐ地域の輪」というテーマを掲げ、「認知症サポーター養成講座」を積極的に展開しました。2019年度は10回開催し、400名近い方に受講していただきました。
「徘徊が発生した際に誰かが気づける地域づくり」を行っています。フラフラとあてどなく歩いているような方を見て違和感を覚えたとき、そのままにするのではなく「誰かにつないでいく」ことを住民全体が意識していけたら良いなと思います。
また、「認知症サポーター養成講座」は小中高生などにも受講してもらっています。若い世代にも地域の課題を知ってもらうことで認知症の問題がさらに顕在化するとされている将来に向けての布石にしたいと考えています。このような取り組みは、現在も継続しています。
「認知症サポーター養成講座」を受講した方には、認知症を支援する目印となる「オレンジリング」を配布します。「認知症サポーター養成講座」開催後には、報告書を作成し、回覧板を活用して地域の皆さんに閲覧してもらっています。

人間防犯カメラが地域を救う!
一連の活動の集大成として企画したのが、「認知症徘徊模擬訓練」です。文字通り、認知症徘徊が発生したときに備えて模擬訓練を行います。徘徊者を防災無線の情報などをもとに探し、通報する訓練です。地域の方に「人間防犯カメラ」となっていただき、地域課題の解決に取り組むというものです。
以下に企画書の一部を掲載します。
エンタメ要素も取り入れた「認知症徘徊模擬訓練」の企画
企画の意義は、認知症徘徊について当事者や家族だけの問題とせずに、地域の課題として住民に当事者意識を持ってもらうこと。認知症に関心を持ってもらえるように、エンターティメントの要素を取り入れ、地域にアピールしていきたい。徘徊模擬訓練をより多くの住民に体験してもらうため、広報に工夫が必要だと考える。
また、「毎年同じ人しか訓練に参加していない」との声も上がっているため、訓練に参加する住民だけでなく、地域住民全体を巻き込むような訓練としたい。徘徊対象者を発見した際の通報について、積極的に対応し、具体的な声かけの方法や通報の訓練をレクチャーする場を提供する。行政が登録者に向けて発信する、防災無線や安全安心メールを活用し、どの程度住民へ情報が伝わっているのか把握するための社会実験的な要素ももたせる。
通報が少なかった場合には、住民の徘徊に対する認識が低いとも分析できるので地域課題としていく。徘徊役には防災無線などにより、徘徊情報が流れる前から地域を歩きまわってもらう。リアルタイムの情報だけでなく「そう言えばそんな人があの時間あのあたりにいた…」といった記憶想起の情報を提供してもらうための仕掛けである。日頃から違和感を感じた際には、その状況を記憶して必要時に情報提供できる地域にしていきたい。
違和感をそのままにせず、記憶に残し、地域の異常に対応していくことや、声かけを積極的におこなってもらうことも訓練の目的の1つである。

地域住民の当事者意識を高めることが重要
地域住民全員が気軽に参加できるような実施方法や、遊びの要素を取り込む工夫を行い、認知症に関心がない方も巻き込んでいきたいと考えています。
より多くの地域住民に訓練に参加してもらうために、数ヵ月前から「〇〇を探せ!認知症徘徊模擬訓練!」といったポスターを張り出します。「ウォーリーを探せ!」のようなイメージです。
社会福祉に関する地域課題を意識する層は、当事者周辺にとどまってしまう傾向があります。しかし、それでは一向に地域課題は解決できません。ですから、こういった訓練やイベントをきっかけに、「みんなで地域課題に取り組んでいく」という空気をつくっていきたいのです。