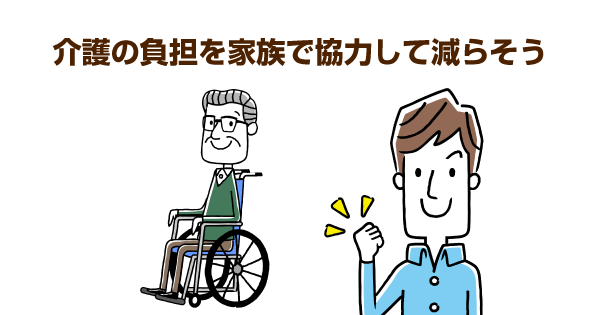皆さん、こんにちは。終活カウンセラー協会の講師をしている小川朗です。
在宅介護の前に立ちはだかる壁の高さや厚さは、人それぞれです。
それは、介護者を取り巻く家庭環境や、要介護者の年齢や体調によっても、大きく左右されます。
そのため、100人いれば100通りの在宅介護があると私は思います。
人気テレビリポーターの菊田あや子さんは、リポーター歴40年目にしてはじめて仕事を断りました。山口県下関市の実家にいる母の明子さんを、介護するためです。
菊田さんの賢明な在宅介護の末に、母の明子さんは亡くなりました。終活カウンセラーの私の立場から見て、菊田さんのご家族と明子さんが迎えられた最期はある意味、「看取りの理想形」だと思いました。
そこで今回は「看取りの理想形~在宅介護で得たもの~」をテーマに、菊田さんのお話を伺いました。

在宅介護を行う決意
2020年5月17日。小春日和の日曜日。
あたたかい日差しが差し込む代官山のオープンテラスで行なったインタビューが、終盤に差し掛かったときのことです。菊田さんの両目から、大粒の涙がこぼれ落ちました。
「私はある意味、ラッキーだったと思います。最後の瞬間まで母との時間を自宅で過ごし、看取ることができたから。母が亡くなったのは、世情が一変する直前の1月7日でした」
在宅介護が始まったのは、それから33日前の12月5日。在宅介護を開始するということは、菊田さんにとって大きな決断でした。

母の介護のために、はじめて仕事をキャンセルした
菊田さんが、日大大学芸術学部放送学科アナウンスコースに入学するため山口県下関市から上京したのは42年前。
在学中にラジオのオーディションを受けてリポーターに合格し、20歳からリポーターとしてキャリアがスタートしました。それから40年間、第一線で活躍してきました。
日本テレビ「ルックルックこんにちは」やTBS「モーニングEye」などで、リポートする姿を多くの方がご覧になったと思います。
底抜けに明るいキャラクターが愛され、着実に実績や信頼関係を築き上げてきました。そんな菊田さんが昨年末、はじめて番組出演の仕事をキャンセルすることになりました。山口県下関市にある実家へ帰り、母の在宅介護に専念するためです。
菊田さんの母の明子さんが、老々介護の末に夫を看取ったのは2003年。その後は、デイサービスに通いながら1人暮らしをしていました。
しかし、83歳のときに認知症の兆候が出始めます。次第に症状が進行し、86歳のときには1人暮らしが困難になりました。菊田さんの2人の兄も別居しているため、明子さんはケアハウスへの入居を選択しました。
海の見えるケアハウスを、次兄とともに下見しました。明子さんはケアハウスを気に入った様子でしたが、荷造りを始めると、2日間ベッドにもぐりこんで動かなかったと言います。
菊田さんは、その様子を見て「姥捨てのような心境になった」と振り返ります。
最後の瞬間まで母のそばにいられた私はラッキーだった
その後、菊田さんは毎月実家に帰って、ケアハウスまで明子さんを迎えに行き、2・3日自宅で食事や入浴、排泄のサポートをしながらともに過ごすようになりました。
東京都から山口県下関市までは、約900キロもあります。介護のために、8年で100回は往復したそうです。
昨年の9月、明子さんは尿感染症が原因で高熱を発症し、一時は危篤に陥りました。そのときすでに菊田さんは、仕事のため5日間ニューヨークへ渡ることが決まっており、断ることができない状況でした。
菊田さんは、祈るような思いでニューヨークでの仕事をこなし、帰国。成田空港から実家に直行しました。
明子さんは危険な状態を脱してはいましたが、嚥下(えんげ)のリハビリを受けても食べ物を飲み下すことができなくなってしまっていました。
同年の11月末、仕事の後に病院へ駆けつけると、中学時代からの友人である看護師長から、在宅介護を提案されたそうです。明子さんが必要とする医療的な配慮は、血中酸素の濃度と皮下注射が体に入っているか確認することのみだったからです。
ほぼ体液と同じ水分量の500ミリリットルを、皮下注射点滴でお腹に24時間かけて入れていきます。毎日来てくれる訪問看護師が、この点滴のパックを1日に1回、針は3日に1回交換してくれます。
菊田さんは会社員ではないため、1ヵ月という長期休暇を取ることも可能でした。
しかし、「フリーランスである自分の立場を考えると、いただいた仕事を断れば、次の保証はない」と仕事と介護の両立に苦しんだそうです。でも結局、「お金や仕事はあとで何とでもなる。私にはまだ馬力があるんだから」と思えたそうです。
同年12月5日。菊田さんは実家に戻り、明子さんのベッドの横に簡易ベッドを並べて寝起きする生活が始まりました。
11時に就寝し、アラームをかけて午前2時と4時に起きる。このとき、酸素マスクが外れていないか、発熱していないか、加湿器の状況は適切かということをチェックします。
9月から飲食ができなくなっていた明子さんはクリスマス前のある日、寝起きに「おなかが空いた」とうれしい言葉を聞かせてくれました。
看護師と相談し、9月以降はじめて食べ物を口にすることになりました。プリンをひとくちだけ口に含みます。しかし、誤嚥しないようにすぐ吸引しました。「クリスマスにはケーキもひとくち食べました」と菊田さんは話します。
年末、明子さんは37.6度の熱がありましたが年を越すことができました。翌年の元日には、孫とひ孫も集まり、家族7人が明子さんのベッドを囲みました。
しかし、1月4日に再び発熱。6日に菊田さんの友人の婦長から「最後にお風呂に入れてあげたら」との提案があり、久しぶりに入浴したそうです。
そして1月7日。微熱が出ており、明子さんの様子がおかしいことに菊田さんは気づきました。体が冷たくなっていき、暮れから泊まり込んでいた次兄をあわてて呼びました。
「目を開いて大きく息を吐いたので『ママ何か言いたいの?』と聞いたんです。でも、そのまま息を引き取りました。兄が『おふくろ、ようやった。大往生だ』と言って、私も『そうだねママ』って」と菊田さんは笑顔で話しました。
その笑顔には、母と娘の双方にとって在宅介護を選択したことがベストであったことを物語る、ある種の達成感がにじんでいました。

「終活」をテーマとした講演活動も行っていく
菊田さんは、それまで認知症に関するテーマの講演も行ってきましたが、母を看取った後は、「終活」の分野に軸足が移りつつあるそうです。
「残りの人生をどう生きるか。どう死んでいくか、ということをテーマに講演を行っています」と話す菊田さん。
菊田さんは母と過ごした33日間で「これからの日々を大切に、十分に生きたい」と考えられるようになったそうです。
断腸の思いで仕事を断り、母と過ごすことを選んだ最後の33日間。「伝えるプロ」としても大きな学びがあったことでしょう。