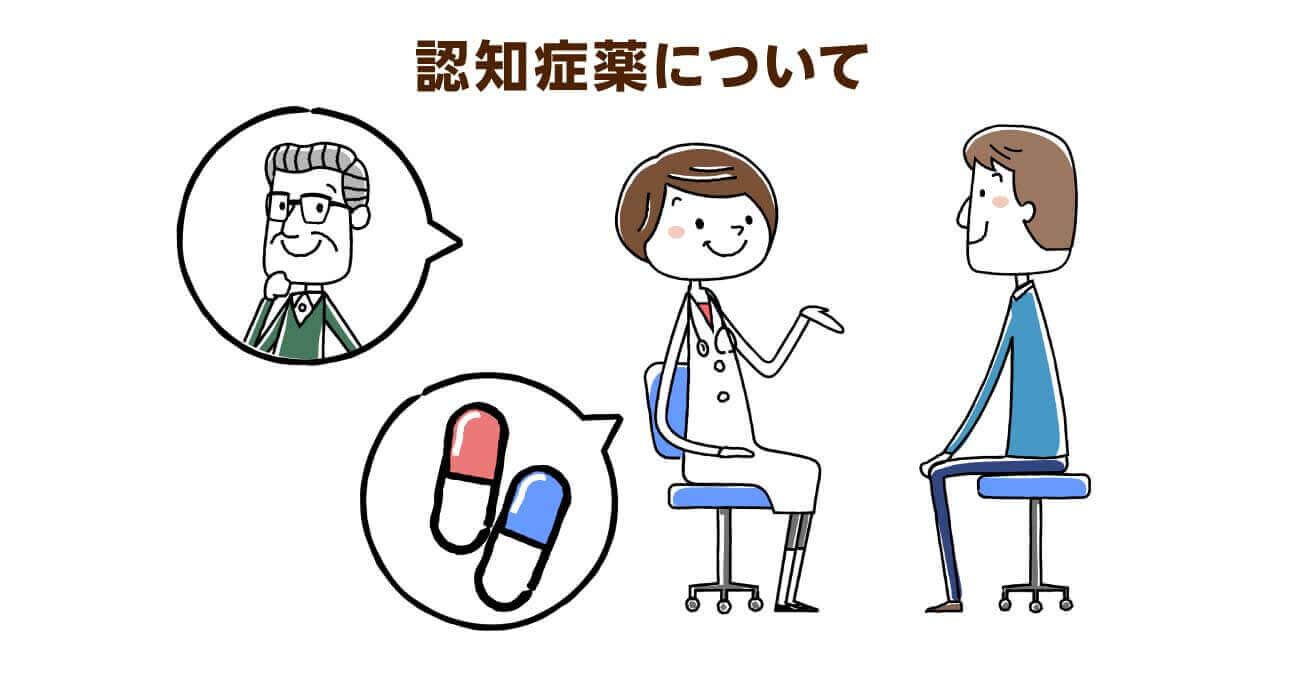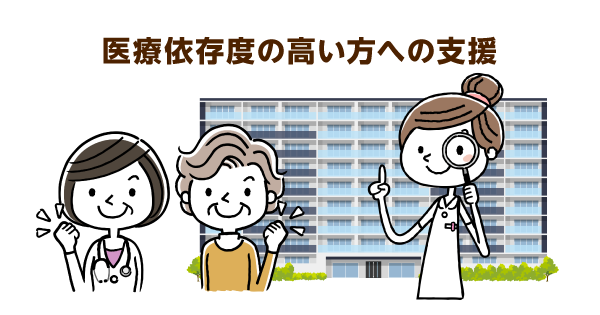こんにちは。リハビリの風でデイサービスの管理をしている阿部洋輔です。
ちょっとした「つながり」が健康に良い影響を与えます。
今回は、介護予防策として再度注目を浴びている「通いの場」についてお話します。
「通いの場」とは高齢者のための触れ合いの場
大まかに説明すれば、「通いの場」とは、高齢者の方々が日常的に近所で地域の方々と触れ合うことができる場所のことです。
住民が活動主体となって地域にある集会所などを活用して、お茶を飲みながら歓談したり、体操をしたり、ほかの人と一緒に趣味を行ったりしています。
高齢者センターや集会所で、民間の事業者がさまざまなサービスを提供する場合もあります。
健康長寿に効果がある「通いの場」
「通いの場」は健康長寿に効果があるというデータが発表され、現在、国や自治体も推進しています。
愛知県武豊町の「通いの場」で2007から2012年を対象に行われた調査によれば、参加していた要介護者の介護度が軽減しました。
ほかにも、下記のような効果が確認されています。
通いの場がもたらした効果
- うつ病のリスクが減少
- 要介護化のリスクが減少
- 転倒や認知症のリスクが減少
2005年前から、高齢者のリハビリテーションとは、単なる機能訓練ではなく、社会参加も含めた包括的なものである必要があるとの声がありましたが、上記のデータによってさらに補強されたことになります。
現在、自治体が行う介護予防事業としての「通いの場」は10万ヵ所以上ですが、65歳以上の人の参加率は5.5%程度だと言われています。
そのため、自治体は高齢者の参加率が上がるように、通いの場の魅力を高めるための取り組みをしています。

地域の茶の間や学習会など、各自治体によって活動内容はさまざま
「通いの場」には、拠点型と活動型などのさまざまなかたちがあります。
「通いの場」のさまざまなかたち
- 「拠点型」サロン・カフェ・地域の茶の間
- 「活動型」各種スポーツサークル・趣味・ボランティア・学習会
自治体の取り組みを紹介します。
拠点型:愛知県武豊町「住民の参加・社会活動の場としてのサロン」
街・大学・社会福祉協議体が一体となり住民ボランティアに対して支援をし、徒歩15分圏内にサロンを設置しました。
その結果、住民が主体的に参加して社会活動をする場所として機能しています。
活動型:大阪府大東市「住民主体の介護予防」
住民が主体となって取り組む介護予防事業を、市内全域で展開しています。
高齢者が小学生の下校時の見守り隊に参加するなど、社会活動が広がっています。
活動型:東京都葛飾区「公園に設置した健康遊具を使用した、介護予防教室」
住民の健康意識を高めるために、区内65ヵ所の公園に健康遊具が設置され、楽しみながら、つまづきやふらつきを予防するための「うんどう教室」を実施しています。
ほかにも全国各地の事例があり、自治体による介護予防が進んでいることがわかります。
高齢者の身近なところに「通いの場」が多数ある地域づくりを進めることで、介護予防や健康に良い影響を与えます。
「通いの場」が多数ある地域が高齢者にもたらすメリット
- 外出目的
- 趣味や運動をする機会
- 居場所
- 役割

住んでいる地域の活動をチェックしてみましょう
「通いの場」に参加することで健康体の維持などさまざまなメリットがありますが、参加率の低さが課題とされています。
自治体は民間の事業者と協力して、高齢者が通いたくなるような空間作りに取り組んでいます。
みなさんも、お住いの地域ではどのような「通いの場」の活動が行われているのか、チェックしてみてはいかがでしょうか。
まずは地域の取り組みを知り、一人ひとりが自分の健康について考え、人が集まる場所の力、地域の力を借りて、みんなで元気になっていきましょう!